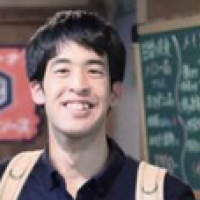- バックエンド
- PdM
- CS職/既存営業
- Other occupations (27)
- Development
- Business
- Other
QA Squadが実践する「攻めのQA」とは?〜対話でつくる協働QAと品質基準の共創〜
Photo by Paul Skorupskas on Unsplash
こんにちは、QA Squad の青柳です。
前回、「3ヶ月でチームは変わる。Wantedly QAが示した『小さく始めて、確実に機能させる』組織変革の具体例」という記事で、QA依頼ワークフローの導入や「QAご意見箱」の設置を通じた、業務効率化と「建設的なフィードバックを交わせる組織文化」の醸成に向けた取り組みをご紹介しました。
こうした初期の地盤固めを経て、QA Squad は次のステップを目指し、FY26のテーマとして「攻めの品質」を掲げています。本記事では、ウォンテッドリーのQAが目指す「攻めのQA」の具体的な定義と、それを実現するための戦略的なアプローチである「対話から始まる協働QA」のロードマップについて詳述します。
目次
QAの役割再定義と「攻めの品質」の必要性
事業成長を支えるQAのミッション
QA Squadがプロダクト開発で果たす戦略的役割
品質を育てる3つのプロセス
協働QAを実現する戦略的アプローチ
エンジニアとの「協働QA」の具体策
「対話から始まる協働QA」の実践
戦略的QAを支える基盤と今後の展望
協働QAを機能させる文化の土台
「攻めのQA」の継続的な挑戦
QAの役割再定義と「攻めの品質」の必要性
事業成長を支えるQAのミッション

私たちが掲げるQA Squadのミッションは、プロダクトを通じてユーザーに「安心(Reliability)」、「安全(Safety)」、そして「信頼(Trust)」を提供することです。これにより、ユーザーが長期的に使い続けたいと思える品質を確立し、事業成長の持続可能な基盤を築くことを目指しています。
従来のQAのイメージは、開発プロセスの最終段階でバグを見つける「テスター・デバッガー」といった、「細かいチェックをしてくれる人」かもしれません。しかし、ウォンテッドリーのQAが目指す「攻めのQA」は、その役割を大きく再定義します。
私たちは、「攻めのQA」を、「単にテストやバグ報告を行うだけでなく、開発プロセス全体に積極的に関与し、品質を向上させるための提案や活動」 と定義しています。
QA Squadがプロダクト開発で果たす戦略的役割
QA Squadの役割は、以下の二つの側面から、プロダクトとビジネスの成長を戦略的に支えることです。
- 開発プロセスへの貢献 : 開発サイクル全体におけるリスクの早期発見と手戻りの最小化
- ビジネス成長への貢献 : ブランドイメージの維持と持続可能な成長基盤の確立
上記2つの役割を実現するために、QA Squadの活動は、単なるテスト実行に留まらず、「品質をチーム全体で育てるプロセスを設計する」ことに主眼を置きます。
品質を育てる3つのプロセス

- 品質の定義 :
- 私たちのプロダクト (Wantedly Visit / Wantedly Hire / Engagement Suite ) によって『ユーザーにとっての価値』は異なります。各プロダクトを狩野モデル*に当てはめたとき、どの品質特性を重視すべきか、事業特性や機能の新規性などを踏まえ、各Squadと共に品質基準を定義していきます。
- 品質の可視化 :
- バグやリスクを早期に発見・共有し、開発のボトルネックではなく、意思決定のための判断材料として提供します。
- 品質のプロセス設計 :
- どのタイミングで QA が入ると最も効果的かを明確にし、手戻りを減らすための仕組みをチームと共につくります。
* 狩野モデル:1980年代に狩野紀昭教授が提唱した、製品やサービスの品質要素を5つに分類し、顧客満足度との関係を明らかにするためのフレームワーク
協働QAを実現する戦略的アプローチ
「攻めのQA」を実現させるための具体的なアプローチとして、私たちは「エンジニアとの協働QA」「対話から始まる協働QA」を経て、「品質基準の共創」を目指すロードマップを描いています。
これは、品質保証を開発プロセスの「後工程 (右側) 」で行う従来の課題 (修正コストの増大、スケジュール遅延) を解消し、「前工程 (左側) 」から関与する Shift Left の考え方を具体的に実行するものです。
エンジニアとの「協働QA」の具体策
協働QAのフェーズでは、QA活動を開発チームにオープンにし、開発プロセスに組み込むことを重視しています。
- プランニングやレビューの場への同席 : QA はプランニングやレビューの場に同席し、開発の初期段階から関与します。これにより、仕様の理解が早まり、潜在的なリスクを早期に発見できます。また、レビュー会に参加することで、その週に実装された機能を同期的に把握できるため、QA が並走してテストを進める際にスコープが明確になります
- テスト工程のオープン化 : 今までブラックボックスであったテスト工程をオープンにし、テストケースなどのアウトプットをステークホルダーにレビューしてもらうことで、テスト品質の底上げを図っています。これにより、QA が一方的に品質をチェックするのではなく、チーム全体で品質意識を高める土壌を築いています
「対話から始まる協働QA」の実践
ウォンテッドリーの開発組織は、職種混合のチーム体制を取っており、領域ごとに求められる品質特性が異なります。画一的な品質基準では、全てのチームにフィットさせるのは困難です。
この課題に対応するため、私たちは「対話から始まる協働QA」を推進しています。
- 定期的な対話の場を設定 : 各領域のリーダーと QA が対話する場を設けています
- 課題と理想の共有 : この対話を通じて、それぞれの領域が抱える課題や理想とする品質を共有し、求められているものを正しく理解します
この「対話」こそが、最適な品質基準を設定するための鍵となります。
戦略的QAを支える基盤と今後の展望
協働QAを機能させる文化の土台
今回ご紹介した「攻めのQA」の戦略は、前回の取り組みで確立した、メンバーが安心して意見を発信できる「建設的なフィードバックを交わせる組織文化」という強固な土台の上に成り立っています。この文化があるからこそ、異なる領域のエンジニアや PdM と QA が率直に対話し、品質基準の共創といった難しい課題に共に挑戦できるのです。
「攻めのQA」の継続的な挑戦
QA Squad は、前回築いた業務効率化の基盤 と、今回紹介した戦略的な協働を組み合わせることで、事業成長を加速させる「攻めのQA」を実現しつつあります。
重要な点は、これらの変革もまた、前回の教訓と同様に、「どちらも一気にではなく、小さく始めて確実に機能させる」アプローチを取っていることです。長期的な理想像 (品質基準の共創) を描きつつ、まずは目の前の小さな協働から確実な成果を出し、それを土台に次のステップへと進んでいます。
私たちは今後もチームと共に学びを重ねながら、ウォンテッドリーのミッションである「究極の適材適所により、シゴトでココロオドルひとをふやす」を、このQAの現場から体現し続けていきます。