- バックエンド
- PdM
- 急成長中の福利厚生SaaS
- Other occupations (24)
- Development
- Business
- Other
ウォンテッドリー 執行役員CTOの安間です。
突然ですが、皆さんは「ハッカソン」と聞くと、どんなイメージを持ちますか? 若手エンジニアが腕試しをする場、新しい技術に触れる機会、あるいは徹夜で何かを作り上げるお祭りのようなものでしょうか。
先日、ウォンテッドリーの全社合宿で、私自身が経営チームの一員としてハッカソンに本気で参加してきました。この記事では、そのハッカソンでの経験を通じて見えた本気の開発の楽しさ、AIツールの活用のヒント、そしてウォンテッドリーが大切にしているカルチャーについて、具体的なエピソードを交えながらお話ししたいと思います。
この記事を読めば、ウォンテッドリーの雰囲気や、私たちがどのような価値観を持ってプロダクト開発に取り組んでいるのか、その一端を感じていただけるはずです。そして、もしかしたらあなたも「こんなチームで働いてみたい!」と思っていただけるかもしれません。
なぜ経営チームがハッカソンに本気で挑むのか?
ウォンテッドリーでは、年に1度全社合宿を実施しており、その中の目玉イベントとしてハッカソンがありました。私を含む経営チームのメンバーも参加しました。
「役員がハッカソン? しかも本気で?」と驚かれるかもしれませんね。私たちが「大人気なく」本気でハッカソンに取り組むのには、いくつかの理由があります。
- 現場感の再確認と技術トレンドのキャッチアップ: 普段の業務では、どうしてもマネジメントや戦略策定に多くの時間を割くことになります。しかし、実際に手を動かして開発することで、現場のエンジニアが直面している課題や、新しい技術の可能性を肌で感じることができます。これは、技術ドリブンな組織であり続けるために不可欠なことだと考えています。
- 部門を超えた連携の促進: ハッカソンでは、普段あまり一緒に仕事をしないメンバー同士がチームを組むこともあります。エンジニアだけでなく、デザイナーやプロダクトマネージャー、時にはビジネスサイドのメンバーも参加します。短期間で集中的に協力することで、職種の垣根を越えた相互理解が深まり、後の業務にも良い影響をもたらします。ハッカソン終了後、ビジネスサイドから楽しかったとの声が多数あがりました。
- Wantedly Valueの体現: 経営チームが「本気で楽しむ」「本気で挑戦する」姿を見せることで、社内に「One Team」「Move Fast」「Code Winds Arguments」をはじめとするWantedly Valueをより一層浸透させたいという思いもあります。
こうした背景から、今回のハッカソンも、私は開発担当の一人として、本気で優勝を目指して臨みました。

開発の裏側:AIツールを駆使した爆速開発と「サービス化」への本気度
さて、今回のハッカソンで私たちが何を作ったのか……残念ながら、それはまだ秘密です。というのも、本気でサービス化を目指せるレベルのアイデアだと考えているからです。いつか皆さんに「あの時のハッカソンで作っていたのはコレだったのか!」と驚いてもらえる日が来るかもしれません。
ここでは、プロダクトの具体的な内容には触れられませんが、その開発プロセスの一端をご紹介したいと思います。
AI活用によって作業を並列化。 調査からコーディングまでフル活用
今回のハッカソンで特に意識したのは、AIツールの徹底活用です。皆さんもご存知の通り、昨今のAI技術の進化は目覚ましく、ビジネスから開発まであらゆるシーンでその恩恵を受けることができます。
- 調査AI: アイディアに関連する競合製品があるのかといった市場調査データの分析アシスト、関連技術やAIやOSSの列挙など、開発の前工程のタスクでもAIの力を借りることで、チーム全体としてプロダクトのコアな価値創出に集中できました。
- コーディング支援AI: 詳細な仕様を伝えるだけで基本的なコードの骨子を生成してくれたり、複雑なアルゴリズムの実装方法を提案してくれたり。これにより、実装のスピードは格段に向上しました。デバッグやリファクタリングの相談相手としても非常に優秀です。
- 画像生成AI: プロダクトに必要なロゴやイラスト、UIのモックアップイメージなどを短時間で生成。デザイナーがいないチームでも、アイデアを素早くビジュアル化し、チーム内でのイメージ共有を円滑に進めることができました。
もちろん、AIが得意なところと人間が得意なところを組み合わせることで、開発生産性と創造性は飛躍的に高まると実感しました。特に、ハッカソンという短期間での開発だからこそ、より強く感じられた点かもしれません。
「サービス化」への本気度がチームを一つにする
私たちのチームが目指したのは、単なる「ハッカソン向けのプロトタイプ」ではありませんでした。時間内にできるものを開発するのではなく、今必要なものに着目して進めていきました。そのため、高速にPDCAを回して、時間ギリギリまで短期集中することができました。
ハッカソンが生んだ「一体感」と「相互理解」という最高の果実
今回のハッカソンは、私にとって技術的な挑戦だけでなく、チームで何かを成し遂げることの素晴らしさを再認識する貴重な機会となりました。
プロ意識をもったチームワーク
限られた時間の中で成果を出すためには、各メンバーが自分の役割を高いレベルで、かつスピーディーにこなす必要があります。アイデア出し、設計、実装、テスト、そして発表準備。それぞれのフェーズで、誰が何をすべきか、どう連携すればスムーズに進むかを常に考え、コミュニケーションを取りながら進めました。
時には意見がぶつかることもありましたが、それもプロダクトをより良くするため。全員が同じ目標に向かっているという信頼感があったからこそ、建設的な議論ができたのだと思います。この高速な役割分担と密な連携こそが、短期間で高い成果を生み出す秘訣であり、チームとしての一体感を育む土壌となるのです。
職種を超えた理解がチームを強くする
ハッカソンでは、エンジニアだけでなく、様々な職種のメンバーが協力し合います。それぞれの専門性や視点が異なるからこそ、一人では思いつかないようなアイデアが生まれたり、多角的な視点からプロダクトを検証できたりします。
例えば、エンジニアが技術的な実現可能性に集中している時、デザイナーはユーザー体験の細部にまで気を配り、ビジネスサイドのメンバーは市場のニーズや収益性を考える。こうした異なる視点が交わることで、プロダクトはより実践的で魅力的なものへと進化していきます。
今回のハッカソンを通じて、改めて他の職種への理解とリスペクトが深まったと感じています。そして、この経験は間違いなく、今後のウォンテッドリー全体のプロダクト開発にも活かされていくでしょう。

結果発表!そして若手エンジニアからの熱い挑戦状
さて、気になるハッカソンの結果ですが……。
私たち経営チームは、15チーム中3位という投票結果でした(経営チームはランク対象外でしたので、記念撮影だけです)。

正直なところ、本気で1位を狙っていたので、悔しい気持ちはあります。しかし、それ以上に、他のチームが作り上げてきたプロダクトの質の高さに驚かされ、大きな刺激を受けました。特に若手エンジニアやビジネスマンたちの斬新なアイデアや、それを形にする総合力には目を見張るものがありました。
閉会式で、あるエンジニアからこんな言葉をかけられました。 「安間さんには勝ちたかったです。次は絶対に負けません!」
彼らが、私たち経営チームを「良きライバル」として見てくれていること、そして本気で私たちに挑んできてくれること。これこそが、ウォンテッドリーが目指すフラットで切磋琢磨できる開発文化の表れだと感じました。

ハッカソンで見えたWantedly Valueで開発を進めるということ
今回のハッカソンでの経験は、まさにウォンテッドリーが大切にしているValueを体現するものだったと思います。
役職や職種に関係なく、全員が同じ目標に向かってフラットに意見を出し合い、それぞれの強みを活かして協力し合う。困難な課題に直面しても、チームで知恵を絞り、乗り越えていく。そして、その過程も結果も、全員で分かち合う。
もしあなたが、
- 自分の意見やアイデアを積極的に発信し、チームに貢献したい
- 職種や役職の垣根を越えて、フラットな環境で働きたい
- 仲間と共に、本気で世の中に価値あるプロダクトを届けたい
そう考えているなら、ウォンテッドリーは最高の環境かもしれません。

まとめ:本気の開発は、やっぱり楽しい!
今回のウォンテッドリーにおけるハッカソンの裏側、いかがでしたでしょうか?
私自身、久しぶりにひとりの開発者として、モノづくりの原点に立ち返ることができたように感じています。AIという新しい武器を手に、信頼できる仲間たちと一つの目標に向かって突き進む時間は、本当にエキサイティングでした。
この記事を通じて、ウォンテッドリーのハッカソンの雰囲気や、私たちがどんな想いでプロダクト開発に取り組んでいるのか、少しでも感じ取っていただけたら嬉しいです。
もし、あなたがウォンテッドリーの文化や、このようなメンバーに少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ一度カジュアルにお話ししませんか? あなたの技術で、私たちと一緒に世の中を面白くするプロダクトを創り出しましょう。




/assets/images/5539046/original/236782ca-57d9-4011-b0fa-82f127640a05?1710328876)

/assets/images/7052304/original/49100b17-5866-4cec-b50b-a37ea73565e9?1638782149)
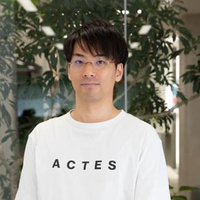




/assets/images/7052304/original/49100b17-5866-4cec-b50b-a37ea73565e9?1638782149)

