こんにちは!ウォンテッドリー株式会社で採用広報を担当している竹内瑞季です。
先日、私たちWantedly Engagement事業のプロダクト開発チームが主催したイベント「1→10フェーズのプロダクト成長戦略:Wantedly Engagement事業開発の舞台裏」を開催しました。このイベントでは、事業責任者、プロダクトマネージャー(PdM)、バックエンドエンジニア、プロダクトデザイナーが登壇し、事業の成長フェーズにおけるプロダクト開発のリアルな裏側と、そこで得られた貴重な学びを共有しました。
今回のイベントでは、5名の異なる職種のメンバーがそれぞれの視点から発表を行い、事業フェーズが浅いプロダクト開発チームには、「不確実性を受け入れ、戦略的な意思決定と柔軟な対応で素早い価値提供を目指す」という共通点があることが浮き彫りになりました。
本記事では、当日参加できなかった方のために、各登壇内容を詳しくご紹介します。
目次
Perkの事業責任者として挑む、事業成長とプロダクトづくりの両立
事業責任者としてのミッションと直面した課題
「ミッション」を意識することの重要性
ミッションと事業を紐づけるために実行したプロセス
なぜ「やらないこと」を決めるのか?PdMの戦略的思考
Perkアプリの技術選定と1年間の軌跡:FlutterとWebViewの協調
1→10フェーズでエンジニアが意識すべきこと:開発コストとビジネス視点
デザインがつなぐ「戦略と現場」:曖昧さを可視化する
まとめ
Perkの事業責任者として挑む、事業成長とプロダクトづくりの両立
登壇者:橋屋 優理(事業責任者)
WantedlyのPerk事業責任者である橋屋優理が、事業の急成長を牽引しながら、どのようにプロダクトづくりとの両立を図ってきたのか、その戦略とプロセスについてお話ししました。
事業責任者としてのミッションと直面した課題
ウォンテッドリーのミッションは「究極の適材適所により、シゴトでココロオドルひとをふやす」ことです。このミッション達成のためには、共感、挑戦、自律を重んじ、働くすべての人々が仕事に没頭し、成長を実感できるようなインフラを構築することが不可欠だと考えています。
事業責任者としての役割は、事業の長期的な利益を確保することにあります。しかし、Perk事業リリース当初は、以下のような問題と特異な事情がありました。
- Engagement事業はプロダクト単体でのマネタイズを前提としていない
- 当時はWantedly Visitの利用社数向上から始まった
- 同じEngagement事業部内に3つのプロダクトが存在し、それぞれの開発優先順位も不明確
- ビジネスサイドと開発サイドの意思疎通も十分とは言えない状況
このような経緯の中で、「マネタイズ」へ舵を切る戦略が確定し、橋屋はこの難局に挑むことになります。
「ミッション」を意識することの重要性
ビジネスサイドでの施策推進と必要なアップデートを重ねることで、3つのプロダクトのうちPerk事業は第2の柱として会社の注力商材へと変貌を遂げました。
しかし、中期事業計画を作成する際、橋屋は立ち止まります。「Perkの事業内容が、Wantedlyのミッションと本当にリンクしているのだろうか?」この問いかけが、その後の戦略に大きな影響を与えました。
事業を推し進めるにあたり、ミッションはチームビルディングと事業成長の両方にとって不可欠であるため、強く意識することが非常に重要です。具体的には、チーム全体の「矢印」を揃え、阿吽の呼吸で仕事を進めるため、そしてビジネスとして明確な競争優位性を築くために不可欠だと感じています。このような考えに基づき、橋屋は下記でご紹介する対応を進めていきました。
ミッションと事業を紐づけるために実行したプロセス
ミッションと事業を深く結びつけるため、橋屋は以下の4つのアプローチを取りました。
1. 人事施策における福利厚生の立ち位置の定義
書籍、セミナー、社内の人事担当者からの学びを得るだけでなく、大学教授へのインタビューや学会への参加を通じて、多角的にインプットを行いました。これらのインプットを通じて、Wantedlyの思想と福利厚生の共通点を見出すことができました。
2. 福利厚生の企業担当者へのインタビュー
既存顧客へのインタビューに加え、既存顧客『以外』へのインタビューも実施しました。この調査により、多くの企業が「自社らしい福利厚生」を目指しているというインサイトを得ることができました。
余談ですが、インタビューは「身銭を切ってでも生の声を聴く」ことが非常に重要です。自社との関係性が薄いユーザーからのヒアリングは、自分たちが想定していなかったアイデアやフィードバックをいただける、非常に良い機会となります。
3. プロダクトビジョンへの落とし込み
上記調査で得られた知見をもとに、「Wantedlyだからこそ取り組むべき課題」を特定し、明確なプロダクトビジョンを策定。具体的な施策例へと落とし込みました。このビジョンへの落とし込みを行うことにより、ウォンテッドリーだからこそ取り組むべき本質的なIssueを発見することができました。
4. ステークホルダーへの発信
経営メンバー、ビジネスサイドのチームメンバー、開発サイドのチームメンバーといった各ステークホルダーに対し、それぞれの関心事に合わせてプロダクトの「想い」が伝わるよう、きめ細やかなコミュニケーションを図りました。
ミッションを大切にすることは、事業戦略上も極めて合理的なアクションです。なぜならミッションは、文化 > 人材 > 機能 の順に、他社が模倣しにくい競争優位性を生み出すからです。
この発表では、事業成長を追求する中で、いかに企業ミッションを深く理解してプロダクト戦略に落とし込み、チーム全体を巻き込んでいくかという、事業責任者として本質的な問いへの具体的なアプローチをお話ししました。
なぜ「やらないこと」を決めるのか?PdMの戦略的思考
登壇者:吉野雄大(プロダクトマネージャー)
プロダクトマネージャーの役割は、チームが「この優先順位でいいんだ」と納得して進められる状態をつくること。しかし、ユーザーニーズが多様化する中で、すべてに応えるのは不可能です。そこで重要になるのが、「やらないことを決める」という逆転の発想です。
「やりたいことを探すよりも、やらないことを消す方が早くて確実」であり、これにより一貫性と軸が保たれ、新しいアイデアに対してもブレずに判断できます。この「やらない」には、やりたくないことだけでなく、「やらねばならないが後回しにできること」や「我慢すること」も含まれます。
では、どうやって「やらないこと」を決めるのか?それは徹底した調査に基づきます。
- 外部環境分析(PEST分析):政治、経済、社会、技術の観点から市場全体の変化を捉え、経営の思考を把握
- 業界・競合分析(3C分析):市場、競合、自社の立ち位置を知り、強みや弱みを把握
- サービス分析:自社サービスのデータ(ユーザー行動、顧客の声)から強みや弱みを裏付け、必要に応じて生成AIも活用
- セグメントとターゲティング(STP分析):顧客層を分け、どのセグメントに価値を提供するかを決定
これらの分析を基にプロダクトバックログを整理し、下記4点を構造的に並べます。
短期的な課題と長期的なビジョンの間で生じがちな「ねじれ」を解消するためにも戦略が不可欠です。各プロジェクトを事業計画や営業目標と紐付け、チーム全体で目標達成に向けて共有することで、ブレのない推進が可能になります。
PdMは不確実な状況下で、チームが納得して進められる状態を作り出すことです。
そして「やらないこと」を決めることで、本当に「やること」が見えてくる、というお話をさせていただきました。
Perkアプリの技術選定と1年間の軌跡:FlutterとWebViewの協調
登壇者:富岡真悟(バックエンドエンジニア)
Engagementチームにはモバイルエンジニアが不在という状況で、以下の要求がありました。
- Webでできることは基本的にアプリでも実現すること
- iOSとAndroidをあまり時間を空けずに揃えられること
- 今後の機能リリース速度をできる限り落とさないこと
- メンテナンスコストをなるべく抑えること
これらの要求を満たすために、開発チームが出した結論は「ガワFlutter + 中身WebView」というハイブリッド構成でした。
WebViewを採用した最大の理由は、初期リリースまでのリードタイムを大幅に短縮できる点です。すでにスマホに最適化されたWeb実装があったため、ほぼそのまま活用することができました。さらに、Webとアプリで実装を共通化できるため、今後の機能リリースも速く行えるメリットがあります。大部分の変更はWebエンジニアだけで対応可能で、ストアの審査を通さずにリリースできる点も大きな魅力でした。
一方で、ネイティブ実装と比較してスムーズさやOSの提供機能を使う際の手間がかかるデメリットはありますが、Perkアプリの特性上、メリットがデメリットを上回ると判断しました。
ガワの部分にFlutterを採用したのは、UIがWebViewベースであるためプラットフォーム依存な実装が少なく、クロスプラットフォーム技術で開発コストを抑えられると考えたからです。また、組織としてFlutterをプロダクトで利用し、その有効性を検証したいという狙いもありました。
結果として、基本的にはWebViewに寄せ、Flutterでないと実装できない部分だけをFlutterで実装するという明確な棲み分けがなされました。この戦略的な技術選定により、Perkアプリは迅速なリリースと継続的な機能開発を両立させています。
1→10フェーズでエンジニアが意識すべきこと:開発コストとビジネス視点
登壇者:池田雅人(バックエンドエンジニア)
事業には「導入期(0→1)」「成長期(1→10)」「成熟期(10→100)」「再構築期」といったライフサイクルがあり、フェーズごとに求められる開発スピードやユーザー数、意思決定のスタイルが異なります。
- 導入期(0→1):開発スピードが非常に速く、機能実装が重視
- 成長期(1→10):開発速度と品質の両立が求められ、優先順位を自分で判断するスキルが重要
- 成熟期(10→100):開発スピードは比較的遅く、バグのリスクも大きいため慎重な変更が求められる
Wantedly Perkはこの「成長期(1→10)」に当たります。
以前の池田は、バグを発生させないことに意識が向きすぎ、動作確認やテストに時間をかけすぎてしまうことが課題でした。また、タスクの優先順位も「大体」でつけていましたが、1→10フェーズの開発を通して意識が大きく変化しました。
特に意識するようになったのは、「開発コストに対する費用対効果」と「ビジネスサイド視点の業務・課題」です。頻繁に使われていない機能のテストに時間をかけるよりも、その機能がユーザーや利益に与える影響を考慮し、100%バグを出さないことよりも他の機能実装を優先すべきだと考えるようになりました。
また、顧客からのフィードバックを聞くことで、事業への影響が大きいタスクを優先するべきだと判断するようになりました。
この意識変化の背景には、現在のEngagementチームで行われている以下の取り組みがあります。
- 昼会やレビューでの目標・優先順位確認
- 毎週1回の開発とビジネス合同での目標・進捗共有
- 隔週での顧客からの要望/行動/悩み共有会
これらの取り組みを通じて、開発とビジネスサイドが足並みを揃えて施策を進めることができ、他のフェーズでは経験しにくい貴重な学びを得たと感じています。1→10フェーズでは、技術的な品質だけでなく、ビジネスへの貢献度を意識した開発が求められることをお話させていただきました。
デザインがつなぐ「戦略と現場」:曖昧さを可視化する
登壇者:田中悠一(プロダクトデザイナー)
この取り組みは、PdM不在によりチームに空いた「穴」から始まりました。プロダクトデザイナーとして、より主体的にUXプロセスを実行していく必要性を感じ、様々な取り組みを行いました。
田中が重要視していたのは、「違和感は課題見直しのサイン」という感覚です。漠然とした違和感を覚えた時こそ、インサイトと課題に立ち戻ることが重要だと考えています。
プロダクトデザインは単なる「見た目の調整」に留まりません。プロダクトデザイナーは「曖昧さを可視化する」役割を担い、それによって戦略と現場の間に存在するギャップを浮き彫りにします。
例えば、言語化されていない抽象的な要件をワイヤーフレームやプロトタイプに落とし込むことで、チーム内で認識のズレがないか、本当にその方向性で良いのかを具体的な形で見える化するのです。そして、一度可視化されたものに対し「なぜ?」と問い直し続けることで、本質的な課題や最適な解決策を見つけ出すことができます。
デザイナーは「最後の砦」であり、常に問い直しを止めず、曖昧さを可視化することで、戦略と現場をつなぎ、プロダクト開発を成功に導く重要な役割を果たします。
まとめ
今回のTech Nightでは、Wantedly Engagement事業の成長を牽引するメンバーたちが、それぞれの視点から1→10フェーズにおけるプロダクト開発のリアルな現場とそこで得られた知見を共有してくれました。
- PdMは「やらないこと」を決め、徹底した調査と戦略でプロダクトの軸を固める
- エンジニアは費用対効果とビジネス視点を持ち、開発とビジネスの連携を強化する
- デザイナーは曖昧さを可視化し、問い直しを通じて戦略と現場をつなぐ
新規事業や事業フェーズの浅いサービスの開発に関わる皆さんにとって、これらの視点や具体的な取り組みが、日々のプロダクト成長に役立つヒントとなれば幸いです。
私たちウォンテッドリーでは、共にプロダクトを成長させていく仲間を募集しています。今回の記事を読んで、少しでも興味を持たれた方は、ぜひWantedlyの募集ページをご覧ください。皆さんのエントリーをお待ちしています!



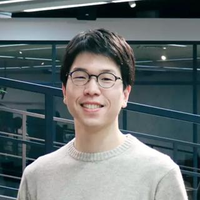


/assets/images/7052304/original/49100b17-5866-4cec-b50b-a37ea73565e9?1638782149)


/assets/images/7052304/original/49100b17-5866-4cec-b50b-a37ea73565e9?1638782149)





/assets/images/7053725/original/28d1b135-13b4-4f46-895f-d5f5fb5ae243?1624246858)

