- カスタマーサクセス
- プロダクトマネージャー
- エンジニアリングマネージャー
- Other occupations (56)
- Development
-
Business
- プロダクトマネージャー
- 採用担当者
- 経理
- 新卒エンジニア採用担当
- 情報セキュリティ
- 法務
- 人財開発・組織開発担当
- HRBP
- パートナーセールス/代理店営業
- 法人向け提案営業
- BizDev/事業開発
- Sales / Business Development
- コンサルティングセールス
- SaaSBizDev/事業開発
- ソリューションセールス
- 事業責任者候補
- メディア幹部候補
- マーケティング・販促
- Marketing / Public Relations
- マーケコンサルティング
- マーケティング責任者候補
- マーケティング責任者
- マーケティングマネージャー候補
- プロダクトマーケティング
- メディアマーケティング
-
Other
- カスタマーサクセス
- マーチャンダイザー/MD
- 決済オペレーションリーダー候補
- ECオペレーション担当
- SCM企画
- 経営幹部候補(次世代リーダー)
- オペレーション推進・DTP
- オペレーション推進
- オープンポジション
- カスタマーサポート
- Operation Bizde
- 制作ディレクションリーダー候補
- 印刷SCMオペレーション
- DTP
- カスタマーエンゲージメント
- SCMオペレーション
- 顧客戦略マーケティング
- 工場長
- 事業開発/Bizdev
- セールスマネージャー
- MD(マーチャンダイザー)
- Customer Relations
- SalesOpsマネージャー
- アカウントエグゼクティブ
- Sales-デザイン事業
- SCM部長候補
- 経営幹部候補
RAKSULグループは、「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」というビジョンのもと、印刷事業「ラクスル」を皮切りに、広告事業「ノバセル」、そして金融事業 「ラクスルバンク」へと事業領域を着実に拡大し続けています。
そんな中、グループの次なる飛躍を技術面から支える重要な部門として位置づけられているのが「プラットフォーム統括部」です。
グループ各事業が共通して利用できる基盤システムを構築し、お客様に一貫したシームレスな体験を提供する ── この壮大なミッションに挑む現場では、いったい何が起きているのでしょうか。
今回お話を伺ったのは、同部門で統括部長を務める二串さんと、プロダクト開発をリードする田渕さん。「個人商店からショッピングモール」への進化に例えられるプラットフォーム構築の舞台裏や、少数精鋭チームならではの「手触り感」のある開発環境、そしてこれから描く未来について、詳しくお話を伺いました。
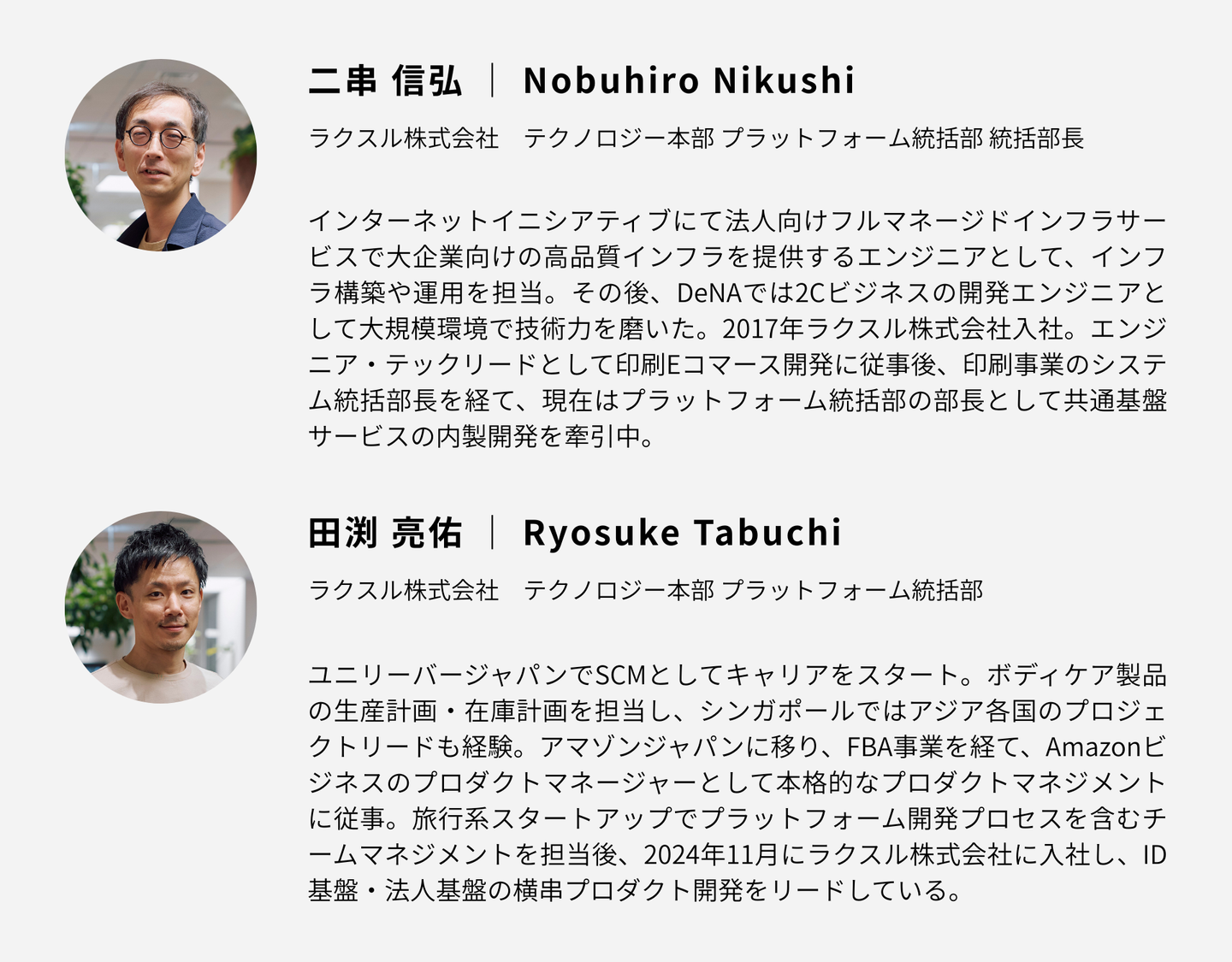
目次
「個人商店→商店街→ショッピングモール」──プラットフォーム統括部が描く壮大な進化ストーリー
3つの共通基盤が変える、RAKSULの顧客体験
第1フェーズ「インフラ構築」から第2フェーズ「シナジー創出」へ
少数精鋭チームで実感する、圧倒的な「手触り感」
《編集後記》 次世代のBtoBエコシステムを、一緒に創りませんか?
「個人商店→商店街→ショッピングモール」──プラットフォーム統括部が描く壮大な進化ストーリー
── まず、プラットフォーム統括部がどのような役割を担っているのか、教えてください。
二串: プラットフォーム統括部の活動を分かりやすく例えるなら、個人商店のように個別に事業を展開してきたグループ内の各事業を、最終的にはショッピングモールのような場所を提供し、事業同士を接続していく取り組みです。
個人商店の場合、それぞれが独自にキャンペーンを実施しても、お客様は特定の店舗にしか足を運びません。しかし、個人商店を集めてアーケードを作ったり、くじ引きイベントを開催したり、他店でも使えるクーポンを配布したりすることで、徐々に商店街となり、そこに集う店舗全体の集客力を高めることができます。
それがさらに発展すると、統一されたショッピングモールが完成します。モール内の各テナントは、お客様が共通して利用する駐車場やトイレ、エレベーターといったインフラを活用しながら、本業に専念できるようになる。
私たちプラットフォーム統括部は、まさにこの「モールのインフラ整備」を担い、事業同士が安心して価値を発揮できるような場所を提供し、接続していく役割 を果たしています。
田渕: 具体的には、プラットフォーム統括部の役割は「グループ全体で共通して使える機能や基盤を定義し、それを提供すること」です。これにより、各事業やサービスは、ユーザー管理や決済処理といった共通機能をゼロから開発または改善する必要はなくなり、本来注力すべき事業ごとの価値提供に集中できるようになります。
つまり私たちは、事業を支える基盤の“全体最適化”を担うことで、各サービスが持つ強みをより純粋に発揮できる環境を実現することを常に目指しています。
── ショッピングモールの例えはわかりやすいですね!ところで、プラットフォーム統括部はどのような経緯で発足したのでしょうか?
二串:実は1年ほど前からプロジェクトとしては進めていたのですが、正式に部門として組成されたのは2025年2月です。
大きなきっかけとなったのは、2024年に現グループCTOの竹内が入社し、「事業間のシナジーを一層生み出していきたい」という強いビジョンを掲げたことでした。これが経営陣からの強力な後押しとなり、プラットフォーム統括部の正式発足につながりました。その後、グループCIO兼グループCDOの藤門が加わったことで、我々の取り組みがさらに加速しています。
── なぜプラットフォームの統合がそれほど重要なのでしょうか?
田渕: もし共通プラットフォームがなければ、RAKSULグループの各サービスは新しいサービスを立ち上げるたびに、ユーザーアカウント管理の画面や機能をゼロから個別開発し、そして保守・運用をしなければなりません。一方で、例えば、印刷事業にとって本来注力すべきは「印刷」や、その裏にある顧客ニーズを深く追求・理解し、課題解決することであり、ユーザー管理などの機能開発は必ずしも事業の本質ではないことが多くあります。
私たちがグループ横断でプラットフォームを構築・提供することで、各事業は本質的な価値創出に集中できるだけでなく、全社的にコストや開発工数を大幅に効率化できます。さらにユーザーにとってもRAKSULグループの複数サービスをシームレスに行き来できる利便性が生まれ、より直感的で便利に活用いただけるようになるのです。

3つの共通基盤が変える、RAKSULの顧客体験
── 具体的には、どのような基盤を開発・運用しているのですか?
二串: 現在、大きく3つの基盤を構築しています。
まずは 会員・顧客基盤。RAKSULグループのいずれかのサービスに一度登録すれば、追加の手続きなしに他のサービスも利用できる、いわゆるSSO(シングルサインオン)の仕組みです。
次に 決済基盤。クレジットカード、後払い、売掛、銀行振込など多様な決済手段を共通化し、同じカードや売掛情報を複数サービスでそのまま利用できるようにしています。
そして最後に 法人基盤。企業規模が大きくなると、支店や事業部単位で全社統一管理をしたいというニーズが高まります。SMB(中小企業)とエンタープライズでは求める利用形態が大きく異なるため、法人単位での柔軟な設定を可能にし、所属する全ユーザーが同じ条件でサービスを利用できる環境を整えています。
── プラットフォーム統括部の業務で、最も困難なのはどの部分ですか?
田渕: 最も難しいのは、各事業部門の思想や要望をすり合わせ、最大公約数を見出すことです。印刷・広告・金融といった事業領域が異なれば、会員情報やシステムに対する考え方も当然異なります。そのため要件は複雑化しやすく、時には「関係者を絞って個別に作った方が早いのでは?」という声が上がることもあります。
確かに事業部単体で見れば、単独開発の方が早さや工数も抑えられるでしょう。しかし、お客様が複数のサービスを併用することを前提に考えると、それでは十分ではありません。だからこそ私たちは、各事業部門と徹底的に対話しながら、「なぜその要件が必要なのか」「真に共通化すべき部分はどこなのか」を一つひとつ紐解き、オーナーシップを持って最適解を見出していく努力を続けています。
── 既存システムとの兼ね合いも複雑そうですね。
田渕: その通りです。例えば請求システムひとつとっても、既存の売掛金管理システムにはすでに「法人」という概念が組み込まれています。新しいプラットフォームを構築する際には、こうした既存システムとどう連携させるのか、あるいは思い切って新規構築するのか ── その判断が非常に難しいポイントになります。
二串:ゼロベースで構築できればシンプルですが、現実には長年積み上げてきた既存のシステムがある以上、それらをどう現在、および将来のビジネスニーズを踏まえ最適化していくかが私たちの腕の見せ所なんです。

第1フェーズ「インフラ構築」から第2フェーズ「シナジー創出」へ
── プラットフォーム統括部が目指す将来像について教えてください。
田渕: 私たちの取り組みには2つの大きなフェーズがあると考えています。
第1フェーズは、共通インフラの構築。グループ各社のサービスが連携し、共通化していくための土台作りで、現在まさにこのフェーズにあります。
そして本丸である第2フェーズ。基盤を活用したシナジー創出です。例えば、印刷事業を利用しているお客様に、そのビジネスニーズを踏まえて最適なタイミングで広告サービスや金融サービスをご提案する。これにより、お客様に新たな気づきと価値を提供し、グループ全体での相乗効果を生み出していきます。
二串: 率直に言って、これらの基盤実現は非常に大きな挑戦です。理想的な将来像を100%とするなら、進捗はまだほんの序盤段階にすぎません。道のりは長いですが、だからこそ未来を形づくっていく手応えがあり、大きなやりがいがあります。
田渕: 最近では、SaaSでお馴染みのインビテーション機能の共通化に取り組んでいます。管理者が法人メンバーを招待できる仕組みですね。
また、権限管理も重要なテーマです。管理者、編集者、参照専用といった基本的な権限分けから、「事業固有の権限をどう扱うか」まで、権限モデリングの設計にも本格的に着手しています。
── そんな難題に挑むプラットフォーム統括部が最も大切にしていることは何ですか?
田渕: 私たちのこだわりは、ユーザーセントリックであることです。
プラットフォーム統括部が向き合うのは、大きく分けてエンドユーザーとステークホルダー(主に社内の事業部)の2種類のお客様。日常的にはステークホルダーとのやり取りが中心になりがちですが、最終的に価値を感じてもらうべきはエンドユーザーです。
そのため、私自身もサービスを実際に使ってみるのはもちろん、カスタマーサポートに寄せられる声やSNS上でのユーザーの反応まで丁寧にチェックし、高い解像度で課題を実感できるよう心がけています。
二串:エンジニアとして開発に取り組むだけでなく、事業部とのフロント役を担うことも重要だと考えています。小さな成功体験を一緒に積み重ねながら、まずは事業部の皆さんに「安心して任せられる」と感じてもらうこと。それがファーストステップです。
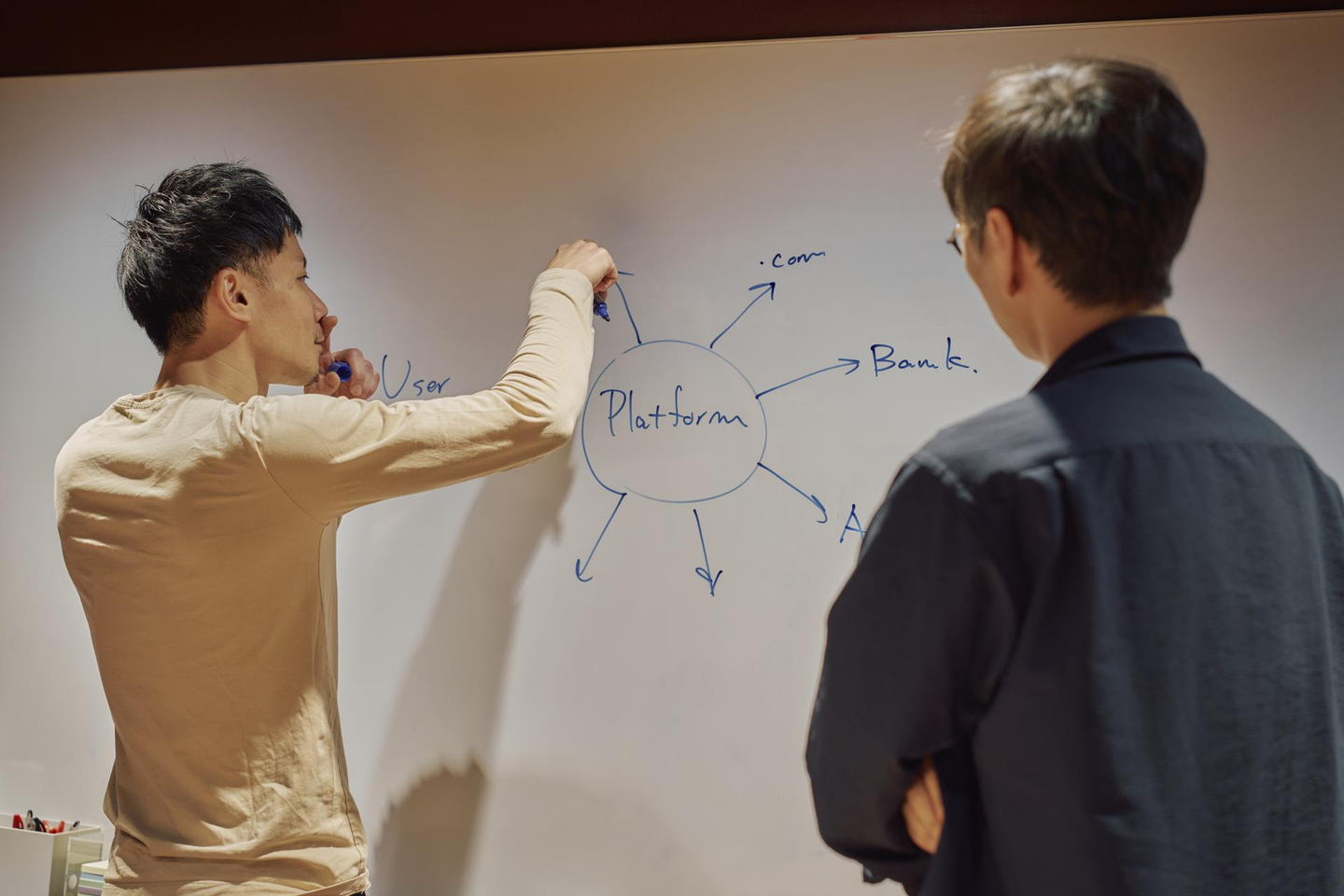
少数精鋭チームで実感する、圧倒的な「手触り感」
── 挑戦が始まったばかりのプラットフォーム統括部で働く魅力は何でしょうか?
田渕: 他社では100名規模で開発するようなID基盤を、私たちは10数名のチームで担当しています。この規模感だからこそ、自分のアウトプットがダイレクトに反映される実感があります。まさに「手触り感」のある開発ができるのが最大の魅力ですね。ベンチャー的なダイナミズムが残る環境でありながら、グループ全体のインフラを支えているという使命感とスケール感を同時に味わえる。これは本当に貴重な経験だと思います。
二串: 田渕さんの言う通り、プラットフォーム統括部では、古い開発プロセスの見直しや、AIツールの活用など、まだ最適化されていない部分の改善にも積極的に取り組んでいます。これからグループ全体の事業がスケールしていくフェーズだからこそ、ダイナミックな変化への対応が求められるのは、大きなチャレンジであり魅力と言えますね。
── プラットフォーム統括部の現在のチーム構成についてもう少し具体的に教えていただけますか?
田渕: プラットフォーム統括部は東京とベトナム(ホーチミン)の2拠点体制です。東京、ベトナムそれぞれにID基盤、決済基盤、そして法人基盤に関わるメンバーが在籍しています。
全体の規模は日本とベトナムを合わせて20名程度。プロダクトマネージャーは3名(日本人2名、インド人1名)と、グローバルなチームが一丸となって業務にあたっています。
── 今後のチーム拡大に向けて、どのような方と一緒に働きたいとお考えですか?
二串: 技術力だけでなく、プロダクトの特性を深く理解して技術をリードできる方を求めています。単に与えられた仕様を実装するだけでなく、「なぜその機能が必要なのか」「もっと良いアプローチはないか」を考え抜ける方ですね。
特に重視しているのは、積極的なコミュニケーション能力です。周囲に関心を持ち、プロダクトマネージャーや他職種のメンバーと積極的に議論・提案を重ねながら「なぜその仕様やリクエストが生まれたのか」を一歩踏み込んで考えられる方と働きたいです。
田渕: 英語力もあった方がいいですね。ベトナムチームとの連携では常にコラボレーションが生まれます。そのため、英語に拒否感がある方には厳しい環境な反面、たとえ流暢でなくとも、英語でコミュニケーションを取りながら成長していきたい方により適している環境だと思います。
── 最後に、 今、このタイミングでプラットフォーム統括部にジョインする価値は何でしょうか?
二串: 「エコシステムが回り始める瞬間」に立ち会えることが最大の価値だと思います。まだ立ち上がったばかりなので、まずは各事業部に「安心して共通基盤を任せられる」と感じてもらえるよう、信頼を築くことが重要です。やがて機能をどんどん預けてもらえるようになれば、エコシステムが回り始め、事業成長の加速器として機能し始めます。そのサイクルを一から作り上げていく過程に参画できる機会は、キャリアにとって非常に大きな価値があると確信しています。
田渕:プラットフォーム統括部は確かに「縁の下の力持ち」的な存在ですが、グループ全体の発展に直結する役割を担えることが最大の魅力です。ユーザー体験の向上という大きなゴールに向かって、チームで知恵を出し合いながら開発を進められるのは、とてもエキサイティングな経験です。
RAKSULグループのように、フィジカルプロダクトとソフトウェア・サービス系のプロダクトの両方を複合的に持つ会社は多くありません。印刷・広告・金融という全く異なる領域の要件を統合的に考える経験や、大規模なマイクロサービス設計、認証・認可基盤の構築、グローバルチームとの協働など、Tech人材として今後のキャリアに大きく寄与するスキルを幅広く磨けます。
そして組織の成長と共に自分も成長できる。グループの拡大に合わせて、責任範囲も影響力も確実に拡大していく変化の最前線で、リーダーシップやマネジメント力を実践的に磨けるのも大きな価値だと思います。

《編集後記》 次世代のBtoBエコシステムを、一緒に創りませんか?
プラットフォーム統括部は、RAKSULグループの成長を技術面から支える重要な部門です。「個人商店からショッピングモール」へと発展していくイメージを重ねつつ、基盤開発の拡張に挑んでいます。
複数事業を統合した一貫した顧客体験の実現という、他では経験できない規模の挑戦。そして、自分の貢献を直接実感できる「手触り感」のある開発環境。インタビューの最後には、二串さん、田渕さんが口を揃えて「活躍できるところがたくさんあるので、ぜひ一緒に働きましょう!」「めちゃめちゃ楽しいので、待ってます!」と、この記事を読んでくださる方に向かってメッセージをくれました。
🚀 挑戦はまだ始まったばかり。だからこそ、あなたの貢献が未来を創る。二串さん、田渕さんと一緒に、RAKSULグループの次なる10年を技術で切り拓いていきませんか?
ラクスル株式会社 エンジニア ラクスル の求人一覧ラクスル株式会社 エンジニア ラクスル の求人一覧です。| HRMOShrmos.co
/assets/images/7551041/original/20bdeac1-7344-4221-93f2-9da6ddfa2469?1631844804)

/assets/images/7551041/original/20bdeac1-7344-4221-93f2-9da6ddfa2469?1631844804)


/assets/images/7551041/original/20bdeac1-7344-4221-93f2-9da6ddfa2469?1631844804)
/assets/images/7551041/original/20bdeac1-7344-4221-93f2-9da6ddfa2469?1631844804)

