こんにちは!バニッシュ・スタンダード HR&Culture(以下、HR)チームリーダーの大山です。
私事ながら、バニッシュ・スタンダード(以下、VS)に入社してから約1年を迎えました。光陰矢の如し。激動の1年でした。この1年間で、HRチームにはたくさんの変化がありました。メンバーも1名から3名に増え、VSの採用の形が徐々に出来てきました。さらには採用だけでなく、人事評価制度の見直しなどなど…たくさんの改善を行ってきました。
今回は、そんなHRチームの取り組みのなかでも「入社オンボーディング」をテーマに記事を書いてみたいと思います。
振り返ってみると、改善前の入社オンボーディングは恥ずかしながらとても簡易的なものでした。採用担当にてPCキッティングや業務使用するツールの説明を行ったり、組織や社内ルールの説明をしたり、パーパス・バリューの説明をしたり…。多くの情報を短時間で詰め込んでいくような設計になっていました。
今回は、そんな反省をもとに再設計した現在の入社オンボーディングプログラムをご紹介します!
VSの目指す入社オンボーディングって?
「入社オンボーディング」とは、一般的に「企業が新たに採用した人材を職場に配置し、組織の一員として定着し、戦力になるまでの一連の受け入れプロセス」を指しますが、VSでは「組織への定着」と「戦力化」という一般的な目的に加えて「自分らしさを発揮しながらスムーズに仕事ができる」状態までサポートすることを目指しています。
”新入社員が「自分らしさを発揮しながらスムーズに仕事ができる」状態にする”
このゴールに到達するために、HRチームがすべき必要なサポートとは何か?新しい入社オンボーディングプログラムの設計にあたっては、以下の3つのポイントを意識しました。

入社時はとにかく不安でいっぱいになるものですよね。HRチームでは、特に不安を感じやすいポイントを以下の3点だと考えています。
- 知りたいことがあるけど、どこに情報があるかわからない!
- 困ったときに、誰に聞けばいいのかわからない!
- 早く会社に馴染めるようになりたいけど、交流する機会がない!
スピード感のあるスタートアップだからこそ情報のキャッチアップは非常に重要です。入社オンボーディングを通じて、必要な情報に効率的にアクセスできる方法を落とし込むこと、「何か困ったことがあってもこの人に頼ればなんとかなる」という安心材料をいち早く提供すること、幅広いメンバーとの交流の機会を早期に創出することをコンセプトに据えています。
新しいVS入社オンボーディングでは、入社1ヶ月後には「自分らしさを発揮しながらスムーズに仕事ができる」状態に到達することを最終目標に、週次ごとに中間目標を設定する形に設計しています。週次目標に紐づくタスクをチェックリスト化し、進捗が見える形にすることで新入社員も達成感を味わえ、HRチームや現場も進捗を共有できる形を目指しました。

↑1週間の目標に紐づく細かいタスクをチェックリスト化して進捗を管理
入社オンボーディング、実際どんなことをしているの?
新しい入社オンボーディングは、ざっくりと以下のカテゴリーに分かれています。
- 座学
- 交流
- 振り返り
今回は、入社初日とそれ以降という2つのパートに分けて内容を紹介したいと思います!
入社初日編

①座学
・人事&CorporateIT&労務担当者による各種説明タイム
日々の業務で利用する社内ツールやデバイスの説明、そしてセキュリティに関する研修はもちろんのこと、日々の勤怠や精算、その他各種労務手続きに関する説明を行います。各担当者がマンツーマンで教えてくれるため、何かあった時にすぐに相談できる関係値もこの時間で構築できます。
・代表小野里が語る事業&プロダクト紹介
入社初日のコンテンツとして、小野里自身が事業とプロダクトについて紹介する時間を設けています。「どのような想いから『STAFF START』が生まれたのか?」「私たちがこの事業を通じて成し遂げたいことは何か?」など、代表が熱く語ります。私たちはなんのために仕事をしていくのか、という本質を知ることができる大切な時間です。
・CCO:磐井によるバリュー解説
CCO(Corporate Culture Officer)もといバリュー大臣である磐井(通称:TOMOさん)がVSのバリューについて解説します。一つひとつのバリューに込められた意味やバリューに基づいたGood/Badアクションなど、VSが大切している価値観を深掘りできる時間です。
②交流
・ユニットウェルカムランチ
入社当日には配属ユニットやチームのメンバーとのランチ会を設けています。VSに入社してくれてありがとうの気持ちを伝えることはもちろん、一緒に仕事をしていくメンバーの顔と名前を覚えていただきやすくすることがねらいです。
③振り返り
・入社初日アンケート
入社初日を過ごしてみての満足度や、各種説明事項の理解度を振り返っていただくアンケートを回収しています。理解度に応じて追加のフォローをしたり、入社オンボーディングプログラムの見直しに活用させていただいています!
・初日の振り返りをお助けする「VS Portal-newcomer」
入社当日は、会社や組織のことをはじめ、会社の歴史や事業内容、パーパス・バリュー、人事評価制度や福利厚生、社内ルールなどなど…多くの説明を行います。ですが、すべての内容を1日で覚えるなんて正直難しいですよね。そこで、入社オンボーディングで紹介した内容のほか、入社後に役立つ情報をまとめたお助けページ「VS Portal-newcomer」を作成し、いつでも振り返りができる仕組みを整えています!

入社初日以降編

時系列ごとにまとめると上記のような流れで進んでいきます。初日は座学が中心でしたが、2日目以降は交流と振り返りがメインになっています!
①座学
・各ユニットマネージャーによるユニット説明
各ユニットマネージャーが、ユニットミッションや業務内容、担当メンバーについて解説する時間を設けています。自分の配属先と連携が多いユニットなど横のつながりを早めにイメージできる&誰がどんなことをしているのかがわかる時間になっています!
②交流
・全社共有会で自己紹介
バニッシュでは月に1回、全社OKRや各ユニットOKRの進捗をはじめ、全社的に伝えたい情報をシェアする「全社共有会」を開催しており、新入社員の紹介もこの場を借りて行っています!自己紹介スライドを作成してもらい、5分ほど自己紹介をお願いしています。趣味の話や好きなものの話など、何を書いてもOK!自分らしさ全開でお願いしています!
・新入社員歓迎会
ユニットや肩書きなど関係なく、幅広いメンバーと交流できる場も設けています。ピザやケ○タ○キーなど軽食を頼んで、オフィスでわいわい過ごすことが多いです。社員の意外な一面を知ることができたり、ここで仲良くなったことをきっかけに業務上でのコラボレーションが生まれたりする大切なイベントです。
・HRチームとのランチ
入社後1週間後(目安)にはHRチームとのランチを設定しています。どちらも歓迎会としての意味合いが強いですが、HRとのランチは選考〜入社を体験してみてどうだった?という選考体験ヒアリングの意味も持っています。入社オンボーディングを通じて、VS採用のいいところ、悪いところをキャッチアップしながら次の採用に繋げていく取り組みを行っています。
・代表小野里とのクォーター同期ランチ
VSでは年間を通じて積極的に採用を行っており、毎月のようにメンバーが増えることもしばしば。一方で、同じ日に入社した「同期」がいない!今月の新入社員は自分だけ!というパターンも多いです。そこで、同じクォーターに入社した人を「クォーター同期」として、入社3ヶ月後を目安に小野里とのランチ会を設けています。
③振り返り
・定期アンケート(入社2週間後・入社1ヶ月後)
VSでは入社初日以降も定期的にアンケートを実施しています。時期ごとに少しずつアンケートの項目も変えており、その時々における事業や業務の理解度、会社や部署に対する満足度、疑問や要望を回収しています。回答内容については必要に応じて所属Mgrにも共有し、HRチームだけではなく現場でもフォローできる環境づくりを目指しています。
・360度フィードバックアンケート
入社3ヶ月後には、業務で関わりの深いメンバーやMGRから新入社員に向けての360度フィードバックをアンケートという形で回収しています。一緒に働くなかで見えた強みや今後の課題を客観的に回答してもらっています。
・定期面談
新入社員の悩みや課題をキャッチアップし、サポートすることを目的にアンケートを回収するタイミングにあわせたHRとの1on1も実施しています。特に入社3ヶ月後に行う面談では、360度フィードバックの内容を共有し、自分自身のGoodポイントや改善点を把握することでモチベーションの向上にお役立ていただけるようにしています!

どんどんブラッシュアップしていくぞ!今後の展望!
VSの入社オンボーディング紹介、いかがでしたでしょうか?
かなり大きな改善を図ってきたところではありますが、まだまだ目指す理想には届いていないと感じており、今後もコンテンツの量と質を高めていきたいと目論んでおります…!
たとえば内定〜入社までのサポートなど、できることはまだまだあると感じています。直近では内定者向けのコンテンツ拡充にも着手しており、内定承諾〜入社までに知っておいた方が便利なことやスピーディーな立ち上がりのために必要な情報をまとめた「内定者向け特別サイト(エントリーブック)」を作成するなど、より手厚いサポート体制を作るべく奮闘中です。
よりよい選考体験をつくっていくだけでなく、よりよい入社体験・就業経験をつくっていくためにこれからも頑張ってまいります!
/assets/images/4717538/original/1f70e309-9769-47a8-b29a-dcdf24db19ad?1583323461)

/assets/images/4717538/original/1f70e309-9769-47a8-b29a-dcdf24db19ad?1583323461)


/assets/images/4717538/original/1f70e309-9769-47a8-b29a-dcdf24db19ad?1583323461)



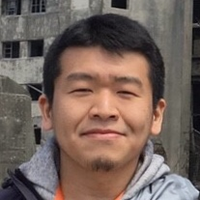
/assets/images/17191315/original/1f70e309-9769-47a8-b29a-dcdf24db19ad?1709532316)

