- バックエンドエンジニア(Go)
- 27卒ビジネス職
- ゲーム|バックエンドエンジニア
- Other occupations (20)
- Development
- Business
※2025年5月20日時点の記事です
スマホ1台でゲーム実況ができる配信プラットフォーム「Mirrativ」を運営するミラティブは、2018年の創業以来、「新しい市場」の創造に挑戦し続けてきました。2025年現在、社員数140名超の規模に成長し、業績も順調に伸びていますが、思い描く未来に向かって歩みを止めることなく、世の中にインパクトを与える新規事業に取り組んでいます。
今回は代表取締役CEOの赤川さんと、2024年に入社し新規事業に取り組む馬島さんに、新規事業への想いや、市場創造の面白さについて話を伺いました。
▼本記事のダイジェスト動画はこちら
代表取締役CEO 赤川 隼一
慶応義塾大学環境情報学部卒業後、2006年にDeNAへ新卒入社。2012年4月より最年少執行役員として海外事業、ブラウザゲーム事業などを管轄。2015年、スマートフォン画面を生配信するライブストリーミングサービス「Mirrativ」を開始。2018年3月に、Mirrativ事業をDeNAからMBOする形で株式会社ミラティブを創業し、現在までに累計100億円超を資金調達。「わかりあう願いをつなごう」をミッションに、日本発の新たなコミュニケーションの形を世に展開。
社長室 プロデューサー 馬島 淳
新卒で株式会社オルトプラスに入社。IPを中心とした数々のスマートフォンゲームのリーダーやディレクター、プロデューサーを経験後、2019年に株式会社ScopeNextの立ち上げと同時にジョイン。2022年に同社執行役員としてゲーム事業を統括。2024年に新規事業のプロデューサーとしてミラティブに入社。
CEOが新規事業にフルコミットするのがミラティブ流
──代表取締役である赤川さんは、新規事業にどのように取り組んでいますか?
赤川:創業から7年、ミラティブは順調に成長し、利益も右肩上がりに伸びています。現在は、「わかりあう願いをつなごう」というミッションと、「好きでつながり、自分の物語が生まれる居場所」というビジョンのもと、世の中に大きなインパクトを与えるべく、新たな領域に挑戦しています。
130名を超える規模の会社なので、0→1の新規事業にはトップが直接関わる方がうまくいくと考え、既存事業を権限委譲した上でフルコミットしています。社内で小さく検証して大きくしていくのが基本的な考え方・得意な型ですが、加えて、ケースに応じてできたばかりの会社ではない強みも活かしています。具体的には、初回から大胆に投資をしたり、M&Aや協業といった手段を選んだりと、ダイナミックに新規事業を進める経営判断を都度行っています。
──馬島さんは、新規事業に関わるポジションで転職されたそうですね。どのような経緯があったのでしょうか?
馬島:前職ではソーシャルゲームデベロッパーで執行役員として、ゲーム事業部を統括していました。退職時にご挨拶して回っていたところ、面識のあった赤川さんから「何らかの形で一緒に仕事をしてみませんか」と声をかけていただいたんです。
赤川さんから新規事業の展望を聞いて面白そうだと感じましたし、赤川さんご自身にも惹かれました。その後も経営陣と話を重ねていくなかで、ミラティブで働く自分の姿がリアルに想像できたので、入社を決めました。
世の中に新しい価値を提供してきたミラティブの歩み
──市場のないところに挑戦し続けてきたミラティブの歴史を教えてください。特に印象に残っている新規事業はありますか?
赤川:前提として「すべてのビジネスが0→1でなくてはならない」とは考えていません。ただ、ミラティブの場合は、もともと世の中に新しい価値を創造するのが好きな会社であり、新規事業・新しいユーザー体験を通じて人々に熱狂を届けるサービスを創り上げてきた歴史があります。
スマホ1台で簡単にゲーム実況ができたり、手軽にバーチャルアバターを使って配信できたりするサービスを世界で最初に提供したのは、私たちミラティブです。そのほかにも、ゲーム会社さんと一緒に配信者の活動を盛り上げる「配信視聴キャンペーン」や、ゲーム実況に特化したライブゲームの立ち上げなど、それまで世の中になかったUXに何度も挑んで成立させてきました。
どの取り組みも印象深く、一つに絞るのは難しいですね。一貫して心がけてきたことは、市場の流れを見ながらも、とにかく「人に欲しがられるものを作る」ことです。泥臭くお客様に向き合って本質的な需要をつかみ、サービスを創り、育ててきたからこそ、今のミラティブがあると思っています。
──馬島さんが、そうしたミラティブのマインドを体感した瞬間はありましたか?
馬島:2024年に入社して最初に取り組んだのが、YouTubeで活動しているVTuberの方々約30名を招いて行った、ライブゲームのランキングイベントです。Mirrativ以外のプラットフォームで活動する配信者さんにアプローチするのは、ミラティブとして初の試みでした。
配信者さんがどれくらいの時間を割いてくれるのか、上位層がどれほどのスコアを出すのかなど、すべてが手探りでの施策設計でした。でも、仮説を立てて実践するなかで気づきが得られ、課題も見えてきました。このプロセスを通して、「仮説を立てる・小さく検証する・大きくしていく」というミラティブのマインドを実感しました。
「人」に向き合いニーズを見極めれば答えは見えてくる
──ミラティブの新規事業が成功している要因は、どこにあると思いますか?
赤川:基本は「人に欲しがられるものをつくる」ことに尽きると思います。たとえば、お客さんが手間ひまかけてでも何かをやっていることを見つけたら、そこにはすでに熱量があります。その面倒な部分をショートカットするだけでも、十分ニーズに応えられるはずです。
「Mirrativ」もすべてをゼロから発明したわけではありません。Mirrativが登場する前から、パソコンやさまざまな機材を準備して、煩雑なセッティングを乗り越えてゲーム実況をしていた配信者さんはたくさんいました。僕たちは、それをスマホ1台でできるようにしただけなんです。
つまり、ミラティブは需要を生み出したのではなく、すでにある需要を観察してすくい上げて、事業の形にしたのです。新規事業の成功要因を挙げるなら、「欲しがられるものをつくろう」「欲しがられるかどうかを検証しよう」という姿勢を徹底していることだと思います。
昔はなんらかの理由で難しかったことでも、テクノロジーや新しい価値観が普及すれば実現できることがあります。それらの「種」を、自分たちの顧客解像度の高い領域、ミラティブで言うと配信者のニーズと組み合わせれば、非連続な成長曲線を描ける可能性が広がります。
ミラティブは、ライブ配信、ゲーム実況、エンターテインメント、ソーシャルネットワークのプロフェッショナルです。顧客に向き合いながら培ってきた知見に「型」を掛け合わせて、新規事業を生み出していくことを大切にしています。
──馬島さんが、新規事業プロジェクトに関わるなかで感じた“ミラティブらしさ”を教えてください。
馬島:赤川さんの考えは社内にも浸透していて、ミラティブのメンバー全員が「ユーザーが何を求めているか」を強く意識して仕事をしています。
先ほどお話ししたライブゲームのイベントでも、メンバーは配信の不具合がないかを監視するだけではなく、「楽しんでもらえているか」をリアルタイムで見て、裏で議論を続けていました。エンジニア、PdMなど職種に関係なく、一人ひとりがユーザーさんに向き合っている姿勢に、ミラティブらしさを感じます。
赤川:ユーザーさんと向き合うことで自然と見えてくる“ペイン”を解消することを、大切にしています。Mirrativは、ユーザーさんがどんなふうにアプリを触っているかを、配信を見るだけですぐに把握できるサービスです。行動から見えるピュアな本音に向き合い、リアルな需要に応えていく。それが、「欲しがられるものをつくる」ための第一歩だと考えています。
トレンドを目的化して需要を妄想しないことが大切
──世の中にない市場を切り拓く上で、大切にしている考え方を教えてください。
赤川:「人に欲しがられるものをつくる」コツとして、「需要を妄想しない」「概念から事業を作らない」は重要です。たとえば、メタバースがブームになったときも社内でよく言っていたのは「お客さんが欲しいのはメタバースという概念ではない」ということです。「メタバースを使いたいです!」というお客さんは見たことがなく、求めていたのは「オンラインで時間を忘れて話せる場所・自分の居場所を得られること」で、そういう体験がFortniteなどのゲームやVRChatにはありました。それらを業界が「メタバース」と後付けで命名しただけです。AIも同様で、「AIを使うから良いサービスになる」のではなく、「AIを使うことで、お客さんの課題が解決される」からこそ、ビジネスになるのだと考えています。お客さんを観察する中で見えてくる「課題」から事業を組み立てます。
馬島:メタバース、Web3、AIなど、流行している技術や概念は、あくまで手段に過ぎません。望む未来を実現するために最適な手段であれば取り入れればよいと思いますが、「AIを使えばきっと良いものができる」という思い込みでは、ビジネスはうまくいきません。
目的と手段を取り違えないこと。これはすべてにおいて重要です。課題解決のために最適だからこそ新しいツールを使う、という意識が大切だと思います。
──現在、まさに新しい市場に挑んでいる中で、どのようなことを感じていますか?
馬島:ワクワクする気持ちと同じくらい、不安もあります。新規事業が難しいのは、ベンチマークが圧倒的に少ないことです。前例のないところから何かをつくり出すのは大変ですが、自分たちでルールや正解をつくれる楽しさも感じています。
赤川:新規事業が百発百中なんてことはありえません。既存事業でさえ、仮説検証のなかで失敗をゼロにするのは不可能です。数々の成功の裏には、それ以上の失敗がありますから、いかに失敗のリスクを最小限に抑え、試行回数を重ねられるかも重要です。
馬島:ミラティブは、「大胆に考える」という行動指針があるように不確実性の高いトライにも寛容なカルチャーがあります。赤川さんをはじめとする経営陣も、失敗を許容して背中を押してくれるので、そこには心理的安全性があります。「失敗が怖いから挑戦しない」という選択肢は、ここにはありません。
赤川:「いくらでも失敗していいよ」というわけではありませんが、仮説が正しいかどうかは「最後はやってみなければわからない」というのが僕たちの考え方です。もちろん、挑戦する側の熱量が高く、「うまくいくはず・需要に応えられるはず」と信じられる解像度を持っていることが前提ですが、全力でトライして得られた結果が思わしくなかったときは、それもまた大切な学びだと捉え、次につなげることを重視しています。
新しい挑戦の先にある事業成長と海外進出の展望
──今後、新規事業を通じて、ミラティブをどんな会社にしていきたいと考えていますか?
赤川:掲げているミッションとビジョンを実現するには、まだ長い道のりがあります。だからこそ、ミラティブをより大きな会社にしていきたいという思いがあります。既存事業で培ってきたものを活かしつつ、新規事業という新しい山を立てて、これまで見たことのない景色を見たいですね。
実は、これまでに3回、海外展開にチャレンジしたことがあります。どれも全力で仮説検証しましたが、結果的にはうまくいきませんでした。今取り組んでいる新規事業の先には、今度こそ日本を超え、世界中の人たちに価値を届けられるかもという手応えも感じています。一足飛びにはいきませんが、今の新規事業群が、ミラティブをまったく新しいスケールの会社へと引き上げてくれることを期待しています。とても優秀なメンバーが集まり、より良いプロダクトをつくっているので、それをより多くの人に届けていくことが経営者としての使命です。
テクノロジーを「道具」と捉えると、誰もがクリエイターになれる時代が来ています。これからは、その道具の使い方も種類もますます多様化し、クリエイターや配信者の数もさらに増えていくでしょう。ミラティブは、そんな伸びしろのある市場に対し、新規事業を通じて新たな価値を創出していきます。
馬島:クリエイターや配信者として生計を立てるライフスタイルは、今後さらに身近なものになっていくと思います。私自身がVTuberになることを考えているほどです。ミラティブの新規事業に携わることで、クリエイティブな活動を通じて人々の幸せが循環するような世界をつくっていきたいです。
ーー最後に、新規事業に興味がある人、これから一緒に働くかもしれない人へのメッセージをお願いします。
馬島:新規事業という言葉だけを見ると、ワクワク感や成長できそうというポジティブな印象を抱くかもしれません。それも間違いではありませんが、輝かしい成功の裏には、何十倍もの失敗があります。
そんな失敗を成功の糧にできるモチベーションがある方と一緒に働き、この先にある成功をともに手にできたら嬉しいです。
赤川:新しい価値を生み出すことに、たった一つの正解はありません。事業のフェーズによって最適解は変わりますが、今のミラティブには、これまでの経験から得た新規事業のつくり方の型があります。これから0→1に挑戦したい人にとって、経験を通じて学びを得られる環境だと伝えたいです。
既に作品やサービスはあふれている世の中で、「世の中にない新しいものをつくりたい」という気持ちは、ほとんど衝動のようなものです。でも、その衝動や願いの連続こそが、世の中を少しずつ前に進めてきたと思います。自分自身もそうした衝動を持っているからこそ、はっきり言えるのですが……0→1って、やっぱり面白いんです。しんどいけど面白い、ひとりでやるよりもチームでやるから遠くまで速く行ける。個人としてやりたい理由と、チームでやる理由とがかみ合ってこそ、一緒に取り組む意義があります。お互いに助け合いながら新しい場所を創り、多くの人の願いをつなげて幸せや価値を生み出せたら——こんなに面白いことはありません。
今回の記事を読んでミラティブの未来に興味を持ってくださった方は、ぜひ一緒に、新しい価値を創っていきましょう。

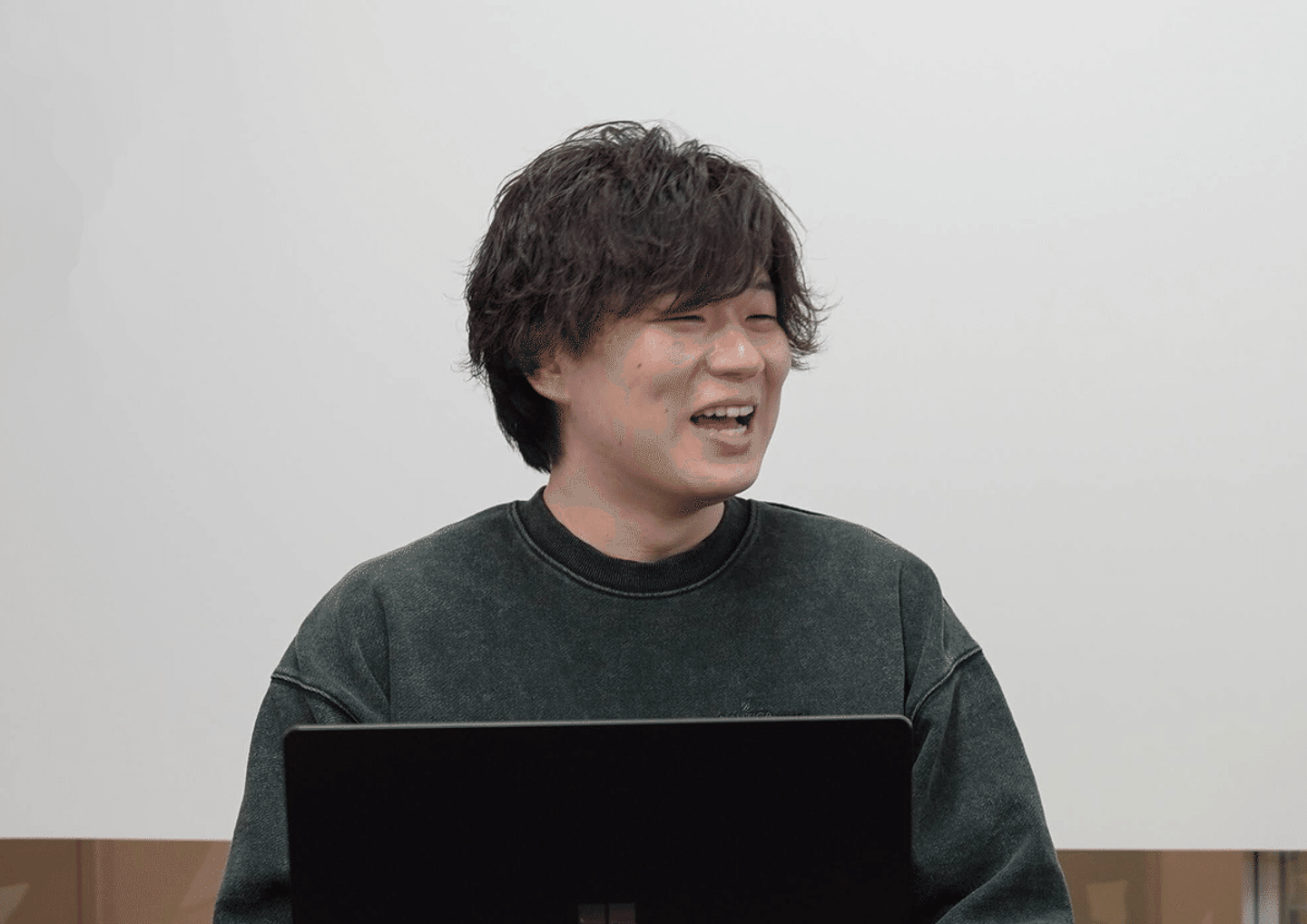

/assets/images/19694158/original/c23e68c2-c645-4f59-8cb6-495e6a473033?1731491678)

/assets/images/8133032/original/32a0a73e-8fe1-49bc-a9b7-626ef356c962?1637051623)
/assets/images/8133032/original/32a0a73e-8fe1-49bc-a9b7-626ef356c962?1637051623)

