manaby Campus柴田で事業所マネージャーを務める長谷川さん。運営と支援の両面から現場を支え、職員との対話を重ねながら、子どもたちの成長を見守っています。事業所の枠を超えた体制づくりにも関わり、地域に根ざした支援環境の構築に挑戦中です。
【プロフィール】
長谷川光
2024年7月入社
manaby Campus柴田 事業所マネージャー
※2025年8月現在
原点は、震災と先生との出会い
-今の仕事、どんなことをされていますか?
子どもたちへの支援と、事業所マネージャーとしての運営管理を両立しています。シフト調整や採用・育成などの人材業務に加え、支援の質向上にも取り組んでいます。
また、事業全体の体制づくりにも関わり、現場と経営をつなぐ役割として、情報共有や環境整備を通じて、より良い支援の場をつくることを目指しています。
-教育に関わる道を選んだきっかけは?
高校時代に出会った恩師の存在です。それまでは、教育に関わることなど全く考えていませんでした。
私は福島県いわき市の出身で、中学時代は卓球に打ち込んでいました。スポーツ推薦で高校進学を目指していましたが、地域の高校には推薦枠がなく、一般受験をすることに。しかし第一志望には届かず、進路に悩んでいた矢先に震災が起こり、将来への不安でいっぱいになりました。
そんな中、すでに募集が終了していた進学高校に震災枠が新設され、運よく合格。その高校で出会ったのが、私の人生を変えてくれた恩師です。
成績が振るわず進級の危機に陥ったとき、先生が一緒に教科担当の先生に頭を下げてくださったこともありました。生徒に本気で向き合う姿に心を打たれ、「こんな大人になりたい」と強く思うようになりました。
その経験が原動力となり、大学では教職課程を選択。中学校の社会科、高校の公民科の教員免許を取得しました。
教育への道へ
―学校の先生を目指されていたのですね
はい。大学時代は教員を志しながら、学校や塾に通えない子どもたちに学習体験の機会を届けるボランティア活動にも取り組んでいました。
その活動を通じて、「教育に関わる方法は学校教員だけではない」という気づきがあり、学習塾や放課後等デイサービスなど、より多様な教育の場にも関心を持つようになりました。
-卒業後は?
ボランティア活動で知り合った方の紹介で、地域の学習塾に総合職として入社しました。最初は運営部門を担当しましたが、慣れない業務や人間関係に悩むこともありました。
その後、現場に異動となり、子どもたちと直接関わるようになってからは、少しずつ仕事が楽しく感じられるようになりました。教室長として教室運営にも携わりました。
-転職のきっかけは?
ちょうど悩んでいた時期に、ボランティア時代の友人から「子ども向けの支援事業を始めるので、一緒にやらない?」と声をかけてもらったんです。
その友人が、現在manabyの教育支援事業部のリーダーを務める菊地さんです。友人と仕事をすることに不安もありましたが、菊地さんなら信頼できると思い、挑戦することを決めました。
-菊地さんとは学生時代からのご縁だったんですね
そうなんです。大学は違いましたが、同じボランティア団体で濃密な時間を過ごした仲間です。
その団体では、いくつかの事業部を学生主体で運営していて、私たちはリーダーとしてそれぞれ事業を任されていました。終電まで議論して、朝帰りするような熱い日々を共に過ごした、大切な仲間です。
正解がないからこそ、対話を大切に
-やりがいを感じる瞬間は?
子どもたちの笑顔や、苦手なことができるようになった瞬間ですね。もう、本当にかわいくてたまらないです。
前職の塾でも、「100点が取れた!」「進学先が決まった!」という報告はもちろん嬉しかったですが、学校に通えなかった子が少しずつできることを増やしていったり、大人との関わりの中で自信を持ってくれる姿を見ると、心からやりがいを感じました。
生きづらさを抱える子が、ほんの少しでも自信を持てるようになる。その瞬間に立ち会えることは、何よりの喜びです。
ほかにも、自己肯定感が低かった子が一歩踏み出せたときや、保護者の方から「ありがとう」と声をかけていただいたときなども、支援の意義を実感します。現場で得た学びや成長を、卒業後もずっと応援していきたいと思っています。
-支援の難しいところは?
障害のあるお子さんへの支援は、初めてのことばかりで戸惑うことも多かったです。身体介助や食事支援なども含めて、日々学びながら取り組んでいます。
言葉でのコミュニケーションが難しい子、自傷行為が出てしまう子もいて、最初は本当に悩みました。教科書通りにいかないことも多く、現場で一人ひとりに向き合うことの大切さを痛感しています。そのためにも、スタッフ同士の対話が何より重要だと感じています。
「どういう声かけなら本人が納得できるか」「この子には絵カードで伝えるのがよさそう」「1日の流れを先に説明して、見通しを持てるようにしよう」など、個性や状況を丁寧に見つめながら、チームでアイデアを出し合って、より良い支援を模索しています。
学校の先生や保護者の方ともよく話をします。先日は先生が事業所に様子を見に来てくださることもありました。支援員、先生、保護者、そして関係機関の皆さんが、チームとして子どもたちのことを一緒に考えていけるといいなと思っています。
地域に根ざした信頼の輪を広げたい
-どうやって地域のみなさんと関係づくりをされるのですか?
放課後等デイサービスでは送迎も行っており、支援学校にお迎えに行くと、他の事業所の方々と顔を合わせる機会があります。待ち時間にコミュニケーションを取ることも多く、「よければ事業所に来てみませんか?」と声をかけて、支援に関する情報交換をすることもあります。
また、相談支援事業所や学校の先生とも連携していて、事業所に来ていただき、子どもたちの様子を見てもらうこともあります。午前中の時間を活用して、こちらから足を運び、連絡を取り、関係を築いていく。そうした積み重ねが、紹介につながったり、新しい取り組みをスムーズに進める土台になると感じています。
-目指している事業所の姿は?
事業所があるのは宮城県の県南地域。ここは地域の絆が深く、昔ながらの「顔の見える関係性」が根づいている場所です。
まずは私たち自身が行動を重ねて、「子どものことをたくさん考えている」「相談しやすい」「県南といえばmanabyだよね」と思っていただけるような、信頼される事業所を目指しています。
-最後に、どんな人と一緒に働きたいですか?
「これが正解」と決めつけるよりも、「こういうのもあるかも」と一緒に試行錯誤できる方が合うと思います。
寄り添える人、相手の気持ちを想像して助け合える人。そんな仲間とともに、地域に根ざした、信頼される事業所をつくっていきたいです。




/assets/images/18558328/original/aa071eb6-e4de-4595-b3ea-f7b54e007183?1720751488)


/assets/images/18558328/original/aa071eb6-e4de-4595-b3ea-f7b54e007183?1720751488)
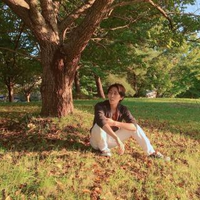
/assets/images/18558328/original/aa071eb6-e4de-4595-b3ea-f7b54e007183?1720751488)

