こんにちは、日本XRセンター人事部のmakiです!
今回は、日本XRセンターに2025年4月からベースUI/UX担当兼渉外顧問として参画いただいている、コヤさん(小山順一朗さん)にお話を伺いました!
コヤさんは、ナムコ(現バンダイナムコ)で100本以上のゲーム開発に関わり、アイドルマスターや戦場の絆などの筐体に加え、VR黎明期から日本のロケーションXRを牽引してきたレジェンド的存在。
VR施設「VR ZONE」シリーズの立ち上げや、フリーロームVRの開発、さらにはOculusとの初期からの関わりなど、日本のXRの「基礎を築いた」と言っても過言ではない方です。
そんなコヤさんがなぜ、スタートアップである日本XRセンターに参画を決めたのか?
そして、XRに込めた想いとは?
たっぷりと語っていただきました!
ー まずは自己紹介をお願いします!
Koya:
こんにちは、UI/UX監修および渉外顧問として参加しているKoyaです。
ナムコ(現バンダイナムコ)で長年ゲーム制作に携わり、アーケードゲームや家庭用ゲーム、そして業務用VR・XRアクティビティなど、100本以上のタイトルの開発に関わってきました。
中でも印象深いのは、「VR ZONE」シリーズの立ち上げです。日本でまだVRという言葉が一般的でなかった頃から、HMDを活用したVR体験や、空間を自由に動き回る“フリーロームVR”の研究・開発を続けてきました。
いま日本XRセンターでは、週に1回のペースで、XRゲームの体験設計・UX監修・プロトタイピングのフィードバックなどを行いつつ、社外連携やパートナー開拓の渉外面でもお手伝いしています。

ー バンダイナムコ研究所など、第一線で長くご活躍されてきたKoyaさんですが、退職されたご経緯と、日本XRセンターへの参画を決めた理由を教えてください。
Koya:
1990年4月に新卒で株式会社ナムコに入社して以来、ずっとゲーム開発部門で働いてきました。去年、そのキャリアに一度区切りをつけて退職しました。
在籍中に関わったタイトルは、100本以上になると思います。
ー 100本以上!すごいですね。当時は今とはかなり時代背景も違ったのでは?
Koya:
はい、当時のビデオゲームに対する世間の空気感って、いまの皆さんにはちょっと想像がつかないかもしれません。
たとえば、
大学の教授からは「もっとちゃんとした仕事に就きなさい」
と言われました。
僕が就職活動をしていた1989年当時、ゲーム業界は、理系の大学生が目指す業界としては完全に“圏外”だったんです。
地元・静岡県東部では、小中学生はもちろん、高校生も校則でゲームセンターは禁止。
ゲームセンター=不良の巣窟、というのが当時の一般的なイメージでした。
ー 世間の見る目は、かなりネガティブだったのですね。
Koya:
ええ。世の中はバブル景気で、僕の大学の友人たちはNEC、トヨタ、三菱重工といった大手メーカーのほか、商社、アパレル、新聞社、出版社、証券会社など、そうそうたる企業にどんどん就職していきました。
そんな中で僕は「ナムコに行きます」と言ったんですが、ナムコを自動ドアとか冷蔵庫の会社と勘違いされたこともありました(笑)。
しかも当時は東証二部に上場したばかりの頃だったので、叔父や大学の教授からは
「せっかく一部上場企業に入れるのに、なんでそんな不良のたまり場で商売してるようなアングラな仕事に就くんだ!」
と何度も諌められました。
ー それでも、迷いはなかったですか?
Koya:
はい、全くなかったですね。
当時の家庭用ゲームといえば、ファミコン。
子どものおもちゃという扱いで、大人たちからすると、子どもたちが外遊びをしなくなって、部屋にこもって夢中になる、理解できない“気味の悪い機械”のような印象だったと思います。
「ゲームばかりしてるとキレやすくなる」とか「ゲーム脳になる」なんて説がまことしやかに語られていて、識者が報道番組で真剣に議論してたんですよ。今聞いたら笑い話ですけどね(笑)。

ー そんな時代背景の中で、ゲーム業界に進む強いモチベーションがあったんですね。
Koya:
そうですね。
ファミコンはもう成熟期を超えて衰退期に入っていて、PCエンジンやメガドライブが盛り上がってきていた頃でした。
でも僕にとって「ホンモノのゲーム」はゲームセンターにあるものだったんです。家庭用ゲームはあくまでその代替品という感覚で。
特に、セガとナムコは別格でした。
見たことも聞いたこともないような遊びやデザインを次々と生み出す、新進気鋭のアートとテクノロジーの発想集団という印象が強くて。まさに脳に刷り込まれるようなインパクトでしたね。
それに、糸井重里さんのコピーに完全にやられました。
「クーソーしてから寝てください」「遊びをクリエイトする」――もう痺れました。
その頃にはもう、叔父や教授の忠告はまったく耳に入らなくなってました(笑)。
ー ナムコでの働き方や雰囲気は、実際どんな感じだったんでしょうか?
Koya:
ちょうど男女雇用機会均等法が適用された直後の時代で、まだまだ「女性は25歳で結婚退職」が当たり前とされていた中、ナムコは性別関係なく、クリエイティビティで尊敬される社風でした。
面白いモノを追求する人にとっては天国のような場所でしたよ。
そのためのルールは、驚くほど自由で。
もちろん、ゲームだけじゃなく、あらゆる「遊び」や「技術」を研究し放題。
深夜までワイワイガヤガヤ、まさに学園祭の前夜のような毎日でした。
横浜のナムコ未来研究所は「不夜城」と呼ばれていましたし、残業200時間なんてざらでした。

ー 現代ではちょっと信じられないですね…!
Koya:
そうですね(笑)。でも、楽しかったです。
当時のナムコは、なんと日本初のポリゴンチップ(※ポリゴン=立体的な3Dモデルを描画するための基本単位を処理する専用半導体)を自社開発していたんですよ。
今でいうnVIDIA(※高性能なグラフィック処理を専門とする米国企業)のようなことを、社内でフルスクラッチでやってた。3DCG(※立体的なコンピュータグラフィックス)という概念自体が日本にはまだ存在していなかった時代なので、CG作成ツールも全部自前。
世にないものは、自分たちで一から作る。そんな天才たちの中に飛び込んだのが、僕のスタートでした。
ー ナムコ時代には、かなり早い段階からXR(当時の言葉で言えば「バーチャルリアリティ」)に関わってこられたそうですね。
Koya:
そうなんです。
僕が初めてHMD、つまりVRゴーグルを被ったのは1992年──もう33年前のことになります。
そのとき、初めて「バーチャルリアリティー」という言葉に触れたんですよ。
使ったのは、イギリス製の「バーチャリティ1000SD」というデバイスです。ぜひ調べてみてください。
当時は、「CG空間の中に入る」という概念自体が非常にマニアックで、映画『トロン』を観たことがあるようなごく限られた人たちにしか共有されていない感覚でした。
ー そんなに早くから、VRの体験があったんですね!
Koya:
そうなんですよ。でも、技術的にはまだまだで……。
当時のPCはアミガ(Amiga)で、テクスチャー(※物体の表面に貼る画像)もなくて、せいぜい100ポリゴン(※物体を構成する三角形などの面)程度のモデルしか扱えませんでした。
フレームレートも15fps(※1秒間に表示されるフレーム数。一般的な滑らかな映像は30〜60fps)くらいしか出ないので、カクカクした動きでとても没入なんてできる代物じゃなかった。
商品としてお金をいただいて他人に遊ばせるには、正直、かなり無理がある状態でした。
ー 実際にお客さんに遊んでもらう機会もあったんですか?
Koya:
ありました。
ゲームセンターで1プレイ500円でテストをしたんですが……途中でお客さんから「金返せ!」と激怒されたんですよ(笑)。
それだけ、当時のVRにはまだ受け入れられるだけの体験のクオリティがなかったということですね。
ー なるほど…。でもそこで終わらずに、別の形でのVR的な体験開発に進まれたと。
Koya:
ええ。ナムコの開発チームはHMDによるVR体験は早々に見切りをつけて、別の形で「仮想と現実の融合」にチャレンジしていきました。
たとえば、50インチのリアプロジェクションモニター(※背面から映像を投影する大型ディスプレイ)にスキー板のコントローラー(※スキーの操作感を再現できるデバイス)を接続して、スキーのダウンヒル体験を開発したり、
自転車のペダルを実際に漕いで空を飛ぶ体験を作ったり、
マツダ・ロードスターの実車の前に巨大なスクリーンを設置して、実車のハンドルやアクセルで運転できるドライビングシミュレーターも作ったりしました。
他にも、空間に赤外線センサーを設置して、プレイヤーが実際に振る剣の動きを検出し、迫りくる敵を切り倒して進んでいく斬撃体験なんかも開発しました。

ー まさに“広義のVR”ですね。
Koya:
はい。当時の技術や環境の中で「仮想と現実をつなぐ体験」を模索していたわけです。
いわゆるXRの原型とも言える体験を、当時からずっと追いかけていたということですね。
ー VR体験の広がりは、技術の進化とともに大きく変わっていったのでしょうか?
Koya:
そうですね。2000年頃、インターネットが当たり前になってきて、携帯電話でもiモードなどのWebサービスが使えるようになったあたりから、
広義のVR体験はますますチャンスを得るようになりました。
つまり、「日常生活とゲームプレイの境界を曖昧にする」という試みが、現実味を帯びてきたんです。
ー それは、どういった体験だったのでしょう?
Koya:
一例として、こんな企画を開発しました。
ゲームセンターを芸能事務所に見立てて、プレイヤーはアイドルプロデューサーになります。
普段の生活の中では、プレイヤーの携帯電話にアイドルから連絡が来るんですよ。
で、「今日、ゲーセンでレッスンね」みたいに呼び出されて、ゲーセンに“出勤”するという流れです。
つまり、ゲームプレイが日常生活に溶け込み、現実と仮想がつながっているような体験を提供していました。
ー それは、今のメタバース的な考え方にも通じそうですね。
Koya:
まさに。しかも面白いのは、そこで作られた架空のアイドルたちが、
実際にCDをリリースしてオリコン1位を獲得したり、アニメ化されたり、映画になったり、
さらには地方自治体の親善大使まで務めたということなんです。
ー ゲームの中の存在が、完全に現実を浸食していったわけですね。
Koya:
そうなんです。
この時期に、エンターテインメントと現実世界の関係性が、ものすごく接近したと感じましたね。
ー その後、現在の映像的VRにつながるような取り組みも?
Koya:
はい。現在の“映像としてのVR”につながる基礎を築いたのは、2002年から始まったある研究開発でした。
それが、ドームスクリーンによるガンダムのゲームです。
当時のナムコ研究部が開発したドームスクリーンは、本当に素晴らしい可能性を秘めていました。
ー ドームスクリーンというと、半球状のスクリーンに映像を投影するものですよね?
Koya:
そうなんですけど、実際に体験するまでは、「単に映像が球体に貼り付いているだけ」だと思っていたんです。
僕自身も、最初はそういう印象でした。
でも、それがまったく違ったんですよ。

ー 実際にどんな違いがあったのでしょうか?
Koya:
ドームスクリーンは、正しく使うととんでもない性能を発揮するんです。
まるでCG映像の中に“入っている”ような感覚になるんですよ。
例えば、そこでは10メートルのモノは10メートルに、100メートルのモノは100メートルに見える。
テレビ画面のゲームだと、時速50キロと100キロの差なんて、身体的にはほとんど感じませんよね。
でも、ドームスクリーンで峠を車で100km/hで下ると、本当に怖いんです。
ー まさに、体験が“現実化”するわけですね。
Koya:
そう。だから、2000年当時のHMD(ヘッドマウントディスプレイ)の性能の低さにがっかりして、
「映像としてのVRはまだ無理だな」と思っていた僕にとって、このドームスクリーンとの出会いは本当に興奮する体験でした。
「やっとCG空間に“入る”VRができる」って。
ー とはいえ、180cmの球体を装着するわけにはいかないですよね。
Koya:
当然です(笑)。
直径180cmの球体スクリーンを頭にくくりつけるわけにはいかない。
なので、“自由に歩き回るVR”は諦めることにしました。
その代わりに考えたんです。
「座ったままで、CG空間を自由に歩き回れる題材って何だ?」って。
ー そこで思いつかれたのが?
Koya:
モビルスーツのコクピットですよ!
「これしかない!」と、ひらめきました。
モビルスーツのコクピットを3DCGで作って、その中にプレイヤーが“座る”。
すると、ドームスクリーンの中心にいるプレイヤーが見ているのは、
まさに“ガンダムのコクピットのモニター越しの世界”そのものになるわけです。

ー それはファンにはたまらない体験ですね!
Koya:
当時はまだPlayStation 2のコントローラーを接続していて、
レバーを動かして、仮想空間の中を「進む」ことができたんですが……。
うわっ、気持ち悪い! 酔う!!
ー 酔う!?
Koya:
ものすごく酔うんです。
例えるなら、目玉を他人に掴まれてグリグリ動かされているような感覚。
強烈な吐き気がして、「これはダメだ」と思いました。
ー 何が原因だったんでしょうか?
Koya:
それまでのゲーム演出手法が原因だったんです。
3DCGゲームが一般化して以降、ゲームでも映像演出の役割が大きくなっていました。
視聴者に“臨場感”や“スピード感”を伝えるために、カメラを動かすんですね。
たとえば、レースゲームでは
- アクセルを踏むと画面が拡大しながら上向きになる
- カーブで画面が斜めに傾く
- 荒れ地では画面を揺らす
こうしたカメラ演出が当たり前のように組み込まれていたんです。
ー 確かに、よく見ますね。
Koya:
でも、ドームスクリーンではそれが一切通用しなかった。
やるとすぐ酔う。猛烈に気持ち悪くなる。

ー では、カメラ演出は排除されたんですね?
Koya:
はい、完全に封印しました。
その代わり、どうやって臨場感を高めるか?が新たな課題になったんです。
この試行錯誤を通じて、2002年〜2004年の間に、VRゲーム制作における「酔い対策」と「臨場感向上」のノウハウを独自に蓄積しました。
ー それは、かなり先進的な知見だったのでは?
Koya:
当時、我々以外ではそんなノウハウを必要としている人すらいなかったと思います。
でも、今のVR開発においては必須の要素ですよね。
ー そのドームスクリーンによるガンダムのVRゲーム、映像体験としても画期的ですが、実は他にも大きな特徴があったんですよね?
Koya:
はい、そうなんです。
このドームスクリーンVRのガンダムは、実は日本初の“商用”他人数リアルタイムネットワーク対戦ゲームでもありました。
ー 日本初の「商用」で「多人数」で「リアルタイム」のネットワーク対戦!?
当時としてはかなり先進的ですよね。
Koya:
今でこそ「FPS(ファースト・パーソン・シューティング)(※自分の視点で銃を撃つタイプのゲーム)」というジャンルは一般的ですけど、当時はまだまだマニアが海外サーバーで細々と遊んでいるというような時代でした。
任天堂やPS2のコントローラーに慣れている一般のゲームユーザーからすると、
マウスとキーボードを駆使して、周囲を索敵して射撃するなんてプレイは、
とんでもなく敷居が高いものに見えたと思います。
ー そんな中での、ドームスクリーン+多人数チーム戦のFPS型VRゲーム…確かに革命的です。
Koya:
はい。このガンダムVRゲームは、100万人のプレイヤーにとって、
「みんなでCG空間に入る」初の体験だったと思います。
しかも、ボイスチャットでリアルタイムに会話しながら、
同じ仮想空間を共有する。まさに「共体験」ですね。
ー いまのApex LegendsやFORTNITE(※世界的に人気のあるバトルロイヤル形式の対戦ゲーム)のような、多人数対戦型オンラインゲームと同じ構造ですよね。
Koya:
おっしゃる通りです。
この多人数型XR体験は、間違いなく現在のApexやFortniteのようなタイトルにつながる基礎を確立したと感じています。
ー ドームスクリーンの開発でVR表現の手応えを掴まれた後、HMD(ヘッドマウントディスプレイ)(※頭に装着して使用するゴーグル型のディスプレイ)技術にも新たな動きがあったそうですね。
Koya:
はい、そうなんです。
2012年ごろのことなんですが、部下が北米のCES(コンシューマー・エレクトロニクス・ショー)に出張して、あるHMDを持って帰ってきたんです。
それが、「Oculus」と呼ばれるものでした。
当時は、学生がスマホの部品を流用して作ったというようなもので、まだ「おもちゃ感」が強かったですね。

ー 今でこそOculusはVRの代名詞のような存在ですが、当時はまだ黎明期だったんですね。
Koya:
はい、まさにそんな感じです。
それで、さっそくこのOculusをドームスクリーンのガンダムゲームに接続してみたんです。
そしたら、思った通り、まったく遜色なく動いたんです。
いきなり、何の違和感もなくプレイできてしまった。
ー それは…すごい衝撃だったでしょうね。
Koya:
もう、「ドームスクリーンがなくても、ついに本当にVRができる!」と確信しました。
ただ…やっぱりハードのつくりはまだまだ“オモチャ”のようなレベルで、商用で使うにはとても耐えられるものではなかったですね。
ー そこから急速に市場も動き始めたんですよね?
Koya:
そうですね。その2年もしないうちに、OculusはFacebookに2000億円(20億ドル)で買収されて、
もう簡単にはパルマー・ラッキー(※)さんからの許可を得られる状況ではなくなってしまいました。
(※パルマー・ラッキー氏:VRヘッドセット「Oculus Rift」を開発した技術者で、Oculus社の創業者。若干20歳でOculusを立ち上げ、後にFacebook(現Meta)により買収されたことで、世界的なVRブームの先駆者となった人物)
同時に、「DK2」(※Oculus社の開発者向けHMDの進化版)と呼ばれる進化版が出てきて、
それを使ったインディーVRコンテンツ(※小規模な個人や独立系スタジオによって開発された、商業大作ではないVR作品)もちらほら登場し始めました。
ー でもこの時点では、まだ3DoF(スリードフ)(※頭の回転〔上下・左右・傾き〕の3軸方向のみを認識するVRトラッキング方式)だったんですよね。
Koya:
はい。まだ“頭の向き”しかトラッキングできない、3DoFの段階でした。
本格的な没入体験には、もうひとつ先の進化が必要でしたね。
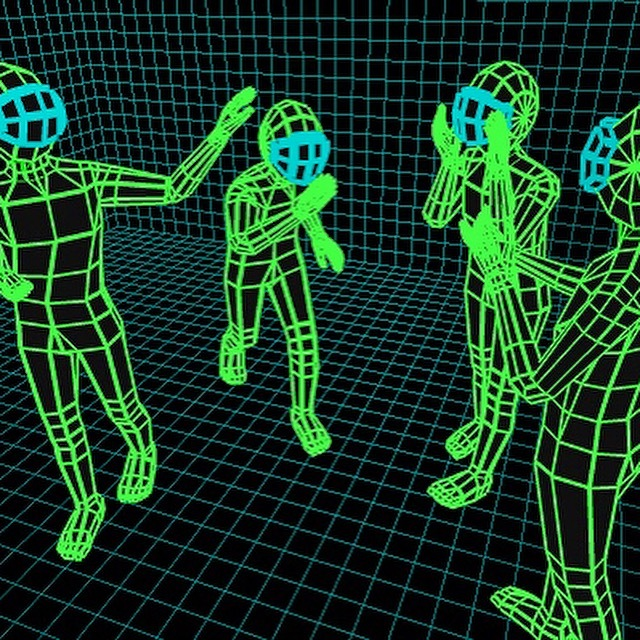
ー Oculus DK2の登場やFacebookによる買収など、VRを取り巻く環境が急速に動き始めたタイミングだったと思いますが、Koyaさんにとって転機となった出来事があったとか?
Koya:
はい、まさに潮目が一気に変わったと感じたのが、Rift(※Oculus社の初期VRヘッドセット)の試作機を体験したときでした。
6DoF(シックス・ドフ)――つまり、頭の向きだけでなく、前後左右上下に“移動”できるVR体験に初めて触れたんです。
それは、もう衝撃的でしたね。
CG空間の中を、自分の足で自由に歩ける。
これはもう、新しい世界が開いた瞬間でした。
ー まさに本物の「没入体験」が可能になったと?
Koya:
そうです。で、私はそのとき決心したんです。
「VRアトラクションを集めた施設を作ろう!」って。

ー それが後の「VRテーマパーク構想」につながっていくわけですね。
Koya:
はい。当時、2014年も終わりかけの頃でした。
私はアーケード部門の開発トップを務めていて、社内全体に向けて、「VRテーマパークを作ろう!」と呼びかけたんです。
ー 大きな勝負に出た瞬間だったわけですね。
Koya:
そうなんです。
膨大なプレゼン資料を用意して、夢を語り尽くしました。
でも、プレゼンが終わった後――
私の構想は社内で“コヤマンランド”と陰で囁かれ、笑いものになってしまったんです。
ー それは…かなり悔しかったですね。
Koya:
ええ、正直悔しかったですよ。でも、その中で3人だけ、協力したいと名乗り出てくれた人がいたんです。
ー 光が差した瞬間ですね。その頃、ソニーや他社でもVR開発は進んでいたのでしょうか?
Koya:
はい、SME(ソニー・ミュージックエンタテインメント)(※ソニーグループの音楽・エンタメ事業を担う企業)もPSVR(※PlayStation VR:ソニーが開発した家庭用VRヘッドセット)を開発していた時期で、
バンダイナムコ社内でも、「女子高生の家庭教師になるゲーム」なんていう試作も進んでいました。
ただ、当時はまだ業務用PS4が存在しなかったので、商用展開はそもそも視野に入れていなかったんです。

ー Oculusを活用しようとされたんですね?
Koya:
そうなんですが、商用利用についてOculus側を説得に行っても、なかなか良い返事はもらえませんでした。
そこで私は、グループ会社であるメカトロニクス部門に出向いたんです。
そこは私の古巣でもあって、かつて数多くの体感型ゲームのインターフェースを作ってきた部署でもあります。
ー 信頼関係がある場所ですね。
Koya:
ええ、私がVRテーマパークの夢を語ったところ、全員が目をキラキラさせて「協力したい」と言ってくれたんです。
そして私は確信しました。
「もう、自分たちでHMDを開発するしかない!」と。
ー 「自前でHMDを開発するしかない」と決意されたKoyaさんですが、そこからどう動かれたのでしょうか?
Koya:
そんな時、社内の電気系メンバーのひとりが言ったんです。
「HTCと懇意にしてるから、一度相談してみましょう!」と。
期待と諦めが半分ずつ…そんな気持ちで、虎ノ門のHTC日本支社(※台湾の大手IT企業HTCの日本法人。スマートフォンやVR機器(例:VIVE)の販売・サポートを担当)を訪ねました。
すると、そこにあった試作機――それは、Oculus Riftにも引けを取らないHMDだったんです。
ー おお、それがあの「VIVE」(※高性能なVRヘッドセット)だったのですね?
Koya:
そう、名前は「VIVE」。
その場で「これを商用利用させてほしい」とお願いしたところ、ガッチリ握手!
HTC側も非常に前向きで、こう言ってくれました。
「バンダイナムコに行って、社長や役員たちにこのVRの凄さをプレゼンしてほしい」と。
ー HTCからの申し出で、バンナム本社へ…?
Koya:
はい。すぐに段取りをつけて、当時はまだ品川シーサイドにあったバンナム本社で、役員の皆さんにVIVEを体験してもらったんです。
そしたらもう、全員が腰を抜かすほど驚いてくれて。
「小山くん、これ、やってみよう。」
と、社長の一言でプロジェクトが動き出しました。
ー 本格的に「VRテーマパーク構想」が走り出した瞬間ですね。
Koya:
そうなんです。準備期間はわずか1年。
しかも、まだ何も無い状態からのスタートでした。
でも、私の中では、作るものはすでに決まっていたんです。
ー どんなタイトルを構想されていたんですか?
Koya:
6つの体験を同時に立ち上げる計画でした。
- クレッセントの小谷さんの施設で体験して驚いた「高所歩き」
- VRと相性が抜群な「ホラー体験」
- 急斜面を滑り降りる「アルペンスキー」
- 最新の山手線をリアルに運転する「鉄道シミュレーション」
- ロボットを操縦して戦う「ボトムズ」的な体験
- そして、ドームスクリーンの技術を活かした「レース体験」
企画・ハード・ソフト、すべてを同時進行で一気に作る。
それが私のビジョンでした。
ー 一斉に6タイトルの制作…。まさに怒涛のスタートですね。
Koya:
はい。各タイトルごとにチームを編成して、試作実験を一斉にスタートさせたんです。

ー VR ZONE構想が走り出してからは、開発だけでなく様々な課題が山積していたのでは?
Koya:
ええ、HTCと「VIVE」を導入するとなると、それだけじゃ済まないんです。
「VIVEって一体どういうものなのか?」「商用利用すると何が起きるのか?」
「どんな取り引き条件で話を進めるのか?」
それから当然、PCはどうする、グラフィックボード(※映像処理を担当する専用のハードウェア)は? nVIDIA(※グラフィックボードを開発する世界的な企業で、ゲームや映像処理、AI分野で広く使われている)は? 大量発注できるのか?
…すべての項目を一から精査していく必要がありました。
ー 技術面だけでも、相当な準備が必要だったんですね。
Koya:
はい、Unrealエンジン(※高性能ゲームエンジン)を扱えるチームを中心に、社内で勉強会を開いてノウハウを横展開しました。
でもね、作るだけじゃ意味がないんですよ。
ー 施設運営という、全く別のフィールドもあったわけですね。
Koya:
そうなんです。VRを仕掛ける場所を探すところから始まり、施設との交渉、運営チームの整備、アルバイトの募集と教育、プロモーション戦略の立案と実行…
これらを全部同時進行でやったんです。
ー どのような場所を候補として検討されたのでしょうか?
Koya:
最初は都内から川崎エリアまで、10数か所を巡って物件探しをしました。
でも、限られた予算内で良い条件の場所はなかなか見つからない。
ゲーセン跡の雑居ビルの地下や、元風俗営業のボロボロの小屋など、選択肢は本当に厳しかったですね。
そんな中で出てきたのが、お台場のダイバーシティ東京。
撤退したアパレル店の跡地、100坪ほどのスペースが期間限定で提供できるという話が舞い込んできたんです。
エンタメエリアではないけれど、アパレルエリアの中なら目立つ。悩みに悩んで、ここに決めました。
ー ついにスタートですね。どんな体制で運営されたのですか?
Koya:
屋号は「VR ZONE」としました。
運営は、ゲーセンの運営を担っていたグループ会社ナムコから人を出してもらい、専用チームを結成。
そして、ついに…2016年3月、「VR ZONE」がスタートしたんです。

ー 国内初の本格的VR体験施設ですね。
Koya:
完全予約制のVR ZONEは、日本初のVRアトラクション施設として、テレビなどのメディアにも多数取り上げられました。
オープンから半年間、予約枠はすべて満席。
予想以上の反響でしたね。
ー そして、その勢いが「VR ZONE Shinjuku」へと繋がっていったわけですね?
Koya:
そうです。2017年7月、新宿・歌舞伎町に2階建ての専用施設「VR ZONE Shinjuku」を建設。
お台場時代の10倍の規模でスタートしました。
アクティビティは18タイトル。
たとえば…
- マリオカートVR
- エヴァンゲリオンVR
- 国産初のフリーロームVR「攻殻機動隊」(25mプールほどの広さ)
- ドラゴンクエストVR などなど。
超一流IPと技術の融合に、国内外のユーザーから大きな注目を集めました。
VR開発者向けには、勉強会でノウハウを公開し、トップランナーとして講演活動も行っていました。
ー 期間限定のプロジェクトだったのですよね。
Koya:
はい。「VR ZONE Shinjuku」は21か月の期間限定営業でした。
その後は池袋・サンシャインシティに移設し、「MAZARIA(マザリア)」という新たなコンセプトのVR施設をオープン。
しかし、コロナ禍の影響で最終的には閉店。
その4年間で、私たちが開発・運用したVRアクティビティは、実に27タイトルにのぼります。
ー Questでの開発も早い段階で?
Koya:
はい。Meta(当時Oculus)社から直接依頼されて、Oculus Quest(現Meta Quest)を使ったフリーロームVRを開発したんです。
それが「パックマンチャレンジ」というアクティビティで、8m×8mのエリアを2人で同時に自由に歩き回るというものでした。
そこで初めて、「床や壁に特徴点がないとトラッキングが失われる」という課題に直面しました。
それで、カラーテープを壁や床に貼っていって、最終的には幾何学模様のような空間になったんです。
今では、世界中のフリーロームVR施設で“あたりまえ”になっているあの床模様、実はそこから生まれたものなんですよ。
ー 知られざる“標準の起源”ですね。
Koya:
まさに手探りでした。誰もやっていなかったからこそ、自分たちでやるしかなかった。
苦労も多かったですが、今では安価で便利に、しかも高品質なフリーロームVR体験ができるようになった。
「ああ、ついにビジネスとして成立する時代が来たんだな」と、感じましたね。
だからこそ“インパクト”というよりは、「感慨深さ」のほうが大きかったです。

ー さまざまな貴重な経験を経てバンダイナムコを退職され、その後、当社代表の小林と出会い、“XRミッション”を体験されることになりますが、そのときどのような印象を受けられましたか?
Koya:
体験させていただいて、まず感じたのは「ついにここまで来たか」という感慨でした。私自身、これまで長くフリーロームVR(※自由に歩き回れるタイプのVR体験)の技術開発に携わってきたこともあり、驚きというよりは、その進化や完成度に深くうなずかされるような感覚でした。
たとえば、ナムコ時代の「VR ZONE」では、空間トラッキング(※ユーザーの位置や動きをリアルタイムで把握し、VR空間内に正確に反映させる技術)をどう実現するか、身体を使ってVR空間をどう自然に歩けるようにするかといったことに、まだ答えのない中で取り組んでいました。
HTC社にVIVEトラッカー(※小型のセンサー機器で、身体や物体の動きをVR空間内に反映させるためのデバイス)の開発を依頼したり、ViconやPhasespace、OptiTrackといった外部トラッキングのパートナーと一緒に現場で何度も実験を重ねたり。MSI社とはバックパックPCの共同開発も行いましたし、VR用の銃や剣といったデバイスの設計も、自ら担当していました。
そうした経験があるからこそ、『バトルワールド2045』の完成度や作り込みには本当に学ぶ点が多く、これまで現場で積み重ねられてきた努力が結実していることを、肌で感じることができました。開発者として、あらためて刺激をもらえる体験だったと思います。
ー では、そんなKoyaさんが、現在、日本XRセンターに参画されているわけですが、数あるXR関連企業の中でも、日本XRセンターに“特別な可能性”を感じたポイントはありますか?
率直に申し上げますと、大河さんの存在です。
真摯な人柄、野望の質、経済合理性を備えた思考力、そして意思決定の速さと正確さ。
そのバランスの良さに、私は強く惹かれました。
さらに、入社後にわかったことですが、インド開発チームとの信頼関係が非常に強く、ここには他社とは違うグローバルな連携の可能性があると感じました。
これだけでも大きな魅力ですが、何よりも私は、
「この組織であれば、自分たちの作品で、XR領域において日本で初めて利益を出すことができるかもしれない」
という、リアルな希望を持てたことが、参画を決めた一番の理由です。

未来の仲間・若手へのメッセージ
ー 日本XRセンターに興味がある方々に向けて、“この組織で働く魅力”を一言で表すと?
「好きな人と、好きなコトを、好きなようにヤル!」が叶う場所。
これに尽きます。
ー 共に挑戦したいと思う仲間に、最後にメッセージをお願いします。
私は、
「好きな人 と 好きなコト を 好きなようにヤル。」
人生が、一番幸せだと思っています。
でも、こんなことを言うと、
「そんな都合のいいこと言って。誰かが嫌なことを引き受けないと回らないだろ」
「我慢や妥協も必要なんだ」
とおっしゃる方もいるでしょう。
もちろん、それもご本人が納得されているなら、それでいいと思います。
ただ私は、こう思うんです。
この言葉を逆にすると、こうなります。
「嫌いな人 に 嫌なコト を 無理強いされる」人生。
それって、やっぱり嫌じゃないですか?
もし、そういう生き方に少しでも違和感があるなら、
誰かの価値観や都合に支配されるのではなく、自分で挑戦する道を選ぶのも、一つの手です。
「やってみたい」「本気で作ってみたい」「自分の力を試してみたい」
そんな想いがあるなら、ぜひ一度、日本XRセンターをのぞいてみてください。

【コヤ所長(小山順一朗氏) プロフィール】
日本大学理工学部精密機械工学科卒業後、1990年に株式会社ナムコ(現バンダイナムコアミューズメント)入社。メカエンジニアとしてアーケードゲームに携わり、1992年には海外VR業務用ゲーム機「VIRTUALITY」を日本向けに展開。VR開発本部では、1995年発売の『アルペンレーサー』など体感マシンを中心に開発を手がける。
『アイドルマスター』(2005年)や『機動戦士ガンダム 戦場の絆』(2006年)など、新しい形の体感型ゲームを数多く生み出し、VR技術を取り入れたエンターテインメント事業にも早期から携わる。屋内型テーマパーク「VR ZONE」や「MAZARIA」のプロデュースを経て、2024年3月に株式会社バンダイナムコ研究所を退社。同年4月に株式会社ホットスタッフ・プロモーションへ入社し、学校法人片柳学園日本工学院八王子専門学校の教育革新プロジェクト「VisionCraft」エグゼクティブプロデューサーに就任。
2024年6月よりクラスメソッドの顧問に就任。
2025年4月より日本XRセンターのベースUI/UX担当兼渉外顧問に就任。
代表作(抜粋)
『ギャラクシアン³』(1993)
『ACE DRIVER』(1994)
『アイドルマスター』(2005)
『新・太鼓の達人』(2011)
『釣りスピリッツ』(2012)
『VR ZONE SHINJUKU』(2017)
講演・特許
国内外カンファレンスでの講演実績延べ110回(2016年~2024年)
体感ゲーム筐体・ネットワークVRに関する特許22件の発明者
ありがとうございました!
コヤさんの言葉が示すように、「好きな人と、好きなコトを、好きなようにやる」ことは、これからのXRの世界を切り拓くための最も本質的な原動力です。
まだ誰も体験したことのない世界を、誰かが形にしていかなければならない。
その「誰か」になる覚悟と情熱がある人と、私たちは一緒に進んでいきたいと思っています。
日本XRセンターでは、理想を現実に変えるための挑戦を、仲間とともに楽しめる場所があります。
もし少しでも心が動いたなら、ぜひ「話を聞きに行きたい」ボタンから、気軽にアクセスしてみてください。
次のステージは、あなた自身の一歩から始まります。
/assets/images/21368374/original/c944e5e3-84f3-4668-b69a-1071f68c4185?1750120829)
/assets/images/21368374/original/c944e5e3-84f3-4668-b69a-1071f68c4185?1750120829)
