- バックエンドエンジニア
- ITプロジェクト品質管理
- ユーザーサポート
- Other occupations (7)
- Development
- Business
- Other
新卒で前職に入社して以来、エンジニアひとすじでキャリアを積んできた青木さん。2023年に初めての転職でJPデジタルを選んだ理由と、仕事のやりがいについてお話を聞いてみました。
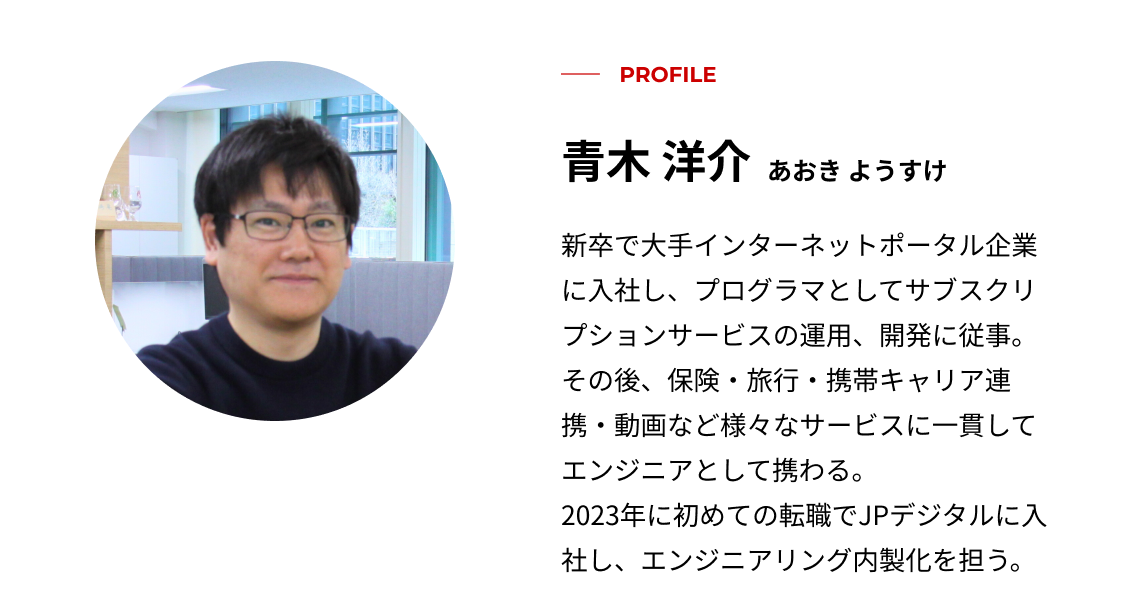
整備されていない環境のほうが価値を発揮できると思った
―—転職を考えた理由を教えてください。
青木 前職にはプログラマとして入社し、PMや開発リーダなど様々な役割を経験してきました。そんななか担当していたサービスのクローズが決まり、別部署へ異動したことが転職を考えるきっかけでした。
前職は開発環境や開発プロセスがしっかり整備されている環境で、社内にはわたしと同じようなスキルを持っている人や、より若くて技術的に優秀な人がたくさんいました。それであれば、エンジニアが不足していて環境整備もこれからの会社に入ったほうがより貢献できる幅が広がるし価値を発揮できるのでは、と考えたのです。
―—なるほど、それでJPデジタルに出会ったのですね。
青木 はい、エージェントから紹介されて話を聞いてみると、郵政事業のDXを推進したい、そのために開発を内製化したいという課題が明確にあってそれをリードする人がいないという状況で、大変ではあるけれどやりがいがあるな、と感じました。
―—整備された会社から整備されていない会社へ、しかも初めての転職で不安はありませんでしたか?
青木 不安がまったくないと言ったら嘘になりますが、もともと形がないところから作り上げていくのが好きというか性に合っているので、そこまで不安には感じませんでした。学生時代には学園祭実行員として新しいものを企画したり、前職でもうまくいっていないプロダクトを引き取って正常に戻したりした経験があったので、整備されていないなかでも前に進めるほうがわたしの価値を出せると思ったのです。
選考中に社員や代表の飯田さんと話して心理的安全性がありそうと感じたこと、携わる事業の社会的意義があること、安定した事業基盤があることなど、さまざまな要素を検討して自分が輝けそうと感じて入社を決めました。

開発組織の内製化を進め、エンジニアにとってやりがいのある組織に
―—現在の仕事内容を教えてください。
青木 これまで外部パートナーとの協業を主としてきた開発業務の内製化を主導することがメインの業務です。その他に業務委託者の受け入れやマネジメント、チーム全体への技術的なアドバイスなども行っています。
―—なぜ開発の内製化を進めているのでしょうか?
青木 外注が必ずしも悪いということではなく、今後も外部パートナーとの連携は進めていきます。ただ、長期的な運用に向く設計になっているかとか、良いプロダクトにするためにエンジニアとして意見やフィードバックを行うだとか、プロダクトにコミットしたエンジニアのいる体制でないとできないこともあります。
それに、担当するプロダクトにコミットする働き方はエンジニアにとっても気分が良いものだと思うのです。同じ釜の飯を食う、じゃないですけれども、ビジネスに立ち会っている社内メンバーと直接コミュニケーションをかわして、より良いものを作って喜ばれる。エンジニアがプロダクトの成功を自分ごととして感じられて自分の評価にもつながる、そんな体制をつくりたいと考えています。
目の前に解決するべき課題がたくさん。それだけ伸びしろと責任を感じる
―—転職時に考えていたような「価値の発揮」はできていますか?
青木 入社後のキャッチアップには思った以上に苦戦しましたしまだまだこれからの部分も多く、会社に大きなプレゼンスを発揮できているとは言えないのですが、それでも少しずつエンジニア組織が拡充し、プロダクトのリリースもできるようになってきました。内製化することで開発スピードが上がったり、リソースがなく着手できなかった箇所を改善できて評価されたりと、周囲からの期待も感じています。
と言ってもまだまだ発展の途上で、今は開発組織内製化の産声が上がったくらいです。会社全体として開発の内製化を支援する体制と雰囲気があり、「将来はこれをやろう、こういうことを目指そう」という前向きな会話もできていて、良い波に乗れつつあると感じます。
―—仕事のやりがいはどんなところに感じますか?
青木 目の前に解決するべき課題がたくさんあって、経営陣や社内からも大きな期待を寄せられているのがありがたい状況だと感じています。解決するべき課題がたくさんあるということは、それだけ伸びしろがあるということです。
そうして取り組んだことがプロダクトのリリースや品質改善につながって社内から感謝され、しかも単なる会社の利益だけではなく多くの人が使うユニバーサルサービスとして社会の役に立つことがやりがいに感じます。
それにまだできたばかりの組織なので、組織や文化も自分たちで作り上げていけるところもわたしに合っていると感じます。

郵政事業DXという大規模プロダクトの本丸に携われる
―—JPデジタルだからこそ経験できることってありますか?
青木 JPデジタルはまだ会社の規模が小さくベンチャー的な雰囲気を持っていて、それにも関わらずこれだけ大規模サービスのシステムの中枢に関われる機会はなかなかないと思います。入社年次に関係なく巨大なシステムの中枢、本丸に携わることができるので、エンジニアとして自分の力を試したい、大きなプロダクトの中心に関わっていきたいと考えている方にはうってつけの職場だと思います。
―—日本郵政グループでWebエンジニアとして働くイメージがわかなくて不安、という方もなかにはいるかもしれません。
青木 ユーザーがより便利になるWebサービスやアプリを開発して提供する。その点では他のIT企業と業務内容は変わりません。郵便をまったく利用しない人はいませんから、JPデジタルの場合はユーザー数がとても多く、それだけ社会的影響力と責任が大きくなり、やりがいにつながっています。
未整備な分だけ自分たちの理想を追求できる
青木 先進的な取り組みをしている会社に比べれば開発環境が整っているとはまだ言えませんが、自分たちの理想のとおりに変えていける環境とも言えます。様々な経験を持ったエンジニアがジョインしているので、それぞれの専門性を活かしてモダンな環境にすべく整備しているところです。
そういった、自分たちの力でものごとを前に進めて良いプロダクト作りにつなげることが好きな方であれば楽しく働けますし、チームに大きな貢献ができると思います。
―—転職理由にもあった、「整備されていない状況を前に進める」ことにやりがいを感じているのですね。
青木 はい。わたしは技術自体を追求するというよりは技術を手段としてプロダクトにどう還元するか、プロジェクトを前に進めるか、を考えるほうが性に合っています。少しずつその成果も出て、周囲から喜ばれたり感謝されたりしてやりがいに感じています。
今後は携わっている様々なプロダクトで成果を上げていくことはもちろんのこと、生産性の高いエンジニア組織や文化をつくって、エンジニアとしてやりがいを持って働ける組織にしていきたいです。

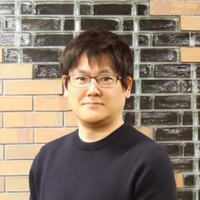
/assets/images/16845279/original/4eadf531-f9ae-4308-acf9-57e0464d5b16?1749514105)

/assets/images/16200134/original/512b15dc-efd7-4460-912c-e6e3af16c020?1701751391)




/assets/images/20568715/original/512b15dc-efd7-4460-912c-e6e3af16c020?1741049405)

