- Legal
- コンサル/未経験歓迎
- Engineering
- Other occupations (5)
- Development
- Business
- Other
私とBuddyの出会い
はじめまして、島田友輝です。
私は新卒で大手SIerに入社し、ITコンサルタントとして3年間、大企業向けの基幹システム導入プロジェクトを推進していました。
安定した環境で、やりがいもありましたが、次第に「同じような仕事の繰り返し」に物足りなさを感じるようになります。
また、システム導入の先にある企業の売上や利益への貢献が、自分の仕事からは少し遠く感じていたのも理由のひとつでした。
もっと多様な経験を積みたい。
そしてもっと自分の成長をより実感できる環境で働きたい
そんな想いが強くなっていきました。
その後、より売上に近い領域で価値を出したいと考え、Webマーケティングのコンサルティングの会社に転職。
広告を通じて企業の一部を支えるやりがいはありましたが、クライアントの本質的な変革に携わっている感覚は薄かったです。
そんなときに出会ったのがSALESCOREの「Buddy」という仕事でした。営業組織の変革を通じて、人と組織に直接的なインパクトを与え、その先の売上にまで貢献できる。
まさに「人の背中を押し、成長を促す」「売上への本質的な貢献ができる」仕事だと感じました。僕はここで、自分が本当にやりたかったことに出会ったんです。
忘れられない体験
会議中に席を立つメンバーがいた日から、変化は始まった。
初めて担当したのは、営業人数10名ほどの人材派遣会社。
若手が多く、マネージャー陣も「メンバーを動かす、働きかける」ことに苦手意識を持っている組織でした。
営業のアクション量向上と質の改善を徹底する文化の定着を目指し、
朝と夕方にそれぞれ30分ずつ、当日の営業の宣言と振り返りをチーム全員で行う”朝会・夕会”を導入しました。
しかし、最初はなかなかうまくいかず、導入初期から壁にぶつかりました。
ある日、朝会の最中に「営業の宣言なんてやりたくないです」と言い放ち、席を立って出ていったメンバーがいたんです。
静まり返る会議室。マネージャーも言葉を失い、場の空気が一気に重くなりました。
その瞬間、「この組織を変えるには、まず信頼関係を築くところからだ」と強く感じたのを覚えています。
マネージャーとの対話から始めた”文化づくり”
初めはこのような雰囲気だった会社へ、強い文化を定着させるうえで最初のキーになったのは、ファーストラインマネージャーたちでした。
彼らが強い営業組織の文化醸成に前向きになりコミットしてくれること。そこからすべてが始まりました。
当初、マネジャーの2人からはメンバーに何かを徹底してもらうこと、メンバーを成長させることを半ば諦めている「どうせ何を言ってもやらない」、そんな空気を感じていました。
それが故に、マネジャーがメンバーに対して向き合いきれず、一部メンバーとの関係も良いとは言えない状態でした。
だからこそ、最初はBuddyが朝会・夕会の意義を毎日マネジャーに説明し、ファシリテーションやってみせ、マネージャーが上手くできたときや成果が出たときにはしっかり賞賛する。時には飲み会などの場で「どうしたら組織の売上を上げられるか」を腹を割って語り合うこともありました。
マネージャーと同じ目線で、組織の売上を上げるために、強い営業組織文化を作るために、本音で議論する。各メンバーの育成計画をメンバーの性格や強み・営業データを踏まえて、すり合わせる。当時は組織を前に向かせ、変えるために無我夢中でした。
そんな時間を重ねる中で、徐々にマネージャーのお二方の朝会・夕会の際の顔つきが変わり、ファシリテーションが徐々に安定していきました。そしてある日、「島田さん、浸透させたいです」と、言ってもらえるようになりました。
そのときにやっと、自分に対して外部のコンサルではなく、共に組織を作り、伸ばす同志(Buddy)として受け入れてもらえた感覚があったし、自分の熱が伝わった気がして、とても嬉しかったのを今でも覚えています。
“やりたくない”と言っていた人と向き合う日々
マネジャーと向き合うことも大事ですが、メンバーとの向き合いも大事でした。なかなか、Sales Enablementの取り組みに前向きになれないメンバー。まさに、朝会の途中で「営業の宣言なんてやりたくないです」とオフィスの中央で宣言し、席を立って出ていってしまったメンバー(Aさん)でした。
当時はそのメンバーだけでなく、取り組みにネガティブなスタンスの人が多かった状況でした。
Aさんはマネージャーも手に余る状態で、自分の方でAさんが前向きに成果創出するための日々の宣言・振り返りに向き合ってもらえるよう対話を重ねていきました。
ときには1on1を行い、ときには喫煙所にまでついていきながら、毎日少しずつ会話の時間を取っていきました。じっくり話を聞いていくうちに、彼の中に溜まった組織や営業の運用への不満や“孤独”が見えてきました。
例えば、ビジョンや理由が明確にない高い目標。
日々の業務で感じる不満を吐き出す場所がなく、吐き出したところで組織は変わらない。そんな日々の中で組織や営業活動そのものへのネガティブな感情が強くなっていたようです。
外部の人間だからこそ様々な不満を話してもらえたのかもしれませんが、そこから徐々に自分に心を開いてくれるようになるAさん。
併せて見えたのは、Aさんの上司には言いにくい不満。一方で、マネージャー側としては言うことを聞かないメンバーたちへの不満があり、それが交錯し、チームの雰囲気が悪循環になっていたことでした。
そこからは、彼や他のメンバーからの不満や現状の営業の運用の不便さをヒアリングし、優先順位をつけながら徐々に日々の営業の運用を改善して行く日々。
並行して、メンバーの日々の小さな成長やキーアクションの実施状況を可視化し、努力を可視化・称賛する運用の導入と実施を行いました。
加えて、高い目標に対してメンバーが目的や理由を理解できていない状況があったときには、「なぜこの目標が必要なのか」「目標を追うことでなぜ成果に結びつくのか」、データを元に対話することも意識しました。
組織に変化をもたらすうえで必要な要素
こうした取り組みを通して、Aさん含めたメンバーの表情が少しづつ変わっていきました。
「やりたくない」から「どうしたら組織がよくなるのか?」「どうしたら成果が出るのか?」を主体的に考える、前のめりで建設的なメンバーに変化していったのです。
こうして、小さな変化の積み重ねが、チーム全体の行動量と質を確実に引き上げていきました。会議での議論もより建設的になり、データをもとにした改善が当たり前になり、最終的には、営業量が1.5倍、時には2倍にまで伸びました。
反発から信頼へ、信頼から共創へ――このプロセスこそ、Buddyという仕事の醍醐味だと思いました。
Buddyになった瞬間
僕のBuddy体験で共通して言えるのは、「データと対話を通じて、人・組織の成長の足掛かりをつくること」です。
マネージャーやメンバーと真摯に向き合い、時には感情に寄り添いながら、納得感のあるデータを元に対話を重ねる。
その上で、どんなステップを踏めば成長できるのか、どんなPDCAを回せば成果に繋がるのかを具体的に示してあげる。そうすることで、彼ら自身が自らの成長にコミットし、やりきる覚悟を持ち始める。そして、いつの日か、彼らの“顔つき”が変わる。
情熱を帯びた眼差しに変わり、言葉にも力が宿っていく。その変化が定性面だけでなく数字にも確かな成果として表れ始める。まさにその瞬間こそ、僕が「Buddyになった」「Buddyをやっていて良かった」と感じるときです。
この仕事で得たもの、そしてこれからの挑戦
この仕事を通じて感じたのは、「人の変化を間近で感じられる」ことの喜びです。
対話を通じて変化の瞬間を共にし、その結果として、組織全体の数字や文化が変わっていく。これほど手触り感のある仕事は、他にないと思います。
今後は、メンバー個人やファーストラインマネージャーの支援にとどまらず、より大きな組織や事業部単位、そして経営層をリードできる存在を目指したいと考えています。
経営層が見ている時間軸や視座を理解し、同じ目線で未来を描けるBuddyに。そして人と組織の成長を仕組みと文化の両輪で支えられるようになりたいと思っています。
未来のBuddyへ
これまで経験してきたどんな仕事よりも、Buddyという仕事は「人と組織の変化」を体で感じられる仕事です。
目の前の人の成長を見届けながら、その先にある組織の成果や数字の伸びを実感できる。その両方を追えることこそ、この仕事の面白さだと思っています。人・組織に真正面から向き合い、成長を後押ししたい。そして売上という成果を直接的・本質的に生み出したい。
そんな想いを持つ人にとって、Buddyという仕事はきっと最高な仕事です。

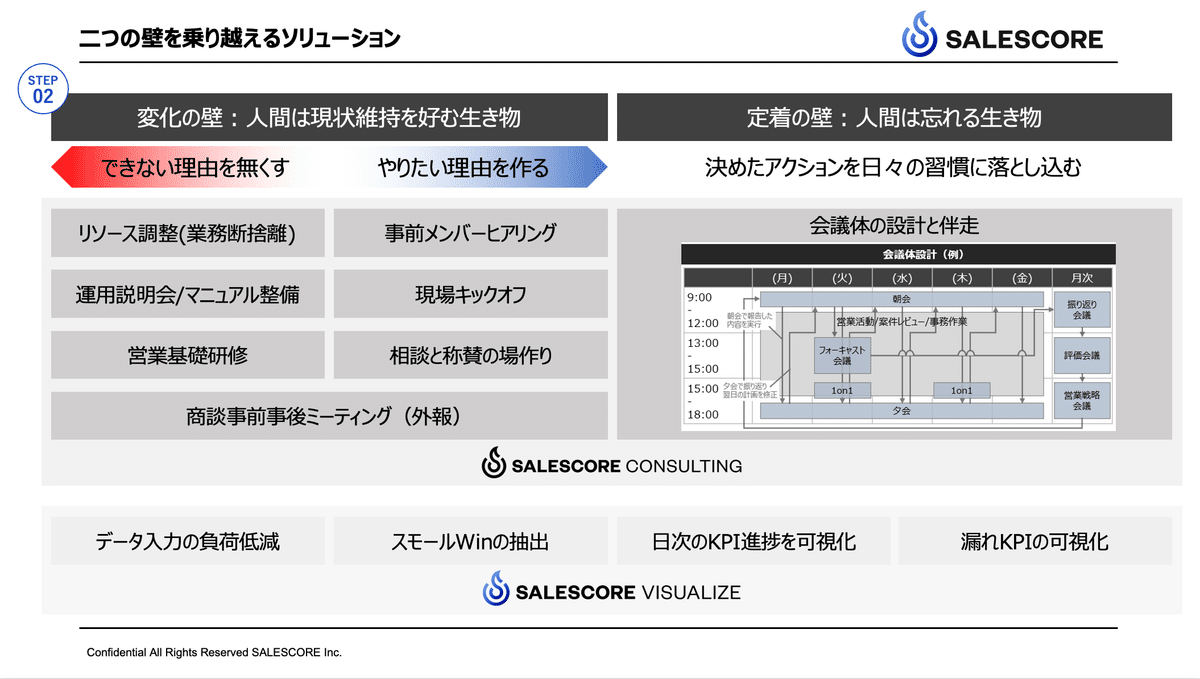
/assets/images/22289550/original/6b173286-e3cc-4896-a895-95669687b174?1760672449)

/assets/images/18411446/original/c704b434-7858-47eb-9d57-5c483875acdf?1719805019)
/assets/images/18411446/original/c704b434-7858-47eb-9d57-5c483875acdf?1719805019)

