- 採用アシスタント
- AWSエンジニア
- オープンポジション|IT志望
- Other occupations (20)
- Development
- Business
- Other
「確認不足?」「抜け漏れ?」「理解できてない?」
仕事でミスしたとき、まず浮かぶのはだいたいこの3つですよね。
そしてそのあとに襲ってくるのが、「あー、私って本当に仕事できないな…」という自己否定の波😖
大丈夫です。 私も何度もそこを通ってきましたし、新人のミスは特権でもあります。
なぜなら、あなたの「小さなミス」の裏には、組織がまだ誰も気づいていない仕組みの穴が必ず隠れているから。
落ち込む気持ちは一旦横に置いて、ミスをチーム全体の成長に変えるチャンスにしませんか?
「次から気をつけます!」の精神論で終わらせず、明日から行動に移せる具体的な「仕組みづくり」にフォーカスした3つの自己分析ステップを紹介します。
このプロセスを経れば、あなたのミスは「自己否定の波」ではなく、
「組織の仕組みをアップデートする最高のフィードバック(FB)」へと変わります。
1.「表面的な原因」を深掘りする:構造的なトリガーを探せ
ミスをした瞬間、感情で「最悪だ」「注意力が足りなかった」と処理しがちですが、大切なのは事実ベースで原因を探ること。
そこには、あなたの仕事の進め方や環境に潜む“構造的な原因”が隠れています。
思いついた理由を出発点に、「なぜ?」を繰り返して根本原因(トリガー)を特定しましょう。

たとえば「時間が足りなかった」なら、「なぜスケジュールが詰まっていたのか?」まで掘り下げます。 「勘違いしていた」なら、「なぜ認識合わせができなかったのか?」を考える。こうして、自分の行動の癖や仕事環境の弱点が見えてきます。
2.「仕事のゴール」から逆算する:ミスの本当の影響度を測れ
原因を特定したら、次はミスの意味を理解するステップです。仕事の目的はタスクをこなすことではなく、最終的な成果(ゴール)を出すこと。
ミスを「小さな失敗」として片付けず、仕事全体にどんな影響を与えたかを冷静に見てみましょう。
- 最終ゴール:社員Aさんが初日から気持ちよく働けるようにサポートする
- ミスの内容:入社案内メールに提出書類リストを入れ忘れた
単なる「うっかり」ではなく、「社員Aさんに不安を与え、良いスタートを妨げた」
という形で、チームのゴールにも影響した。
この視点を持つことで、ミスを自分の評価と切り離し、
「次はチームのゴールを支えるためにどう動くか」という前向きな意識に変えられます。また、ゴールまでの流れを見直すと、「どの時点でミスを発見・挽回できたか」も見えるようになります。
3.ミスを「予防・発見」する仕組みを作る:再発防止をシステム化せよ
根本原因を特定したら、具体的な「仕組み化」の行動に移しましょう。

「反省」や「気をつけます」では再発は防げません。
しかも、あなたがしたミスは他の誰にも起こりうるもの。
だからこそ誰がやってもミスが起きにくい仕組みを具体的に作り上げることが大切です。
結論:ミスはチームの「財産」にミスは決して一人で抱え込まないでください。
たとえば私の所属する人事チームでは、毎週の定例会で「ヒヤリハット報告」を行っています。そこでは、「こんなミスが起きた」「これってあってますか?」という話を、
誰かを責めるのではなく、次に活かすための前向きな対話として共有しています。
「ミス→共有→改善→仕組み化」という流れを積み重ねることで、誰かのミスがチーム全体のFBにつながります。 単なる状況の報告だけでなく、作業をする上で気を付けているポイントを聞けたり、時にはシステムの変更を行ったりと、チーム全体の学びや注意喚起の場になっています。
あなたのミスは、チームの仕組みの穴を示す最高のヒントです。
自己否定に終わらせず、このサイクルを回し、個人の経験を「誰がやってもミスが起きない仕組み」というチームの財産に変えていきましょう。
あなたの失敗こそが、組織をアップデートする最も貴重なフィードバックなのです。
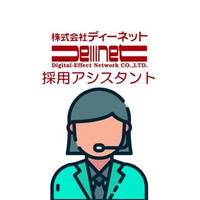

/assets/images/20409788/original/c7759344-5d81-41dd-84d8-3498af84e149?1739435698)

/assets/images/10036878/original/59bd3188-ca79-4888-af3d-c93410655eef?1659426515)



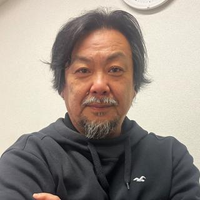
/assets/images/17025525/original/59bd3188-ca79-4888-af3d-c93410655eef?1708052842)

