※このストーリーは、noteで発信した記事を転載しています。
こんにちは! カンリーでエンジニア採用を担当している宮本です。
以前、EM4人が座談会をしている様子をお届けしましたが、いかがでしたか? きっと、「もっと知りたい!」と思った人が多いんじゃないでしょうか...? ということで、今回は、Dev2のEMをしている佐々木さんに、お話しをお聞きしてみたいと思います。
佐々木さんが今、何を考え、どんなことに取り組んでいるのか。また、EMの役割についてどのように考えているのか——ふだんはなかなか聞けないことも盛りだくさんの内容なので、ぜひ、ご覧いただけると嬉しいです。
▼【EM座談会】リーンコーヒーやってみた|EMが考えていること、悩んでいること、ちょっとだけ公開します!
”全員”がAIを活用できる環境をつくる
宮本:
まずは、EMとして力を入れていることを教えていただけますか?
佐々木さん(以下、佐々木):
やはり、AI活用ですね。エンジニア組織全体としてAIを使った開発の効率化を目指していて、OKRにも入っているので、わたしだけが力を入れているわけではないですが。主に、DevinとCursorを使っていて、Devinの活用率は全PRの10数%〜20%2025年6月時点)。もちろん、人が作成したPRの中でもCursorを利用しているはずなので、Cursorでメトリクスを取れるようになれば、AIの活用状況がもっと具体的にわかるはずです(現時点では、Devinしかメトリクスが取れてない状態)。
宮本:
Devinは今年の2月から使い始めて、ここ2ヶ月くらいでみんなが一気に使い始めた感じがします。
佐々木:
AIに限らずこういうツールは、CTOやEMなど、一部の人だけが使えてもしょうがないですからね。全員が使ってはじめて、組織全体の生産性向上につながるものですから。そこでいうと、メンバーにもどんどん使ってもらって、使いこなせるようにフォローするのが、EMの役割だと思ってます。
![]()
ありがたいことにうちのチームでは、AIにあまり抵抗がなく、すぐに触って使い始めてくれるメンバーが多かったのですが、一方で、なかなか踏み出せないメンバーもいました。そこで、エディターの導入から一緒に始めて、AIには繰り返し作業が向いているんじゃないか、などアドバイスをしながら、少しずつ慣れてもらうようにしました。
ほかの例を挙げると、いきなりコーディングを始めるのではなく、AIを使ってdatadogのダッシュボードでアクセス数や500系のエラー件数、データベースのCPU使用率などのチェックや調査をお願いするケースもあります。そこで不正アクセスと思われるものが見つかった場合などは、AIを活用しWAFルールを追加してもらうなどの対応を行います。こうして調査からコーディング、と、段階的に任せていくことで、より俯瞰的な視点で「こうやったら効率化できるかも! 」と思いついたりできると、自然と「もっとAI使ってみたいな」と感じられるようになるのかなと。仕事なんだからやってください、ではなく、モチベーションを持って取り組めるように、一人ひとりの志向や得意・不得意に合わせて整えてあげるのが大事な気がしています。
宮本:
CTOの小出さんも言っていましたが、ツールを渡して「はい、使ってください」だけじゃ、浸透しないですものね。
佐々木:
ほんとに。当面の目標としては、使いこなせるだけでなく「このタスクはDevinにお願いしよう」という判断が自分でできるようになれば、最高ですね。
1on1:タスク確認はなし、キャリアを一緒に考える
宮本:
EMといえば、メンバーマネジメントが重要な役割のひとつだと思うのですが、佐々木さんのお考えをお聞かせいただきたいなと。具体的に、1on1はどのような形でやっているんですか?
佐々木:
基本的には、月1回、1時間です。
宮本:
一般的には、週1回、30分〜1時間という形が多い気がするのですが。あえて少なくしているのですか?
佐々木:
少ないことに理由があるわけではないんです。日々、コミュニケーションをとっていて、タスクの進捗確認や相談などは週次でMTGをしていて、緊急の相談があればすぐに会話もしている。その上でさらに週1回の1on1があると、メンバーにとっても負担になってしまうのかなと。
宮本:
コミュニケーションが多ければいい、というわけではないと。
![]()
佐々木:
ですね。ちなみに1on1ではコンディションやタスク確認などは一切しません。ふだんのコミュニケーションとは、目的を完全に切り分けていまして。1on1はキャリアについて真剣に向き合う場だと取り決め、お互いに認識できているおかげで、深い話ができていると感じています。
宮本:
1on1のテーマはキャリアということですが、具体的にはどんなお話しをされているんですか?
佐々木:
マネージャーになりたいとか、エンジニアとしてレベルアップしたいとか。目指しているキャリアに近づけているのか、もし近づけていないのなら、どうやったら近づけるのかを一緒に考えています。やるべきことを決めて、毎月、進捗を確認したり、必要であればアドバイスをしたりもします。
また、できる範囲で、本人のキャリアにとってプラスになるような役割だったり、業務だったりを任せるようにもしています。
チーム開発:できるだけ個人の成長、willに寄り添う
宮本:
一人ひとりのキャリアに向き合う姿勢、めちゃくちゃすばらしいです! 一方、会社である以上、また、チームで開発している以上は、組織と個人のバランスも考えなくてはいけないのかなとも思っていまして。実際、どのようにバランスを取っているのですか?
佐々木:
むずかしいテーマですよね...。会社と個人のやりたいことが重なる部分を見つけて、両方の成長に寄与するというのは。ただ、放っておくと、どうしても個人の成長が後回しになってしまうので、チームの状況に合わせて意図的に仕事を配分するようにしています。
宮本:
意図的、というと?
佐々木:
Dev2は、時期によって開発スタイルが大きく変わります。その特性を利用しているという感じですね。
ひとつは、カンリーホームページやカンリーカスタムシリーズのリリース、リニューアルに合わせて開発をする時期です。とにかくリリースに間に合わせるのが最優先なので、期限、スケジュールに合わせてメンバーを配置、役割分担をしていきます。
とはいっても、Dev2のメンバーは比較的、在籍期間が長い人が多く、最適な配置、役割がほぼ決まっているんです。しかも、本人たちも役割を自覚していて、自ら動いてくれるので、めちゃくちゃありがたいです。
この時期は、個人の成長とリンクしているかどうかは考えず、リリースという目標達成に向け、チーム一丸となって開発に取り組みます。
宮本:
たしかに、この状況で個人の成長を考えるのはむずかしいですね...。いわゆる適材適所で回していくのが正解な気がします。
佐々木:
ですよね。ただ、それ以外の時期は、期限がない分、時間やリソースに少し余裕ができるんですね。そこで、他の領域に挑戦してもらったり、初めての作業をしてもらったりと、できるだけフルスタックに動いてもらうようにしています。もちろん、プロダクトや事業のグロースに向けてスクラムを回し続けることは大前提ですが、こういう、メンバーにとって新たなチャレンジ・個人の成長となる時間もしっかり作っていきたいなと考えています。
EMはたいへん?──それでも“人と向き合う”おもしろさがある
宮本:
そもそものところも聞きたいなと思っていたのですが、佐々木さんはなぜ、EMになりたいと思ったのですか?
佐々木:
もともとシステムの機能がどのように作用するのかを考えたり、動かしたりするのが得意だったんです。それで、人も同じようにできるんじゃないかと考えていたのですが...浅はかでした。
人の感情や動きには正解がなく、システムを動かすのとは比べものにならないくらいむずかしくて、今も試行錯誤し続けています。それでもなんとかやってこれているのは、メンバーのおかげです。ほんとにありがたいです。
![]()
宮本:
人を動かすのはむずかしいとおっしゃっていましたが、マネジメントや組織づくりで気をつけていることはありますか?
佐々木:
そんなたいそうなものではないですが、一番大事にしているのは、笑顔です。仕事って、楽しいことばかりじゃなくて、たいへんなことのほうが多いじゃないですか。だからこそ、笑っていられる環境を作れたらいいなと思っています。





/assets/images/6358952/original/2305ec05-b5a2-47e5-8d8b-19992877635b?1614908067)
/assets/images/6358952/original/2305ec05-b5a2-47e5-8d8b-19992877635b?1614908067)


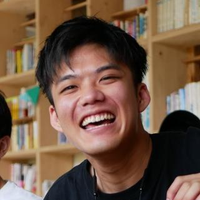

/assets/images/6358952/original/2305ec05-b5a2-47e5-8d8b-19992877635b?1614908067)
