- 広告プランナー・ディレクター
- 人材紹介コンサルタント
- 労務・会計・総務
- Other occupations (23)
- Business
- Other
ビジネスシーンでよく出てくる言葉、
「BtoB」
これは「企業と企業の取引」を意味する
「Business to Business」
の略語なのですが、この「BtoB」、あなたはなんて発音しますか?
はい、
「びーとぅーびー」
もしくは
「びーつーびー」
の2択で、まぁ「びーとぅーびー」と読まれることが多いんじゃないかなと思います。多分。
「びーつーびー」
と読むケースは、この
「BtoB」
を、さらに
「B2B」
と略す風習が生まれ、
「2」は、わん、つー、すりー、の「つー」と発音されやすいことから
「びーつーびー」
と呼ばれるに至ったのではないかなと推測しています。
どっちが正解か、と言われればどちらも間違いではないですが、
「とぅー」派の方が多いと思います。
そこでマーケティングのややこしいところである
「不特定多数への発信」と「たまに変な人がいる」のコンボが合わさるとどうなるか。
「to」も「two」も「とぅー」の発音の方が近いから
「びーつーびー」はありえない!「びーとぅーびー」こそ唯一の正解だ!
という「とぅー原理主義過激派」が急に現れるんです。
別にどっちでもいい。
でも急に暴れだすんです。
「自分は間違っていないのに!」
と、とても悲しい気持ちになります。
べつにどっちでもいいので無視したいんですけど、やたら声がでかくてしつこいケースもあり、ややこしいので可能なら避けたい。
「びーつーびー」では危険性がある。
では、常に「びーとぅーびー」と言っておけばいいのか。
それもまた違うんですよ。
例えばプレゼンの場で、資料上の表記では「B2B」となっているのに「びーとぅーびー」と読むと
「BtoB」ではなくあえて「B2B」と記載してあるんだから、ここは「びーつーびー」と読むべきだろ!
という、また別の「2ならばつー原理主義過激派」が出てくる可能性もあります。
とはいえ、過激派はごくごく一部のレアキャラです。
基本的には穏健派が多く、
(こいつ変な事言う奴だな・・・)
という熱い想いを心の内に秘め、人知れず発言者を見下す「原理主義穏健派」の方が数としては圧倒的に多いです。
結果何が起きるかというと、本人としては「しっかり話せたはず!」という自己評価なのに「なんか全く刺さってなさそう」という結果に陥るのです。
穏健派は迷惑ではないのですが「変な奴」や「非常識な奴」のレッテルをそっと貼り付けてくるので関係性構築上、非常によろしくないという訳です。
他の事例もたくさんあります。
例えば、日本語の誤用関連での勘違いとして次のようなものもありますね。
申し付けください 問題
「申す」は謙譲語なので「お申し付けください」という言い回しを不自然に感じる人がいる問題。
別にまったく問題ない。
おられる、いらっしゃる 問題
「おる」は「いる」の謙譲語なので、他者に対する「〇〇様はおられますか」のような使い方は不正解だ!とする人が日本に半分くらいいる問題。
別に間違いではない。
特に関西と関東で感じ方が大きく変わったりする。
有難うございます 問題
公文書において「ありがとうございます」はひらがなで表記することを基本とする決まり(?)があるそうです。
これを根拠として漢字表記を間違いだと勘違いしている人もいますが、間違いではありません。
なお「有難うございます」の「ございます」を「御座います」と表記するのは日本語のルール的に間違いです。
などなど。
あとは商品名やブランド名の固有名詞をそのモノを表す一般名詞として間違って使っているケースとか。
ユンボ 問題

ショベルカー全般を「ユンボ」と呼ぶことがありますが「ユンボ」は商標ですので、例えばコマツ製のショベルカーを「ユンボ」と呼ぶのは間違いです。
小型のプロペラ機を全部「セスナ」と呼ぶ、
テレビゲームを全部「ファミコン」と呼ぶなども同じケースです。
現代のSNSでPS5のことを「ファミコン」などと呼称しようものなら「おじいちゃんwww」といったコメントが入ることは想像に難くありません。
ユンボ問題に近いところで、
タイラップ、インシュロック 問題
というものもあります。
どちらもいわゆる「結束バンド」の商標なのでユンボ問題と似たような事例なのですが、こちらはもっと根深いです。
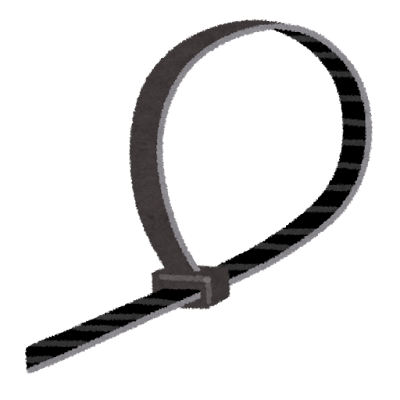
自動車業界では「タイラップ」、電工界隈では「インシュロック」と呼ばれることが非常に多く、どれくらい多いかといわれると「結束バンドと呼んだところ全く通じなかった」という現象がそれなりに起こるくらい多いです。
ここまで来ると知識ゲーです。
ショベルカーのことを「ユンボ」と呼ぶことは、PS5のことを「ファミコン」と呼ぶことと同じレベルで間違いなのは確実ですが、場合によっては結束バンドのことを「結束バンド」と呼ぶことも間違いになりうるのです。
間違ってはいないので、使っても問題が無いか、と言われればそれはまた違う、という事例です。
「定義上 間違っているかどうか」は重要ではない
LP制作、広告配信、SNS投稿、メルマガ配信、などなど
マウスをかちっとすれば、1秒後には自分が書いた文が何千人、何万人に届いてしまうものです。
すると、1秒前には「これでヨシ!」と自信満々だったものが「間違い」として表れてしまいます。
こわい!
大事なことは
「目的を果たすこと」
もっと極端な例を挙げましょう。
「アップルパイを売りたいので、このアップルパイの素晴らしさを語る」
というシチュエーションにおいて
「正しいから」
という理由で
「あっぷるぱい」
を
「/ǽpəlpài/」
と発音したとしましょう。
そうするとどうでしょう?
お客さんは
「なんだコイツ?なんでこいつアップルパイだけ発音いいんだ?なんのため?どういうこだわりだ?バナナのときも発音いいのか?バナナについての質問してみたら分かるかな?」
みたいなことを考えだしてしまうのです。
すると当然、
「このアップルパイの魅力」
は十分に伝わらず
「アップルパイを売る」
という目的も果たせなくなってしまうのです。
ユーザーの脳内に「ん?」とか「どっちなんだろう」という雑念が発生した瞬間、思考力はその疑問に割かれ、商品への興味が0になります。
つまり、どんなに良い事が書かれている記事でも、その記事の価値も0になるんです。
予定外の議論が発生した時点で負けなんです。
(炎上商法を狙う場合はそれに限りませんが・・・)
ターゲットの集団に対して、
誰が読んでも一緒、誰が読んでも同じ結論、という事が大事。
ターゲットを「男性」と設定するのならば、
「21歳男性のAさん」にも「89歳男性のBさん」にも同じ結果を届けるのが理想です。
定義やルール上は正しい表現だとしても、
ターゲットの集団がその表現をどう捉えるかによって、あえて間違った表現を選ぶ
であったり
個人によってとらえ方、解釈が分かれる表現は積極的に避ける
といった手段をとる必要があります。
ここで必要なのはいろいろな人になりきる想像力です。
年齢、性別、親の趣味、育った環境などなど、さまざまな属性の人をちゃちゃっと10人くらい頭の中に用意して、その人になりきって違う人の気持ちで台本を読んだり、動画を見たり、記事を読まないといけない。
もっと言うと記事を10回も読んでると時間がかかってしょうがないので、脳内に10人を用意してから同時並行で「なりきり読み」をする、という感じになります。
・・・と、ここまで
人の気持ちを考えましょう
という小学校の道徳みたいなことを3000文字以上に及んで書いてみたのですが、実際のところはそこまで考えすぎても無駄なことが多く、
些事は捨て置け!気にしすぎんな!まぁがんばれ!
くらいのマインドの方が大事です。
fin.

/assets/images/22260996/original/cc1637dd-5f32-487f-b267-bdf03d46aaaa?1760407212)

/assets/images/3751900/original/c21aebb8-dc5f-4ec0-800c-30c9e3062223?1557821330)





/assets/images/3751900/original/c21aebb8-dc5f-4ec0-800c-30c9e3062223?1557821330)

