私たちアクトビは2018年の創業以来、クライアントの事業成長に徹底的にコミットし、DX支援やシステム開発を手掛けてきました。本記事では、代表取締役CEO藤原とCTO石村の2人から、8期のリアルな軌跡と9期、そしてその先に見据えるビジョンについて語っていただきました。
インタビュイー紹介
藤原 良輔/ ACTBE Inc. 代表取締役 CEO
1987年9月22日 大阪生まれ 自動車整備の専門学校を卒業。
メルセデス・ベンツ正規ディーラーにてメカニックとして勤務。メルセデス・ベンツ公認メカニック2級を取得後、退職し個人でダイニングバーを開業。その後、プログラマを志し東京のSIer企業へ転職。複数のiOS/Androidアプリ受託案件やIoTサービスの立ち上げを経験。アプリケーションエンジニアとして主にiOS/Androidアプリを企画からローンチ、運営までを一人で経験する。同時にマーケティング、サポート業務も経験。 その後、コンサルティングベンチャー企業を経てフリーランスエンジニアとして独立。地元大阪へ戻った後、2018年2月 ACTBE Inc.設立。
石村 真一 / ACTBE Inc. 取締役 CTO
1987年8月9日 兵庫県生まれ 新卒でシステム開発会社に就職し、7年でCTOポジションを経験。案件提案から納品まで複数の受託開発案件を経験した後、2017年にフリーランスエンジニアとして独立。独立後は、Webのフロントエンドからバックエンド、インフラ、設計まで幅広い領域での案件を個人受託しながら、複数の企業へ常駐エンジニアとして参画。2018年5月より、アクトビにフリーランスエンジニアとして所属し、エンジニア、プロジェクトマネージャーとして大規模案件を受け持つ。2020年4月に執行役員CTOとしてアクトビに参画し、実装も行う傍ら、フリーランスエンジニアのマネジメントや技術体制の強化、案件品質の担保に注力しエンジニアが最大限のパフォーマンスを発揮できる現場環境と、製品品質の担保に重点を置き、プロジェクト管理を行う。
わずか1年で売上150%を達成。その裏側にあった「苦闘と変革」のリアル
![]()
──まずは8期を終えられた際の率直な心境からお聞かせください。
藤原: 僕個人で言うと、8期はひたすら会社のステージを上げるための重要なプロジェクトに翻弄されていた一年でした。組織の“未来”を僕が、“現在”は石村に託すという役割分担をしているので、現場の最前線で舵取りをしてくれた彼が一番大変だったのではないかと思っています。
石村: 正直「しんどかったな」というのが率直な感想で、毎期気づいたら終わっている感覚です(笑)。特に8期は、内部管理体制を強化していく過渡期でした。これまでとは違うルールや体制への変化に、社内メンバーもかなり混乱したと思います。それに加えて、人の入れ替わりも激しかったので。だからといってやらないわけにはいけないし、プロジェクトも待ってはくれないので、残ったメンバーでどう乗り越えていくか、マネージャー陣と共に頭を抱える時もありました。
藤原: まさに、組織の成長痛です。人が辞めていく中で、残ったメンバーには相当な負荷がかかったと思います。
石村: そうですね。ただそのおかげで、マネージャー陣含むメンバー全員が大きく成長してくれたのも事実で。僕は以前まで“責任・権限を人に委譲する”というのが苦手で、マイクロマネジメント気味になってしまう部分もあったのですが、そこの改善に努めた結果、マネージャー陣が「自分たちで考えて解決しよう」と自走してくれるようになった。彼らの課題解決能力の高さに気付かされた一年でもあり、自分と同じく熱意を持って、諦めずやるべき事に取り組んでくれるという信頼がより強くなったからこそ、心理的な負担は、以前までと比べるとむしろ軽くなったかもしれません。
「現在」の地盤固めと「未来」の市場開拓。両輪で進めた、成長戦略とは
![]()
──困難も多かったと思いますが、そもそもどのような目標を立て、その達成に向けて何に取り組まれていたのでしょうか?
石村: 8期の目標として大きく掲げていたのは「売上」と「人員計画」です。この両輪を回すために、僕の方では組織の地盤を固めることに注力しました。具体的に取り組んだのは、大きく3つで、
1つ目は「自身の役割を変えること」。それまでは僕自身がプレイングマネージャーとして動きすぎていたのですが、それでは組織はスケールしない。そこで、プロジェクトの初期段階で「誰がボールを持つか」を明確にし、僕はアドバイスと管理に徹するよう意識的にシフトしました。
2つ目は「教育方法の変革」です。そのために、僕自身の思考や行動を完全にオープンにしました。自分が行った商談の録画や面談の記録、たとえ失敗したものでも全てメンバーに共有したんです。生々しいリアルなやり取りや失敗すらも見せることで、教科書にはない学びを得てもらうことが目的でした。
──かなり思い切った情報共有ですね。フィードバックの方法も変えられたとか。
石村: それが3つ目のアクションです。どのような場面でも“ストレートなフィードバック”を徹底しました。相手の感情や言葉の言い回しを気にしすぎると、本当に伝えたかったことがぼやけてしまう。遠回しに言われても、相手は結局どう動けばいいのかわからないですよね。だから、「できていること」と「できていないこと」をあえてオブラートに包まず、感情的にならず、事実としてストレートに伝えるようにしました。その上で「どうするか」を本人に考えてもらう。この方が、結果的に本人の成長に繋がると考えたんです。
藤原: 石村が組織基盤を固めてくれている間、僕の方では会社の新たな収益源となる、中小企業マーケットの開拓に集中していました。既存のやり方だけでは持続的な成長は難しい。そこで、新たな市場として中小企業に目を向け、彼らがなぜDXに投資しないのか、その本質を探るために約100社の経営者に直接ヒアリングして回ったりしていました。
──100社!すごいですね...!そこから何が見えてきたのでしょうか?
藤原: 見えてきた結論は、非常にシンプルでした。中小企業経営者の心を動かせるのは、綺麗なコードやフレームワークなどの理屈じゃない。「あなたに頼みたい」と言わせられるかどうか、その人間関係が大切なんだと。つまり、技術力以前に、人として信頼される人間力が問われるわけです。
石村: 藤原が導き出したその結論は、僕が現場の顧客体験で感じていたことと、まさしくリンクしていました。僕たちもDX推進は必ず「人の問題」に直面すると感じていたので。技術的な解決策を提示するだけでなく、その実行過程で生まれる社内の軋轢や人間関係といった、泥臭い部分まで踏み込んで支援できることこそが、アクトビの提供価値なんだと。
藤原: そうですね。そして「人間力」が重要という気づきが、会社全体の大きな方針転換にも繋がりました。8期の夏に行った役員合宿で「うちって何の会社なんだ?」という根源的な問いに向き合った結果、僕たちは「人を育てる会社作り」を会社の根幹に据えることを決めたんです。それに伴い、僕自身の役割も変えました。これまで自分が策定していた予算計画の権限を、今期から石村とマネージャー陣に委譲し、僕はより未来の構想に集中できる体制を整えました。
──8期の目標に対する最終的な着地はどうでしたか?
石村:結果として、売上目標は達成しました。前期比で150%の成長です。一方で、人員計画は達成できませんでした。期末に着地35名という計画だったのですが、退職者が相次ぎ、最終的には28名ほどになりました。
藤原: つまり、“人が増えていないのに売上が50%伸びた”ということです。これは、一人ひとりの提供価値が上がった証拠でもありますが、同時に、組織としては非常にいびつな状態だったと言えます。この点は9期でも引き続き向き合っていく必要があるテーマですね。
失敗から得た確信。9期、そして未来へ繋ぐ「人を育てる」という思想
![]()
──そうした様々な取り組みを通して、お二人が得た一番大きな「気づき」や「学び」は何でしたか?
藤原: やはり一番の学びは、採用のあり方、特に「期待値コントロール」の重要性ですね。8期は人の離職に苦労しましたが、これは入社してくださった方と僕たちとの間で、お互いの期待値がズレていたことが大きな原因だと考えています。
特にキャリア採用では、ご本人がこれまで培ってこられた成功体験や仕事の進め方と、僕たちが求めるベンチャーならではの動き方との間にギャップが生まれてしまい、お互いにとって不幸な結果になってしまいました。
石村: 特に、「成長したい」という言葉の解像度を面談・面接の中で高められていなかったなと思います。例えば、「会社が用意した環境を活用してスキルアップしたい」という想いと、「環境を自ら作り出し、未知の挑戦を繰り返すことで成長したい」という想いでは、求めるものが全く違います。僕たちは後者のようなより能動的な方を求めていたにもかかわらず、面談や面接の中で細部まですり合わせすることができず、入社後のギャップを生んでしまった。これは大きな反省点です。
藤原: ただ、この大きな学びがあったからこそ、明確な一歩を踏み出すことができました。それが、先ほど話した「“育てる前提”で人を採用する」という方針へ、完全に振り切るという意思決定です。短期的な戦力を追うのではなく、長期的な目線で仲間を育てていく。そのために、再現性高く成長できる仕組み、「アクトビOS」の構築にも着手しました。この方針転換こそが、8期に得た最も価値ある学びだったと思っています。
![]()
アクトビOS:アクトビという組織に在籍することで、時代に沿った活躍のフィールドを広げられるための滑走路と正しく成長するためのルール
──その学びは、9期の目標にも繋がっているのですね。
石村: はい。9期は新たに16名を採用するというチャレンジングな目標を立てていますが、これは「育てる」覚悟の表れです。この目標達成の鍵は、間違いなく「メンバー一人ひとりの成長」。45名規模の組織になった時、恐らく僕一人では見きれないでしょう。全員が自分自身で考え、責任を持って自走できる組織を作ることが、9期の最重要課題です。
そのためにもまずは教育体制を確立したいと考えています。現在は僕自身がジュニア層を教えるなど、階層を飛び越えた「教育のジャンプ」が頻発しており、これでは組織がスケールしません。マネージャーがシニアを、シニアがジュニアを教えるという「ピラミッド型」の教育体制で、再現性のある人材育成を目指すとともに、それぞれが注力すべき業務や向き合うべき課題に取り組める状態を作りたいと考えています。
──石村さんが組織内部の強化に注力される一方で、藤原さんは全社的、対外的な視点からどのような目標を掲げていらっしゃいますか?
藤原: 9期は、僕たちが策定した5カ年の中期経営計画「エンジニア・デザイナーの職域の再定義」の実行元年。この計画を全社員にオープンにし、全員で目標達成に挑みます。
その中でも戦略の核にしていきたいと考えているのが、AIエージェント領域です。今後、ソフトウェア開発会社のM&Aが活発化し市場が淘汰されていく中で、僕たちのような「単に作るだけでなく、顧客の課題解決まで踏み込める会社」には大きなチャンスが来ます。その好機を捉え、「AIエージェントといえばアクトビ」というブランド認知を本気で獲りに行きます。
そして、この大きな戦略を加速させるために、自社での成長だけでなく、他社との業務提携やM&Aも積極的に視野に入れています。8期は基盤固めに徹した分、今後はあらゆる手段を講じて事業を「拡大させる」つもりです。
圧倒的な成長を約束できる、アクトビという環境
──最後に、9期の目標を達成するために、どのような仲間を求めているか、メッセージをお願いします。
石村: 一言で言うと「根性のある人」ですね。もう少し具体的に言うと「レジリエンス力」のある人。僕たちの環境は、体験からの学習が基本です。チャレンジして、失敗して、そこから立ち上がって強くなっていく。そのプロセスを楽しめる人、変化に対応できる人と一緒に働きたいですね。
藤原: そうですね。ここ数年、IT業界は「ワークライフバランス重視」というイメージが定着しましたが、その流れに乗って3〜5年を過ごしてきた人と、死ぬ気で努力してきた人とでは、今、圧倒的な差がついています。ただコードを書くだけで稼げる時代は終わりつつある。そのことに焦りを感じ、ビジネスパーソンとして本気で成長したいと思っている人であれば、僕たちは絶対に成長を約束できます。
石村: アクトビは、その「正しいしんどさ」を体験できる場所です。
藤原: 勿論、成長するというのは簡単なことではありませんが、道中すらも楽しみながら、その先にある圧倒的な成果を一緒に掴んでいきたい。そういった“想い”を持った方からのエントリーを、心からお待ちしています。
さいごに
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
今回は、CEOとCTOの対談を通じ、組織の「現在と未来」をお届けしました。 前年比150%という急成長を遂げるアクトビが、今まさに変革の真っ只中にいることを感じていただけたかと思います。
アクトビは現在、採用強化中です!
この記事を通して、少しでもアクトビにご興味をお持ちいただけましたら幸いです。 カジュアル面談も常時受け付けていますので、ぜひご応募ください。
▼アクトビ各種サイトリンク
◼︎公式YouTube【ACTBE CORE】
◼︎アクトビ公式Podcast【Purpose Driven|次世代のエンジニア組織】
◼︎アクトビ公式 Member Tech blog






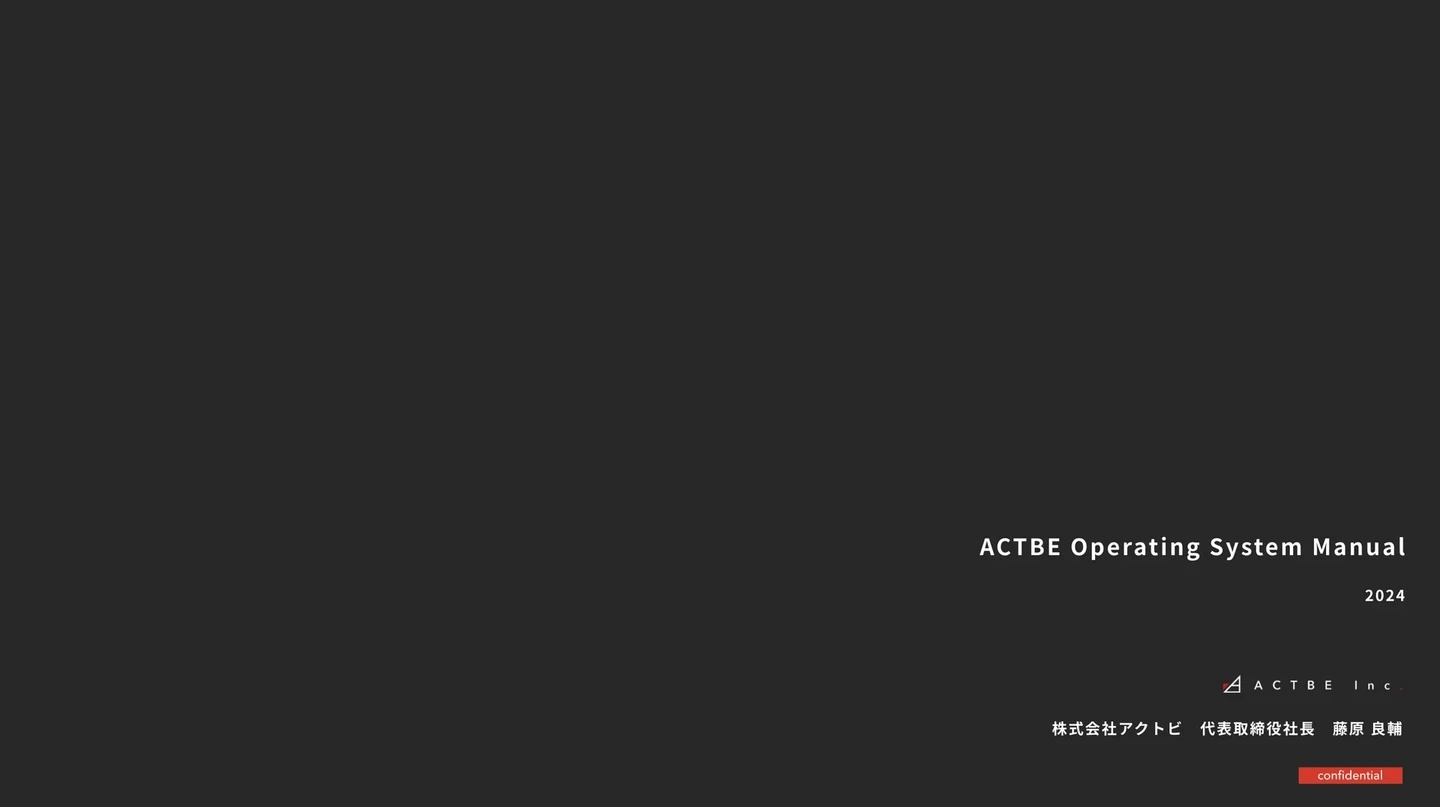
/assets/images/21567198/original/2cb93679-4a52-4b1a-97e3-aa24d0312e4a?1752215427)

/assets/images/5294989/original/db8e32e9-5207-446d-bc78-2ee587fea895?1594858379)


/assets/images/5225085/original/0a69dfdf-2913-4300-94fe-b9cc71812787?1593509626)

