- 採用人事
- リードバックエンドエンジニア
- Others
- Other occupations (10)
- Development
- Business
- Other
今回は、エンジニアとして活躍する川又亜弓に、これまでのキャリアと仕事への想いを聞きました。幼少期のパソコンとの出会い、SIerでの多岐にわたる開発経験、そしてアソビューへのジョイン。常に直感を大切にし、変化を恐れずに新しいことに挑戦してきた川又の言葉は、エンジニアだけでなく、自由で柔軟なキャリアを切り開くヒントが詰まっています。
プログラミングとの出会いは、物心つく前から
川又にエンジニアを志すようになったきっかけを聞くと、幼少期の原体験に遡ることになった。
きっかけ、明確なものはないんですよね。家にあったパソコンを物心つく前から触っていて、小学校の低学年の頃には「きっとこれでご飯を食べていくんだろうな」と直感的に思っていました。
父が買ってくれたパソコンで、色々なゲームをしていました。夢中で遊んでいました。
その流れで、小学校の卒業文集には迷うことなくプログラマーになりたいと書きました。
当時はシステムエンジニアとかプログラマーという言葉自体を知らなかったので、母親に「きっとこれでご飯を食べていくんだけど、職業は何?」と聞いたのをそのまま書いたんです(笑)。
プログラマーになりたいという思いは冷めることなく続いていましたが、高校生まではソフトボールに打ち込んでいて、ソフトボールができる強い部活がある高校に進学し、大学は、情報系の学部を選びました。実はこの大学選びも、一番最初に行ったオープンキャンパスで「ここだ!」と直感で決めたんです。
決断の源泉を直感で選択してきた川又。彼女の直感力は就職活動でも発揮されたのでした。

▲今でも川又はソフトボール社会人チームの所属している
SIerでの6年間はまるで「精神と時の部屋」
大学卒業後は、SIerに就職しました。そこを選んだのも直感だったんですけど、面接で「ものづくりを大事にする会社」という言葉に惹かれたんです。実際に入ってみると、必ずしもそうではなかったのですが(笑)。
就活自体はIT企業を中心に見ていて、作ったシステムを使うお客さんの手触り感を感じられるものづくりがしたいと考えていました。
その中で、自社サービスをやっている会社と、BtoBで受託開発をやっている会社で迷いましたが、最終的には、目の前で「ありがとう」と言われる仕事がしたいという思いが強くて、SIerを選びました。
自社サービスだと、自分が作ったサービスを使っている人が見えにくいイメージがあったんですよね。SIerなら、目の前のお客さんのためにものづくりをして、直接感謝の言葉を聞ける。そこに貢献実感があると感じたんです。
顧客・使い手に貢献している手触り感を大切にする川又はSIerに新卒から6年間で多岐に渡る業界のシステム開発をになってきたといいます。
私がたまたま配属されたチームの課長が、マネジメントと並行して自分でもバリバリ開発をする人で、新規開発案件を1年くらいの短いスパンで要件定義から開発まで行うのを繰り返していました。
1年周期で、お客さんも業界もどんどん変わるので、常に新しい技術や知識を吸収する必要があって、すごく鍛えられました。
例えば、インフラ系企業様の実証実験のシミュレーションを作ったり、食品製造会社さんの倉庫で使う在庫管理アプリや一般のお客様向けのオンラインショップを作ったりと、本当に多種多様な開発を経験させてもらいました。まるで「精神と時の部屋」にいるみたいで、6年間があっという間でしたね。
SIerでの6年間で、様々な業界のシステム開発に携わることができた経験は、現在の川又のキャリアの土台になっているといいます。
アソビューへの転職。「伸びしろ」に惹かれた
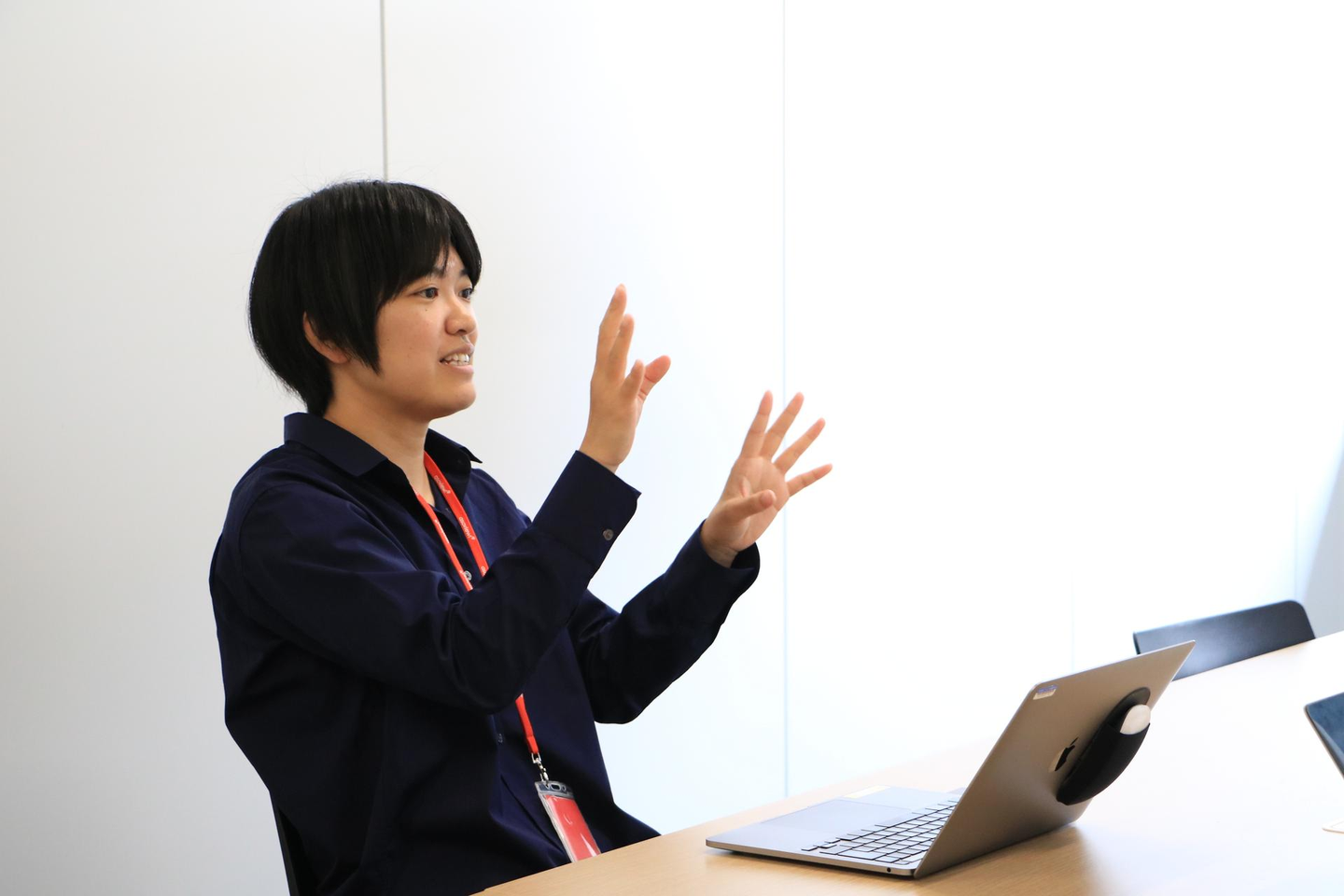
アソビューへの転職のきっかけを聞くと、完璧なアプリサービスを提供する企業と、改善できることが山積みのアソビューの2社から検討し、伸びしろしかないアソビューに決めたといいます。
SIerでの仕事は面白かったのですが、後半はマネジメント業務が増えてきて、自分で手を動かす時間が減ってきました。「もっと自分で作れる仕事がしたい」という思いが強くなり、就職活動の時から気になっていた自社サービスをやっている会社への転職を考え始めました。
その中で「アソビュー!」は利用した経験もあったので選考に進んでみることにしました。採用面談の中で横峯さんとお話した時に、すごく可能性を感じたんです。
正直、当時のアソビュー!は、競合他社と比べるとまだまだ改善の余地があると感じました。
でも、横峯さんが「伸びしろしかない。一緒にやってほしい」と語っていて、その事業を成長させるという部分にすごくやりがいを感じたんです。「ここなら、一緒に成長していける」と思い、入社を決めました。
最後、アソビューともう1社から決めることにしたのですが、もう1社の方は、利用者として使ってみるととても洗練されたサービスを提供していて、とても好きな会社ではあったんです。
でも、既に完成されたサービスより、伸びしろしかなくて、これから一緒に大きくしていけるという感覚がアソビューにはあって、ワクワクしました。
入社後、1年経たずして川又は、新規事業のふるさと納税の開発責任者に抜擢されました。
いつか、新規事業の開発責任者をやりたいという思いはあったのですが、実は、私自身、当時ふるさと納税をしたことがありませんでした。
当時CTOの江部さんに「ゼロから事業をやるのは面白いぞ」と背中を押されて、挑戦してみることにしました。事業責任者の富岡さんをはじめ、営業チームのメンバーと密に連携を取りながら、まずは年末の公開に間に合わせることを最優先に、開発を進めていきました。
開発を進めるに当たって一番意識したのは、営業チームとの連携です。どんなに良いサービスを作っても、自治体さんに掲載してもらえなければ意味がありません。そこで、開発の初期段階から、営業チームと密にコミュニケーションを取り、彼らが自治体さんに提案しやすいように、サービスの内容や魅力を共有し続けました。まだ動かない状態でも、画面イメージのようなものを見せながら、「こんなサービスを作っています」と伝えてもらうようにしていました。
例えば、自治体の担当者様は、寄付者からはどんな画面で寄付に進めるのかやその使いやすさを気ににされます。そのため寄付者の方に見える部分を先に作ったり、自治体さんが掲載を検討しやすいような情報を提供したりと、事業を一緒にスタートさせるために、どうしたら良いかを常に考えていました。
前職では、どうしても開発側だけの視点になりがちだったので、アソビューに来て、事業全体を見るという意識が強くなったと思います。
スクラムマスターとして、チームの成長を後押しする
ふるさと納税事業を軌道に乗せた川又は、現在座席指定の開発チームに席をおいています。0→1を自らの手で作り上げたふるさと納税を離れることになった経緯を聞きました。
座席指定はプロダクトとして非常に期待されている領域で、現在も開発と実装が同時並行で事業運営をしています。ところが、開発がなかなかスムーズに進んでいない、という課題があったため、スムーズな開発を実現する優先順位付けやチームビルディングをメインのミッションとして、異動することになりました。
実はこの異動が自分のキャリアを見つめ直す良い機会になっていて。これまで、ずっとものづくりの現場に携わってきましたが、AI技術の進化などによって、自分が手を動かさなくてもできることが増えてきています。そんな中で、「自分にしかできないことは何だろう?」と考えるようになりました。
私は認定スクラムマスターの資格も持っているので、その知識や経験を活かして、座席指定開発チームをより良い方向に導けるのではないかと考えました。スクラム開発の考え方をチームに浸透させ、開発スピードを上げ、チーム全体の成長を後押ししたいと思っています。
川又は前職マネジメント経験があり、手を動かせなくなることへの懸念があったことから、スクラムマスターとマネージャーの違いを聞くとコーチングに近いという答えが返ってきました。
スクラムマスターは、マネジメントはしません。チームメンバーが自律的に成長し、行動できるよう促す、コーチのような役割です。メンバー自身に課題解決のイメージを持ってもらい、そこに向かって進めるようにサポートします。
座席指定開発チームに異動してまだ1ヶ月ほどですが、エンジニアの意識や行動が少しずつ変わってきているのを感じています。その変化を見るのが、今はすごく楽しいです。
アジャイル開発の概念はエンジニア以外の職種にも転用できると思っていて、アジャイルな考え方は、様々な分野で活用できる可能性を秘めていると感じています。
今後は座席指定開発チームでアジャイル開発を定着させ、チームと一緒に成長していきたいです。そして将来的には、アソビュー全体がアジャイルな組織になれるように、その考え方を広めていきたいと思っています。スクラムマスターとして、チームや組織の成長をサポートすることに、大きなやりがいを感じています。
常に直感を信じ、変化を楽しみながらキャリアを切り拓いてきた川又。彼女の直感力とそれを正しい選択にしていく好奇心と探究心は良いプロダクト作りに貢献しています。
撮影:加藤源也









