- Webディレクターアシスタント
- Web Engineer
- オープンポジション・新卒/中途
- Other occupations (35)
- Development
-
Business
- Webディレクターアシスタント
- Project/Product Management
- Webディレクター
- Webディレクション
- テクニカルディレクター
- webディレクター
- Webディレクター/実務経験無
- Webディレクター/プロマネ
- リモート/プロジェクトリーダー
- コンテンツディレクター
- 企画・制作ディレクター
- Webディレクター(業務委託)
- ディレクター・プランナー
- 経理・会計
- アカウントプランナー
- デジタル広告の企画・運用
- SNS運用(新卒・中途・副業)
- デジタルマーケティングの提案
- SNS運用アシスタント
- Marketing / Public Relations
- SNS運用ディレクター
- 社会人インターン|副業ライター
- webメディアライター・編集
- Other
「AIを使えば、未経験でも開発ができる」と耳にすることが増えました。でも実際にそれを体験し、形にして、リリースした人のリアルな声は、まだあまり聞かれません。
クリエイティブ・テックエージェンシーのTAMに入社した和田優里香さんは、前職が教育関連という異業種出身。そんな彼女が、入社わずか2日目からAIを相棒に、社員紹介ツールの開発を任されました。
3ヶ月でツールを完成させた和田さんが、その過程で得たのは「AIをどう使いこなすか」以上に、「自分の頭で考える力」だったと語ります。実務未経験からIT領域へ。AIと共にキャリアを切り開く、ひとつの等身大の実践記です。
入社2日目、突然の依頼はあまりにも衝撃的だった
──入社して最初に任された仕事は何でしたか?

株式会社TAM テクニカルディレクター 和田優里香
大学卒業後は、お子さま支援の会社に就職。2年半、発達支援に携わる中で、今とは違う形で人のためになる仕事がしたいと転職を決意。コロナ禍に学んだプログラミングを生かそうと、半年間のプログラミングスクールを経て、TAMに入社。
和田:入社初日はPCのセットアップで終わって、「明日から仕事かな」って思っていたら、2日目に突然、「社員検索ツールをAIで作ってください」と、代表の爲廣さんから言われました。
だけど、最初の頃の私は「CMSって何?」というレベルで(苦笑)。いきなり面と向かって「技術スタックはどうしますか?」と聞かれても、言葉の意味すら分からなくて、頭が真っ白に。
伴走役で上司の藤原(寛明)さんに後から聞いたのですが、その頃社内でAIを使った社員教育のプロジェクトが立ち上がっていて、「私がそこに“ちょうどよく”入ってきた」んだそうです。
──前職から全く違う分野への挑戦ですが、転職のきっかけは?
和田:以前は発達障害のある子どもたちを支援する仕事をしていました。でも、精神的に負荷が大きくって…。違う形で人の役に立てないかと思い、大学時代に触れていたプログラミングをもう一度やってみようと思いました。
TAMを選んだのは、「この会社は自由だよ」と社員のみなさんが本当に楽しそうに働いていたから。お客さんに真摯に向き合っていて、元々自分の中にあった「人のためになりたい」という部分とマッチする印象もありました。
AIと開発したのは「社員検索ツール」しかも0から、ほぼ1人で
──和田さんが開発したのはどんなツールですか?
和田:社内で使う「社員検索ツール」です。開発のディレクションができる人を探したり、社員の顔と名前とスキルがパッと見て分かるようなツールを作りました。ちょうど、既存のツールが「使いづらいよね」という話が社内で持ち上がっていて。
一覧で社員が表示され、キーワードやタグで検索ができるようになっています。また、個々のマイページでは、スキルや趣味をタグ化し、仕事だけでなくいろんな面から、その人の人となりが見えるようになっています。
また、自己紹介のスライドや座席表など、今まで別々に管理されていた情報も社員の情報としてこのツールの中に盛り込みました。
技術スタックは、フロントエンドが「React + Next.js」、バックエンドが「Supabase」を使っています。この選定もAIや藤原さんと相談して決めたのですが、当時はどちらもほぼ使ったことがなかった状態で、AIに訊きながら用語を一つひとつ理解していくところからのスタートでした。
──会社としては、なぜ和田さんに任せたのでしょう?
藤原:もともと開発のディレクションができるスタッフを増やす必要があり、AIを使えば、技術とディレクションの両方を同時に習得できるのでは、と考えていました。
和田さんはプログラミングスクールを出ていて、基礎的な知識はある。知識ゼロだと難しいけれど、「これは試してみる価値があるな」と思って任せました。基本的にはAIとの対話だけで開発を進めてもらい、困ったときだけ、僕がサポートに入るスタイルにしました。
「AIを使う」ってどういうこと? ◯◯はやっぱり人間の仕事だった
──AIを使っての開発、どのように進めていきましたか?
和田:コーディング作業自体は、ほとんどAIに任せてました。体感で言うと、99%くらい。
それよりも大変だったのは、「何を作ればいいか」を自分で考えないといけないところ。というのも、「どういう機能がこの会社にとって本当に必要か」は、AIだけでは分からない。スクールでは、何を作るかとか使う技術とかは、最初から決まっていましたし。
たとえば、「検索機能をつける」って言っても、どういう条件で検索できるようにするとか、表示する検索結果の優先順位とか、そういう細かいところって、TAMの人たちが日々どんなふうに働いているかを知らないと見えてこないんです。
だから、AIに訊くだけじゃ足りなくて、藤原さんに相談したり、他の社員さんに「こういうのってどうですか?」って意見をもらったりしながら詰めていきました。
本当に “レシピを書くのは私で、調理するのがAI” という感じ。AIがいくら答えを出してくれても、それが本当に “現場に合っているか” を判断するのは自分。人や会社のことを理解するって、やっぱり人間の仕事なんだなって思いました。
AIを使う落とし穴。“分かった気” “できた風”になる
──AIとの開発で気づいたことは?
和田:コーディングの99%はAIがやってくれると言っても、ビジュアルの調整は大変でした。
たとえば、「右上のボタンを左下に移動させたい」とか、そういう細かいデザインのニュアンスって、言葉にするのが難しくって。AIに伝えても意図通りにいかないことが多くって、そこは結局、自分でコードを修正して対応しました。
それから、AIから出てくるコードはキレイだし整っているんですけど、AIに頼りすぎると “分かった気になる” ことがあるんです。
コードの中身を理解してないと、いざお客さん(今回は爲廣さん)に「ユーザー認証はどうするの?」とか聞かれたときに、まったく答えられなくて焦ったりして(苦笑)。一見ちゃんと動いていても、「実は理解していなかった…」ってことが何度もありました。
藤原:開発が “できた風” になってしまう落とし穴は、たしかにあります。実際は自分ができるようになったわけではなくて、AIがすごくなっただけ、ということも。だからこそ、自分自身の深い理解や判断が必要なんです。
和田:本当にその通りで、AIは日々進化していて、この3ヶ月間だけでもエディターに毎週のようにアップデートが入り、機能がどんどん追加されました。その一方で、AIがやってくれる分、裏側がブラックボックスになる怖さも。
「AIが答えを出したら、そのメリット・デメリットを知って、自分でどういう判断を下したかは自分で認識しておかないと痛い目を見る」と、藤原さんには今でも言われていて。AIは答えが二転三転したり、人間に迎合するような部分もあるからです。
ですから、AIに「やってもらう」ではなく、「一緒にやる」という感覚が大切。分かった気になるのは、AIに「やらせた」結果なんですね。
AIと一緒に、キャリアは作れる
──このプロジェクトを通じて得られたものは?
和田:ツールが完成したこと自体は大きな達成感がありましたが、同時に「物はできたけど、自分はこれでいいのかな?」という不安が、自分の中に残りました。
つまり、AIとの関わり方、そして “AIの見えない部分の怖さ” を体感できた。これは大きな学びです。「AIは魔法じゃない。自分の能力以上のことはできない。だけど、味方にはできる」ということが分かりましたから。
また、爲廣さんとの定例ミーティングでは、「お客さんが何を求めているのか」を受け取り、「今後どう進めていくか」を伝えることも求められたので、ディレクションのスキルも身についたと感じます。
藤原:大事なのは、「自分が何を分かっていないのか」をちゃんと認識し、それを分かっている人に教わって、自分の知識やスキルにしていくこと。分からないことを放置したり、そもそも分かっていないことに気づいていない状態は、とても危険。これは、AIを使うかどうかは関係ないとも思います。
──和田さんは今後、どんなことに挑戦していきたいですか?
和田:次はこのツールをもとに、社内マッチングアプリの開発に取り組む予定です。もっと上流から関わることになるので、新たなチャレンジが始まります。でも、「分からないから無理」ではなく、「分からないからやってみよう」と思えるようになりました。
藤原:和田さんは今回、管理者側の機能まで構築してくれたので、今後社内インフラとして使い続けられるものになりました。しかも、社員の座席をドラッグ&ドロップで編集できるなど、実は革命的な機能も入っているんです。
成長スピードも想像以上で、会社として、教育・育成の観点で「新しい学習曲線」を発見できたことも収穫でした。
従来は、先輩の横で難易度の低い案件を分担し、ディレクション力を身につけながら、少しずつ開発知識についても学ぶという"徐々に積み上げるモデル"。それに対し、和田さんのケースは、いきなりツールを一つ作りきったことで、「開発知識の基盤」を一気に習得し、そのうえで、これから「ディレクション力」を伸ばせる順序にシフト。
普通なら数ヶ月、いや、1、2年かけるステップを、AIを味方にすることで一気に圧縮できました。
なにより、 “自分で何かを作った” という感覚や、お手伝いで作ったものとは比べ物にならない “完成させた喜び” が、和田さんの中にしっかりと残ったはず。それはきっと、これからの大きな糧になると思います。

[取材・文] 岡徳之 [撮影] 藤山誠、篠原豪太







/assets/images/20737703/original/dc282c22-e523-4333-8595-84328f51cc08?1742876492)

/assets/images/5818/original/27855b33-34d8-4fc8-986d-891836dcb7fb.jpeg?1495011949)
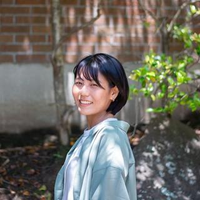

/assets/images/3478188/original/27855b33-34d8-4fc8-986d-891836dcb7fb.jpeg?1549953460)

