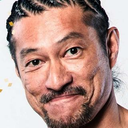今回はそれらに続けて、成長するマーケットってどんなところだろうかって話をカキコしたいと思う。
目次
- マーケットの基本
- IT業界のこれから
①マーケットの基本
成長するマーケットってどんなところなのかを考えるって、なかなか難しいよね。社会経験のない学生さんからしたら、見当もつかないかもしれない。
でも意外とそんなに難しいことじゃない。
そのサービスが欲しいって思う人が、サービスを提供する人を上回っていれば、基本的にそのマーケットは成長し続けるだけの話なんだ。
すげー不謹慎だけど、例えをすると葬儀屋のニーズって増えるよって話。
どうあがいても日本は高齢化社会へまっしぐらなんだから、その分老人が増えれば亡くなる人が増えるに決まっている。
すると今まで間に合っていた葬儀屋の数では足りなくなるわけだよ。
そうなるとサービスを欲しい人がサービスを提供する人を上回る現象に陥るから、サービス単価が上がり始める。サービス単価が上がれば、儲かると思った人たちがどんどん葬儀屋に参入してくる。
この現象は、欲しい(ニーズ)と提供(サプライ)が均衡するまでずーっと続く。
葬儀屋に納入する業者たちも、引っ張られて儲かるようになることは言うまでもないよね。花屋さんとか棺桶屋さんとか、燃やすための燃料屋さんとかね。
この高齢化まっしぐらの観点でいけば、葬儀マーケットだけでなく、その前段階の介護マーケットだって成長を続けるのは間違いないって言うことになるよね。
日本はこれから、少子高齢化が進み人口が減り続ける。
一方で世界を見たときに、人口は70億人を優に超え、発展途上国を軸に急激な人口増加をたどっているわけだ。
人が増えれば、一次産業(たべもの)とかエネルギー産業のニーズは高まり続けるから、そういった事業をやっていて国際的に展開してる企業を選ぶのも悪くないだろうね。
このように人口の観点で物事をとらえると、より単純に成長するマーケットを見つけることができるかもしれないから参考程度にね。
※別に成長しなくていい、ゆったりと働きたいと思っているなら、逆にこういうとところを選んじゃだめだよ。
![]()
②業界のこれから
それでね。
これから先はいかにIT業界が成長を続けるかを書くね。ポジショントークだと思って見てね (笑
え?なんでポジトってか!?
俺、IT企業の社長だからだよ!!
今、企業を取り巻く競争環境は非常に激しい。
ネットのおかげで国境の概念はなくなり、常に国際競争にさらされている状況だ。
前も書かせてもらったけれど、競争対象が広域になればなるほど、化け物みたいに強いやつらと戦うことになる。高校野球でいうと、地域大会の対戦相手と甲子園の対戦相手くらいレベルが違うものだ。
そんな化け物と戦って生き残るためには、企業の競争力を高め続けないといけない。競争力を高めるには、作業の効率化は欠かせないわけだよ。
効率化と言えば、IT技術は最重要テーマとなる。
最近だとDX(デジタルトランスフォーメンション)とかAIとか。ちょっと前なら、クラウドとかロボット。更に昔だとWEB2.0とか。
やたら横文字を使いたがるし、小難しいと思うかもしれない。
けどこれらの技術って前からあるモノの延長線上にあるだけなんだよね。それにイケてる単語(概念)をのせただけの話だから、あんまり気にしないで。
まぁ~要するに、IT技術は人がやっていたことをコンピューターが代わりにやったら効率的じゃね?ってだけの話だ。
企業の競争力を高め続けるうえで、こういったIT技術は欠かせないわけよ。
![]()
人件費が発展途上国より高くなった日本ではなおさら重要だ。
いつまでも工場に人をたくさん並べて家電を作り続けたら、原価が上がって製品が高くなるに決まっている。途上国の同等製品と比べたら、値段だけが高くて売れないわけだ。
いやいや日本ブランドはまだまだ強い!って思っているかもしれない。
もうその考え方はキチガイだよ。
日本の優秀な技術者も、外資企業に引き抜かれて技術的にはもう差がないからね。
下手したら、レベルは劣っているかもよ。
国際競争に負けて、日本のナショナルブランドだってもうすでに日本の資本じゃないところがあるぐらいだからね。
・・・・
・・・
・・
ふぅ~、ちょっとだけ脱線したから、話を戻すね。
こんな激しい競争にさらされていて、IT投資をしない企業はないわけで、
経産省のデータに基づけば2030年には約80万人エンジニアが不足すると言われている。
つまり、まだまだIT業界は成長マーケットまっしぐらってことなんだよね。
ニーズが供給を超えるということは、単価が高くなる。ITエンジニアの価値は高いまま維持され続けることを意味するんだわ。
だから成長したい人たちはこっちにおいで~って話なんだけれど、もう1点、非常に重要なポイントをカキコしたい。
でもちょっと長くなって、読むのが大変だから、次回書くね。
ほんとは、俺が書き疲れたらかんあだけどねw
次回もまた、違う視点で、続きを書くね。
⇩おすすめ記事⇩
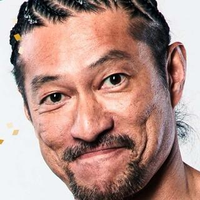


/assets/images/8122498/original/9f23d7ce-b38b-45cb-a392-8e80f5a06e75?1671159279)
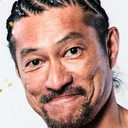
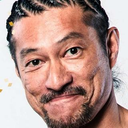
/assets/images/8122498/original/9f23d7ce-b38b-45cb-a392-8e80f5a06e75?1671159279)

/assets/images/21562894/original/9f23d7ce-b38b-45cb-a392-8e80f5a06e75?1752198067)