「あの時の商談、どんな提案したっけ?」
「前回の打ち合わせで決まったこと、なんだったかな…」
仕事をしていて、こんな経験はありませんか?
私たちModelistは、この問題に対して明確な答えを持っています。
それは「記憶に頼らず、記録に頼る」という考え方。
実は弊社では、採用面接時に「寿司打」というタイピングゲームである程度の点数を取ることを推奨しています。一見すると奇妙に思えるかもしれませんが、これには深い理由があるんです。
今回は、Modelistが大切にしている「記憶力より記録力」という働き方について、代表・呉縞(くれしま)の実体験を交えながら、前編・後編の2回に分けてご紹介します。
前編では、なぜ記録にこだわるのか、その確信に至った背景と実績についてご紹介します。
目次
きっかけはSalesforce時代の「情報つなみ」
対応案件数No.1の仕組み化 ― 確信に変わった実績
型・ガイド・サンプル ― 記録を仕組み化する3要素
個人の成功から組織変革へ
記録しながらやることで生産性が上がる ― 意外な事実
記録は「作業」ではなく「投資」
記録のハードルは、スキルで越えられる
きっかけはSalesforce時代の「情報つなみ」
この「記憶力より記録力」という考え方は、弊社代表の呉縞がSalesforceに入社した時の体験から生まれました。
「入社直後のブートキャンプから膨大な情報が押し寄せてきて、正直パニックでした」
10近いプロダクト知識、業界用語、社内ルール、案件情報、顧客情報、提案準備、デモ環境...etc
覚えなければいけないことが山のようにあり、最初は必死にメモを取り、記憶しようとしていたそうです。
しかし、ある時ふと気づきます。
「過去の情報を探す作業って1ミリも付加価値のない時間で、これを限りなく0にできればストレスなく成果にフォーカスできるようになるのでは…!!」
確かに、会議の内容を思い出そうとしたり、過去のメールや資料を探したりする時間は、新しい価値を生み出していません。それならば、作業をしているその瞬間に、後から振り返ったり、関係者にシェアをするという前提で、探しやすい形で記録しておけばいい。
最初は記憶力トレーニングの本を読んだり、記憶術のセミナーに参加したりもしたそうですが、結局たどり着いたのは「記憶に頼らない仕組み」でした。
対応案件数No.1の仕組み化 ― 確信に変わった実績
「僕は確実に成果につながるという実績と確信があるので、記録をしているんです」
呉縞はそう語ります。Salesforce時代、多いときで同時に20件近くの商談を並行して担当していました。1時間刻みで隙間なく次から次へと社内外の会議が連なる日々。結果、売上数字は1番。しかも、2番目の人と比べて担当していた案件数はおよそ1.35倍。つまり35%多くの案件をこなしていました。
普通の仕事の仕方をしていたら、これだけの量をこなしきれません。
なぜなら、複数の異なる業界や提案内容の案件を連続で対応するには頭切り替えと、資料やデモの準備の切り替えが間に合わないからです。
なぜ1.35倍という圧倒的な差が生まれたのか?
「全てを記録していたから、脳みそで思い出す必要がなかったんです」
レコード管理のルールはもちろん、記録の仕方(見出し、画像、コメント、絵文字)、テンプレート、ファイルの命名規則、チームでの情報入力オペレーションまで徹底的にルール化。絵文字一つ打てば必要なデータに絞り込まれ、お客様の名前を入力すれば、会議の議事録から顧客理解まで、必要な情報が瞬時に取り出せる仕組みを作り上げていました。
「3ヶ月前に商談を行って止まっていた案件が再スタートしたときに、普通なら『どこまで話したっけ?』となりますよね。でも僕の場合、過去の提案内容もデモの準備状況も、すべて画像、テキスト、コメントの形でテンプレートに合わせて記録してるので、状況がすぐ思い出せます。」
1ヶ月空こうが、3ヶ月空こうが、半年空こうが、クオリティを落とさずに再開できる。それが記録の力でした。

型・ガイド・サンプル ― 記録を仕組み化する3要素
呉縞の記録システムの核心は、「型」「ガイド」「サンプル」という3つの要素にあります。
- 型(テンプレート):基本的な枠組み
- ガイド:各項目に何を記入すべきかの説明
- サンプル:実際に入力された例
「型(テンプレート)だけ渡されても、何を埋めたらいいかわからないですよね。だから僕は、型(テンプレート)を作ったら、まずは自分でそのテンプレートを活用して業務を行って、使いづらい部分は改善しながら、テンプレートをストレスなく使える状態まで持っていきます。」
「そして、その時の業務内容が記入されたテンプレートは実業務サンプルとして、テンプレートを展開するときに、他のメンバーに共有できるんです」
新しいメンバーが入ってきたら、テンプレートをコピーして渡し、実績のサンプルを見せる。「こんな風にデモ環境を作るんだよ」と言えば、あとは教える必要がありません。
「一般的にはメンターが1から10まで教えるか、教えずに現場に放り出すかの2パターンしかないんです。教えずに現場に出したら部下は育たないし成果も出ない。頑張って教えようと思ったら自分の工数が削られて、結局自分が商談する時間が減る」
型・ガイド・サンプルによる仕組み化。これがあったからこそ、1.35倍という圧倒的な生産性を実現できたと思っています。

個人の成功から組織変革へ
この成功体験は、個人レベルで終わりませんでした。
まず、呉縞が作った型を自分が関わっている営業チーム(7人の組織)に展開。すると、そのチーム全員が年間目標を達成という結果が出ました。
この実績を受けて、営業本部全体で呉縞のオペレーションの仕方で運用することが決定。執行役員と共に営業部の働き方改革を実行しました。
「確実に成果が出るという仕組みを構築したので、何回やっても絶対に成果が出るんです」
そして現在、Modelistではこの仕組みをさらに磨き上げています。
「今までは研修としてお客様に提供していたものを、自社の中でさらに進化させています。完全に自分の会社なので、今まで以上に業務オペレーションを文化として浸透させられるし、みんなで同じ方向を向いて実践できる環境を作れると考えています」
記録しながらやることで生産性が上がる ― 意外な事実
ここで興味深い事実があります。
「10分で終わる簡単な作業は、記録し(画像とメモの手順を残し)ながらやると13分くらいになるかもしれません。でも、100分かかる複雑な作業は、記録しながらやった方が80分で終わるんです」
なぜでしょうか?
呉縞は最近の体験を例に説明してくれました。
「先日、メンバーのエンジニアにGoogleなどのSNSサービスのAuth認証の設定を指示を受けながら作業したんです。画面を見ながら言われた通りに操作しました。でも3日後に『設定を間違えたので差し替えてください』と言われて...」
覚えていられるはずがありません。Google、X、LinkedIn、Facebook...全部画面が違うのです。
「でも1回目やったときに記録(画像とメモ)を残しながらやっていれば、2回目やるときは、前回のメモをみながら上から順番に『ここを押して、これを押して...』とスクリーンショットを見ながら進められる。そうすると、1回目1つのSNS設定で30分かかっていた作業が、2回目は10分くらいで終われます」
複雑な作業ほど、調べながら進めることが多く、詰まったときに人に聞くことも増えます。その際、記録を残していれば「ここまでやりました」とプロセスを共有でき、的確なアドバイスがもらえます。
「手順を残す、マニュアルを作るのは他人のためだと思って気持ちが乗らない方が多いのですが、難しい仕事をやっている方であればあるほど、2回目以降同じ作業する”自分のためのもの”だと思ってほしいです。」
記録は「作業」ではなく「投資」
「記録するのは面倒」という声もあるでしょう。確かに、最初は手間に感じるかもしれません。
でも、Modelistでは記録を「作業」ではなく「投資」だと考えています。
今日残した記録は、明日の自分を助けます。 来月の新メンバーの学習を加速させます。 来年のプロジェクトの参考資料になります。 そして、組織全体の知的資産として蓄積されていきます。
呉縞はこう断言します。
「記録をしていないのは、個人としても、組織としても生産性をあげません!って言ってるのと同じだと思ってます!」
強い言葉ですが、それだけ記録の効果を実感しているからこその発言です。

記録のハードルは、スキルで越えられる
では、なぜ多くの人は記録をしないのでしょうか。
「スクリーンショットの撮り方がわからない、注釈の付け方がわからない、めんどくさい...理由はいろいろあるでしょう。でも、これらのスキルは習得できます」
Modelistでは、オンボーディングでこれらの基礎スキルを徹底的にサポートしています。パソコンの使用スキル、Notionの使用スキル、スクリーンショットへの注釈の付け方...
「別に難しいことじゃないんです。世の中の人がやってないだけ。これをちゃんとできるようになれば、みんなが誰も迷わない手順書を残せるようになります」
呉縞はよくこう言います。
「記憶力はすぐ2倍にならないけど、記録力はトレーニングすればすぐ何倍にもなる。」
「そして記録力が身につけば、積み上げ式の確実な成長につながる。」
前編では、「記憶力より記録力」という考え方が生まれた背景と、それが確実に成果につながるという確信の根拠についてお話ししました。
1.35倍という圧倒的な生産性の差。個人の成功から組織全体の変革へ。そして、記録は面倒な作業ではなく、未来への投資であるということ。
でも、これはまだ序章に過ぎません。
後編では、Modelistの記録文化が生み出している価値をご紹介します。
記録がもたらす4つのメリット、寿司打を重視する理由、そして日々進化する記録環境とAIとの連携。
継続することで見えてきた、記録文化の本当の価値をお伝えします。
後編はこちら:
【記憶力より記録力】 できなくても、忘れても、大丈夫。記録文化が生み出す価値
/assets/images/20928012/original/ae04bcc0-a1fc-4d1a-985c-8042d185a977?1744941943)
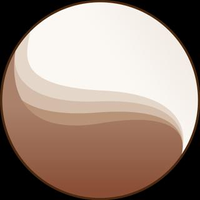
/assets/images/20928012/original/ae04bcc0-a1fc-4d1a-985c-8042d185a977?1744941943)


/assets/images/20928012/original/ae04bcc0-a1fc-4d1a-985c-8042d185a977?1744941943)
/assets/images/20928012/original/ae04bcc0-a1fc-4d1a-985c-8042d185a977?1744941943)

