▶ 前編はこちら:【記憶力より記録力】採用面接で寿司打をする、Modelistが記録にこだわる理由
前編では、代表・呉縞がSalesforce時代に築いた「記録の仕組み」により、35%多い案件数をこなせた実績についてお話ししました。
型・ガイド・サンプルという3要素による仕組み化。個人の成功から組織変革へとつながった経験。そして、記録は「作業」ではなく「投資」であるという考え方。
後編では、Modelistの記録文化が生み出している価値について詳しくご紹介します。
目次
「記録」がもたらす4つの圧倒的メリット
1. 生産性の飛躍的向上
2. 属人化の撲滅
3. 心理的安全性の向上
4. 自然な他者貢献
なぜ寿司打が採用の参考に? ― 記録力の土台
記録力を上げるための仕組み化を毎日Update
AIとの相乗効果で加速する生産性
未来の自分が「ラク」になることを徹底的に事前準備する。
私たちと一緒に、記録で支え合う組織を作りませんか?
「記録」がもたらす4つの圧倒的メリット
Modelistで記録文化が浸透した結果、4つの大きなメリットが生まれています。

1. 生産性の飛躍的向上
「組織全員が高いレベルの記録を残すようになると、組織の中で起こる業務のプロセスのほぼすべてが記録されている状態になります」

※Modelistでは「高いレベルの記録」を、その業務をやっていなかった他の人がその情報をみて、質問や確認をすることなく同じことが再現できる状態 と定義しています。
しかも、ただ記録されているだけではありません。
Wikiとして整理され、Notion AIで検索すれば必要な情報がすぐに見つかる状態になっています。
誰か一人ができるようになったことは、組織の全員ができる状態になる。
誰か一人がやったことは、2人目以降は半分以下の時間でできるようになる。
これが記録力の効果です。
2. 属人化の撲滅
特定の人しかできない作業があると、組織の柔軟性は低下します。
でも、記録があれば違います。
呉縞はこう説明します。
「自分が初めてやる仕事は、すべてSTEP by STEPでスクリーンショット(注釈付き)と簡単な補足をNotionに時系列で記録していきます。そうすれば、次自分がやるときは1回目の20-30%くらいの時間で同じことができます。
さらに、それを誰かに依頼するときも、その手順メモを渡して『これ見てやってみてください』で依頼は完了します。自分が一度やりきった作業は他の人も迷いなくできるわけです。
記録されていなかったら、次の人にお願いするときに、口頭で伝えないといけないし、しかも依頼した方が不明点がでてきたときに記憶を辿って教えないと行けない。
この記憶を辿って、過去やった膨大な作業の中から具体的な操作や仕事内容を思い出す時間って無駄で非効率なので、質問されたら『これです!』で依頼や回答が終われると考えれば、記録する労力はすごくROIが高いアクションだと思っています。」
Modelsitでは、この業務プロセスの記録のことを「プロセスナレッジ」と呼んでいます。プロセスナレッジがあることで、組織の誰かがやっているものは残っていて参考にしながら仕事できる!という安心感が醸成されます。
この文化により特定の人しかできない仕事がなくなり、組織全体の生産性が高まるのです。
3. 心理的安全性の向上
「忘れても大丈夫」という安心感は、メンバーの心理的負担を大きく軽減します。
あるメンバーはこう話してくれました。
「以前の職場では、重要な情報を忘れたらどうしようという不安が常にありました。でもModelistでは、すべてNotionに残っているから、必要な時に検索すればいい。この安心感のおかげで、目の前の仕事に集中できるようになりました」
新しいことを依頼されたときも安心です。
「誰か組織の中でやったことある人がいたら、確実に記録が残っている」
この安心感が、チャレンジへの心理的ハードルを下げ、新しいことへの挑戦を促進します。
4. 自然な他者貢献
一般的には、「ナレッジ共有」はハードルが高いと思われがちです。
その理由は、ナレッジ共有は仕事とは別でわざわざ行うものだと考えられているからです。
「仕事する⇢振り返って学びの抽出を行う⇢コンテンツを作る⇢投稿文章を作る⇢投稿する」
これが、ナレッジ投稿までに必要だと”思われている”プロセスです。
しんどくて、大変で、面倒ですよね。
しかも、こんなに頑張ったのに投稿しても、「いいね!」やコメントなどのリアクションがもらえない環境だとやる気を失ってしまう。これが世の中の多くの組織でナレッジ共有がうまく進まない原因です。
Modelistでは、独自の記録メソッドのスキルをオンボーディングフェーズでトレーニングして全員ができる状態で業務をスタートしていただきます。
この「業務プロセスの徹底的な記録」という文化があって、普通に仕事していたら各自が仕事しながら記録したレコードが、他のメンバーにとっての「プロセスナレッジ」として自然とアウトプットされる仕組みになっています。
その一例をご紹介します。以下は、Notionの画面です。

Notionで会議や活動の記録を残したときに、これは他のメンバーにも参考になる記録や仕事の仕方だなと思ったらProcess Knowledgeにチェックを入れるだけで

SlackのProcess Knowledgeチャンネルで自動通知されるようにしています。
「仕事する⇢組織に取って価値のある記録か仕事の進め方か判断⇢チェックボックスON ✅」
これだけで「プロセスナレッジ」が自動で組織全体に共有されるのです。
やった仕事を記録するだけだったらハードルはほとんどないし、記録をしながら仕事したほうが自分が後で同じことするときにも楽になるし、人に教えるときも記録したドキュメントをシェアするだけでOK。
普通に仕事をしてたら、だれかの為になっている。このオーガニックな他者貢献アクションで、自然な助け合いが生まれます。
他者貢献の中でも特に特徴的なのが、「未経験の人の不明点と失敗が組織の学びになる」という側面です。
呉縞はこう説明します。
「分からないこと、できないことは問題じゃない。そういったできない、分からないを社内のNotionやSlackで調べて記録がなければ、自分がやりながら記録していけば、後に続く人が楽になるし感謝される。」
「先人の記録(道しるべ)が残ってさえいれば、同じ仕事を効率的に進められるし、応用もできる。この記録の徹底ができる組織は生産性がガンガン上がっていくんです」

なぜ寿司打が採用の参考に? ― 記録力の土台
ここで前編の冒頭の「寿司打」の話に戻ります。
なぜタイピングゲームのスコアを採用の参考にするのか。
それは「記録力」と密接に関係しているからです。
呉縞はこう説明します。
「目にした情報、耳にした情報をデジタルのテキストで落とす。この能力を測るために寿司打をやっています」
寿司打が速い = 目にした情報をデジタルでPCを使ってアウトプットするスピードが速い
つまり、日々やっている仕事すべてをデジタル環境に記録するという基礎スキルがあるということ。
タイピングが速ければ、記録文化に慣れていない人でもすぐに適応できます。
そして記録の習慣が身についた未経験の方だからこそ、組織に残せるプロセスナレッジ(価値)が多くあると思っています。
実際、Modelistの新人でIT未経験のメンバーでも顧客商談で議事録を書いているだけで、お客様からその記録の制度と質について感動されることが非常に多いです。
つまり、未経験の方が組織や顧客に貢献できることで、一番簡単で効果的なのが「経験の記録」なんです。
もちろん、タイピングが速いだけで仕事ができるわけではありません。でも、記録する習慣と、それを支える基礎的なスキルは自己成長のためにも組織成長のために重要です。
寿司打のスコアは、その指標の一つなんです。
記録力を上げるための仕組み化を毎日Update
Modelistでは、記録しやすい環境づくりにも力を入れています。
「枠がない場合、ゼロから記録を作成するのは面倒だし、人によって記録の仕方が変わる。他の人が記録を見たときに理解しづらい」
そこで重要なのが、テンプレート(型)の存在です。
Modelistでは、下記の例のように、会議を始めるときに全員が同じ情報構造で記録できるようにしています。

これによって、情報を探すときに情報の記録の場所という共通認識がうまれ、他の人が書いた議事録だったとしても、自分が見たい情報をすぐに探しにいくことができます。
AIとの相乗効果で加速する生産性
呉縞は現在、「Notionでの徹底的なデータ集約と生産性フレームワークの構築」に注力しています。NotionのカスタムAIブロックやAI項目を活用し、過去の記録をRAG(検索拡張生成)として活用する仕組みを構築中です。

先ほどご紹介した会議議事録などの記録したデータを基に、Notion AIで会議後のNext Actionの整理、アウトプット作成補助、話している方の傾向分析など業務において毎日行われる会議での思考レベルの進化をAIがサポートしてくれる仕組みを構築しており、ほぼ毎日Updateしています。
「1年分の会議録、プロジェクト記録、顧客とのやり取り...これらすべてが、AIの学習材料になります。自分たちの仕事の文脈を理解したAIアシスタントを作れるんです」
最近では、Notionに記録しているお客様との会議議事録を基に、AIが半自動で個別化した提案書も作ってくれるようになりました。「記憶」に頼っていた時代には考えられなかった、圧倒的な生産性の差が生まれています。

未来の自分が「ラク」になることを徹底的に事前準備する。
最後に、記録文化を自分や組織に根付かせるために大切にしていることがあります。
テクノロジーツールを使うのも、AIを使うのも、記録を徹底するのも
前提、自分が「ラク」をするためです。
その瞬間は一見面倒に見えることでも、その行動が少し長い目で見たら自分も周りもすごくラクになっている。しかもそれが組織全体から感謝されている。
そんな未来の妄想をしながら、今の目の前の少し面倒に見える価値のある「未来のラクの仕込み」にチャレンジしてみてください。
Modelistの「記憶力より記録力」という考え方は、この未来志向の積み重ねから生まれる価値を信じているからこそ生まれたものです。
私たちと一緒に、記録で支え合う組織を作りませんか?
Modelistでは、一人ができるようになったことを、組織全員ができるにかえ、組織のできることを、社会全体のできるに変えられれば自ずと個人も企業も成長していくという成長モデルを提唱しています。

- 情報を探す時間を価値創造に使いたい
- チームの知識を資産として蓄積、活用したい
- 自分の仕事が誰かの役に立つ実感を得たい
- デジタルツール、AIツールを最大限活用した最先端のワークスタイルに興味がある
皆さんの中で上記に当てはまるポイントがもしあればぜひ一度お話ししましょう。
記憶力はすぐに上がりませんが、記録力はトレーニングですぐに変化が現れます。
記録力で個人と組織のポテンシャルを引き出せる環境と文化を一緒に作っていける仲間を探しています。
私たちと一緒に、「記憶に頼らない、記録で支え合う組織」を作っていきませんか?
エントリーをお待ちしています。
/assets/images/20928012/original/ae04bcc0-a1fc-4d1a-985c-8042d185a977?1744941943)
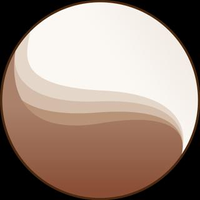
/assets/images/20928012/original/ae04bcc0-a1fc-4d1a-985c-8042d185a977?1744941943)


/assets/images/20928012/original/ae04bcc0-a1fc-4d1a-985c-8042d185a977?1744941943)
/assets/images/20928012/original/ae04bcc0-a1fc-4d1a-985c-8042d185a977?1744941943)

