ITエンジニア採用って
ナリコマのシステム部に8名の新卒社員が入社した 。世の中にたくさんの企業がある中で、ナリコマを選択してくれた8名のエンジニアの卵たちなので、嬉しいことはもちろんのことそれ以上に胸を撫でおろした想いの入社式だった。
それと言うのも、昨年のシステム部での採用実績は0人だったのだ。 昨今のデジタルニーズの高まりが人材市場にも影響を与え、デジタル人材のニーズは年々高まっている。本当に困ったことだ。コンサルティングファームが破格の条件で大量採用を行ってやがるし、普通の事業会社もDX推進の旗のもと、わけもわからずエンジニア採用を進めている。市場は大荒れで、IT人材市場は年々採用が難しい市場となっていることは、この業界の方ならば痛感されていることだろう。IT系の商談中のムダ話でも恨み節がちらほら聞こえてくる。
ナリコマにとってITは事業の根幹だ。その人材獲得が芳しくないことは大きな課題なのだ。なのに肝心のシステム部は人材市場には鈍感であることが最も解決すべき課題であった。そこで私は、エンジニア採用を人事部門ではなくシステム部門が主に担当するように、システム部内にエンジニア採用チームを作ったのだ。私が主幹となり採用課からスタッフを引き抜き、エンジニア主導の観点で採用を進めるような組織に変えた。やる時にはやらねばならない。同時に採用戦略や採用プロセスもゼロから見直し、学生さんや求職者さんの立場に立った選考の仕組みに作り変えた。選ぶ採用から選ばれる採用に向けて体制も選考方法も採用戦略もシフトチェンジしたのだ。
採用ゼロの危機的状況を逆手に取って、これまでの採用手法を全否定した。「昨年と同じことをしても結果はゼロなのだから、思い切って変えて行こう」とシステム部に発破をかけた。採用マーケティングの考え方を取り入れ、面接ではIT担当役員が必ず対応することをアピールし、私自身が採用活動の最前線に居るよう心掛けた。マスではなく求職者一人一人に沿った対応を行う、BtoC的な採用活動を行った結果として8名の採用につながったことは、システム部全体が採用に前向きに取り組んだ結果だと言えるだろう。まさしくシステム部は目を覚ましたのだ。今では他社がうらやむほど、ITエンジニアの採用業務や教育業務に積極的である。
デザイナーさんもいるよ
ナリコマホールディングスに採用された新卒さんは、システム部以外にもマーケティング部に1名いる。実は私がスカウトしたデザイナーの卵さんなのだ 。とある学校の卒業制作の講評会に参加させていただいたことがご縁で、私がポートフォリオに「ビビビッ!」と来て、アプローチさせていただいた唯一のデザインコースの学生さんである。聞けばPHP言語やマーケティング手法を自学でマスターしたという向上心の塊のような学生さんであった。コードが書けるデザイナーというキャリア志望を持っていたこともあり、ナリコマでの育成プランもその場で提案させていただいた。その甲斐もあって、ナリコマならデザインとITの両方で成長できる環境だと他社の内定を断り入社承諾してくれた。
なぜITエンジニア採用中にデザイナーをスカウトしたのか?それは、ナリコマが提供するアプリのUI/UXが、顧客満足度に大きく影響する非常に重要な要素だと捉えているからだ。しかしながら、このUI/UXの分野だけがナリコマで唯一内製できておらず、外注に頼っていることが残念である 。そこで、UI/UXもいずれ内製化できるように、デザイナー採用を強化しようと思案しているところで出会ってしまったのだ 。常日頃からアンテナを張っておくことの大切さを実感したのは言うまでもない。
本当に運命の出会いだったので、求人票などもデザイナー採用のものが準備されていない中で、ナリコマを選択してくれたことは至極感謝しかない。10月までは同期の新卒ITエンジニアたちと一緒に半年間のエンジニア新人研修に参加している。是非ともデザイナーとITの両輪で活躍するまで育って欲しい、そしていつの日かバーチャル本部長の2Dモデルを制作してくれないだろうか。
新卒さんが来る~!
システム部の新卒社員8名は、理系、文系、大学院卒、専門学校卒など経歴は様々で、男女比も半々だ 。彼らに共通しているのは、「ITでモノづくりがしたい」という強い気持ちを持っていること。ナリコマは事業会社では珍しく、ガチで開発するインハウスエンジニアなのでITを創る側に立つ人材を求めている。これまでは毎年1〜3名程度の入社だったため、今年は例年のおよそ3倍の新卒が入社したことになるうえ、みんな開発者魂の種火が備わっている 。
新卒を受け入れる先輩社員たちも、例年になく気合が入っていた 。一昨年の6月頃には「新卒採用って順調なんですよね?ホントに10人くらい入るんですか???」と焦っていた。これまでは採用人数が少数だったこともありOJT中心の育成だったのだが、観念したのか2025年度は体系化された育成カリキュラムを構築してくれた 。250ページに及ぶ研修テキストを作成し、未経験者でも技術を得ることができる環境を整え、自己学習支援としてUdemyも導入した 。また、パートナーのSierと包括契約を結ぶことで、システム開発だけでなく技術者教育の面でも協力体制を整えた。そう、システム部が燃えに燃え、9名の新人受け入れに向けて育成環境は大幅にアップしたのだ。システム部もやればできるじゃないか。
すくすく育って欲しいのさ
育成について課題がないわけではない。おじさんエンジニアたちは最近の転職市場での若手層が、自分たちの時代と照らし合わせても実力不足であることを感じている。5年実務経験でも3年実務経験程度に感じてしまうのは仕方がない、デスマーチをくぐり抜けたおじさんたちは面構えが違うのだ。
かつては、月250〜300時間の稼働が平常運転だった時代もあったし、トラブル対応や終電逃しての夜間作業は軽いイベント感覚であった。しかし、働き方改革やコロナ禍を経て労働環境は大きく変化し、時間を費やしてのスキルアップが許されなくなってしまったのは、ITエンジニアの経験値的には幸せなのか不幸なのか 。だが、昔は良かった的なことを言っても埒が明かない、これからの時代は効率的なスキルアップを求めているのだ 。だから私たちは、技術のインプット手段を増やしたり、知識を経験に変えるアウトプットの機会を増やしたり、社員と協力会社の垣根をなくして相互に育成し合ったりといった取り組みを実践している 。今の時代に合った育成スタイルでも、古参のITエンジニアに引けを取らない成長曲線を描ける環境を築くことが、ナリコマ先輩エンジニアたちの使命だと考え、さらなる育成スキームの構築に取り組まなければならないのだ。
そのような中、入社4年目の若手社員がプロダクトリーダーに抜擢された 。若手エンジニアが目指すアイコンとして、今後も彼に続く後輩が出てくることを期待している 。ナリコマの事業はもっと成長するだろうし、これからもIT投資に積極的であることは間違いない。開発テーマに困ることはない、寧ろシステム部が積極的にDIGしなくてはならない。システム部が日和らなければ、ITシステムを開発する環境としてはこれからも魅力的な職場であることは変わりない。だから入社してくる新卒社員たちには、ITを楽しいと感じ、この仕事を選んでよかったと思えるような開発者としての基礎を築いてあげたいのだ 。
さぁ「技術の前では皆平等」を実践しようじゃないか。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
この記事を書いた人のインタビューはこちら
東京新拠点への挑戦!チームの垣根を超えるシステム開発〈前編〉
東京新拠点への挑戦!チームの垣根を超えるシステム開発〈後編〉

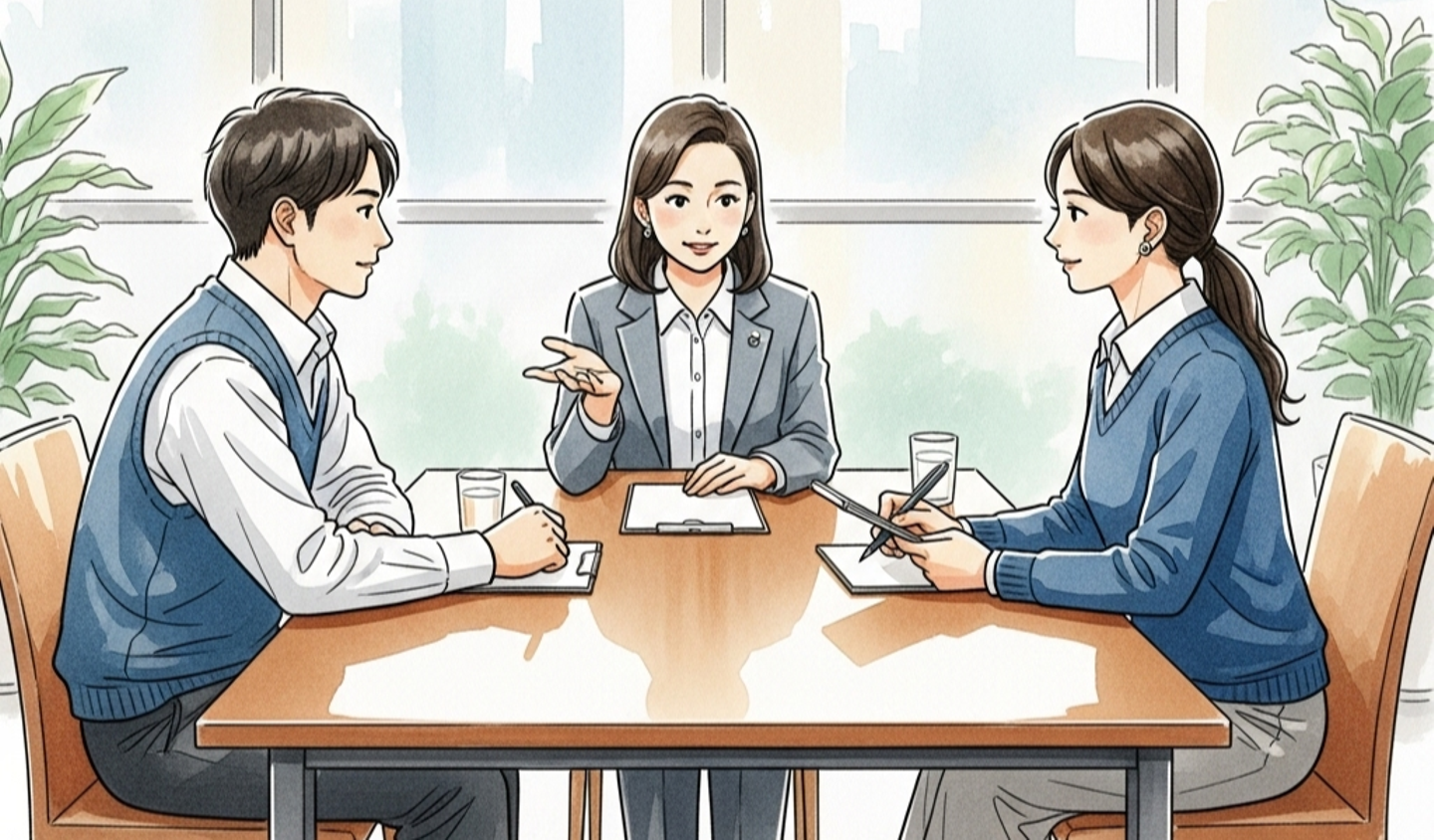

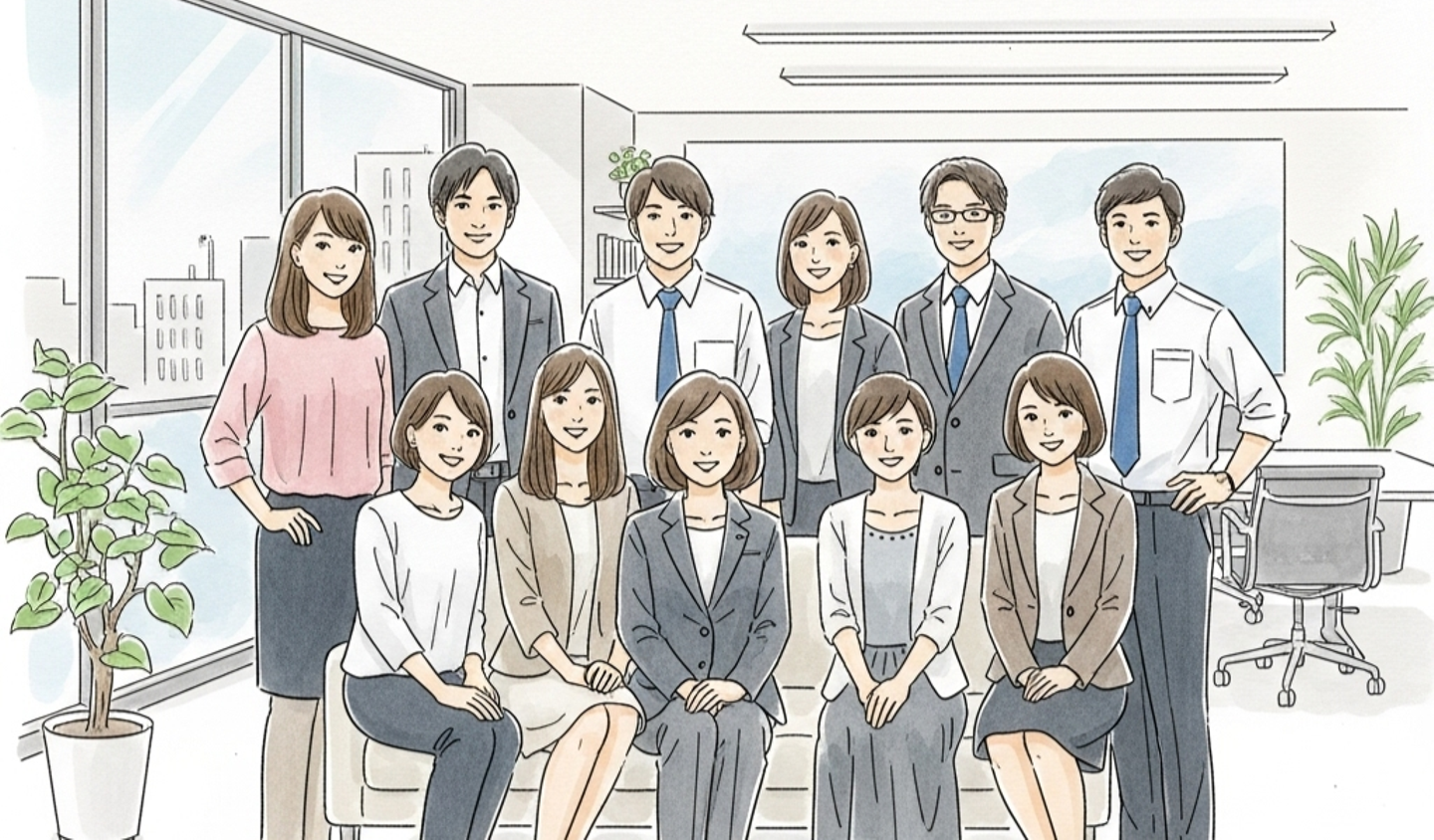

/assets/images/21018613/original/e473d4a1-4cfd-4b9c-abc7-8be6261ea157?1746061627)


/assets/images/21018613/original/e473d4a1-4cfd-4b9c-abc7-8be6261ea157?1746061627)




/assets/images/21018613/original/e473d4a1-4cfd-4b9c-abc7-8be6261ea157?1746061627)

