人事の現場から学ぶリアル解決メソッド|新卒採用にあたってのマインド編~信頼できる柱が欲しい経営者のための『プロパーCHRO』の育て方Vol:19~
こんにちは。株式会社シンシア・ハート代表の堀内猛志(takenoko1220)です。
僕は、前職時代に、50名から4000名まで成長した企業の人事役員として、各ステージに合わせた人事戦略・組織づくりを実践してきました。この経験をもとに、現在は、外部人事顧問として複数の企業をサポートしています。
この連載では、実際に人事担当者が現場で直面した「悩み」と、それに対する僕の解決アプローチを抽象化して共有します。採用活動や人材定着に悩む方に役立つアイディアが見つかるはずです。
より具体的なシーンを思い浮かべながら理解できるよう、対話形式でわかりやすく解説していきますので、経営者や人事担当者の方はぜひ参考にしてください。
初回となる本記事では、新卒採用活動の真っ只中にある企業様のケースから、実践のヒントを探していきたいと思います。
目次
応募の「数」だけ見ていないか?
▼実践のヒント
学生の「共通項」を見つけられているか?
▼実践のヒント
ターゲットが泳ぐ「池」はどこか?
▼実践のヒント
大手サイトやエージェントに頼らない「モデル」を作れるか?
▼実践のヒント
本記事のまとめ
応募の「数」だけ見ていないか?
人事:現在、新卒の採用活動を実施中です。ただ、開始当初と比べて、説明会の参加者数やエントリー数をキープするのが難しくなってきました。
堀内:できることをやっているのであれば、時間が経つにつれて下がってしまうのは仕方がないかもしれませんね。
人事:ただ、明るいニュースもあって、1次・2次ともに面接の通過率は上がっています。説明会の時点で感触がいい学生も増えてきているので、その人を放したくないですね。
堀内:説明会の参加者の中で「いいな」と感じた学生が、その後の選考フローでどうなっているかは追えていますか?
もし、その学生が落ちているようであれば、人事担当の目線と、面接官の目線が合っていないということになります。
あとは、学生に辞退されていないかどうかも確認したいところですね。選考フローの途中で逃げられているのか、最終選考までは進むけれども、別の企業を選んでしまっているのか。
人事:確かに、そこは大事なポイントですね。
堀内:時系列が週単位で大きく動く中で、全体だけを見ているとなかなかクリティカルな頭にはなれません。ターゲットを絞ってその後を追ってみると、本質的な課題がわかると思います。
たとえば、応募してくれた学生が数人しかいなくとも、全員いい子で、かつ、順当に選考を通過していればグッドです。でも、逆に「いいな」と思う学生がゼロだとしたら問題ですよね。「いいな」と思う学生の人数と、その後を追える状況が作れるといいと思います。
人事:週に1人はウチにカルチャーマッチしている学生が来てくれている感触があります。データとして追うこともできると思うので、やってみます!
▼実践のヒント
☆大事なのは、応募者の数よりも質
☆採用したい学生の「その後」を追う
☆人事担当と面接官のズレは要チェック
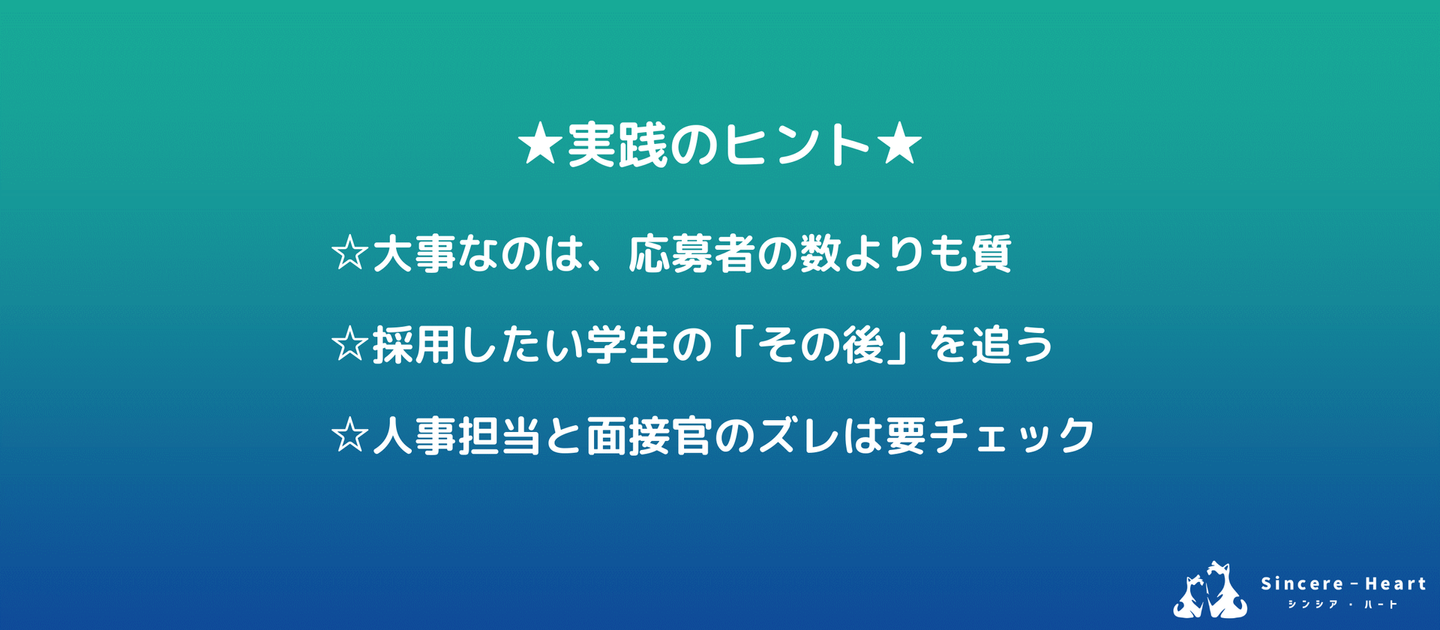
学生の「共通項」を見つけられているか?
堀内:今、「いいな」と思っている学生さんのバックボーンを詳しく教えてもらえますか?
人事:スポーツに打ち込んできた学生が多いですね。大手を狙っていたけど落ちてしまった方や、部活で就活を中断している時期があったために、受けている企業の絶対数が少ない方、という印象です。
堀内:大学のレベルはどうですか?
人事:中堅私立大学ですね。それより下位ランクの大学もいます。
堀内:他の企業は落ちてしまうけど、自社の社風にマッチするっていうのは大きいキーワードですね。偏差値は高くなくとも、相性の合う大学はあると思います。たとえば、商業系の大学で、ある程度お金の勉強をしてきているとか。
あとは、アルバイトの共通項もありますね。学生時代に、あるチェーン店の居酒屋でアルバイトしていた方を立て続けに採用したという企業もあります。
内定者に話を聞いてみると、その居酒屋の店長の教え方がすごく良くて、アルバイトを通じて社会人としての基本が身についていたんですよね。
人事:それで言うと、ウチは学生時代に焼肉屋でアルバイトしていたメンバーが多いかもしれないです。
堀内:面白いですね。アルバイト先として焼肉を選んだ理由まで掘り下げてみて共通するものがあれば、それは確かな共通項かもしれません。
人事:でも、「家から近かった」とか「時給が良かった」みたいな理由だと、あまり意味がないですよね?
堀内:確かに、相関関係を分析するときのミスリードにならないように気をつける必要はあります。たとえば、夏はかき氷が売れるというイメージがありますが、実際は、夏でも温度が低ければ売れません。つまり、かき氷と相関関係にあるのは「夏」ではなく「温度」です。
アルバイトとして焼肉屋を選ぶ理由の中に、何かしら社風と相関する“タグ”があるかもしれないと考えてみてください。
人事:メンバーと話してみます!
堀内:大学のレベルは高くなくとも、体育会系の学生ならカルチャーマッチしそうだという発見ができたのは大きな進歩です。今後も、「受かるのはこういう学生が多いですね」とか、逆に「こういう学生は絶対通らないですね」とかを継続して考えて、共通項となる“タグ”を言語化していけるとすごくいいですね。
▼実践のヒント
☆大学のランクに惑わされてはいけない
☆「いいな」と感じる学生の共通項(=タグ)を探す
☆自社カルチャーと結びつく“本質的なタグ”を見つけるべし
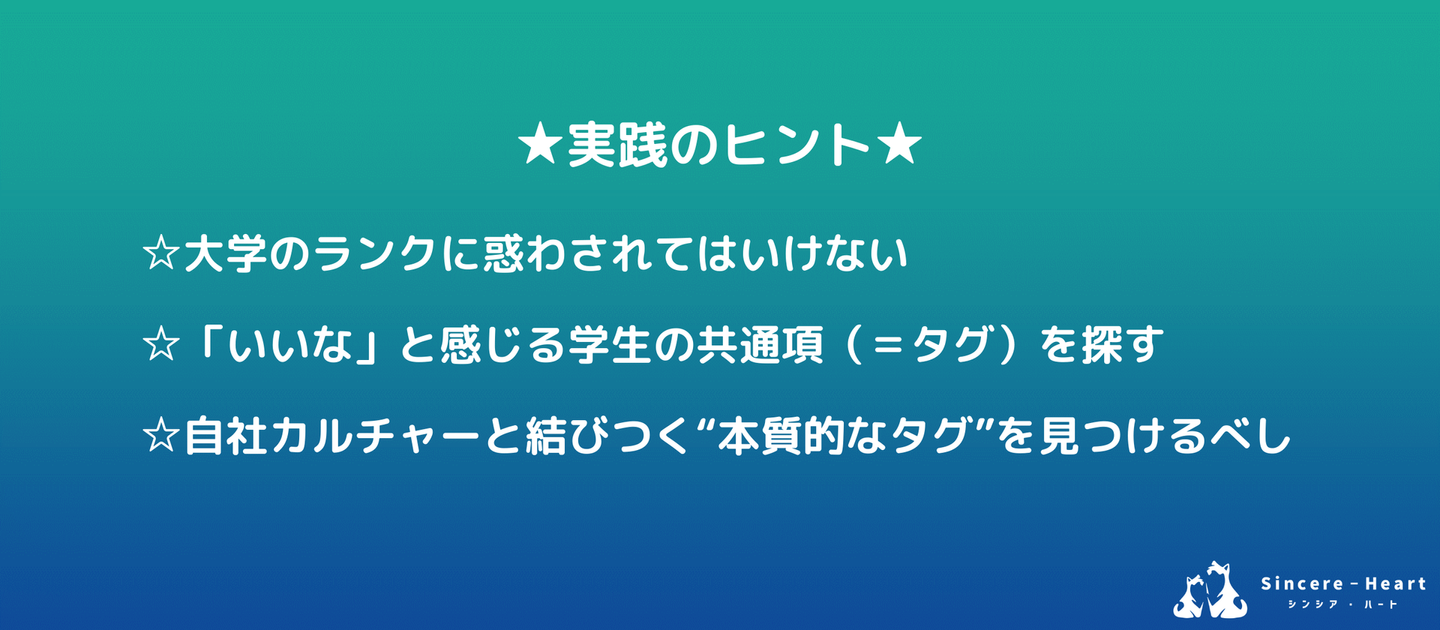
ターゲットが泳ぐ「池」はどこか?
堀内:共通する“タグ”が見つかったら、今度はそんな学生が泳いでいる“池”を見つけたいですね。
人事:池ですか。
堀内:まず、「クラスター」をイメージしてもらうとわかりやすいですね。類似の特性や行動を持つ集団という意味です。その集団がいる場所が“池”です。
現代の就活市場は、マイナビやリクナビなどの大手ポータルサイトに登録しているたくさんの学生に対して、広く網を張っているような状況だといえます。
でもこれは、言ってしまえば「どんな魚が引っかかってくるかわからない」状況とイコールなんですよね。しかも、他社とバッティングすることも多い。
なので、「自社の狙う魚が泳いでいる」かつ「他の釣り人が狙っていない」という池を見つけることができれば、効率的に、そして、有利に採用活動を進められます。
人事:当社の「スポーツに打ち込んできた人」や「焼肉屋でアルバイトをしていた人」だと、どんな池が考えられますか?
堀内:現時点で感触がいい中堅私立大学の運動部やサークルが一つ。あとは、その大学のキャンパスのそばにある焼肉屋などの飲食店も可能性がありますね。
人事:確かに、探しに行ってみる価値はありそうですね。
堀内:スケジュール感も大事です。たとえば、体育会系の学生だと、5〜6月にある学生最後の大会に向けて活動している方が多いと思います。
となると、就活が解禁される3年生の3月くらいに一旦動き出して、早めに内定を取ることを目指す。ここが第一のタイミングです。これが叶わなかった場合、最後の大会が終わった後にまた動き出す。ここが第二のタイミングですね。
学生の集団の動きがわかってくると、企業側がそれに合わせてアクションを起こせるので、そういう目線も持っておくといいと思います。
▼実践のヒント
☆自社に合う学生は特定の池(=集団や場)に存在する
☆狙い目の池で学生と接点を持つことが採用成功につながる
☆大手サイトやエージェントに頼りすぎない
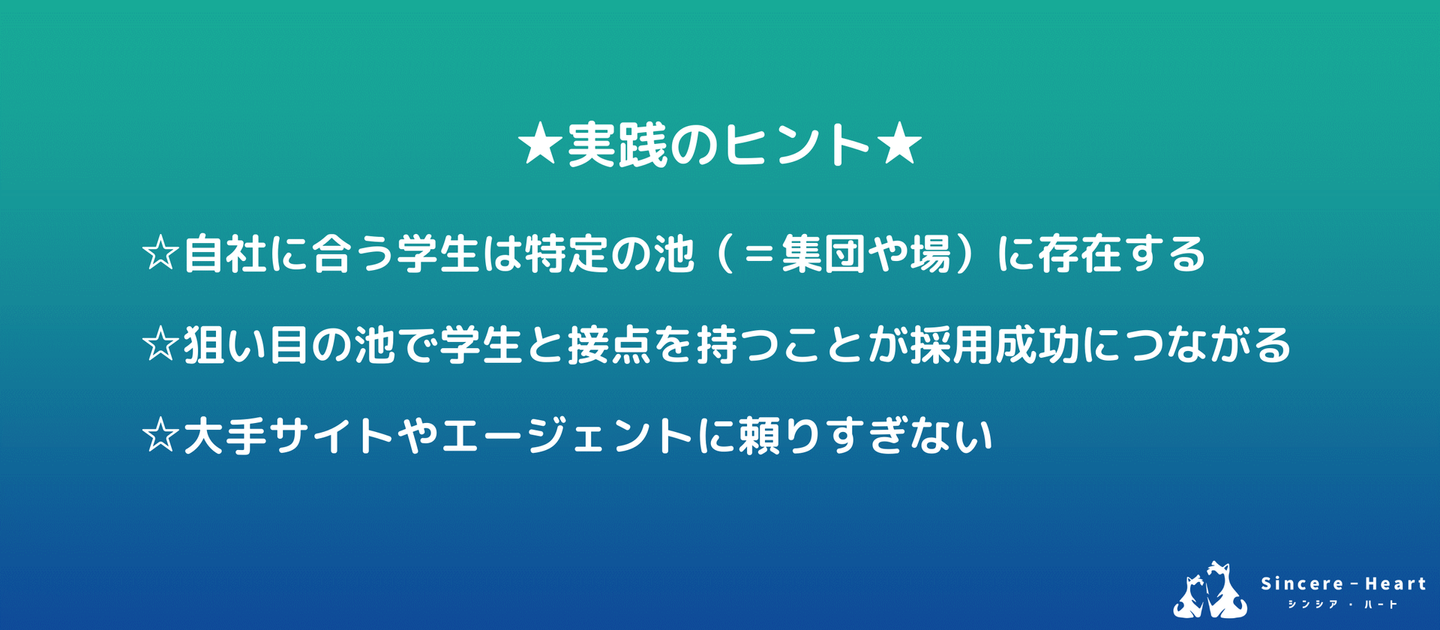
大手サイトやエージェントに頼らない「モデル」を作れるか?
人事:でも、池を見つけたとして、どうやって接点を持てばいいんでしょう?
堀内:先ほど例に挙げた、あるチェーン店の居酒屋出身の学生を連続して採用したケースでは、内定者を通じて店長を紹介してもらって仲良くなり、その店を会場にした就活セミナーを開かせてくれませんか?と依頼しました。実際に開催までことが進み、約20人が集まりましたね。
ここで全ての新卒採用を完結するというのはさすがに無理がありますが、半分はそういった手立てで、もう半分はエージェントなどを活用するというモデルが作れたら、すごく楽になると思いますよ。採用にかける経費も削減できますし。
人事:ぜひ取り入れたい事例ですね!ちなみに、セミナーの内容は就活以外がテーマでもいいんでしょうか?
堀内:もちろん!自社にマッチする思考を持っている学生が「面白い」と思ってくれるようなコンテンツならOKです。
人事:当社はリユース事業を行っているので、古着とか、せどりとかのセミナーがいいかな。
堀内:いいですね。コアファンが多い領域なので、学生は集まりやすいのではないかと思います。
あとは、その場でアルバイトやインターンの募集もできるといいですね。学生としても自分の大好きな仕事ができれば嬉しいでしょうし、会社としてもメリットは大きいですよね。
その学生がそのまま就職してくれたら、辞めにくい人材になってくれると思います。
人事:新しい視点ですね!これまではマジョリティに打って出るやり方をしていたと思うので、もっとコアなところを攻めていけるように考えてみます。
▼実践のヒント
☆学生向けのセミナー・イベント開催で学生の心を掴む
☆自社事業と親和性のあるコンテンツがGood
☆その場でアルバイト・インターンを募集するのも効果的
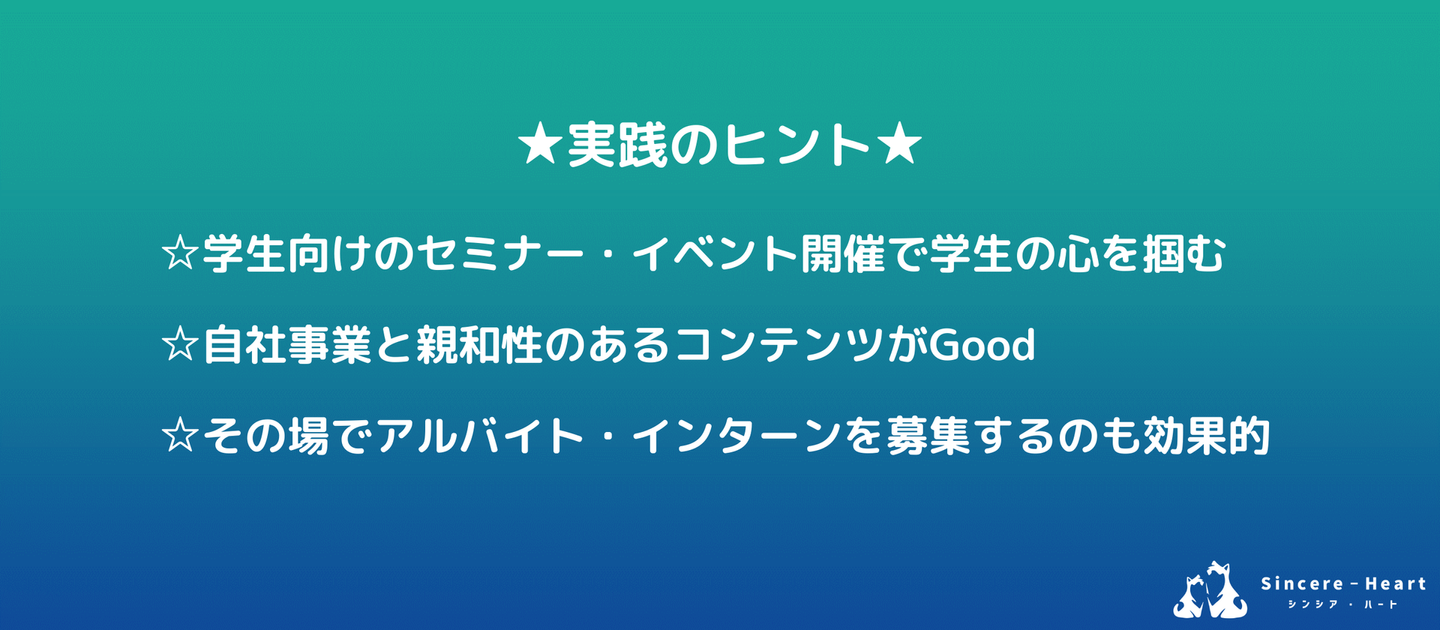
本記事のまとめ
今回のケースを通じて、4つの押さえておきたいポイントが見つかりました。
- 応募の「数」よりも「質」を重視する
- 採用に至る学生・至らない学生の「共通項」を見つける
- ターゲットが泳いでいる「池」を探し出す
- 大手サイトやエージェントに頼らない採用の「モデル」を作る
大手企業であれば、学生からの知名度が高く、採用活動に資金を費やせるため、苦労しなくても学生を集めることができます。そんな企業と同じ土俵で戦っても、あまり良いことはありません。
「新卒の応募者が集まらない」
「他社に入社するからと辞退されてしまう」
「大手就活サイトやエージェントを利用しているが、効果がイマイチ」
そんな悩みに直面したときは、今回のヒントをぜひ現場で試してみてください。
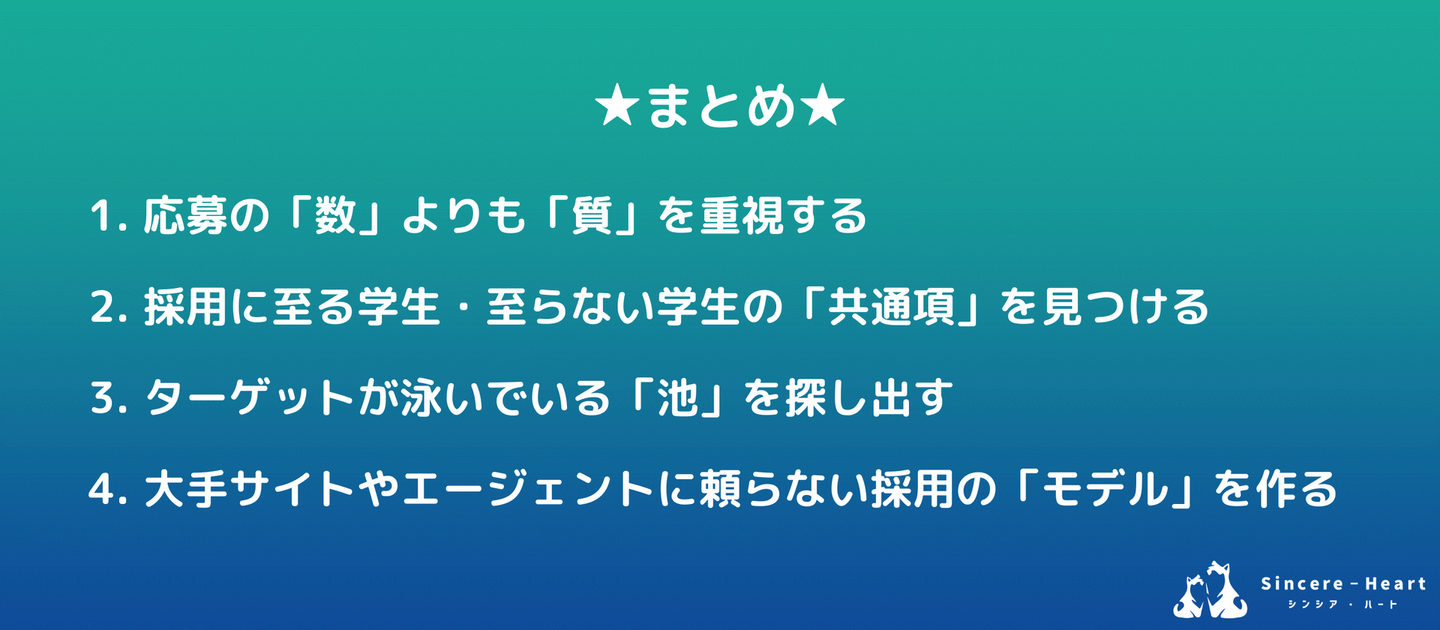

/assets/images/18942872/original/bf614d2e-b864-4369-9dd1-f4b26e0c80ac?1724117188)


/assets/images/18942872/original/bf614d2e-b864-4369-9dd1-f4b26e0c80ac?1724117188)
/assets/images/18942872/original/bf614d2e-b864-4369-9dd1-f4b26e0c80ac?1724117188)

