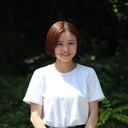これまで多くの社員インタビューを通じて、当社の魅力や働きがいをお伝えしてきたできるくんの採用ブログ。今回は代表取締役の岩田真さんにお話を聞きました。
AIの急速な進化により、大きな転換期を迎えているWeb制作業界。約2万社が乱立する非効率な業界構造はどう変わるのか。Webディレクターの役割はどう変化していくのか。できるくんが描くビジョンも含め、岩田さんにじっくりと語っていただきました。
岩田 真
株式会社できるくん 代表取締役
京都大学経済学部卒業。2012年新卒で株式会社ジャフコに入社、投資部にて数億円単位のベンチャー投資事業に従事。2015年4月株式会社できるくん設立。設立から3年間で上場企業からベンチャーまで50社以上のWeb制作・システム開発・マーケティング支援を実施。2018年、オンライン相談窓口「Web幹事」をローンチ。2024年よりAI BPO事業「ホームページできるくん」をローンチ。
Web制作は入り口に過ぎない
ーーWeb制作事業からスタートしたできるくんですが、現在はマッチングサービス「幹事シリーズ」やAI BPOサービス「できるくんシリーズ」を展開しています。今後も「Web制作会社として山を登るつもりはない」とのことですが、具体的にどのようなビジョンを描いているのでしょうか?
岩田:私たちの最終目標は、中小企業の事業成長を支援するプラットフォームをつくること。そのために、まずはあらゆる経営課題をAIとBPOで解決する、従来のWeb制作会社とは全く違う存在を目指しています。
中小企業の経営課題は大きく3つに集約されます。集客、採用、そして資金繰りです。これらは相互に関連していて、集客がうまくいけば売上が上がり、資金繰りが改善する。資金繰りが良くなれば採用に投資でき、良い人材が集まれば更なる成長が見込める。この好循環を生み出すことが重要です。
現在はホームページ制作を入り口にしていますが、これは中小企業にとってあくまでデジタルデビューの第一歩に過ぎません。開業したばかりの方や、これまでデジタルに触れたことがない経営者の方々が本当に多くいらっしゃいます。そういった方々にとって、初めて触れるデジタルツールがホームページなんです。
ーーそうしたデジタル初心者の方々に対して、できるくんはどのようなアプローチを取っているのでしょうか?
岩田:感動体験の創出です。例えば、LPやホームページを作り、問い合わせがくる体験は、デジタルに触れたことがない方には魔法のように感じられます。
「デジタルってすごい!」という成功体験を起点に、次は集客をもっと本格的にやってみよう、採用にも活用してみよう、という形で領域を広げていき、最終的には企業の成長を総合的に支援するプラットフォームを構築したいと考えています。
これは決して弱者救済のボランティアではありません。成長意欲のある中小企業を、デジタルの力で飛躍的に成長させる。そのためのインフラを作っているんです。Web制作はあくまで入り口。その先にある、中小企業の成長を総合的に支援するプラットフォームをつくる。それが、私たちできるくんが目指す姿です。
約2万社が乱立する業界構造を変える
ーー10年前にWeb制作事業を開始し、これまで5,000件以上の制作支援を行ってきた岩田さんから見て、Web制作業界の課題は何でしょうか?
岩田:端的に言えば、プレイヤーが多すぎることです。Web制作会社だけで約2万社、フリーランスのWebデザイナーやエンジニアも含めると、それ以上が存在しています。これは社会的に見て非常に効率が悪い構造です。
なぜこんなに多いのか。それは参入障壁が極めて低いからです。実際、私も最初は3人で会社を始めましたが、3人いれば月150万円くらいは頑張れば売上げられます。月300万円売り上げれば、普通のサラリーマンよりもリッチに暮らせる。生存ラインが低いから、みんな独立していくんです。
ーーWeb制作という仕事の本質から見ると、この状況をどう捉えていますか?
岩田:ホームページ制作は本来、型化できる仕事です。誰もが上部にメニューバーがあることを期待し、上から下に読み進め、最後に問い合わせフォームがあることを想定している。UI/UXの基本パターンはほぼ確立されています。これほど再現性の高い仕事なのに、そのノウハウが5,000社に分散している。本来なら100社程度で十分なはずです。
この構造の問題は、中小企業の経営者側にも大きな影響を与えています。5,000社もあれば、どこに頼めばいいか分からない。完全に「ガチャ」状態です。たまたま声をかけた会社、知人から紹介された会社が良いか悪いかは、実際に頼んでみるまで分からない。
ーーその課題認識から「Web幹事」というマッチングサービスを立ち上げたわけですね。
岩田:はい。実際に自分たちがWeb制作事業をやっていて、この非効率さを痛感していました。お客様にとって最適な制作会社を見つけるのは本当に難しい。だからこそ、良質な制作会社とお客様をマッチングするプラットフォームが必要だと考えました。
Web幹事は順調に成長し、業界トップクラスのプラットフォームになりました。しかし、生成AIの登場で、私たちの戦略は大きく変わることになりました。
AIがもたらす業界構造の大転換
ーーAIの登場でWeb制作業界はどう変わっていくのでしょうか?
岩田:根本的に業界構造が変わると考えています。AIを活用することで、これまで人間がやっていた制作業務の多くが自動化されます。重要なのは、規模を持つことが初めて競争優位性になるということです。
従来のWeb制作会社は、規模が大きくなるほど管理コストが増大し、生産性が下がっていました。バックオフィスのコストは増え、コミュニケーションコストも増える。「一人でやってた方がよっぽど儲かる」という状況になりがちでした。だから小規模な会社が乱立する構造になっていたんです。
しかしAIを活用すれば、状況は180度変わります。規模が大きいほどデータが集まり、AIが進化する。AIが進化すれば、より良いものを安く提供できる。更に顧客が増えてデータが増える。この好循環が生まれます。つまり、規模を持っている会社の方が圧倒的に強くなるんです。
ーーユできるくんでもAIでWebサイトが簡単に構築できるシステムを開発中ですよね。
岩田:はい。今期中にAIを活用した制作システムの試験導入を予定しています。実は既に、プロンプトとテンプレートを組み合わせることで、かなりのレベルのサイトが自動生成できるようになっています。
具体的には、まずシステム的にプロンプトを作成し、それを基にレイアウトを生成します。問い合わせゾーンや強みを訴求するゾーンなど、セクションごとに元となるテンプレートデザインを持っていて、AIがそれを呼び出して組み合わせる仕組みです。
ーー実際にAIで生成されたサイトの品質や課題について、どのように感じていますか?
岩田:現段階では似たようなサイトになってしまうことです。AIは効率よく平均点を叩き出すことは得意ですが、オリジナリティを出すのはまだ難しい。そこで当面は、AIが作った基本構造に対して、デザイナーがファーストビューや見出しデザインなどの要所でオリジナリティを加えるハイブリッド型で市場投入する予定です。
しかし、これは過渡期の話です。来年、再来年には、オリジナリティのある部分も含めて完全自動化できるようになるでしょう。GPT-5のようなより高性能なモデルが登場すれば、本当にゲームチェンジが起きると思います。
そうなると、業界構造は「小さい会社が無数にある」状態から「AIを使いこなす数社が市場を押さえる」状態へと変わっていきます。マッチングする意味もなくなる。だから私たちは、マッチングプラットフォームに加えて、自らAIを活用してサービスを提供することにしたんです。
Webディレクターは、より付加価値を生み出すポジションへ

ーーAI時代において、Webディレクターの役割はどう変わっていくのでしょうか?
岩田:短期的な視点と長期的な視点で分けて考える必要があります。
短期的には、まだ人間のディレクターが絶対に必要です。なぜなら、AIで完全自動化するためには、まず人間が良いオペレーションを作り、ノウハウを蓄積する必要があるからです。
これは記事制作でも同じですよね。手作業で記事を書いたりインタビューをしたりした経験があるからこそ、AIを使いこなせる。いきなりAIだけでやろうとしても、質の高いものは作れません。私たちは今、そのノウハウを蓄積するフェーズにいます。
しかし中長期的に見ると、制作進行管理やワイヤーフレーム作成といった従来の仕事は確実にAIに代替されていきます。現時点でもAIを使えばそれなりのワイヤーフレームは簡単に作れてしまいますよね。
ーーでは、Webディレクターの仕事はなくなってしまうのでしょうか?
岩田:いいえ、そうではありません。むしろ、より価値の高い仕事にシフトしていくことになります。
制作進行という仕事がなくなれば、空いた時間でお客様の成長を支援する新しい価値を生み出していくことになります。
例えば、ホームページ制作後のデータを分析して改善提案を行ったり、集客施策を提案したり、採用ページの最適化を提案したりする。場合によってはクロスセルで新しいサービスを提案することもあるでしょう。
つまり、単なる制作ディレクションから、お客様に伴走するパートナーへと役割が変わっていくんです。従来の「作って納品して、あとはよろしく」という関係性から、長期的にお客様の成長を支援し続ける関係性へと変化していきます。
最後まで残るのは顧客接点です。お客様の多くはデジタルに詳しくない。テクノロジーでできることを翻訳して伝え、お客様の課題を理解して最適な提案をする。この部分は、まだまだ人間が担い続けるでしょう。
ーーAI BPO事業に参入する大手企業もある中で、できるくんの優位性はどこにあると思いますか?
岩田:大手企業は、AIによる自動化にまだ本気で取り組めていません。なぜなら、彼らには既存の大口クライアントがいて、まずはそこを満足させなければならないからです。新しいチャレンジよりも、既存事業の維持が優先される。
一方、小規模な制作会社は、そもそもAI開発に投資するキャッシュがありません。私たちのようなサブスク型のサービスを提供するにしても、月額数千円程度の価格設定で最初は確実に赤字になります。サブスク型のAI BPOは月額で費用を回収するモデルなので、その赤字に耐えられる資金力が必要です。
当社は投資家から資金調達をしているので、結果として、できるくんが最もAI活用とWeb制作の領域に投資している会社になっています。だからこそ、AIが最も進化し、規模の経済が最も働く。この好循環に最初に入れる可能性が高いのが、私たちだと考えています。
従来の枠を超えて。業界変革の最前線でキャリアを築こう
ーー今、Webディレクターとしてできるくんで働く魅力についてどうお考えですか?
岩田:できるくんは「これって本当に必要?」「自動化できるんじゃない?」という視点で仕事を見直すことができる環境です。
既存のオペレーションは誰かが決めたものではなく、いくらでも変えていい。すべてはお客様に価値を提供し、事業目標を達成するためにある。この2つに対して前進するかしないか、その判断軸だけで動いていいんです。
さらに言えば、私たちはホームページ制作の領域で日本一を目指しています。次世代の業界リーダーになる可能性がある会社で、貴重な経験を積むことができるのです。
5年後、10年後に「あの時、変化の波に乗っておいて良かった」と思えるか、「従来型の仕事に固執して取り残されてしまった」と後悔するか。その分かれ道に今、立っているんです。
しかも、最先端のAIと協働してサービスを作ることができます。Webディレクターとしての知見を活かしながら、それをAIに代替させる仕組みづくりに関わることができる。これは将来のキャリアを考える上で貴重な経験になるはずです。
ーー最後に読者の方々に向けて、メッセージをお願いします。
岩田:まず伝えたいのは、これから日本は人口が減少し、人材の価値は確実に高まっていくということです。その中で、従来型のディレクション業務に留まっていては、自分自身がAIに代替されてしまう。せっかくの人材価値を活かせないのは、本当にもったいないことです。
私たちが求めているのは、「このままでいいのか」という健全な危機感を持っている人です。目の前の案件を捌くことに追われながらも、もっとお客様に寄り添いたい、自分の価値を高めたいと思っている。そういうモヤモヤを抱えている方は、ぜひ一緒に頑張りましょう!
最後までお読みいただきありがとうございました。
ご興味をお持ちいただけましたら、募集ページからぜひご応募ください!
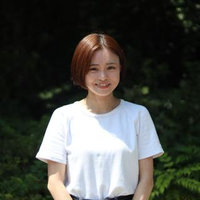



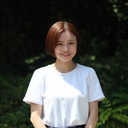
/assets/images/22759706/original/641fd617-97a1-45e6-bf58-13f5f0856a35?1766469554)
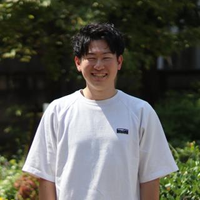

/assets/images/22847364/original/d4d563d9-65c5-4060-a9f0-6cf7be4a6da5?1767844480)