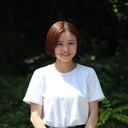中小企業のデジタル化支援を加速させる株式会社ユーティルのAI BPO事業部。今回は制作チームのマネージャー後藤 雄太郎をインタビュー。
後藤は新卒で介護系ベンチャーに入社し、訪問歯科医療事業の立ち上げを経験した後に、ユーティルに転職。その後、「Web幹事シリーズ」のDXアドバイザーを経て、AI BPO事業部の立ち上げメンバーとして、未経験からWebディレクターへ転身。AI BPO事業部の制作チームを牽引してきました。
AI BPO事業部の制作チームをどのように立ち上げてきたのか。何を信条に仕事に打ち込んできたのか。AIを活用した新たな制作体制の構築も含めて、詳しく聞きました。
▼過去に後藤が登場した記事
「Webディレクター 2.0」AIをフル活用して中小企業のデジタル革命を支える仕事の流儀
後藤 雄太郎(ごとう・ゆうたろう)
株式会社ユーティル AI BPO事業部 制作チーム マネージャー。新卒で介護系ベンチャー企業に入社し、訪問歯科医療事業の立ち上げを担当。その後、システム導入をきっかけにユーティルと出会い、2020年7月に入社。未経験からWebディレクターとしてキャリアをスタートさせ、現在は月100件規模の制作体制構築と仕組み化を推進している。
同じゼロイチでも、スケールが違う
![]()
ーー介護、医療、そしてWeb制作と異なる業界を経験されていますが、一貫している軸はありますか?
後藤:昔から「せっかく働くなら、困っている人を助ける仕事がしたい」と思っていました。新卒で介護系ベンチャーに入ったのは、困っている人たちのQOLを上げたいと思ったからです。
今も仕事選びの軸は同じです。大企業向けの仕事にはあまり興味がなくて。「ホームページを持っていなくて困っている人たちを助けたい」「中小企業が抱える不便を解消したい」そんな思いで仕事をしていますし、実際に毎日楽しく働けてます。
ーー前職でも新規事業立ち上げを経験されたそうですが、ユーティルでのゼロイチとの違いはどこにありましたか?
後藤:ゼロイチという点では一緒なんですが、目指す規模感が決定的に違いましたね。前職の訪問歯科医療事業は、6年かけて年商1億円に届かない規模。
町の歯医者さんと老人ホームの間に入って、歯医者さんに訪問診療をしてもらう体制を作るビジネスモデルで、一度クリニックとの関係性を築けば、あとは比較的手離れが良い。個人の人間力で維持できる、デジタルとは真逆の構造だったんです。
一方、ユーティルでは社会により大きなインパクトを与えるべく事業を非連続に拡大させていく(その過程でIPOを目指している)ので、スケールが違います。個人プレイから再現性のある状態にしていく工程は一緒ですが、その重要性と、仕組みによる再現性の精度の高さが全く違う。
前職では個人が街の歯医者さんと関係値を築けていれば何とかなりましたが、今は型を作って、それを実装し、仕組みとして回さないと成立しない。特に規模を拡大する上ではAI活用が肝になり、チーム作りのやり方も根本的に変わってきています。
未経験から、月100件対応できる体制を構築
![]()
ーー未経験からWebディレクターとして、どのように仕事を覚えていったのですか?
後藤:まずは限界までやってみる。試行錯誤の中で失敗とも向き合う。この繰り返しで仕事を覚えていきました。前職は紙とFAXの世界でしたから、入社当初は「LPって何ですか?」という基本的なことから質問していました(笑)。完全に未経験だったので、本当に手探りでしたね。
体制づくりに関しても最初は一人だったのですが、AIを活用することで徐々に月10件、20件と対応できるキャパを増やしていきました。もう1名のディレクターが入社した頃には、すでに月40件ぐらいは対応していたと思います。本当に突貫で体制を作り、今では月100件近い案件に対応できるチームになりました。
ーーそれだけの量をこなすのは大変だったのでは?
後藤:積極的にAI活用をしていくことで活路を見出すことができてます。それに加えて、重要だったのは「同じ失敗をしない」という意識です。未経験だと何が起きるか予測できないし、どうしたらこうなるか分からない。
だから実際に失敗して、「こういうエラーが起きるんだ」「こうゆう原因ででスタックしてしまうんだ」という経験を一つずつ体に刻んで覚えていく。加えて、AIに置き換えられる部分はないか検討する。この積み重ねで最低限の土台ができました。
ーー圧倒的な数の案件を回しながら、お客様満足も実現する。この両立はどう実現しているのですか?
後藤:大きく2つのポイントがあります。1つ目はスピード感。やりたいと思った後にこんなにすぐ公開できるんだという顧客体験の創出です。そのために、今も積極的にAIを活用しています。
もう2つ目は、サイトを作った後の道しるべになること。初めてデジタル投資をする人にとって、サイトを作った後に何をすべきか絶対分からないはずなんです。「次はこうしましょう」「こうやったらWebで集客できます」という道筋を示すことがAI BPO事業部ディレクターのやりがいです。
キレイなサイトを作ることも顧客満足度を高める一つのポイントですが、それだけではお客様の事業の成長につながりません。お客様自身も気づいていない「デジタル投資をする価値(=「感動」)」に気づいてもらうことが重要なんです。そのためには、制作工程を通して信頼を勝ち取ることが必要で、この辺はディレクターの腕の見せ所であり、楽しみでもありますね。
お客様の事業を徹底的に理解し、訴求ポイントを整理する
![]()
ーーWebディレクターとして心がけていることは?
後藤:お客様の事業に興味を持つことです。簡単にサイトを作る知識を求めてくるようなお客様だったら、他でやってもらえばいい。私たちが価値提供すべきお客様は、デジタル投資をしたことがなくて、でも「さすがにもうWeb使わないとやばいよな」と何となく不安に思っている人たちです。
そういった方々に伴走するためには、Webサイトにいかに詳しいかではなく、お客様の事業をいかに短時間で理解し、課題に共感できるかが重要です。
具体的には、登場人物と価値提供の流れを絵に描けるようにすること。誰が誰に何を提供して、対価としてお金がどう流れているのか。最近はサービスやビジネスモデルが複雑になってきているので、お金の流れと価値提供が違ったりもします。でも、登場人物と誰が誰にどんな価値を提供しているのかを整理できれば、事業構造自体は理解しやすくなります。
ーーなぜお客様の事業理解が重要になるのでしょうか?
後藤:「この人プロではないな」と思われて、信頼されないからです。お客様はサイトの知識だけではなく、自分たちの事業をどれだけ理解しているかによって、私たちがプロであるかどうかを判断するケースがほとんどです。
お客様の事業と課題感を理解した上で「だからこういう情報を発信しましょう」という話になるべきなのに、最初から「このサイトどうしましょう?」と見せ方の話になってしまうと、お客様は「うちのことを理解してない」と思ってしまう。
それにお客様はWebのプロではないので、「どうしましょう?」と聞いても、答えを持っていないんですよ。仮にお客様の言われるがままにサイトを作ったとしても、情報が整理されていないサイトが出来上がってしまう。だいたいサイト制作がうまくいかない要因はこれだと思っています。
いかに短い時間でお客様の事業内容を理解して、そのためにこういう情報を発信すべきだ、見せ方はこうした方がいいと言い切れるようになる。そのためには、信頼を勝ち取れるコミュニケーション設計が重要なんです。
ーー数字目標達成を重視する中で、やることとやらないことの線引きはどうされていますか?
後藤:難しい問いですよね。お客様一人ひとりの顔を見ていくと、「ここまでやってあげたい」という思いはあります。でも、ユーティルが掲げる「日本中の中小企業のポテンシャルを解放する」というビジョンを達成するためには、及第点を何%作れるかが重要です。
AIが中心にあるオペレーション設計で、品質、スピード共に期待値を上回るか。サービスとしての基本ガイドライン、SLA的な線引きをどこに置くか。ここまではやる、これ以上は今はやらない。ただ諦めてもらうのではなく、「今じゃなくて次の段階でやりましょう」と納得してもらう。その握り方を含めて、サービスとして統一できる状態を目指しています。
AIが変える未来。1年後のWebディレクター像
![]()
ーー1年後Webディレクターはどんな役割になっていると思いますか?
後藤:Webディレクターの役割は変わると思います。今までサイト制作に100%の稼働を割いていたのが、AIの活用に10〜20%でサイト制作をする世界に変わります。残りの80〜90%で、作ったサイトをどう見られるようにするのか、作った後の提案比重が重くなるでしょう。
ーー理想のチーム像と、一緒に働きたい人を教えてください。
後藤:課題を楽しめるチームがいいですね。やっぱりポジティブな方と一緒に働きたいです。できない理由を探すんじゃなくて、「どうすればうまくいくか」の方法を話しあえるチーム。そして、それぞれがプロ意識を持っていることが理想です。
プロ意識というのは、お客様への興味と責任感。この2つは別に知識やスキルがなくても持てるものです。そこを持っていて、みんなそこは自信があるというチームが理想ですね。
採用面接をしていて気づいたのですが、世の中には「作った後の運用ができない」「お客様に寄り添えていない」「納品だけでその後の運用は何もできない」という理由で転職を検討されている方が多くいらっしゃいます。そういう方にこそ、ユーティルは最適な環境だと思います。
今後はAIで制作工程を代替できるようになり、本当の意味での伴走支援が実現できる世界になっていきます。私たちは、制作会社と言えば「ユーティル」と言われるような会社にしたい。そのためには制作工程や作り方を根本から変える必要があります。
従来の制作会社の常識を超えた新しい仕組みを作りたいと考えているので、柔軟な発想と行動力がある方と一緒に働きたいですね。「作るのは全部AIで、作るためのAIをうまく使える人」が未来のディレクター像かもしれません。
未来のディレクターには、経験よりも変化を恐れず挑戦する姿勢、そして課題を楽しめる姿勢が求められます。お客様との接点が多いポジションだからこそ、やりがいも大きい。そんな魅力的な環境で、一緒に新しい制作会社の形を作っていきましょう!
最後までお読みいただきありがとうございました!ユーティルではWebディレクターを募集しています!ぜひこちらよりご応募ください!
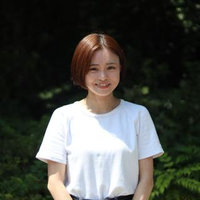




/assets/images/21653080/original/a97c3240-4379-4fd2-adc0-8fba15dfb564?1753165134)
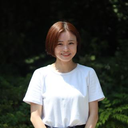
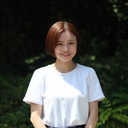
/assets/images/21653080/original/a97c3240-4379-4fd2-adc0-8fba15dfb564?1753165134)
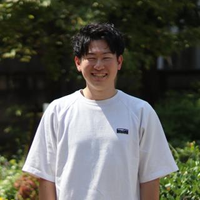
/assets/images/21774106/original/a97c3240-4379-4fd2-adc0-8fba15dfb564?1754525164)