メガベンチャーのレバレジーズで5年間、新規事業部門や難易度の高いM&A部門におけるトップセールス、さらには支店マネジメントまで経験し、確かなキャリアを築いてきた梶家。そんな彼が、なぜ創業間もないHRXへのジョインを決意したのか。その決断の裏には、代表・新との深い縁と、自身の揺るぎないキャリア観がありました。今回は、梶家のキャリア変遷を辿りながら、HRXで描く未来について語ってもらいました。
梶家 康平(Kajiya Kohei) / HRX 執行役員COO
1996年生まれ。神戸大学を卒業後、2020年4月にレバレジーズ株式会社へ入社。エンジニア採用支援で100社以上の採用成功に貢献。その後、同社のM&A事業部へ異動し、スタートアップや中小企業の経営・事業承継支援に従事。「組織構築・採用支援の初期フェーズから関わりたい」という思いから、株式会社HRXに参画。
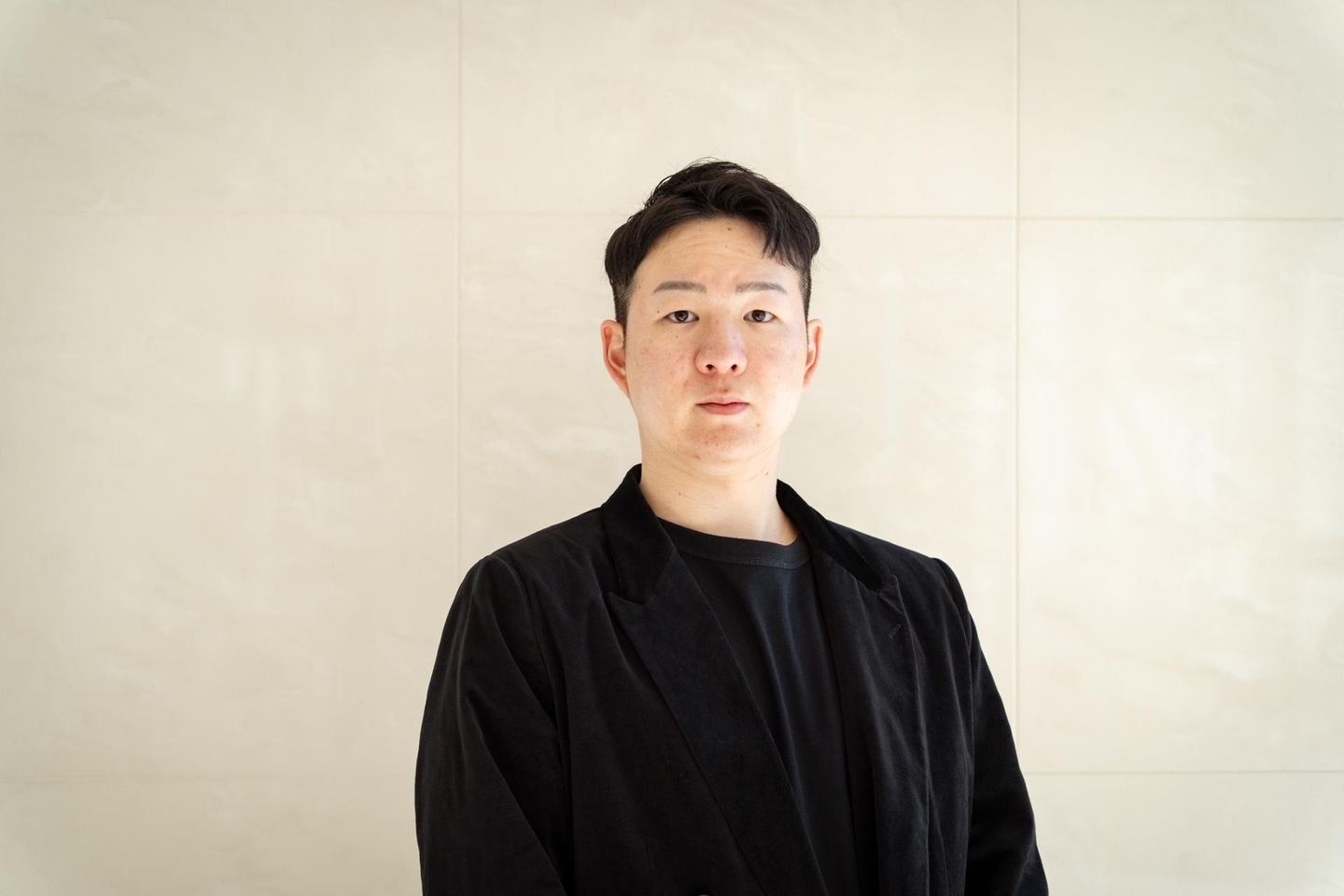
突出した存在になるために。最適な環境を求めてたどり着いたファーストキャリア
——キャリアの原点として、就職活動の話からお聞きします。当時、大事にしていた軸はどのようなものでしたか?
第一に、最速で成長できる環境を求めていました。将来、ある程度の選択肢は自ら選べるような状態になりたくて、早いうちから「自分で稼ぐ力」をつけたいと思っていたんです。
職種については、将来どんな道に進むにしても、営業スキルは必須だと考え、営業職を目指しました。「トップセールスになりたい」「スキルを尖らせたい」という気持ちが強く、営業力や成果主義でキーエンスを志望し、無事に内定をいただくことができました。
——第一志望のキーエンスに内定をもらったものの、最終的にレバレジーズを選んだ決め手は何だったのでしょう?
最も大きな決め手は、そのほうが、自分にとっては難易度が高い道だと感じたからです。
正直、知名度でも待遇面でも、キーエンスで働くほうが恵まれていたと思います。一方で、収入面や会社の安定性が約束されている環境よりも、成長フェーズのベンチャーで結果を出す方が「個」の職能を高めることに繋がる気がして。そのうえで、金銭的な目標も達成できたら、すごくかっこいいんじゃないかと感じ、敢えて普通の人が取らないような選択をしました。
当時、周囲からは反対されることが多く、かなり悩みましたが、「後悔しないようやり遂げる」という強い覚悟を持って、入社しました。
徹底したKPIドリブン思考。「再現性」ある営業スタイルの確立へ
——入社後はどのような配属・キャリアを歩まれたのでしょうか?
最初に配属されたのは、当時立ち上がったばかりの新卒人材紹介部門でした。法人営業を担当し、新とはこの部署で同期として出会いました。
設立間もない組織ということもあり、入社4年目の事業責任者を中心に、若手メンバー数名で組成された、まさにベンチャーらしい環境でした。言うまでもなく、営業マニュアルや成功事例などは一切存在せず、何もかも自分でやり方を確立していく必要がありました。
——そんな環境で、どう成果を出していったのですか?
今思えばとてもシンプルですが、目標から逆算して必要なタスクを超細かく分解し、それを月次、週次単位で徹底的に実行していました。
ゴールまでの道筋が明確になったら、あとはもう愚直にやるだけです。ただ、一年目は何をするにも遅いため、とにかく時間が掛かりながら日々業務をこなしていましたね。
——最初は、行動量に重きを置いていたんですね。
そうですね。ただ、圧倒的な行動量で結果を出す同期は、私の他にもたくさんいました。そこで「さらに突き抜けるには」と考え、私は再現性を持って成果を出せる仕組みづくりに、徹底的に向き合いました。
単に「ガムシャラ」な行動ではなく、一つひとつの行動が、ゴールへつながっている確信を持ちながら仕事を進めていったんです。「この行動は何のためにやっているのか」を意識するのと、しないのとでは、成果に大きな差が出るからです。
大きな仕事に挑むときも、考え方は変わりません。そのたびにゴール設定、KPI設計、具体施策の立案、あらゆる手段でKPIを達成する。このサイクルを高速で繰り返す中で、アウトプットのレベルもスピードもどんどん磨かれていきました。
飛びぬけたセンスやスキルは持っていませんが、この経験から再現性ある思考プロセスは確立できたと思っていますし、今、育成する際も大いに活きている気がします。
理想とする組織づくりを実現したい。「個の力」を高めに新たな環境へ
——その後のキャリアについても知りたいです。
入社2年目には、大阪支店へ異動しました。そこで得た経験が、「組織づくり」を深く考えるようになった大きなきっかけになっています。
当時の大阪支店は、目標未達が続き、メンバーのモチベーションもあまり高くない組織でした。しかし、この組織が変革する過程を経験できたことで、「自分で組織を作りたい」という気持ちが強く芽生えました。
——目標未達が続いていた中で、梶家さんはどのように組織づくりをしていったのですか?
まず取り組んだのは、思考の「型」を装着させることです。目標達成に向けたKPI設計やタスク分解といった具体的な思考法を言語化し、体系的に伝えました。これは、僕自身が新人時代に行った「成功サイクル」をチーム全体で再現するための最初のステップでした。
しかし、人は簡単には動きません。最も大切にしたのは「内発的動機づけ」です。結局、人から言われるより「自分でやりたい!」と思ったほうが、人は圧倒的に学習します。だからこそ、それぞれの“ツボ”を探し出すことに徹底的にこだわりました。
そのために、週次の1on1はもちろん、ランチや飲み会などの雑談を通したコミュニケーションをめちゃくちゃ取りましたね。とことんメンバーと向き合い、時間を掛けて心を開いてもらうことで、それぞれのモチベーションの源泉や強み、そして本音を引き出していったんです。
こうした地道な対話と、再現生のある「型」を組み合わせた結果、単に指示を出すのではなく、メンバー自身が「何をすべきか」を考え、自律的に行動する文化が生まれました。半年後にはチームの意識が劇的に変わり、目標達成が当たり前の「強い組織」へと生まれ変わっていったのです。
——その成功体験から、組織づくりへの思いを強めていったんですね。
正直に言うと、異動前の部署のほうが、新規事業ということもあり、個人としては優秀な人が多かったと思います。ですが、組織として見たときのパフォーマンスは、大阪支店の方が明らかに高かったのです。
この経験から、組織のパフォーマンスを左右するのは、個人の能力ではない。リーダーやマネージャーが日々どのようにメンバーと向き合い、いかに良いカルチャーをつくっていくかが非常に重要なのだと、改めて実感したんです。
メンバーとの良好な関係を築き、良い習慣を組織へ根付かせ、結果として成果が出る。私が本当にやりたかったのは、こうした組織づくりだと確信しました。
同時に、理想とする組織づくりを実現するためには、自分自身の「個の力」をもっと高めなければならないとも感じていました。組織を率いるリーダーのケイパビリティが、組織全体のパフォーマンスに直結するからです。そこで、社内でも特にチャレンジングな環境であるM&A事業部門へ、自ら異動を希望し、挑戦しました。
——異動後のM&Aの部署は、どんな雰囲気だったんですか?
社内でも異質な部署でした。中途入社の方が9割を占め、元銀行員や証券マン、M&A経験者など、金融業界出身者が多く集まっていました。
また組織というよりも、トップセールスの集団、個人事業主の集合体といった雰囲気でした。ひとり一人のビジネス戦闘力が非常に高く、自分の至らなさと向き合う日々でしたね。
——M&A事業の経験を通じて、どのようなスキルが身についたと感じますか?
難易度が高い環境で多くのことを経験できました。M&Aの業務は完全に新規開拓で案件を見つけていくうえ、折衝相手は社長です。数億円規模の案件をデリバリーするためには、高度な専門性や営業スキルが求められました。
例えば、財務、法務、人事、税務といった幅広い知識。また、買い手と売り手の双方にとって、M&Aでどのような経営・事業戦略上のシナジーが生まれるのか、どのような条件で成約できたらベストなのか、といったことを語れなければ信頼してもらえません。
高度な専門性や交渉力、提案力が求められる中で一定の成果を出せたことは、今でも大きな財産だと感じています。
なぜ、これまでのキャリアを手放してHRXへのジョインを決めたのか
——レバレジーズで3つの部署を経験して、順調にキャリアを広げてきた梶家さんが、HRXへジョインしたいきさつはどんなものだったのでしょうか?
入社1年目の頃から、新とは「将来、一緒に何かできたらいいね」とは度々話していたんです。お互いに働く環境が離れてからも交流は続いており、彼が独立してからも何度も声をかけてくれていました。
当初は、30歳くらいまではM&Aの領域でキャリアを積んでいこうと考えていました。しかし、ちょうど担当していた案件が成約したこともあり、描いていたキャリアプランより少し早い決断でしたが、「リスクが大きい挑戦をするなら20代のうちに」と、意思決定しました。
——得られるスキルや待遇の面では、前職でも十分満たされていたとも思います。それでもHRXを選んだ、一番の決め手とは?
決め手は、自分の理想とする「組織づくり」を追求できると思えたことです。
一般的な創業期のベンチャーは、プロダクト拡大や事業の黒字化を最優先に考えることが多い印象です。当然それらは重要ですが、HRXは「Human Resourceの最大化」を掲げ、企業のMVVや事業戦略、組織戦略を踏まえた採用支援を行っています。
大切にしているのは、目先の利益ではなく、まず組織のあり方から向き合うこと。クライアントだけでなく、自社においても「事業よりも組織をつくることに、創業フェーズからコミットする」という考え方に強く共感しました。
正しいことを、良いカルチャーの中でやり続ければ、結果的に成果もついてくる。実際にそれを本気でやっている会社はそう多くないと感じています。だからこそ、私たちはそこを全力でやりきりたいと考えました。
関西でイケてるベンチャーへ。HRXのカルチャーと未来のメンバーへ向けて
——現在、HRXでは採用活動も強化しており、組織を広げていくフェーズを迎えています。組織として、どのようなことに力を入れていく予定ですか?
今後は、会社としての一体感やカルチャーの構築に取り組みたいですね。
新とは根底で大切にしたい価値観を共有できていると感じています。一方で、これから仲間になってくれる人たちにも、その思いやスタンスをきちんと言語化したうえで、伝えて、カルチャーまで落としこむ必要があると思っています。
「関西」を拠点に「少数精鋭」で「イケてる」会社。私たちが目指すのは、そんなイメージを体現する組織です。HRXっぽさを醸成することで、自社採用から案件までリファラルを中心に集まるような、強い組織をつくっていきたいですね。
——組織拡大を見据えて、どんな人と一緒に働きたいと考えていますか?
大前提として、素直で誠実であること。
そのうえで、何事においても自分なりの信念とオーナーシップを持ち、成し遂げたいことに向かって突き進める芯がある人ですね。
また、相手を尊重したコミュニケーションが取れることも大切です。自分の意見を通すために攻撃的になったり、他人を貶めたりするような言動は、組織を疲弊させるので絶対にNGです。配慮は必要ですが、遠慮は不要。気遣いのある率直なコミュニケーションができる人と一緒に働きたいです。
そして何よりも、「まず挑戦してみよう」というスタンスを持っていること。例えば「5年目の社員が任されるような仕事を1年目からやりたい」「最速で新規事業を立ち上げたい」といったように、常識を超えるスピードで自ら高いハードルを設定し、やり切る胆力を求めています。挑戦の数だけ成長の機会があると捉え、打席に立つことを楽しめるようなポジティブな方と働きたいです。
——そんなマインドをお持ちの方に、HRXにジョインすることで得られる経験や成長を伝えるとしたら、どんなところでしょうか?
HRXでは、自社内での事業開発からクライアントワークまで、幅広い経験を積むことができます。特に創業期である今、抽象度が高く困難な案件も多いため、それを自ら考えてやり抜く過程で圧倒的な成長スピードを得られるはずです。
また、私たちは労働時間と対価が比例するような働き方からは脱却したいと考えています。30代後半以降は、重要な意思決定がメインの役割となり、そこでバリューを発揮する。そのために「若いうちにどれだけビジネスの解像度を上げられるか」が重要と考えています。未来の自分や大切な人との時間を手に入れるための最短の道だと信じ、今この瞬間も挑戦を続けています。
最後になりますが、私たちは、「Human Resourceの最大化」というミッションを掲げています。事業起点ではなく、創業フェーズから組織/カルチャーを第一に考え、イチからつくっていく。そして、その強固な組織/カルチャーが、魅力的な事業/サービスを生み出す。
もしミッションに共感し、少数精鋭の環境で挑戦したい方がいらっしゃれば、ぜひ一度お話しさせてください!共に挑戦する仲間を待っています。









