- 経歴不問|ラボ型開発エンジニア
- ビジネスオープンポジション
- フレックス|オープンポジション
- Other occupations (70)
-
Development
- 経歴不問|ラボ型開発エンジニア
- 文理不問|IT・DXエンジニア
- 経歴不問|AIプロダクト開発
- フロントエンド|自社開発
- ITエンジニア|プロダクト開発
- モバイル開発|プロダクト開発
- Web開発|サーバーサイド
- 開発エンジニア|Web開発
- モバイルアプリ開発経験歓迎
- 受託開発|自社開発
- プロダクト開発|Go
- サーバーサイド|自社サービス
- 受託開発|自社プロダクト
- 自社開発・自社サービス
- ラボ型開発|自社開発
- 実務未経験歓迎|リモート
- 実務未経験歓迎|リモート可
- 実務未経験歓迎
- HRTech|自社サービス
- AI|リモート相談可能
- リモート可|自社サービス
- 自社プロダクト|リモート可
- ノーコード・ローコード|DX
- Web開発エンジニア
- フリーランス|フルリモート可能
- Webエンジニア|自社サービス
- エンジニア|自社プロダクト
- 開発エンジニア|AI
- 開発エンジニア|フルリモート
- バックエンドエンジニア
- フロントエンドエンジニア
- 受託開発|ラボ型開発
- モバイルアプリエンジニア
- Web開発者歓迎|リモート
- 自社プロダクト|組織立ち上げ
- SaaS|プロダクト開発
- データエンジニア|自社開発
- データエンジニア|自社サービス
- Studioデザイン&マーケ
- webデザイナー|フルリモート
- webデザイナー
- デザイナー|フルリモート可能
- Business
- Other
今回は、グロースピリットで現在開発中の自社AIプロダクト「Hugmus(ハグマス)」についてCOOの安永さんに、開発の背景やチームの挑戦、そしてHugmusに込めた想いを聞きました。
創業3期目を迎えたいま、私たちは次のフェーズに踏み出しています。
これまで蓄積してきたHRとDXの知見を掛け合わせ、より多くの人と企業が私たちのVisionである“ビジネスを愉しめる社会を創造する”に近づく自社サービスの開発に踏み出しました。
今までは、クライアントの現状の課題を解消するキャッシュエンジンビジネスを中心に収益を上げてきたグロースピリットですが、今後は更なるスケールを目指して自社ブランドのサービス開発に力を入れていきます。
そんな私たちの思想を形にする初の自社AIプロダクトが、Hugmusです。
Hugmusは、AIの力で企業の「マネジメント課題」を根本から解消することを目指しています。
2025年11月の展示会で初めてのお披露目をする予定です。
現時点ではリリース前の段階でこうして記事にしているのは、私たちの「挑戦の途中」を伝えることに意味があり、「共に会社やプロダクトを創っていく人」にジョインして欲しいという想いがあります。
グロースピリットに興味を持ってくれた方の理解が深まる記事になると嬉しいです。
“情報の分断”をAIでつなぎ直す、マネジメント支援プロダクト
──まず、Hugmusとはどのようなプロダクトでしょうか?
Hugmusは、SMBに特化したAIマネジメント支援プロダクトです。
私たちグロースピリットは、「ビジネスを愉しめる社会を創造する」というビジョンのもと、HR×DX×教育の3領域で事業を展開してきました。
その中で、最も多く寄せられる相談は「人」に関するものでした。
どのようにコアメンバーを育成するか、幹部候補をどのように成長させていくか──。
こうした“人と組織の育成”に関する悩みは、経営層・マネージャー層を問わず、あらゆる企業で共通しています。
さらに深掘りしていくと、その根本には「マネジメント」の課題があるケースがほとんどでした。
そしてそれは、マネージャーや管理職の能力やスキルよりも、構造的な仕組みの問題で生じているケースが多々ありました。
一時的な研修や部分的なツール導入では、持続的な解決につながりにくい。この点には強い課題意識を持っていました。
これまでは、私たち自身が組織に入り込み、経営陣やマネージャー層と対話を重ねながら、いわば“人の力”で課題解決を支援してきました。
その取り組みを継続する一方で、テクノロジーの力を掛け合わせることで、より多くの企業に価値を届けられないか──。
この問いが、Hugmus開発の出発点です。
- 上司は個人の売上も求められ、十分にマネジメントに割ける時間がない。
- メンバーは十分なフィードバックを受けられず、成長しない。
- 人事は現場の実態を把握できず、正しい課題や打ち手が分からない。
- 経営は組織の温度感をつかめず、気づけば離職が発生している。
多くの企業が、こうした“情報の分断”に悩んでいます。
Hugmusは、この分断をAIの力でつなぎ直し、マネジメントの在り方をアップデートしていくことを目的としています。

Hugmusのイメージカラー・プロダクトロゴ。開発チームメンバーで総選挙を行い、デザイナーが作成した200案から自分たちで選出。
構想の始まりは日報──。日報、見れてますか?
──Hugmus誕生のきっかけを教えてください。
きっかけは、「日報」に対する社員それぞれの共通する原体験でした。
多くの方が、これまでに一度は日報を書いた経験があると思います。
メンバーの立場では、「この日報、ちゃんと見てもらえているのかな?」と感じたことはないでしょうか。一方で、マネジメントの立場に立てば、「忙しくてすべての日報を見切れていない」と感じたこともあるはずです。
情報はあるのに、活かしきれない。
この構造は多くの企業に共通しており、マネジメントが課題として挙がる一方で、現場からの日報や日々の情報は十分に育成に機能していない現状があります。
「この形骸化しやすい日報文化から、何か新しい打ち手を生み出せないか」
そんな問いから、Hugmusの構想が始まりました。
そこから、さまざまな要素を掛け合わせながら、従業員の“発信”と“行動”の情報をAIが正しく見える化し、従業員・管理職・人事・経営──それぞれのマネジメント課題にワンストップでアプローチできる仕組みを形にしました。
人がパフォーマンスを最大限に発揮できるかどうかは、マネジメントの質に大きく左右されます。
Hugmusを通して、AIの力でマネジメントを支援し、「ビジネスを愉しめる人が多い組織」をつくる支援がしたいと考えています。
「育む」×「増す」──Hugmusという名前に込めた想い
──Hugmusという名前には、どんな意味があるのでしょうか?
CEOの野脇が考えた名前です。
「育む(はぐくむ)」と「増す(ます)」を掛け合わせています。
人と組織の可能性を“育て”、成果や成長を“増やしていく”──そんな意味を込めました。
HugmusはAIによって人を評価・管理するのではなく、AIと人が協働することで組織運営やマネジメントをサポートする「手法」です。
AIの力でマネジメント業務の代替できる部分を担いつつ、情報を見える化することで、「育む」機会を「増や」し続けるプロダクトを目指しています。

サービス名は開発チームで意見を出し合いながら決定。COO安永は「ホジョリン」というセンスを疑う名前を最後まで提案していたとのこと。
全員兼務の「超アジャイル開発チーム」───それが愉しい。
──現状の開発体制を教えて下さい。
現在の開発チームは、ビジネスサイド2名(CEOとCOO)とエンジニア2名の、計4名体制です。
全員が他業務を兼任しながらも、技術選定から要件定義、設計、開発、テスト、プロダクト名、ロゴ、カラー、サービス資料、LP、プロダクト動画、ノベルティ、マーケティング施策、展示会ブース装飾まで──すべて自分たちの手で決めて、実行しています。
特徴的なのは、トップダウンではなく**「Co-creation(共創)」**のスタイルで進めていることです。
グロースピリットでは、肩書や役職は一切関係ありません。
CEOやCOOの意見にも遠慮せず、「こっちの方が良いと思います!」と率直に意見を交わす文化があり、私たち経営陣もそれを大歓迎しています。
全員がオーナーシップを持ち、議論を重ねながらプロダクトをつくり上げていく。
この“共創のカルチャー”こそが、グロースピリットの大きな強みだと思います。
もちろん、メンバーの多くはプロダクト開発以外にも多様な業務を担っており、決して楽な環境ではありません。
それでも、自分たちの想いが“自分たちのブランド”として形になっていく過程は、何にも代えがたいほど愉しいと感じています。
──Hugmusの技術スタックや開発スタイルを教えて下さい。
開発面では、技術スタックにフロントエンドはReactとTypeScript、バックエンドはGo、インフラはAWSを採用しています。
基本的に技術選定はエンジニアに一任しています。
PdMを担っているエンジニアが、技術選定を行う際の判断基準は主に3つありました。
1つ目は、スピード感を持って開発を進められること。
短期間でのプロトタイプ構築とリリースを見据えていたため、エンジニアがこれまでの経験を最大限に活かせる技術を選ぶことを重視しました。
2つ目は、モダンな技術を取り入れ、長期的なリプレイスコストを抑えられること。
プロダクトを継続的に成長させるためには、開発スピードだけでなく、将来のメンテナンス性や拡張性も重要な要素です。
そして3つ目は、チーム全体の成長につながる技術であること。
プロダクト開発を通じてエンジニア自身が新しい技術を学び、スキルを高められる技術や最新環境であることを大切にしました。
これらの観点から、過去の経験を活かしながらも未経験の技術を適切に取り入れることで、“実現可能性”と“成長機会”の両立を図る技術選定に至りました。
加えて、エンジニアは技術的な実現可能性だけでなく、ビジネス視点を持ってプロダクト開発に取り組んでいます。そのためユーザー目線のUI/UXはもちろん、必要な機能要件をエンジニアが積極的に提案していく文化もグロースピリットの強みの一つです。
人数が限られている分、スピード感を持った開発を意識しており、AI活用も積極的に進めています。
「AI予算」を設けて、エンジニア自身が開発効率を高めるツールを選定・導入できる仕組みを整えています。
計画を丁寧に定めて順序だてて行うウォーターフォールとは対極にある、完全なアジャイル体制のもと、現在はβ版リリースに向けて開発を進めている段階です。
経験ゼロからの0→1開発──「今はできなくても、やればできるようになる」
──初の自社プロダクトということで、開発に苦労はありましたか?
もちろんありました。
グロースピリットとしても、0→1のプロダクト開発は初めて。
チーム内にも構想からプロダクトを作り上げたという経験者はいませんでした。
だからこそ、知恵を振り絞り、社内外の知見を借りながら進めました。
「今はできなくても、経験して、できるようになればいい」というマインドが全員にある。
この“できることを増やしてやりたいことを叶えていくスタンス”が、グロースピリットらしさだと思っています。
──スピード感を持って開発を進められているポイントはありますか?
前提としては、エンジニア陣が非常に優秀で、常に先回りした動きができていることが一番大きなポイントです。
そういった意味で言うと、グロースピリットのエンジニアは開発力や技術力だけでなく、プロダクト全体を俯瞰して立ち回る経験が身に付くと思います。
加えて、開発速度を後押ししているのは、「展示会出展を先に決めたこと」です。
半年後の展示会に出すと決め、出展費用を支払い、逃げ道をなくしました(笑)。
「そこまでに絶対に形にする」という意思決定が、チーム全体を動かす原動力になりました。
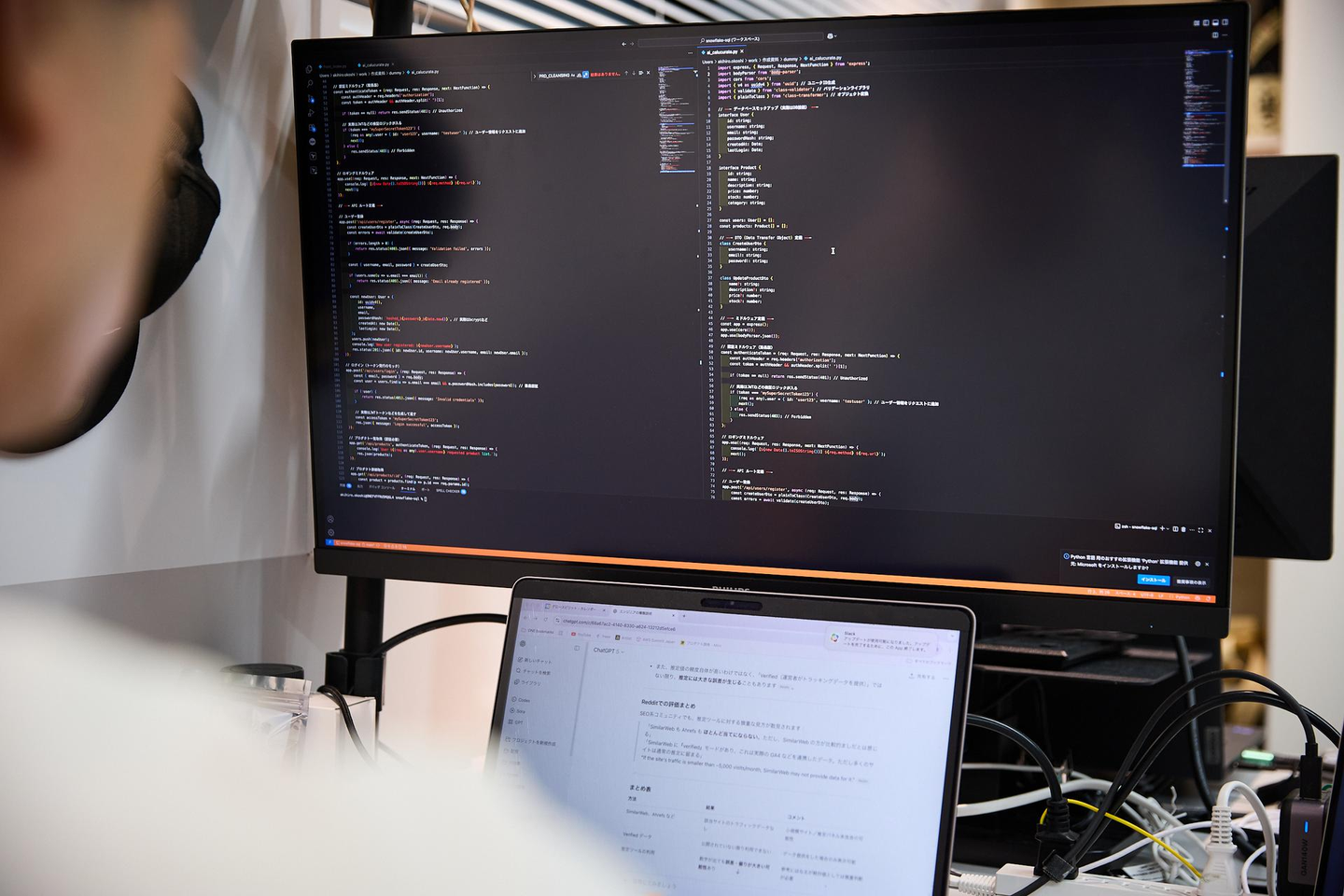
チームを支えるのは、フラットで誠実な文化
──開発チームの雰囲気はどのようなものですか?
とてもフラットです。
会議でも誰かが一方的に話すことはなく、全員が意見を出し合います。
冗談を交えつつも、議論は本質的です。
特に特徴的なのは、ビジネスサイドとエンジニアの関係性が非常に良いこと。
お互いを尊重し、役割を理解し合いながら動けています。
この「Co-creation(共創)」の文化が根付いているのは、創業初期からの大きな特徴です。
チームでやっているからこそ、時に頼り、時に任される。
そんな関係性の中で、全員が“ビジネスを愉しむ”ことを体現しています。
Hugmusが目指すのは、管理職の「負」を減らす世界
──Hugmusが描く未来像を教えてください。
Hugmusが広がることで、まずは管理職の負が軽くなると考えています。
AIがケアすべき部下や称賛すべきメンバーをリアルタイムで検知し、
「誰にどう関わるべきか」を提案することで、限られた時間をより有効に使えるようになる。
結果として、メンバーへのフィードバックやフォローが自然に増え、チームの関係性やモチベーションが向上していく。そんなポジティブな循環を生み出したいと思っています。
また、グロースピリットではプロダクト開発において、コンパウンド戦略を検討しています。現在は「Hugmus」の開発をまずは進めていますが、リリース後にはシナジーを創出する領域で、同時多発的に複数プロダクトの立ち上げをしていきたいと考えています。
いずれにしても、私たちのVision、Missionの実現に繋がるプロダクト戦略を描き続けていきます。
「誠実さ」と「柔軟さ」が、グロースピリットで働く人の共通項
──新たなプロダクト開発に挑戦しているグロースピリットですが、どんな人と働きたいと感じますか?
誠実な人ですね。
これは全ての職種に共通して大切にしている価値観です。
スペシャリストでもジェネラリストでも構いません。
ただし、社内外問わず、人に誠実であること、相手を尊重できること。
これがないと、グロースピリットのカルチャーには合わないと思います。
また、プロダクトに対する執着よりも、「ビジョン実現のために今できることをやる」姿勢を大切にしてほしいです。
Hugmusだけでなく、次のプロダクトも控えています。
その都度フェーズは変わるので、柔軟に楽しめる人と一緒に働きたいですね。
構想で終わらせず、実行で示し続ける
──最後に、この記事を読んでいる方へメッセージをお願いします。
Hugmusの開発をはじめ、まだグロースピリットは途中段階です。
だからこそ、**“未完成を愉しめる人”**にとっては最高のフェーズだと思います。
一般的にはスケールを目指すSaaSプロダクトや自社プロダクトを開発している企業は、VCや投資家からの大型の外部資本を入れている一方、現在グロースピリットは100%自社株保有で経営しています。
そのため、最短で自分たちが実現したいVisionに向けて、挑戦していくことができます。
構想を語るだけでなく、自ら投資し、行動し、形にし、Visionの実現を目指す。
それが、グロースピリットの在り方です。
挑戦はこれからが本番です。
この“リアルな成長フェーズ”を共に走り抜けてくれる仲間と出会えることを、心から楽しみにしています。








