皆さんは...「建築設計=デザインを考える仕事」だと思っていませんか?
医薬品や化学製品などをつくる“プラント”の設計では、実はデザイン以上に大切なことがあります。
たとえば、大型の設備や機器との取り合い、安全な動線設計、法規との整合性……
見えないところで、人の命や社会のインフラを支える“裏方の設計力”が求められるのです。
テックプロジェクトサービス(TPS)の建築設計チームは、そうした視点を持って医薬・化学・エネルギー分野の最前線で活躍しています。
今回の記事では、キャリア入社のTさん・新卒入社のHさんという2名の建築設計者にインタビュー。
それぞれの視点から「TPSの建築設計とは?」「どんな魅力があるのか?」を語ってもらいました。
——Tさん(2024年 キャリア入社)

これまで、医薬・化学メーカーなどの研究開発センターの設計を多く手がける設計事務所に勤務。実験室のスケールから、いわゆる”キロラボ”と呼ばれるスケールまで様々な研究所を設計してきました。
「いわゆる“プラント”とは少し違っていて、スケールとしてはもう少し小さく、意匠的な工夫やユーザー目線での配慮が求められる案件が多かったですね。設計者として、とてもやりがいのある仕事でした」
そんな中で出会ったのが、テックプロジェクトサービス(TPS)という新たな環境。入社の背景には、建築設計という仕事への確かな手応えと、TPSのビジョンへの共感がありました。
「建物って、単なる“箱”ではなく、そこで働く人の安全や効率、そして事業の成長を支えるものだと思っています。前職で医薬系のお客様と関わる中で、そうした“建物の力”を強く実感しました。TPSが医薬分野を柱の一つに据え、今後さらに建築設計に力を入れていきたいと聞いたとき、自分の経験を活かせる場所かもしれないと感じました」
——Hさん(2022年 新卒入社)

東京都市大学の建築学科で学ぶ中で、特に興味を持っていたのは設備設計。
大学4年生のときには、小学校の教室を対象にしたCO2濃度や室温の計測・分析に取り組み、熱中症リスクや快適性に関する研究を行っていました。
「どの時間帯にCO2濃度が高くなるのか、気温とどう関係しているのか――。たとえば、私が調査した実例の一つに、北海道の小学校があります。涼しい地域というイメージから空調機の設置率が低く、結果的に熱中症の発生率が高くなっているケースがありました。
医薬建屋では、売上げに直結する生産設備を主役として設計を行うため、事務室や休憩室などの人が主役になる部屋は最低限の作業環境となる事例が多い。そういった部屋にも着目し、快適な作業環境を提案したい。自分がその橋渡し役になれたらと思っていました。」
就職活動では設備設計を行うサブコンを中心に探すなかで、医薬分野に強みを持つTPSと出会います。
「医薬品製造って、清浄度が求められるクリーンルームが多いため設備設計がすごく大事なんです。TPSの話を聞いたとき、これは自分の興味を活かせる分野だと直感しました。いまは意匠設計が中心ですが、ゆくゆくは建物全体の性能設計や環境配慮といった視点も組み合わせて、価値のある建築を提案していきたいと思いTPSへ入社を決めました」
設備・法規・動線…「見えないものを設計する」建築設計の奥深さ
「建築設計」と聞いて、どんな仕事を思い浮かべますか?
住宅やオフィスビルの“デザイン”を考える仕事――そんなイメージを持っている方も多いかもしれません。
でも、TPSの設計チームが向き合っているのは、『プラントや医薬品製造施設』。
ちょっと特殊で、ちょっと面白い“建築設計”の世界なんです。
「建築設計=デザイン」だけじゃない――。

これはTPSに入社してから、Tさんがより強く実感したことのひとつです。
プラントや医薬品の製造施設では、建物の中に大型のタンクや設備、配管が所狭しと配置されます。
建築設計者がまず取り組むのは、それら設備機器の配置や動線に合わせた“建物としての最適なカタチ”をプランに落とし込むこと。
また、医薬施設では封じ込め設計(Containment)やゾーニングなど、 「人が安全に作業できる環境」「交差汚染の防止」といった視点も欠かせません。
「医薬ファイン(医薬中間体など)の設計では、危険物を扱う場合もあるので、“外に漏らさない・人に触れさせない”設計が求められます。そういった視点から空調や動線、部屋の構成を考えていくのも私たち建築設計の役割です」
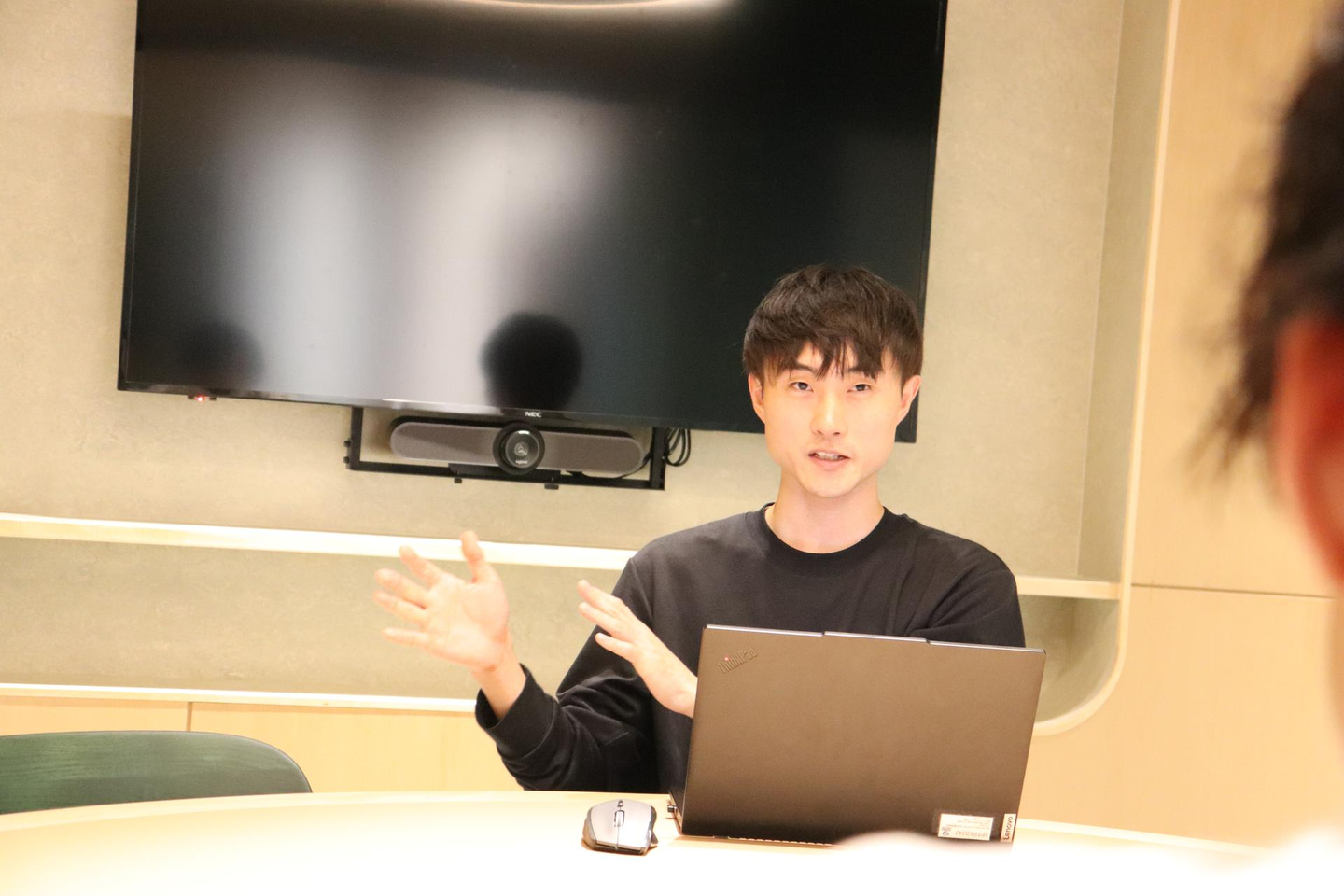
さらにHさんは、建築設計者の役割は、プランをつくるだけではないといいます。
建築基準法や各種法令を踏まえた確認申請業務も重要な仕事のひとつです。
「ときにはお客様から『ここをこうしたい』というご要望があるのですが、 法的に難しいケースもあります。そういうときに建築側の視点から“これはNG”と伝えられるのも、私たちの大事な役目です」
他部門と築く“最適な器”
「TPSの建築設計の特徴は、他部門との連携の多さにもあります。」と話すHさん。

たとえば、営業が持ち帰った要求条件をもとに、設備や配管、機器設計の担当者たちと“どんな建物がベストか”を一緒に組み立てていく。
「医薬施設では“どういうモノをどういう手順でつくるか”が出発点です。私たちはそこから逆算して、必要な部屋の機能やサイズ、動線を考えるんです。この時、他の設計部門や営業・プロジェクト側と丁寧に“すり合わせ”をしながら全体の方向性を揃えていくことが、プロジェクト成功のカギになります。そして、それが“法規的に建築できるか”・“コストパフォーマンスの高い最適な設計か”を建築側が担保していくイメージですね」
一般的な建築設計の仕事では、建築(=意匠)が中心になることが多いですが、 TPSでは「機器・設備ありきの設計」――いわゆるインサイドアウト設計が基本ですとTさんは話します。
「オフィスビルや商業施設のような“外から内をつくる”のではなく、 “内(=製造設備)を基準に外をつくる”のがTPSの設計です。 建物の主役は“モノをつくる設備”で、私たちはそれを支える器を設計しているイメージですね」
とはいえ、建築士の資格が必要な規模の建築物が多く、 全体計画・法的整合性・品質やコストを含めた最適化といった観点から、建築設計者が担う責任も大きい仕事です。
図面の中に人の動きや製造の流れまで描き出す――そんな設計の仕事に興味がある人には、ぴったりの環境です。
一つひとつの設計が、医薬やエネルギーの未来を支える
キャリア採用で入社したTさんは、こう語ります。

「社会人として年齢を重ねる中で、“自分がやりたいこと”だけでなく、その仕事がどれだけ社会に貢献しているか――そんな視点が私にとってますます大切なものになっていきました。
最終的にTPSに入社を決めたのも、この考えがあったからです。
建築設計といっても、担当するのはプラントの中のほんの一部、たとえば電気室だけということもあります。一見すると小さな設計かもしれませんが、その一つひとつが、社会の安心や安全、暮らしの基盤を支えるための大切なパーツになっています。
私たちが関わった施設から出荷されたものが、最終的に人々の暮らしを支えたり、命を守っていく。
そんなふうに“世の中に役立つ何か”を支えている実感が持てるのが、TPSの設計の魅力だと思っています。」

/assets/images/21523423/original/f378d9a8-2a0c-4a6c-80c4-064a50969fce?1751855078)

/assets/images/21172619/original/2705f398-a11f-47f3-b20e-9e8824bb3083?1747889336)

/assets/images/21180761/original/2705f398-a11f-47f3-b20e-9e8824bb3083?1747964211)

