キャリアパス(昇格・マネジメント/スペシャリストルートの有無)
「この先、どう成長していくか」を、自分で描ける場所。
PMとしてプロジェクト全体を動かしたい。
エンジニアとして技術を突き詰め、深く価値を届けたい。
──その意志を、役職や年次に関係なく尊重し、任せていくのが私たちのスタイルです。
①「どう成長したいか」から逆算するキャリア設計
私たちは、役職やキャリアパスを一方的に押しつけることはありません。
・PMを目指すなら、どの力をどう伸ばしていくか。
・技術を極めたいなら、どんな責任と裁量を担うべきか。
──キャリアの出発点は、あくまで「個人の意志」と「なりたい姿」です。
たとえば、当社には20代後半で複数案件を率いるPMもいれば、アーキテクチャ設計から実装まで、技術でチームを牽引するテックリードもいます。
どちらが上かではなく、互いの専門性とスタイルを尊重し、対等な立場で信頼し合えるカルチャーが根付いています。
② PMにも、テックリードにも「果たすべき役割」がある
私たちは、プロジェクトの成功とは
「進行管理がうまくいくこと」だけを指すものではないと考えています。
PMは、クライアントやチームの意図を的確に汲み取り、全体を正しい方向へと導く存在。
テックリードは構想を技術で形にする中核として、開発の質を担保し実装を導く存在。
異なる役割、異なる視点。
しかし、どちらもプロジェクトの根幹を支える“不可欠なピース”です。
私たちは、誰かが誰かを管理する関係ではなく、それぞれが専門性を発揮し、共に目的地を目指すチームであることを重視しています。
役割の違いは、上下の違いではない。
当社では、PMもテックリードも、
プロジェクトの中核を担う対等なコアメンバーとして位置づけています。
この2つは、まったく異なる軸でありながら、
いずれもプロジェクトを前進させる“意思決定者”であることに変わりはありません。
──それが、私たちのキャリア観です。
③ チャンスは手を挙げた人のもとへ
私たちは、経験年数や年齢に関係なく、「この案件を任せてみたい」と思える人にチャンスを託します。
過去には、入社1年目でPL補佐に入り、クライアントの窓口を担うポジションを任されたケースもあります。
ただし、それは勢いで投げるものではなく、小さく試しながら、着実にステップを踏む設計になっています。
要件定義の一部を担当する、仕様検討に同席する──そんな“小さなリーダーシップ”の積み重ねから、自然と次のステージが開けていくのです。
④ 誰もが、経営陣とキャリアを話す組織
評価面談では、代表や取締役と1on1で今後のキャリアについて話す場を設けています。
評価を一方的に伝える場ではなく、
「3年後、どんな立場で何をしていたいか」まで一緒に描くための対話です。
目先の昇格・昇給だけでなく、長期でキャリアの軸を築きたい人にこそ、対話を重ねながら伴走するカルチャーが合うはずです。
⑤「どれだけの価値を届け、どれだけの対価を得るか」という視点を持つ
キャリアが進むにつれて、私たちは「スキル」だけでなく「付加価値」を問うようになります。
クライアントに何をもたらしたのか。
その成果に、どれだけの価値を感じてもらえたのか。
──それが、プロとしての存在意義であり、対価としてのフィーに直結するものだと考えています。
同時に、“時間単価”というコスト感覚も重要な視点です。
いま自分が行っている作業に、どれほどの期待値が込められているか。
その期待に応えるためには、どのくらいの時間を使うべきか。
この意識を持てるかどうかで、プロジェクト全体の価値設計や立ち回りは大きく変わります。
これは、マネージャーであれ、テックリードであれ、キャリアの方向性に関係なく共通する“プロフェッショナルとしての土台”す。
私たちが一時請けとして、付加価値の高い提案と実装を両立できているのは、こうした価値観を共有している組織だからこそだと自負しています。
最後に、キャリア形成は、
肩書きより、「何を担い、どう価値を出すか」が重要
自分の意志で選び、自分の頭で考え、自分の力でチームに貢献する。
その一つひとつの積み重ねが、キャリアになっていく。
だから私たちは、役職より役割、序列より信頼、年次より中身を大事にしています。

/assets/images/6617051/original/2ef1fd63-99f4-4325-a7e1-57a817f7d3dd?1619410507)
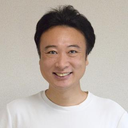
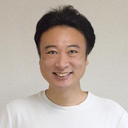
/assets/images/6617051/original/2ef1fd63-99f4-4325-a7e1-57a817f7d3dd?1619410507)
/assets/images/21633115/original/2ef1fd63-99f4-4325-a7e1-57a817f7d3dd?1752826773)

