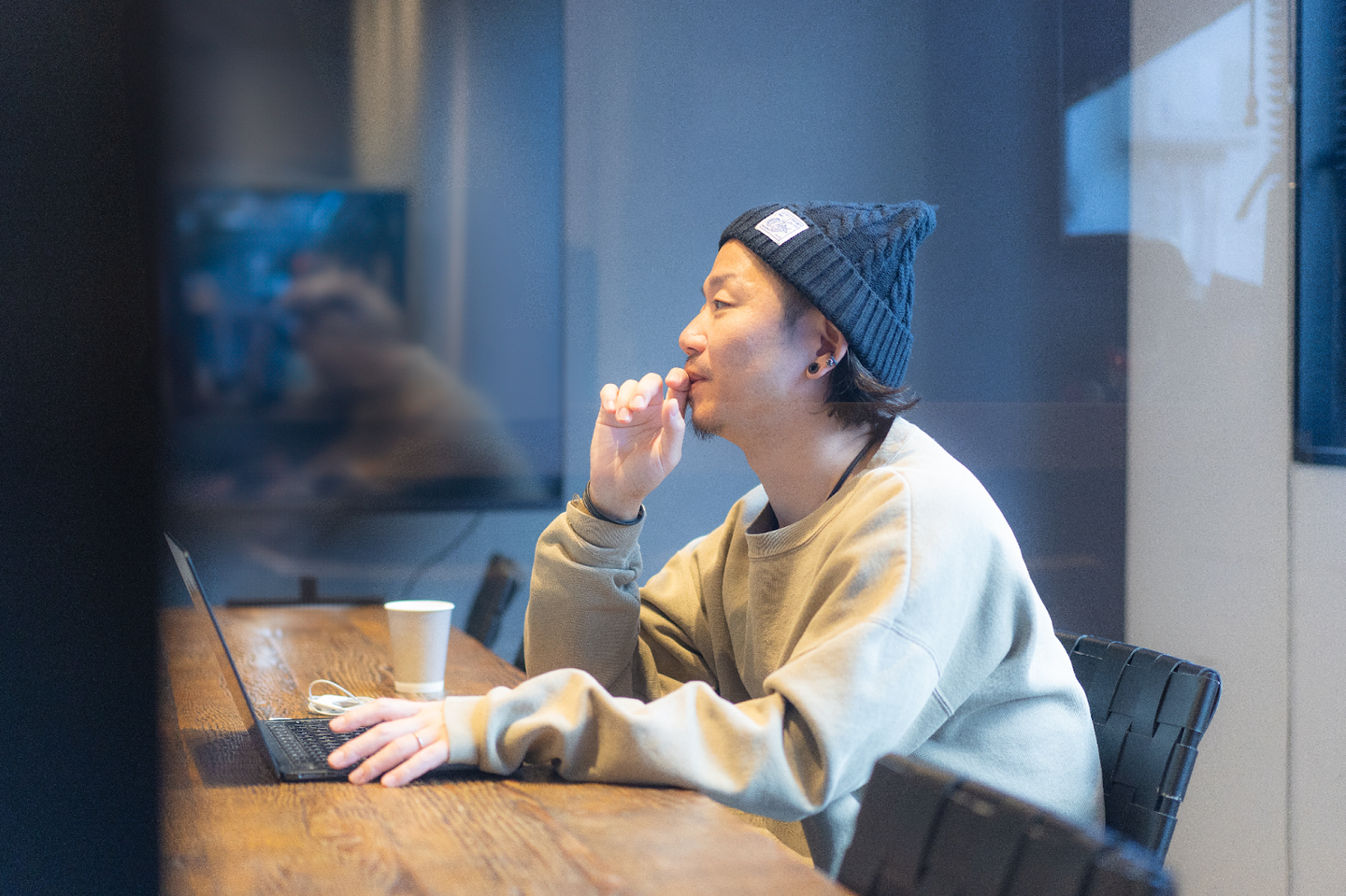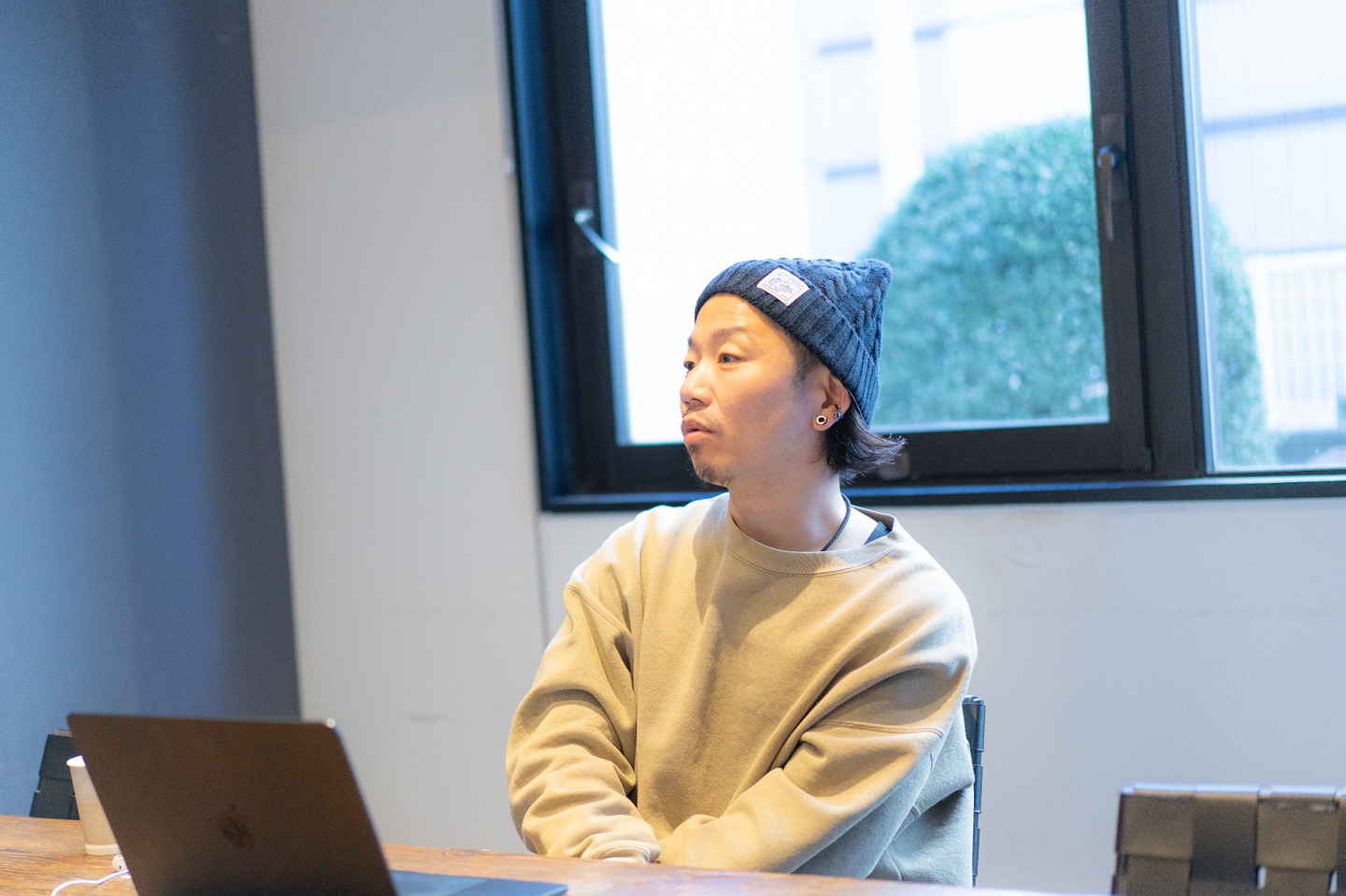【前編】黎明期を支えてきた開発組織の最古参が語るVS成長の原点 | 社員インタビュー(Dev)
主力事業である「STAFF START」を軸に着実な成長を歩んでいるバニッシュ・スタンダード(以下、VS)。事業の成長に合わせて、開発チームの強化にも力を入れています。今回は「STAFF STA...
https://www.wantedly.com/companies/v-standard/post_articles/944526
主力事業である「STAFF START」を軸に着実な成長を続ける株式会社バニッシュ・スタンダード(以下、VS)。事業の成長に伴い、開発チームの強化にも注力しています。
前編に引き続き、「STAFF START」の開発を支えるDevユニットのマネージャー植村哲朗(以下、てつお)に、開発組織の変化と今後の展望についてお話を伺いました。
植村 哲朗(うえむら てつお)
2017年12月入社以降、プログラマおよびディレクションを担当。システム導入・運用・保守業務の傍ら開発チームのスクラムマスターも兼務し、2024年春よりDevユニットのマネージャーに着任。
(聞き手:Corporate Design・大熊 彩乃)
ーー社員数も増え、今の原宿オフィスにお引越しをされたわけですね。西麻布オフィス時代に”開発チーム”の土台ができあがったとのことですが、新しいオフィスに移ってからの変化にはどのようなものがありましたか?
てつお: 一番大きな変化は、なんといっても先代マネージャーのジョインですね。昨年の夏に惜しまれながらも卒業してしまいましたが、開発組織としての基礎を整え、今のDevユニットまで連なる方向性を作ってくれた人でした。アジャイルコーチに入ってもらったり、技術的なところにしっかり投資をしたり、スクラム開発導入に向けて動き出したのもこの時期です。
ここから本格的な”開発組織”への道がスタートし、エンジニアが役割ごとにチーム分けされるようになりました。メンバーが増え、情報共有すべき範囲が大きくなったことで、ドキュメントの重要性も高まってきました。「誰が見ても分かり易いように情報を整理・蓄積していこう」という意識が根付き始めたのも一つの変化だったと思います。
ーーここ数年でスクラム開発が導入されてきたんですね。開発組織のなかでのてつおさんの立ち位置はどのように変化しましたか?
てつお:エンジニアだけでなく、CSのメンバーも増えてきたので自分がお客様先に同行することは減ってきましたね。会社として大きくなったことはすごく喜ばしいと思う反面、個人的にはお客様の声を直接聞きに行く機会が少なくなってしまって、少し寂しいな、という気持ちもありました。
ーーてつおさんは直近スクラムマスターも担当されていましたよね。何かスクラムマスターをやり始めるきっかけなどがあったのでしょうか?
てつお:2022年頃からスクラムマスターを担当するようになりました。タイミング的には、原宿オフィスに移転してから1年くらいだったかな。アジャイルコーチに入ってもらってスクラム開発をやっていこう、となったところで先代マネージャーから打診がありました。
僕は開発組織の中でも導入〜運用領域がメインだったこともあって、今までとは全く別の動き方をすることになりました。スクラムマスターを担当させてもらうことでプロダクトの開発に貢献できるようになったことが素直に嬉しかったです。
また、よくよく考えてみれば、今までの自分の仕事の特性としても、エンジニアやCSのメンバー、外部のステークホルダーなど広い範囲の方々とやり取りをする役割を担っていたので、スペシャリストというよりはジェネラリスト的な動きが求められる、という点においてはスクラムマスターも同様だったのかもしれない、とも思います。
ーーVSの黎明期からSTAFF STARTの導入〜運用を担当し、2022年からはスクラムマスターとして開発を牽引。そして、2024年4月にユニットマネージャーに就任!ということでご自身の立場も大きな変化がありましたよね。
てつお:正直めちゃくちゃびっくりしました。本当にサプライズ人事だったので(笑)。
マネージャー就任が発表されてからはもう目まぐるしくて、細かいところなど全然覚えていないのですが、とにかく頭を整理することでいっぱいいっぱいでした。先代マネージャーとは週に何回も1on1を組んでもらいながらレクチャーと引き継ぎを受けました。先代マネージャーを独り占めして、たくさん贅沢をさせてもらいました(笑)。
それまで僕はマネージャーとしての経験がなかったこともあり、マネジメントの型もまったくない状態でした。そのため、まずは先代マネージャーと同じやり方を実践してみて、そこで感じた違和感・不具合をもとに調整し、「自分なりのマネジメントの型」をつくっていこうと考えたんです。マネージャーに就任してから1年が経ち、マネージャーとして1回目のサイクルがようやく一巡した状況です。現在はこの1年で感じた課題感をもとに調整やチューニングをしているような状態です。
最近は、社外の事例や取り組みなどをキャッチアップするために、他社さんのEM(エンジニアリングマネージャー)がどんな悩みをもって、どんな取り組みをしているのかを勉強したいと思うようになりました。自主的に外部コミュニティーに参加するなどして、キャッチアップの機会を設けるようにしています。
ーーてつおさんが率いるDevユニットについてもっと解像度を上げていきたいと思うのですが、現在のチームの規模や構成、役割など改めて教えてください。
てつお:Devユニット全体の構成人数としては15名ほど(うち正社員10名)ですね。「STAFF START」と昨年ローンチしたばかりの「FANBASSADOR」、それぞれのプロダクトごとのサービス開発を担うチームが1つずつ、そして各チームを状況にあわせて横断的に行き来するネイティブアプリチームの計3チームという構成になっています。
ーー普段の開発で利用している技術スタックなどはいかがででしょうか?
てつお:バックエンドに関してはGoを、フロントエンドに関してはReactを使って開発をしています。以前はRubyなどを使っていたんですが、先代マネージャー時代に開発生産性とサービスのパフォーマンスの向上を目的にリプレイスを進め始めました。サービスのコア部分はリプレイスが終わり、新規機能はすべてGo、Reactで開発できる状況になっています。
ーーありがとうございます!リプレイスのお話などは、まさに直近フロントエンドで活躍している長谷川さんが現場で抱えている課題としてもインタビューで語られていましたよね!
ーーてつおさんがDevユニットのマネージャーに就任してから約1年が経ちましたが、技術負債の問題以外の現場の課題などはいかがでしょうか?
てつお:Devユニットは、(1)サービスの新規開発と(2)プロダクト改善という2つのミッションを担っています。個人的には、この2つのミッションをバランスよく推進していける組織にしていきたいと考えているんですが、現在はサービスの新規開発に注力するあまりプロダクト改善に向けた動きが後手に回ってしまいがちなところに課題を感じています。
Devが目指すべき形はどのようなものか。社内でも組織のあり方など様々な議論を重ねてきました。「お客様にとって価値のあるサービスを提供する」という本質的なゴールを達成するために、今まで安定的に行うことができていなかった「プロダクト改善」の重要性が社内でも見直され始めており、今後はより注力していきたいと考えています。
組織・開発の課題について、より具体的で生々しいお話しについてはカジュアル面談で赤裸々にお話しさせていただいているので、興味のある方はぜひ面談の際につっこんで聞いていただければと思います!
また、もう一つの課題としては「プロジェクトをリードするメンバーをもっと増やしていかなければいけない」ということが挙げられます。これは採用を強化する、という形ももちろんですが今、一緒に頑張ってくれているメンバーが成長できる環境をつくり、サポートしていきたいと考えています。
ーーより強い開発組織を目指していくために短期施策と中長期施策、それぞれを考えているんですね。
ーー短期施策としては採用の強化を考えているとのことですが、どのような経験をもった方に入社していただきたいと考えていますか?
てつお:チームをリードされてきたご経験と技術選定のご経験が大きなポイントになると思っています。というのも、今後は「STAFF START」と「FANBASSADOR」という2つのプロダクトごとに新規開発とプロダクト改善を高い水準で進めていかなければなりません。技術的なリードやプロジェクトを推進できるメンバーが複数名必要になってくるため、こうした経験をお持ちの方がいてくださると非常に心強いです。
ーーこれから先、事業の発展にともなって開発組織の構成なども変わってくるかと思います。今後、新規でジョインしてくれるメンバーにはどのような経験を提供できると思いますか?
てつお:そうですね、今のチームの形は最小構成だと僕も思っています。今は各プロダクトでも、チーム単位で動いていますが、将来的にはユニット(部)単位になったり、事業部単位になったりする可能性もあります。
組織が大きくなり、細分化するに伴ってリーダーやマネージャーが複数必要になると思っていますので、新しくジョインしてくれる方々には、まずチームメンバーもしくはリーダーとしてジョインしていただきつつ、プロダクト開発をリードしていただきたいと考えています。
個人的に、VSのエンジニアとして働く上で最も魅力的な経験として「ユーザーの生の声が聞ける環境で開発を進められること」が挙げられると思います。不定期ですが、「STAFF START」を使っていただいているEC担当者や店舗スタッフをお招きしたインタビュー会を開催することもあるんですよ。
実際に現場でどう使われているか、どういった部分に困りごとがあるか、など、自分たちが作っているプロダクトに対するフィードバックを直接いただけることでモチベーションも上がりますし、こうした取り組みは、どの企業でも当たり前にできることではないと思います。
また、プロダクトへの直接的なフィードバックという意味合いとは異なりますが、VSが全国の店舗スタッフが接客の技術を競い合う「STAFF OF THE YEAR」というイベントを開催していることも大きなモチベーションになっています。
「STAFF START」をきっかけに店舗スタッフの方の人生が大きく変わっていく姿を現場で見ると毎回、本当に感動します!「誰のためにプロダクトをつくるのか」を意識しながら開発できるので、プロダクト志向の強い方にとって魅力的な環境を提供できると思います。
今のVSは、「STAFF START」という一定安定した売上をあげているサービスを磨くことも、「FANBASSADOR」という新しいプロダクトづくりを経験することも可能な面白いフェーズです。成熟期と開発/導入期という異なるフェーズのプロダクトがあるので、開発状況にもよりますが、エンジニアとして挑戦したいフィールドを選択してもらえる余地があるのは、現在のVSならではだと思います。
ーー最後に、これから一緒に働くかもしれない世の中のエンジニアさんに向けてメッセージをお願いします!
てつお:エンジニアとして働いていると、技術的にも組織的にも様々な課題に直面することがあると思います。その場で声をあげて解決ができればベストですが、置かれている環境やタイミングなどで思うようにできないこともあると思います。環境を変えてエンジニアとして更なる挑戦をしたい、と考えたことのある方は、ぜひVSでトライしていただきたいです!
今でこそ「いわゆる開発組織」らしくなってきましたが、まだまだ出来ていないことや、やりたいことがたくさんあります。レガシーなコードがまだ生き残っていたりしますし、「なんでこれができてないんだ!?」というようなカオスさがまだまだ残っていたりします。会社としても、まだまだスタートアップということもあり、常に変化があり、そこに順応すること、サバイブしていくことが求められるのは一定大変かもしれません。
ですが、変化に寛容なフェーズだからこそ、声をあげて周りを巻き込んで動いていければ結果もついてくる、という環境でもあります。Devユニットとしても挑戦を歓迎し応援するカルチャーがあるので、自ら課題を見つけ能動的に動ける人は活躍いただけると思います。そして、最も大切にしたいと思う価値観は「フォロワーシップ」です。自分が挑戦するだけでなく、同時に仲間の挑戦も応援できるような方と一緒に働きたいと考えています!
カジュアル面談では、事業フェーズや今回お話ししきれなかったことなどもフランクにお話しさせていただきます。もちろん、僕たちのお話だけでなく「次の転職先で何をしたいのか」「どんな環境を求めているのか」といったWill(志向)についてのお話も積極的にお伺いしていますので、遠慮なくどんどんお話ししてください!ご自身のWillを叶えられる場所かどうか、VSでどんな経験や環境を提供できるか、一緒にすり合わせていきましょう!
ーー今日は本当にありがとうございました!