思想は、実装されて初めて血肉となる。──CEOの「想い」とCTOの「再現性」が交差する、プロダクト組織の現在地【プロダクト開発の現場から vol.1】
「人と組織で勝ち続けていく」
その理想を掲げる会社が、皮肉にも組織成長の壁に直面する──。
スタメンが直面した開発組織のスケーラビリティの課題。その大きな課題にCEO大西と、CTO野口は、いかにして向き合っているのか。
プロダクト組織へのインタビュー企画、第一弾です。
今回は、理想の体現を目指すスタメンが、TUNAG(ツナグ)というプロダクトで直面する、現在進行形のリアルな挑戦の過程を、CEO・CTOにインタビューしました。
写真左:執行役員CTO 野口 卓也|写真右:代表取締役CEO 大西 泰平
大西 泰平 | 代表取締役CEO 2016年に株式会社スタメンを共同創業。2020年の東証グロース市場への上場を経て、2023年より現職に就任。現在はプロダクト開発にも深く関わりながら、次の目標として売上100億円突破を掲げ、事業を力強く牽引。
野口 卓也 | 執行役員CTO 国内外の企業でエンジニアリングとマネジメントの要職を経験後、2023年にスタメンへ参画。前任CTOからの誘いを受け、エグゼクティブ採用としてジョイン。入社後は、技術的負債の解消と組織のスケーラビリティ向上をミッションに、開発組織全体の設計を担う。
成長の壁と、二人の出会い
ー本日はよろしくお願いします!早速ですが、お二人の出会いや野口さんがCTOとしてスタメンに参画されるに至った背景について教えていただけますか?
大西: 野口と出会ったのは2023年の春ごろですかね。技術をリードしてくれるエグゼクティブ層の採用に力を入れていたタイミングでした。
当時はちょうど僕が代表取締役に就任したばかりの頃で、TUNAGの開発組織は創業から続く『一つの巨大なソースコードをみんなで触っている』状況でした。
TUNAGは、1つのサービスで多面的なソリューションが提供できることを提供価値としていますが、開発内部では組織規模の拡大に比例して環境がどんどん複雑化してしまい、思ったように開発速度が上がらないという壁にぶつかっていました。「人と組織で勝つ」という創業からのコンセプトを掲げているにもかかわらず、開発体制がその思想を体現しづらくなっている、というジレンマを抱えていたんです。
そんなタイミングでの出会いだったこともあり、出会ってすぐの段階から野口には課題を曝け出して相談しました。
色々と課題を伝えたのですが、野口がそれぞれに具体的な解決の糸口を提案してくれたことを覚えています。自分たちが直面している課題を既に乗り越えたことがある経験豊かな技術部門の頼もしいリーダーとして、僕たちの理想のあり方を一緒に探っていってもらいたいなと感じました。
野口: 私は当時ロングバケーション中だったのですが、最初は、晴れ渡る青空の中、雪景色を見ながら屋外で前任CTOの松谷氏と会話することから始まりました。
その後、代表の大西を含めて会食でもどうかと問われ、周囲からも評価の高かった松谷氏の人柄に惹かれていたこともあり、その会食に応じることにしました。
二人と話をして、スタメンがプロダクト領域を拡大していく中で、これまで私がやってきたオープンソース技術が活用できるのではないかという解決の糸口がいくつか思いついたんです。
思想の源泉 なぜ、スタメンは「人と組織」を大事にするのか
ーそもそも「人と組織で勝ち続ける」という思想は、大西さんのどのような原体験から生まれたのでしょうか?
大西: 自身がこれまで経験してきたことや、見聞きしてきたビジネスのリアルに強く影響されています。たとえコモディティ化した事業であっても、強い組織やチーム、そして体制をしっかり作れたことで、最終的に競合優位性を生み出すことができた会社も見てきましたし、逆に、どれだけいいプロダクトがあっても、組織の崩壊がキッカケになって、結果的に衰退してしまった会社もたくさん見てきました。
開発やプロダクトはとても重要だけれど、勝負の分かれ目を決めるのは、最終的には「人と組織」なんだなと。企業の勝ち筋を高めるためには、人と組織にどれだけ投資し、うまく機能させられるかが事業の成否を分ける。それが、僕の中で時間をかけて育まれていった大きな成功哲学なんです。
人には「合理」と「感情」の両方があり、その両面を持った人間がたくさん集まれば、当然放っておけば複雑性もどんどんと増すものだと思います。だからこそ、組織としての方向性やスタンス、指針を明確に示しつつ、それぞれのメンバーの感情面にも適切な形で向き合っていけるか。そこをどれくらい組織運営としてやりきっていけるかで、ビジネスとしての成果に大きな差が生まれてくるのかなと思います。
そういった考えを事業として形にしたのが、スタメンの創業プロダクトである「TUNAG」です。
ーなぜ、特に「ノンデスクワーカー」の市場に可能性を見出されたのですか?
大西: 日本の労働人口の大半を占めるノンデスクワーカーの方々は、人手不足や組織の変化を最もダイレクトに感じる状況にあります。にもかかわらず、彼らに向けたITソリューションは、今一番届きづらい状況にある。世の中のB2Bサービスの多くが、導入しやすく利益率も高いホワイトカラー市場に集中するのは、ある意味で合理的な経営判断です。
だからこそ、ここに特化することは大きなビジネスチャンスですし、社会にとってもプラスが大きいと考えました。日本の労働人口の約6割を占め、今もなお日本の国際競争力を支えているのは、ノンデスクワーカーの方々なのです。
この巨大な市場を支援することが、大きなビジネスチャンスであると同時に、社会にとっても計り知れない価値を生む。──そうは、思いませんか?
実は、今でも日本が世界で「存在価値」を発揮できている領域、例えば外食産業や高い品質のサービス業、物流システム、伝統工芸といった産業は、その多くがノンデスク産業なんです。そこを僕らが支援することで日本企業の競争力が上がり、日本の存在価値や国内総生産の向上にも繋がる。そのインパクトは大きいと信じています。
ー日本の競争力の根幹を支える市場への貢献、ということですね。野口さんは、大西さんのこの想いのどのあたりに共感し、参画を決意されたのでしょうか?
野口: 「日本の企業を強くする」という点ですね。キャリアを通じて、年々日本の弱さ、弱体化を感じる場面が多くなっていました。しかし、日本にはまだまだ、非常に良い価値を生み出している会社がたくさんあります。TUNAGは、そういった企業に対して直接的にソリューションを提供できるプロダクトです。そこに非常に熱が高まるものがありましたし、自分の情熱を注げるなと感じました。
僕自身、経歴上、グローバルな組織・プロダクトに接する機会が多いキャリアを歩んできました。元々海外に興味があったんですよね。ただ、だからこそフラットに見た時の日本の弱体化を、よりダイレクトに感じやすかったんだと思います。僕の視点とスタメンがやろうとしていることが、ここで重なったんです。
想いの実装 - 失敗から生まれた「3つの開発哲学」
ー大西さんの「想い」を、野口さんはCTOとしてどのように開発現場の「仕組み」へと実装していったのでしょうか。具体的な取り組みについてお聞かせください。
野口: はい。まず取り組んだのは、創業時から続いてきた組織構造のアップデートでした。これは私が入社する以前からの課題でもありましたが、そこから学んだ教訓を元に、大きく3つの**「組織」「数字」「技術」**という柱を軸に再設計を進めていきました。
【組織】失敗と再構築 ___
野口: 当時の組織は、スクラムを導入する過程でチームを細分化しすぎてしまった結果、いくつかの問題が起きていました。例えば、スタメンが就業先の1社目というような、経験の浅いエンジニアだけで構成されるチームが生まれてしまい、メンバーが育ちづらい環境になっていたんです。
大西: まさに、人が増えても開発の生産性が上がりづらい、という「成長の壁」の原因の1つがそこにありましたね。
野口: その反省から、一度スクラムを廃止し、組織をまとめて大きく二つに分割しました。一つは、新規の価値創造を担う「プロダクト開発部」。もう一つは、開発生産性や開発者体験の向上に責任を持つ「プラットフォーム部」です。これは一般的な手法ではありますが、スタメンが組織としてスケーラビリティを獲得し、人が増えることと生産性、さらには本質的なプロダクト改善や品質向上を連動させていくための1番の近道であり、必要不可欠な意思決定でした。
【数字】本質の追求 ___
インタビュアー: 組織構造の次が、パフォーマンスの可視化ですね。野口さんがジョインされた直後に「Four Keys」を導入されたと伺いました。
野口: はい、ただし、僕らが大事にしているのは「数字を見過ぎない」ということです。計測はしますが、その数字だけに振り回されてはいけない。なぜなら、数字を追いすぎると、その数字ばかりに気を取られ、本質を見失うからです。
大西: これはSaaSの営業と似ています。例えば、獲得件数という数字だけを追いかければ、すぐに解約されてしまうような契約を取ってくることが正義になってしまう。開発も同じで、リリース回数だけを追えば、ドキュメントが整備されず、結果的に未来のメンテナンスコストを増大させることにも繋がりかねません。僕らがやりたいのはそういうことではない。手段が目的化してはいけないんです。
【技術】合理性の選択 ___
インタビュアー: 三つ目の技術について伺わせてください。スタメンの技術戦略の核ともいえる考え方はなんですか?
野口:私たちは目新しいものをすぐに取り入れる、というよりは今ある技術をいかに効率よく活用するのか、を重視しています。もしかすると、RubyやRuby on Railsは巷で「枯れた技術」と言われているかもしれません。
インタビュアー:「枯れた技術」ですか。なかなかパンチのあるキーワードですね。ただ、その「枯れた技術」という言葉は、求職者の方から「技術的な挑戦がしにくい環境なのでは?」と誤解されてしまうリスクもありませんか?
野口:もちろん、最新の技術に挑戦できない、と言いたいわけでは全くありません。
過去にも、最新技術を取り入れて開発する、ということにもトライしてきました。しかし、最新技術をメイン技術にすると、開発者には楽しい反面、本来顧客に届けたかったものにエラーが起きやすくなり、結果的にユーザーからのクレームに繋がり、満足度が減少するリスクが増します。それって、本質的な価値を届ける行為からだんだん遠ざかっていて、技術のキャッチアップが目的となってしまっている状態だと思うんです。
僕は「事業価値を最速でユーザーに届ける」という目的を達成するために、市場でもっとも使われた技術を選択し、その技術をより効率的に活用することが最も合理的だと考えています。
もちろん、技術を追求する部門も段階的に作っていきたい。ただ、今の事業規模では、まず「TUNAG」というプロダクトを単体で伸ばし、事業を大きくしていくことが最優先です。そのために、技術選定に時間を割きすぎたり、先端技術を導入して陥ってしまうリスクは極力避けたいと考えています。
大西:すごく大事なポイントだと私も思っています。「枯れた技術」と言ってしまうと響きが悪いかもしれませんが、僕らが一番伝えたいのは「新しい技術に挑戦しない」ということでは全くないんです。実際に野口自身が最新技術のキャッチアップに、誰よりも取り組んでいるところを日常的に見てきています。僕らが伝えたいのは、**「最新技術の導入そのものが、目的になってはいけない」**ということ。あくまでプロダクトを伸ばすための手段として、合理的な判断をする。そのバランス感覚こそが、僕らの大事にしているポイントなんです。
9年分の資産という「挑戦機会」
ー経験が豊富なハイレイヤーエンジニアの方々にとっては、その裁量を何に活かせるのかが、一番知りたいポイントだと思いますがいかがでしょうか?
野口: 我々にとって、今の最大の武器であり、同時に課題でもあるのが、創業以来9年間蓄積してきた「データ」という資産です。
大西: そうですね。TUNAGは現在、1,200社を超える企業様で、100万人を超えるユーザーの方々に日々ご利用いただいています。その結果、本当に膨大なデータが溜まっている。ただ、そのデータ資産の活用にあたっては、いまだに我々自身の「マンパワー」に頼ってしまっている部分が多いんです。言い換えると、9年間の航海で、僕らの船には巨大な「宝の地図」、つまり膨大なデータ資産が眠っています。
ただ、僕らはまだその宝を「素手」で掘っているような状態なんです。テクノロジーという最新の道具を使って、その価値を最大化しきれていない。システムやテクノロジーで、このデータを活用しきれていない。それが、今のリアルな課題ですね。
野口: ええ。プロダクトの価値提供として、例えばAIを組み込んだエージェントのような機能はまだ提供できていません。この巨大なデータ資源を、いかにして新たな顧客価値へと転換していくか。これこそが、僕らが今まさに挑もうとしていることです。9年分のデータと、それをまだ活用しきれていないという、壮大な「余白」。それこそが、新しい仲間と挑みたい挑戦です。
大西: まさに野口が伝えた通りで、この「今まで積み重ねてきた時間とデータ」を活用できる可能性は、とてつもなく大きい。ですが、今の体制では正直やりきれていないんです。だからこそ、この挑戦をリードしてくださる方が必要なんです。
野口: そして、この挑戦は、今のスタメンだからこそ面白いフェーズにあると思っています。僕らの組織規模は、アーリーフェーズのスタートアップのようにリソースが全く足りないわけでも、国内のメガベンチャーのように動きが制限されるわけでもない。「資産と自由」の双方がある、というユニークなポジションです。この環境で、これだけ大きなテーマに取り組める裁量がある。そこが、我々の最大の魅力ではないでしょうか。
大西: 9年分のデータという巨大な資産と、それをテクノロジーで価値に変えるという壮大な挑戦。そして、それを実現するための裁量と自由がある。これこそが、今のスタメンだからこそ提供できる、ハイレイヤーのエンジニアの方にとっての「挑戦機会」だと思っています。
「筋肉質な組織」へ ― 物語の次のピースは、あなただ
ー最後に、今後のスタメン、そして開発組織が目指す未来についてお伺いします。お二人は、これからどのような組織を創っていきたいと考えていらっしゃいますか?
野口: 私が目指しているのは「筋肉質な開発組織」です。スタメンはこれまで、他のITサービス企業と比較しても一人当たりの売上高が高い、つまり、かなり少人数で高い生産性を維持してきました。そして、AIがソフトウェア開発・プロダクト開発にパラダイムシフトをもたらした。今後もこの強みを維持し、少数精鋭で大きな価値を生み出せる組織であり続けたい。その挑戦を、共にしたい方を求めています。
大西: ええ。そして、その「筋肉質」という在り方は、まさに僕らが掲げる思想そのものだと考えています。会社のコンセプトである「人と組織で勝ち続ける」は、開発チームこそが「体現」する存在でなければならない。僕らは、プロダクトを通じてお客様に強い組織作りを提案しているわけですから、まず自分たちがそうでなければ、説得力がありません。
ーお話しを伺っていると、序章で語られた「成長の壁」、それを乗り越えるために失敗から学んだ「3つの柱」、そして未来の挑戦である「9年分のデータ活用」、その全てが繋がってくるように感じます。
大西: まさしく、その通りです。僕らが9年間かけて向き合ってきた、成長の壁、失敗から学んだ仕組み、そして「人と組織で勝つ」という思想──その全てが、今、一本の線として繋がろうとしています。
この資産をテクノロジーの力で本当の価値に変えることこそ、僕らが単なる「筋肉質」なだけでなく、本質的な価値提供を実現する、真に強い組織になるための鍵です。
だからこそ、僕らはもっと自信を持って「自分たちの開発組織は、思想を体現できている」と言えるようになりたい。この壮大な物語の最後のピースを、僕らと一緒に埋めてくれる仲間を探している。この挑戦に、一緒に本気になってくれる方に、ぜひジョインしていただきたいんです。
最後に
スタメンでは、一緒に挑戦をしてくれる仲間を絶賛募集中です!
少しでも興味を持ってくださった方は、ぜひ下記ページからエントリーをしてください。




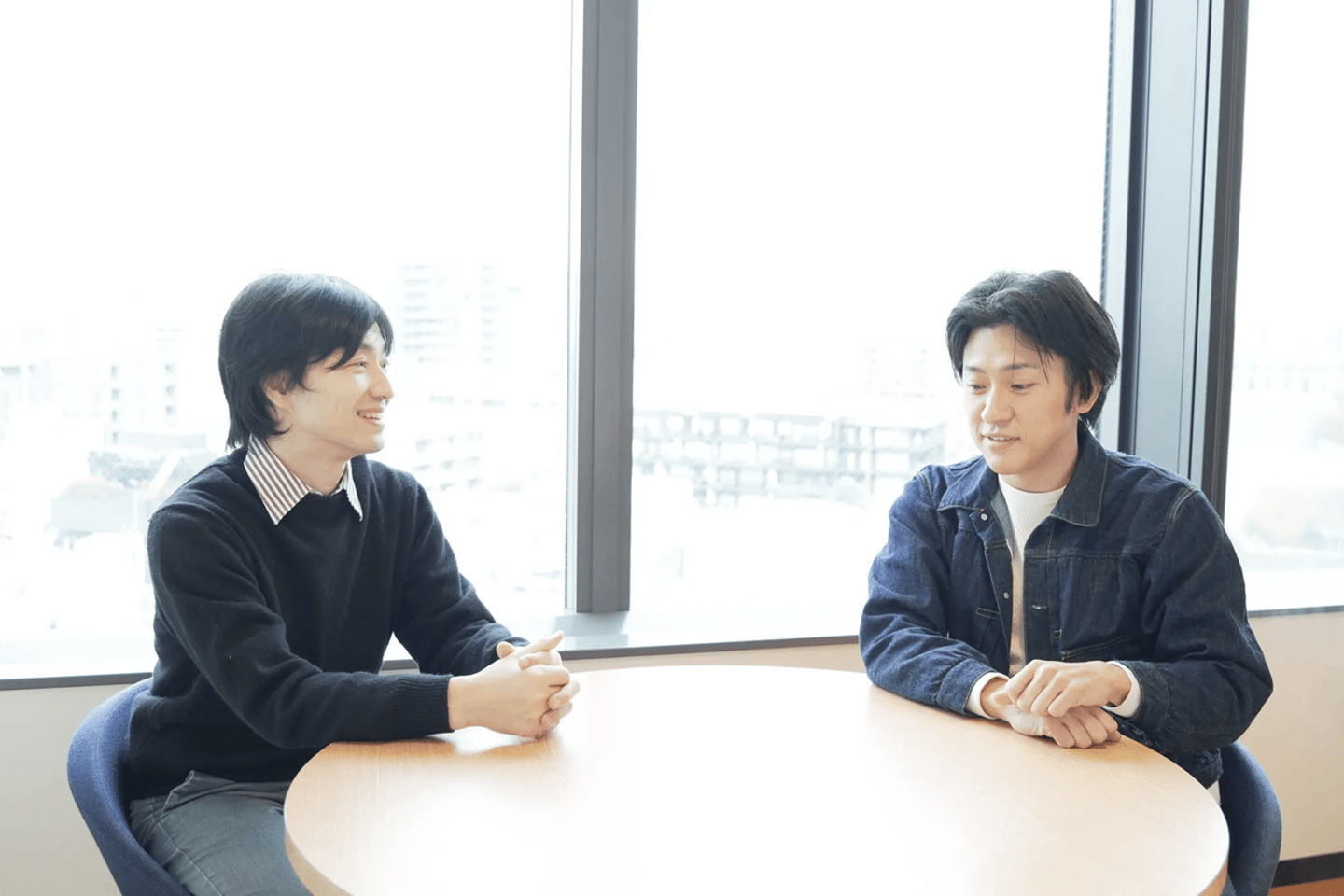




/assets/images/22173359/original/db238ad1-0ae1-44a4-9f26-184ef4460129?1759291300)

/assets/images/18529455/original/510df1fb-e466-4f64-9417-852f1e80d4b0?1720584516)

/assets/images/19847315/original/76beffe6-430c-48ed-99be-e59d5b6082da?1733105496)

