- 未経験 / Webエンジニア
- 人事 採用 広報
- 未経験OK|開発エンジニア
- Other occupations (24)
- Development
- Business
- Other
プログラマー時代は終わった?AIが攻めるエンジニアの生存戦略
最近、海外の記事で非常に示唆的な内容を目にしました。テーマは「AI時代がプログラマーに与える影響」です。この記事を読んで、昨年初めてGitHub Copilotに触れたときの衝撃を思い出しました。
数行のコード補完から、ツールスクリプトの丸ごと自動生成まで──あまりにも快適すぎて、
「これ、もうAI使えば誰でもエンジニアになれるじゃん?」とさえ思ったのです。
しかし今振り返ると、それは甘い幻想でした。
AIは「不利」を「断崖」する
💡経営者の視点
新しい技術は一見「誰でもできる化」が進むように見えます。しかし
実際には、「トップ人材と平均層の差を圧倒的に広げる」ことが多いです。
Copilot や ChatGPT といった生成 AI は、人材の質のばらつきを対話化するレンズです。
結果として──AI はプログラマーの間のほんのわずかを見据え、断崖レベルまで広がってしまいました。
以前はトップエンジニアと普通のエンジニアの差はおよそ10倍。
今ではそれが100倍、1000倍までになります。
💡経営者の視点
AIが実現したのは「普通の人の生産性を2倍にする」よりも、「トップ人材の生産性を50倍にする」こと。
組織は「普通の人を少し良くする」よりも「トップをフル活用する」構造設計が重要です。
AIがぶり出した「作業依存型エンジニア」の限界
AIは、平凡な技術者の弱点を容赦なく暴き出します。
ループやCRUD実装、API接続など、それまでかかっていた作業は、AIが数秒で生成されてしまいます。
一つは、システム分解やアーキテクチャ設計に長けたエンジニアにとっては──AIは戦う「専用チートツール」となる。
💡経営者の視点
AIは「実装型人材」の価値を下げ、「設計・構想型人材」の価値を爆上げする。
採用や評価基準も、「コードの行数」から「設計力・構造化能力」を重視して移行すべきである。
「書く」から「考える」へ──9割は頭の中の戦い
カーソルやクロード コードのようなコード支援ツールは、「意図が明確であるほど」強力な結果を返します。逆に、考えがあいまいだとAIも迷走するだけです。
昔は「1考えて9書く」でしたが、今は「9考えて1書く」になりました。
コードを大量に書く力よりも、構造を設計する力の方が遥かに重要になっています。
💡経営者の視点
とりあえずのエンジニア教育は、「書く」ではなく「考え方」を鍛えることが中心になります
。
選べるカギは「代替不可能な判断力」
ツールが賢くなればなるほど本当、比較は一箇所に集中されます。
AIは「どうやるか」を肩代わりできますが、
「何をやるのか」や「なぜそうするのか」は、人間が領域として考える、これからさらに価値が見えます。
まとめ:AI時代のエンジニア・組織戦略
💡経営者視点(総括)
- 採用戦略:作業型ではなく、発想型・設計型人材を重視する。
- 育成戦略:「AIの使い方研修」より、「構造設計・判断力の育成」に投資。
- 組織設計:トップ人材の生産性を最大化し、その成果を全社に与える。
- 評価認証:実行数や実行時間ではなく、「価値ある判断と設計」を評価軸に。
技術が進化しても、「考える力」「決める力」は奪われない。
プログラマー時代は終わったと感じるかも知れませんが、
AI時代は「設計・発想力を持つエンジニア」にとって、最高の追い風でもあるのです。

/assets/images/11010934/original/654c912d-792c-43e7-8c6e-0bced2263011?1667182788)


/assets/images/11010934/original/654c912d-792c-43e7-8c6e-0bced2263011?1667182788)


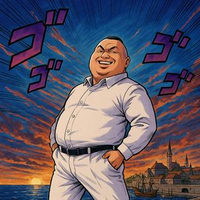
/assets/images/20408409/original/654c912d-792c-43e7-8c6e-0bced2263011?1739429121)

