こんにちは、Senjin Holdings代表の下山です。
私は東大2年の時に起業し、4年生で6億円で売却。その後東京藝術大学に進学しながらSenjin Holdingsを経営しています。
弊社は「若き才能を集めて、ビジネスで熱狂的に世界を変える」をミッションとしている、Webマーケティングのプロ集団です。
気になった方は、ぜひこちらをみて見てください。
私・弊社についての理解が深まる内容になっています。
なぜ今、若手がベンチャー企業を志望するのか?
新卒でベンチャー企業を志望する学生が年々増えています。従来の「安定=正解」という価値観が崩れ、「成長」「挑戦」「スピード感」といったキーワードが学生の志向に強く現れるようになりました。特にSNSや動画メディアで、20代の起業家や若手社員が成果を出している姿が可視化されることで、「自分にもできるかも」「このスピード感の中に身を置きたい」と感じる学生が増えているのです。
ベンチャー企業の最大の特徴は「変化の速さ」と「裁量の大きさ」です。たとえば、入社1年目からマーケティング施策の立案や、プロダクト改善の提案を任されることも珍しくありません。大企業であれば数年かけて経験する工程を、半年で体験できることもあります。このスピード感こそが、若いうちからスキルや実績を積みたい人にとって魅力的なポイントです。
しかし、誤解もあります。「自由でフラット」な職場というイメージが先行し、実際には高い成果主義や長時間労働、明確な評価基準がないことで苦労するケースも存在します。だからこそ、「挑戦したい理由」や「得たい経験」を明確に持つことが、新卒でベンチャーに入社する上での前提条件となるのです。
急成長市場でのキャリアが“武器”になる時代
IT、SaaS、地方創生、エネルギー、AIといった分野で急成長中のベンチャーに入ることで、5年後、10年後に「市場価値の高い人材」になる可能性が高まります。業界選びもキャリア戦略の一環です。
「裁量」と「スピード」が欲しい学生が増加中
「ゆっくり育ててくれる環境より、自分で試して失敗したい」——そんな志向の学生が、今は主流になりつつあります。ベンチャーはその舞台として最適です。
ベンチャー企業の採用情報はどこを見ればいい?注目ポイント5選
新卒でベンチャー企業を目指すなら、採用情報の“読み解き力”が必要です。表面的なキャッチコピーだけではなく、企業の実態を見極める目が求められます。まず注目すべきは、「ポジションの具体性」です。「幹部候補」「社長直下」など抽象的なワードではなく、「入社半年で〇〇を担当」など、成長プロセスが明示されている企業は信頼できます。
次に、「経営陣のバックグラウンド」や「資金調達状況」もチェックしましょう。連続起業家が率いているのか、初の起業なのか、調達ラウンドが順調かどうかは、企業の将来性に直結します。また、社員数の推移や離職率、口コミサイトのレビューも参考になります。
他にも注目すべきポイントは以下の通りです:
- 業務範囲の広さと深さ(幅広く任せるが中途半端、になっていないか)
- 育成体制の有無(OJTか、メンター制度か、放任主義か)
- 働き方の柔軟性(リモート可、勤務時間、休日制度)
採用情報は、企業が「どんな仲間を求めているか」のメッセージでもあります。その行間を読み解くことが、ミスマッチを防ぐ最善の方法です。
「社長直下」や「幹部候補」は本当?
こうした言葉が並ぶ場合は、その裏付けとして「実際に過去にどんな新卒社員が抜擢されたのか?」という事例を探しましょう。無ければ“釣りワード”の可能性も。
資金調達や売上成長率をチェックせよ
TechCrunchやPR TIMESでのリリースを確認し、調達額・シリーズ・出資元を把握することで、企業の信頼性や事業の拡張余地が分かります。
就活ナビには載ってない、穴場のベンチャー採用情報を見つける方法
多くの優良ベンチャー企業は、リクナビやマイナビには掲載していません。理由は明快で、「知名度ではなく、価値観の合う人材」を求めているからです。では、そういった“穴場”の採用情報をどう見つけるか?
まず最も効果的なのが《Wantedly》です。単なる求人媒体ではなく、企業カルチャーをストーリーとして知れるプラットフォームであり、企業側も「人柄」「志向」でマッチングしようとしています。また、「話を聞きに行きたい」ボタンでカジュアルに接点を持てるのも魅力です。
次に《note》や《X(旧Twitter)》など、社員や代表が直接発信している場です。「#採用」「#新卒募集」などで検索すれば、生の声に触れられます。これは就活生だけでなく、転職市場でも注目されている手法です。
さらに、《就活イベント》や《起業家登壇セミナー》などにも積極的に参加することで、ナビには載らない企業と出会えます。特にオンライン開催のイベントが増えており、地方学生でも参加しやすい環境が整っています。
Wantedly・note・X(旧Twitter)を活用せよ
“リアルな声”を拾うことで、その企業がどんな文化を持っているのか、どんな未来を描いているのかを知ることができます。求人票には現れない、価値観のマッチングに繋がります。
OB/OG訪問とイベントで一次情報を掴む
「大学の先輩」だけでなく、「志望企業の現場社員」に直接アプローチを。LinkedInやSNSでのDM、企業の登壇イベントでの名刺交換も効果的です。
ベンチャー就職のリアル:よくある誤解と失敗談
ベンチャーという言葉には、自由で革新的なイメージがつきまといますが、実態は「自己責任と変化への適応」の連続です。新卒でベンチャーを選んだ学生の中には、「裁量があると思っていたのに、放置された」「やりたいことができると思っていたのに、何をすべきか分からなかった」といった声も少なくありません。
多くのベンチャー企業では、マニュアルや研修制度が未整備です。そのため、自分で考えて動ける人でないと、環境に流されてしまうリスクがあります。新卒であっても「自分でタスクを設計し、相談しながら実行する力」が求められるのです。
また、評価制度が曖昧なケースも多いため、「頑張っているのに評価されない」「方向性が分からない」と感じることもあります。これは成長機会ではありますが、精神的な負担も大きくなる可能性があります。
「自由」は自己責任とセット
“自由な社風”の裏には、「成果を出せないと淘汰される」という厳しさも存在します。自由=楽ではない、という認識を持つことが大切です。
“人材育成”は会社によってピンキリ
人を育てる文化があるベンチャーもあれば、「即戦力しか採らない」という方針の会社もあります。インターンや面談での質問を通じて見極めましょう。
未来を変えるキャリア選択:ベンチャーに向いている人・向かない人
最後に、私たちが実際に多くの新卒採用を行ってきた経験から見えた、「ベンチャー向きの人材」とそうでないタイプの特徴を紹介します。まず、ベンチャーに向いているのは「走りながら考えられる人」です。これは単に行動力があるという意味ではなく、不確実性を楽しめる感性、自分の言葉で物事を捉えられる思考力が必要だということです。
また、「自分の市場価値を高めたい」「20代で圧倒的に成長したい」といった意欲がある人は、ベンチャーの持つ“変化の波”をエネルギーに変えることができます。一方で、「安定した環境で丁寧に育ててもらいたい」「言われたことをしっかりやるのが得意」といった方には、カルチャーショックになる可能性もあります。
自己分析を通じて、「どんな働き方が心地いいか」「どのように成長していきたいか」を言語化することが、最適な就職先選びに繋がります。正解のない時代だからこそ、自分に合った環境を自ら選び取る力が求められています。
向いているのは「走りながら考える人」
完璧主義よりも、まず動いてみる姿勢が大切。トライ&エラーを重ねながら自分の軸を見つけたい人には、ベンチャーは最高の環境です。
向いていないのは「マニュアル重視タイプ」
手順が決まっていないと不安になる人や、変化よりも安定を好む人には、ベンチャーのスピード感がストレスになる場合があります。

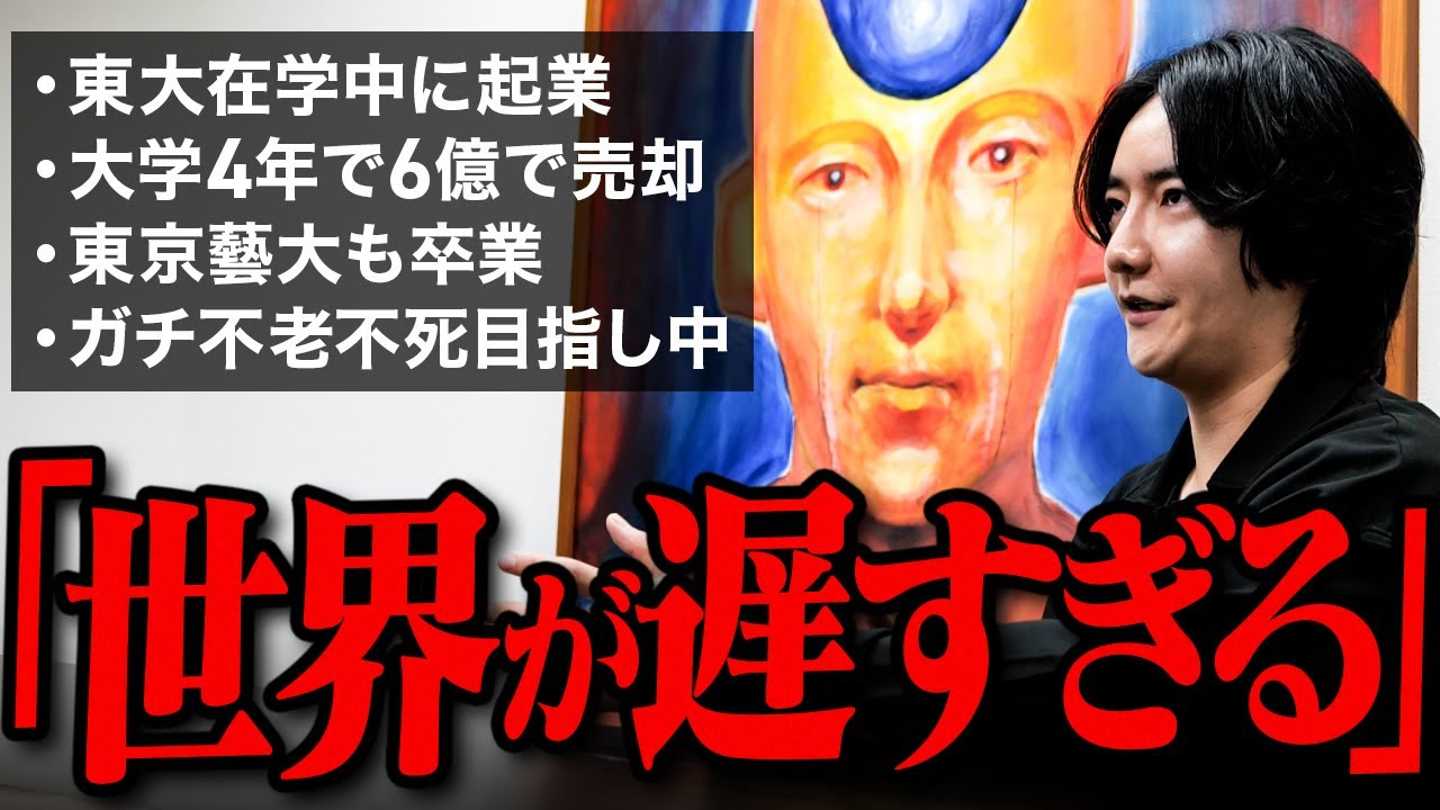
/assets/images/7131832/original/e041f50c-3007-49ea-b9e4-b779a28a8c9d?1750485492)

/assets/images/3835909/original/8f6acf18-04bd-42cd-9219-b1f47873bf0d?1674693574)
/assets/images/21089010/original/8f6acf18-04bd-42cd-9219-b1f47873bf0d?1747018129)

