こんにちは!広報の村上です🐶🐱
採用における新たな試みとして、TYLは今年度より「新卒総合職」の募集に力を入れることとしました!そこで「新卒総合職とは?」「TYLでどんな仕事をするか?」ということをよりわかりやすくするため、「TYLの26卒新卒総合職採用」と題して、数回にわたり「新卒総合職」についての連続記事をお届けしています。
今回は前回に引き続き、TYLで初の「新卒で総合職」に採用された24新卒の山田さんが「『論理的思考力』がどんな仕事で発揮されるか?」というポイントをご自身の経験から語ってくれました。ご期待ください!
前編からの続き
こんにちは!私は、株式会社TYLに「総合職」として入社した24新卒の山田純平です。
この記事は、当社の総合職採用の推進を目的とした発信のうち、当社が就活生に求める「論理的思考力」を深くご理解いただくための2部作コンテンツの後編です。そもそも「総合職」というお仕事の詳細を知りたい方は、Vol.1の記事をご覧ください。
また、前編冒頭の繰り返しとなりますが、この2部作を読むと何が分かるかを改めて確認しておきましょう。
・ビジネスをするうえで論理的思考力がなぜ必要か(前編)
・TYLの総合職で論理的思考力を要求する理由(前編&後編)
・山田は仕事上、具体的にどんなシーンで論理的思考力を使ったか(後編)
1点目について詳しく知りたい方は、前編の記事をチェックしてください。
それでは、ここから後編です。ぜひ最後までご覧ください!
私が代表と取るコミュニケーション その1:1on1
前回の結びに、下記のような次回予告をして終わりました。
「総合職のポジションで論理的思考力が重視されるのは、総合職が『事業を創る仕事」』だからです。」
今回はこの真意を説明することがメインテーマとなります。取っ掛かりとして、「総合職で入社した先に何が待ち受けているか」をまずはお伝えしましょう。
総合職で採用された暁には、「経営幹部になってほしい」という役員陣の期待のもと、1年目から役員や社内の高いレイヤーの社員と仕事をする機会が与えられます。
私の場合、まず配属の時点で、代表取締役社長の金児さんが直属の上司となりました。26新卒の募集要項にも「代表取締役直下」の記載があるとおり、総合職の場合代表が直接の上司となるケースは珍しくありません。
「直属の上司」と聞くと、「あれをやれ、ここをこうしろ!」と業務指示を与える立場をイメージするかもしれませんが、私が金児さんとの間で交わしたコミュニケーションは、主に以下の3つに分類されると思います。
(1)Willの確認と目標設計
(2)仕事のお作法
(3)事業戦略上の問い
まず第一に「Willの確認と目標設計」ですが、これはあなたも採用面接でお話しすることになる、「〇年後にどうなっていたい?そのためにこれから〇年間、あるいは〇カ月間はどう過ごそうか?」という話題です。
本パートは論理的思考力という本筋から逸れますが、あなたが働く根本的な理由に関わる非常に大事なテーマなので、自己分析のスパイスとしてお読みいただければ幸いです。
Willの確認は、一般的なビジネス用語で「1on1」と呼ばれます。自分よりも視座が高く、社会人経験が豊富な上司と話し、あなたの最終的なGOALに辿り着くための補助線を引いてもらいます。その上で、短期的な自己変革のための取り組みを宣言し、何週間か経ったら取り組みを一緒に振り返る、そのための時間を取ってもらうのです。
そもそも私が働く理由は、生活するためのお金を稼ぎ、同時に「あっ、困っている人がいる。何とか力になりたい!」という欲求を満たすためです。したがって、より儲かる仕組みを作れるようになることと、どんな課題でも解決に持っていける実力をつけること、この2つが私にとってのWillです。このWillを実現するために、TYLという会社で金児さんの力を借りるのが良いという判断のもと働いているので、1on1でのやり取りは私にとって必要不可欠であり、この時間がなければ働く意味を見失いかねません。
現在、TYLでは社員と会社の関係性を整理するうえで「社員と会社の相互発展」をスローガンに掲げています。もちろん会社から給与をもらう以上、社員は会社の利益に貢献する約束をするわけですが、一方でそれと同じくらい、あなたはあなた自身の自己実現のために、人生の大切な時間を使う権利を有しています。とりわけ2025年の新卒就活市場は、数から考えれば、就活生が会社を選べる構造(俗に言う「売り手市場」)なので、あなたのWillを主張することが存分に可能だと私は考えています。
例えるなら、あなたの自宅のクローゼットに服が1種類しかないのであれば、それを着る他に選択肢がありませんが、サイズも模様も形もブランドも、ありとあらゆる服がたくさんあれば、その日の気分にピンポイントでマッチする服が見つかる、このような状況とまったく同じです。
![]()
Willを叶えるのに、数ある選択肢をよーく吟味しましょう!
(参考:株式会社インディードリクルートパートナーズリクルートワークス研究所「第41回 ワークス大卒求人倍率調査(2025年卒)【大卒求人倍率1.75倍】引き続き高い採用意欲が続く見込み―2024年卒では初任給引き上げが大幅に進む―」
https://www.works-i.com/surveys/report/240425_recruitment_saiyo_ratio.html)
そういうわけで、総合職で入社すれば代表取締役という最高の壁打ち相手を直属の上司にでき、あなたのWillに向かうための職業生活を送ることができます。
ただし、自分のWillが強すぎて会社が期待する役割を全うしていなかったり、反対に、会社の希望ばかり優先して自分のWillが叶えられないということがないよう、入社前には採用面接、入社後は1on1でしっかりと相互に求めることをすり合わせましょう、という話でした。
私が代表と取るコミュニケーション その2:「お作法」
さて、2つ目は「仕事のお作法」についてです。これは前編の記事で触れた制度理論すなわち、「世間の常識や当たり前」と深く関係があります。
具体例から紹介すると、例えば、説明資料として用いるスライドは、
・ワンスライドにワンメッセージ
・左上にタイトル
・中央上部、タイトルよりも低い位置にキーメッセージ
・中央にボディ
・右下にスライド番号
この基本レイアウトに従いましょう、みたいな話です。
このように、ビジネスマナーと言うほど一般性はありませんが、多くのビジネスマンが慣れ親しんだ仕事の型のことを私と金児さんの間では「お作法」と呼んでいます。守破離で言うところの“守”ですね。
※守破離…基本を身に着けてから既存のやり方を発展させるやり方のこと。
「お作法」を学ぶ最大の理由は、情報を受け取る側の認知負荷を下げるためです。その型の良し悪しはさておき、慣習的にそのようなスライドのレイアウトがよく使われるから、それに従って作成することで、見る側に「中央上部に書かれた文が、このスライドで言いたいことなんだな」と分かってもらえます。そうすることによって、中身の議論に集中できるわけです。
![]()
「お作法」の一例。「スライドと言えばこの形!」のフォーマットに従うことで、
打ち合わせ相手と本質的な“中身”の話をしやすい。
一方で、考え無しに真似をすれば十分というわけではありません。ここからが論理的思考力の使いどころです。
業界に定着している「お作法」であれば、その型が優れていると考えられる、何らかの理由がある場合がほとんどです。植物が葉っぱを放射状に広げて、空から見て重ならないように配置しているのは、葉っぱが日光を受ける確率を高め、より効率的に光合成を行うためと考えられます。数億年間の生命の進化の歴史がこれを担保するのと同様に、過去に多くのビジネスマンが様々な方法を試した結果として現在の「お作法」が定着しているので、「なぜそのやり方が理にかなっているのか」ちゃんと説明できる可能性が高いのです。上記のスライド作成の例で言えば、横書きの文章を読むことを繰り返した結果、多くの人が「Z字型」に視線を動かす癖があることを利用しています。
このように、若いビジネスマンに求められるのは、まずは「お作法」を踏襲しながらも単に言われた通りに淡々とこなすだけではなく、その「お作法」が常識として定着している本質的な理由を論理的に暴こうと試みることです。そして、その「お作法」に従うのが有効であれば“守”を選択し、逆に従うことが不適切であれば積極的に“破”を選択できること。この決断力を持つにはやはり、論理的に「なぜこの『お作法』が『お作法』たり得るのか?」を常日頃から考えておく必要があると私は考えています。
(...右から左に文字を書くアラビア語圏では、どんなレイアウトになっているんでしょうね!)
私が代表と取るコミュニケーション その3:事業戦略上の問い
おそらく、あなたがイメージする上司との会話に一番近いのが、3つ目に挙げた「事業戦略上の問い」です。ただし、「このタスクを処理しておいて!」のような上司からの“業務指示”とは全く違うということをご理解いただくために、「事業戦略」と「問い」の2つのブロックに分解してお話します。
まず「事業戦略」についてです。前編の記事では、会社経営や事業運営においてリソースは有限であり、それゆえ、そのリソース分配こそが会社や事業の行く末を決める、という話をしました。「どこに注力し、いくらのお金を使い、どれくらいの利益を見込むのか」という分配のことを我々は「戦略」と呼んでいます。総合職はWhyとWhatを考え、事業を創ることが仕事ですから、上記の「事業戦略」を立案し、実行し、成果を出すことがまさに私の仕事の本丸と言えるわけです。
次に「問い」ですが、先のとおり「あれをこうして!」という業務上の“指示”や、「それはズバリ、こうすると良いよ!」という“アドバイス”とは明確に異なります。考えるテーマを与えるのが「問い」なので、「事業戦略上の問い」を話し言葉に換えると、「この事業を成長させるには、何に力を入れたら良いと思いますか?その判断の理由って何ですか?」になります。このようなコミュニケーションを行うのに、論理的思考力が必要不可欠なのは言うまでもないでしょう。
なんだかハードルが高そうだなと感じたかもしれませんが、あなたがレベル認識を間違えないよう、最後に私が最近行った仕事をそっくりそのまま公開して本記事を締めたいと思います。
1年目の山田の仕事
私は入社後から今日まで、当社の中でもM&A仲介事業の領域で仕事をしてきました。
無知の極みである4月の時点から、「もっとM&A仲介事業を伸ばしていくために、事業改善をしていこう」と金児さんにミッションを与えられていたので、まず私は、当社のM&A仲介事業の実態を把握するところから仕事を始めました。
役割で言えば最初はマーケティング、次にインサイドセールス(商談のアポイント確保)、そして夏が過ぎるころからフィールドセールス(実際の営業活動)を経験しました。
1年間の詳細な仕事内容や苦労話は直接お聞きいただければと思いますが、ひとまず、私が事業理解・顧客理解をしたいと考えたことと、会社が最適な人員配置を計算した結果として、このような役割を担ってきました。
![]()
24新卒山田が1年目に担当した仕事。基本的にM&A仲介の領域で、
複数の役割を兼任しながら進んできており、現在のメインは営業推進となっている。
失敗も大小たくさんしながら経験を積み、季節が冬を迎えるころ、少しづつではありますが事業課題が見えてくるようになってきました。
あくまでも当時の私の体感に過ぎないのですが、特に気になったのは、「仲介をご依頼いただいた顧客のうち、基本合意書の締結に至る割合が小さ過ぎるのではないか」という点です。
※基本合意書・・・M&Aにおいて、買い手と売り手が概ねの譲渡条件に合意することを示す契約書。それ以降は独占交渉となるため、買い手は他の売り案件と、売り手は他の買い手候補と話を進めることなく、双方が譲渡の実行に向けた準備に集中する。
このような実感を金児さんに共有したところ、案の定、「じゃあ、どうしましょうね〜」という問いが返ってきました。さあ、ここからが、私に求められていた事業改善のスタートです。
突然ですが、あなたなら、「基本合意書の締結率の低さ」という“問題点らしきもの”が直観的に見えたこの場面で、どのようなアクションを取りますか?
金児さんとの話し合いの結果、私は下記の通りに改善を進めると決めました。
- 定量的な現状分析
- 理想的な数値と現状の数値の差分の算出
- 問題点の洗い出し
- 問題点の分解、課題の優先度付け
- 改善によるインパクトの試算
- アクションプランの策定
- モニタリングの設計
- 実行および定期的な振り返り、アクションの改善
もしあなたが、「より多くのマッチングを、より早く生み出すには、〇〇してみたらどうか?」と打ち手を考え始めてしまったのであれば、当社に来る価値があります。私と一緒に勉強しましょう。
つまり、いきなり「〇〇したらどうか?」と解決策から考え出すのはご法度。世界初のコンサルティングファームである「ボストン・コンサルティング・グループ」出身のコンサルタント、高松智史氏の言葉を借りれば「打ち手バカ」です。
直観的に「改善したほうが良さそう!」と感じた際、いきなり打ち手を実行すべきでない理由は主に2つです。
1つは、手段が目的に合っていない可能性があるからです。穴の開いたバケツにどんなに多くの水を注いでも、バケツを水で満たすことはできません。バケツを水で満たすことを目的とするなら、水を注ぐでも、念力を使うでもなく、まずは穴を塞ぐことが現実的で適切な手段と言えます。
もう1つの理由は、“問題点らしきもの”を解決しても、さほど嬉しくない可能性があるからです。例えば体重を減らしたいダイエッターが、「体中の細胞が活性化して、代謝が良くなるイメージが大事だ!」と考えて1日15分の瞑想を取り入れた結果、1カ月後、1日あたりの消費カロリーが0.01%増えたとします。確かに代謝は改善されましたが、15分散歩すれば5%も消費カロリーが増えたり、深夜の暴飲暴食によるオーバーカロリーを控えることにより摂取カロリーを10%減らせたりするなら、イメージトレーニングは二の次で良いはずです。
当たり前かもしれませんが、限られたリソースを効果的に投下して結果を得るためには、このようにしっかり頭で準備して、実行のキレを良くしておくことが非常に効果的だと、私は一年かけてようやく理解することができました。
![]()
事業の進捗分析。飛行機のコックピットのように、現状を精緻に理解し、進行方向を決定するのに用いる。
TYLで私たちとともに、エレガントで地道なファーストキャリアを
以上、後編では論理的思考力の使いどころとして、
・「お作法」を真似しながら、その「お作法」の優れている点を探るとき
・事業を伸ばすために、問題点の中から取り組むべき課題を特定するとき
・課題に対して適切な打ち手を考えるとき
などを例に挙げました。これで論理的思考力がなぜビジネスマンに必要か、とりわけ、当社の総合職でなぜ強調されるか、についてご理解いただけたかと思います。
記事全体を通して少し偉そうに先輩風を吹かせましたが、私もまだまだ足りない点がたくさんあります。現時点での習熟度をポケモンで言えば、相棒を手に入れ、故郷から一歩出た草むらで野生のポケモンを一体倒した程度です。それにもかかわらず、失敗したり悩んだり、とにかくうまくいかないことが山ほどありました。「金児さんから投げられた問いにうまく答えが出せない」「分析の成果物はイメージできるが、集計の技術が足りず想定の何倍も時間がかかる」「改善アクションの計画を立てたが、これまでのやり方に慣れている先輩に対して素人同然の自分が『こうしましょう!』とズケズケ物を言うのは反感を買いそうで怖い」...そんな時に必ず自問自答をしてきました。
「確かに君の言うとおりかもしれない。でも、それで諦めたり、日和ったりして、在りたい姿に近づけるか?」
高校の数学の授業で、非常に簡素でキレイな定理も、地味で堅実な証明の結果であることを知りました。難しい問題に対する、嘘みたいにシンプルな解法も、問いの本質を捉えた合理的な着想の産物であることを学びました。
ツボを押さえ、要領よく事業を前進させることは、結果だけ見ればスマートでエレガントです。しかしその裏側には、地道で泥臭い何かが必要です。ドブ板営業かもしれないし、一次情報のリサーチかもしれないし、はたまた、恐怖心を徹底的に排除することかもしれません。そのような困難に立ち向かわなくてはいけない瞬間が、遅かれ早かれあなたには訪れます。なぜなら、あなたには、キレ良く問題解決に取り組める素質があるからです。本記事にご興味を持って、ここまでお読みいただいたことが何よりの証拠です。その力を、ぜひTYLの総合職で発揮してみませんか?頼りになるかは分かりませんが、同じ総合職として入社した私がいます(笑)
もしTYLの総合職で働くことにポジティブな印象をお持ちいただけたのであれば、ぜひ一度カジュアル面談でお話しましょう!下記リンクからフォームを入力いただき、実際にエントリーするか否かはその後で判断していただいてOKです!
最後までご覧いただきありがとうございました。それでは、カジュアル面談でお待ちしております!






/assets/images/1784513/original/5ccdcc19-c911-401c-88da-78371b0f867c?1504322123)


/assets/images/1784513/original/5ccdcc19-c911-401c-88da-78371b0f867c?1504322123)

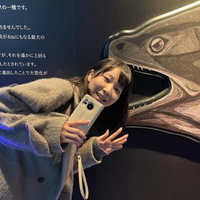

/assets/images/1784513/original/5ccdcc19-c911-401c-88da-78371b0f867c?1504322123)

