「評価って枠組みなんですよね。人が大きくなって比べるのが難しいから評価ができる。でも、その仕組みの中でやることをやるのではなく、いま大事だと思うことをやっていった方が良い結果につながったんです」
こう語るのは、BtoBセールス支援のデジタルセールスプラットフォーム「openpage」でCTOを務める渡邊恒介氏だ。長年のエンジニア人生で辿り着いた働き方の本質について、詳しく話を聞いた。
一貫したものづくりの軸—想定外の連続で築いたキャリア
渡邊氏のキャリアを振り返ると、その根底に流れるのは「ものづくり」への一貫した思いだ。
「一貫してるのはものづくりですね。開発だけでなく、全体の整合性を取りながらつなげていく。開発じゃないけど開発みたいなことをやっている感じです」
実際、渡邊氏は最初から現在のようなキャリアを描いていたわけではない。
「最初は商業施設の企画に関わっていたのに、気づいたらWEBエンジニアになっていて、そこから受託開発のプログラマー、事業責任者と変わっていったり。計画通りにいったことがほとんどない」
その後、大手企業やIPOしたベンチャー企業などで開発責任者やVPoEとして開発組織をリードする経験を積み重ねてきた。WEBエンジニア以外の経験も含め、それらすべてが本質的には「ものづくり」だったという。

渡邊氏は、楽しさを感じながらやっているうちに、自然と現在の形になったという。
「アピールできる点はなく、結果的にそうなった。20代に描いていたものと全然違う世界観でした。大手企業に行って、スーツを着て、定年まで勤めるという世界観が正しいと思っていたんですが、自分が向いてるのはそっちじゃないなと感じて1社目からベンチャーに行き、今に至ります」
キャリアの変遷について渡邊氏は「毎回毎回想定外でキャリアが変わっている」と振り返る。
「ドリコムでは技術的な仕事をしていたつもりが、いつの間にか組織づくりの話をしていたり。エンジニア定年35歳説があって、ドリコムで最後かなと思ったんですが、全然そんなことはなかった(笑)。市場や環境、市況が変わって、5年単位でも先が読めないですね。だからこそ、目の前のことに集中して、結果的にキャリアが形成されていく感じです」
openpageを選んだ理由—本質思考への共感
豊富な開発組織のリード経験を持つ渡邊氏にとって、openpageは「エンジニア2周目にちょうどいい」場所だった。
「延長で積み上げるより、2周目として1エンジニアとして入社しました。前職は数十名のマネジメントをする開発責任者だったのですが、その延長ではなく、まっさらにしてopenpageの1人目のエンジニアとして入社したんです。だからコードも書くのは入るときに重要な要素でした」
これまでの経験を活かしながらも、新しい挑戦というよりは「本質に向き合う」ことを重視したという。
「openpageの本質思考、クリティカルシンキングの社風に共感したんです。表面的な課題解決ではなく、根本的な問題を見つめて解決していく姿勢がある」
決め手となったのは、サービスの面白さと可能性だったという。
「WEBの新しく大きな新規領域が生まれることはそうそうないと思っていたんですが、新しいカテゴリを創造できる真新しさがあった。かつ巨大な未来が見える、その製品にものづくりとして関われるタイミングだと感じました。そんなタイミングはなかなかない」

渡邊氏は、特にBtoBの事業開発において技術と事業の両方への関心が重要だと強調する。
「法人向けの事業の開発をやるなら、ビジネス側のアンテナは張れないと良いものは作れない。興味を持って拾えるようにする。やるべきことの答えを出すための要素を偏ったものにしないようにすることが大切です」
技術選択においても、渡邊氏は独自の判断基準を持っている。
「文脈を大切にしています。フレームワークは前提がある。そこから外れると苦しい。それぞれのツールは、これは何をやることを前提にしているのか。それは大事にしている。その文脈を無視しない。うまく組み合わさるものを見つける。フレームワークの思想などを理解することですね」
この考え方の実践例として、渡邊氏はopenpageでの技術選択を振り返る。
「例えば、開発においてAIエージェントツールを導入するとき、単にコード生成が早くなるからという理由だけで使うのではなく、なぜそのツールが作られたのか、どんな開発プロセスを前提にしているのかを理解する。そうすると、チームの働き方や品質管理の仕組みも含めて、全体的な設計ができるようになる」
実際にopenpageに入社後、渡邊氏は開発組織の生成AI活用を推進し、開発生産性を従来の倍に引き上げる成果を上げている。これも「文脈を大切にする」技術選択の考え方が活かされた結果だ。
「評価を捨てる」—働き方の本質を見つめ直す
openpageでの働き方について尋ねると、渡邊氏は興味深い発言をした。
「挑戦とは思っていないんです。やることをやる、その中で自分がどれだけ楽しめているかが重要です。自分も大切にして取り組むことが大事だと思います」
この発言の背景には、評価制度に対する深い洞察がある。冒頭の発言のように、評価は枠組みに過ぎず、その中でやることをやるのではなく、今大事だと思うことをやっていった方が良い結果につながったという。
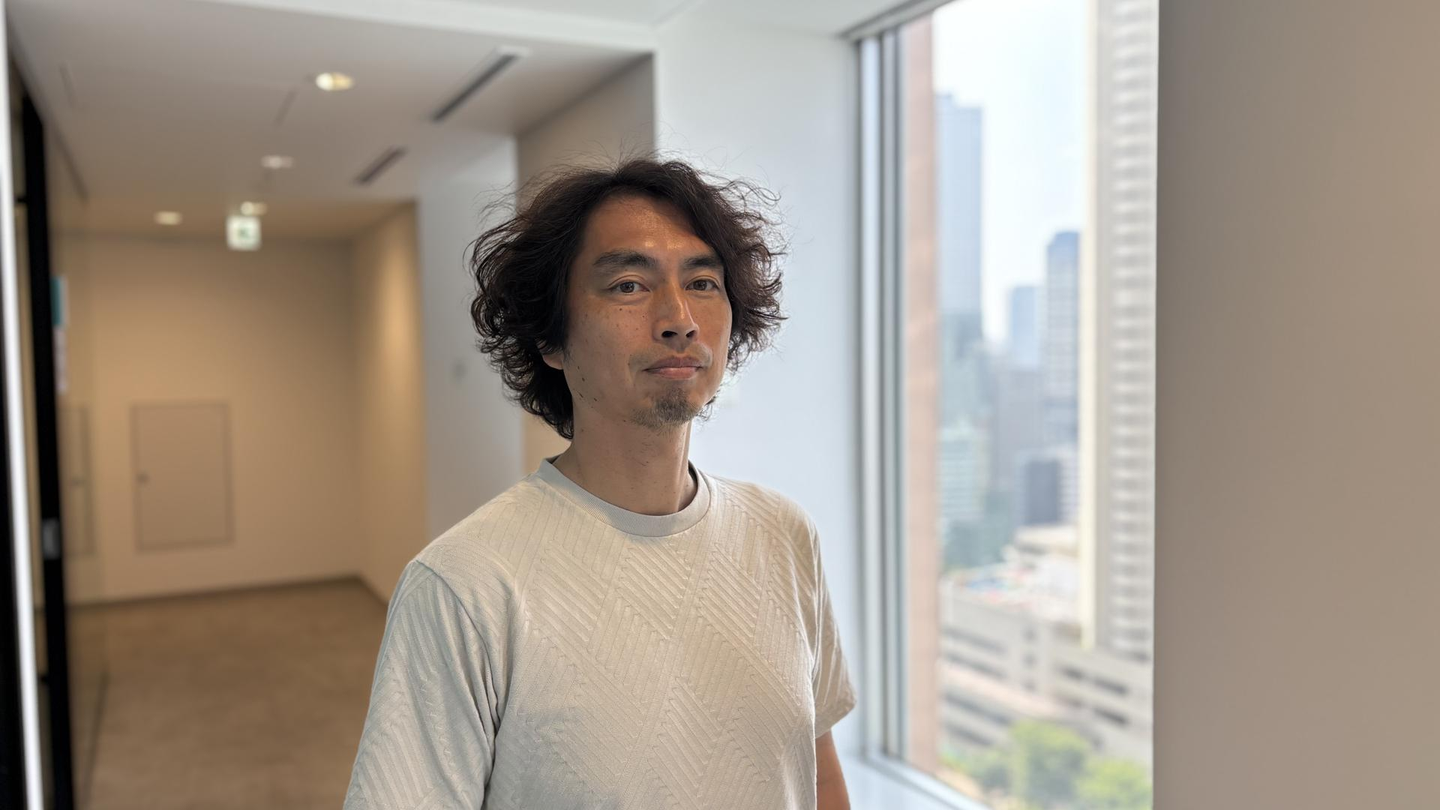
では、具体的にどのような場面で「評価を捨てる」ことが良い結果につながったのか。
「例えば、会社の四半期目標に直接関係ない技術改善でも、将来的に重要だと思えばやる。短期的な評価項目にはないけれど、プロダクトの根幹に関わる部分を優先する。そういう判断を重ねてきました」
渡邊氏が「評価を捨てる」と表現するのは、評価制度を無視するという意味ではない。
「会社としてやるべきことを変えましょうというつもりではないんですが、変に評価に合わせて仕事をしてはめ込んでもだめ。そんなこと気にしないでやる方がいい。結果として、それが一番会社にとっても良い成果を生むんです」
「会社のための自分」から「自分の存在を大事にする」へ
この働き方の変化は、より根本的な価値観の転換から生まれている。
「楽しさ追求というより、もう少し自分を信じるようになった。会社のための自分ではなく、自分の存在を大事にする。会社を主語にするんじゃない。会社の中での自分も大事なんです」
この価値観の転換には、複数の会社を経験する中で気づいた現実がある。
「会社の経営にとって技術要素は大事だが、交換可能なものである。技術をメインにしているとそこは必ず交換可能になる。そうすると残るのは自分だけ。自分に紐づくものを大事にした方がいいですよねに変わる。会社をいくつか移ってくる中でそう感じました」
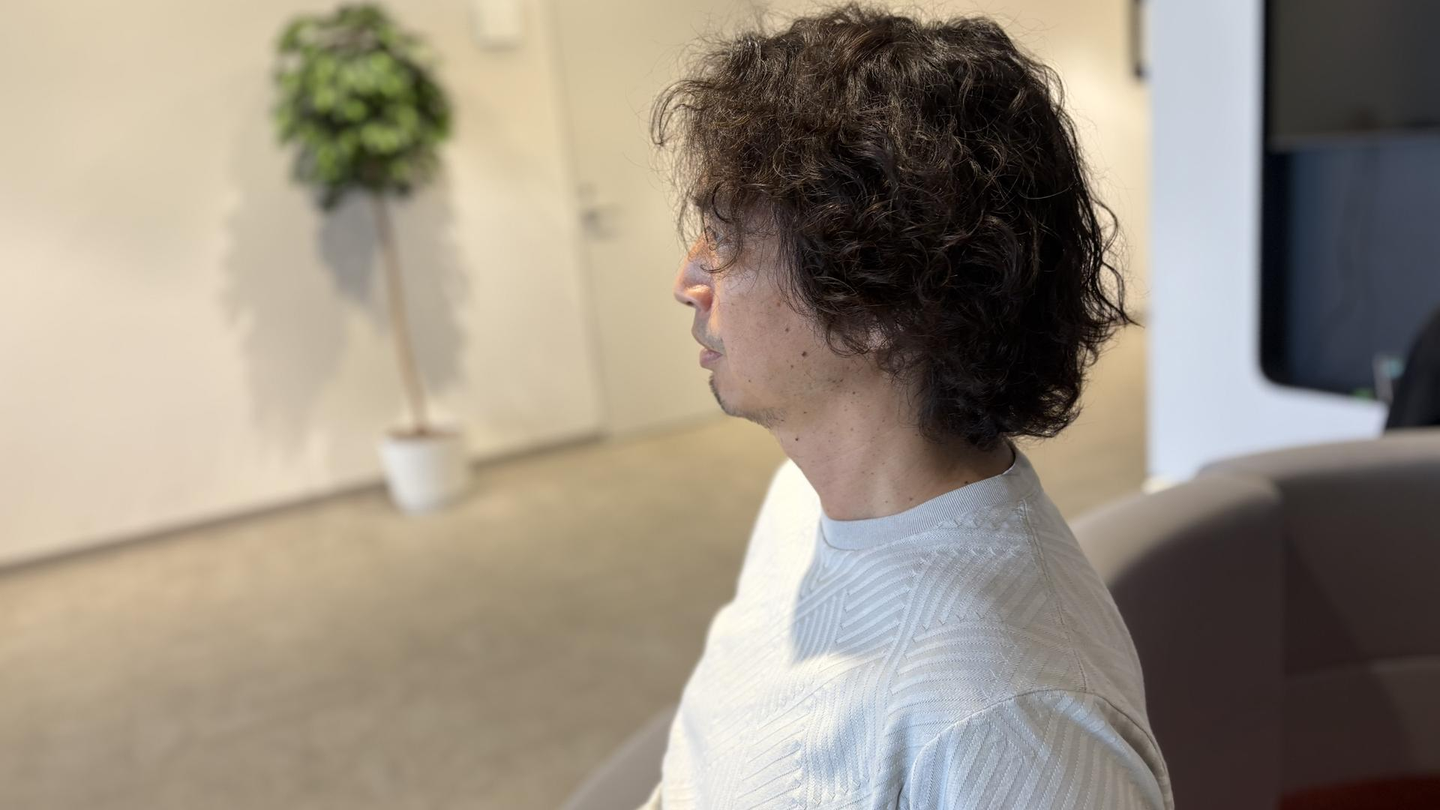
20代、30代の頃との違いを振り返って、渡邊氏はこう語る。
「残るものは自分と最後はなる。自分の大切さは意識の比重が大きくなった。前は自分はどうでもいいが会社で成果が出れば、という感じだったんですが、今は違います。だから今後のチームも、みんなに自分を信じてもらって、それぞれが自分の芯を持つ組織にしたいと思っています。メンバー一人ひとりが自分の軸を大切にして働ける環境を作りたいんです」
エンジニアへのメッセージ
最後に、同じエンジニアとして歩む読者へのアドバイスを求めると、渡邊氏は穏やかな口調で語った。
「自分の大切にするべきことに真面目に取り組んだ方が良いです。結果がついてきます。目先の評価だけにとらわれず、良いと思うことを信じて取り組んだ方が良いです」
より具体的には、どこから始めれば良いのだろうか。
「まず、自分が本当に大事だと思うことを1つ決めて、評価を気にせずやってみることから始めてみてください。技術的な改善でも、チームの働きやすさでも何でもいい。小さなことでも、自分の判断を信じて行動してみる。それが積み重なって、結果的に良い成果につながるはずです」

技術的なスキルアップだけでなく、人としての成長を重視してほしいとも語る。
「芯がしっかりした、エンジニアとしてじゃなく人としての成長を大事にしてほしいですね。技術は交換可能だけど、あなた自身は交換不可能。だからこそ、自分に紐づくものを大切にしてほしい」
後編では、渡邊氏が考えるエンジニア組織づくりの哲学や、チームの雰囲気・文化への思い、そして今後の技術ビジョンについて詳しく探っていく。

/assets/images/21165365/original/3ff4f912-5858-4406-b3ee-8f29caf7faf7?1747810835)


/assets/images/21165365/original/3ff4f912-5858-4406-b3ee-8f29caf7faf7?1747810835)



/assets/images/21165365/original/3ff4f912-5858-4406-b3ee-8f29caf7faf7?1747810835)

