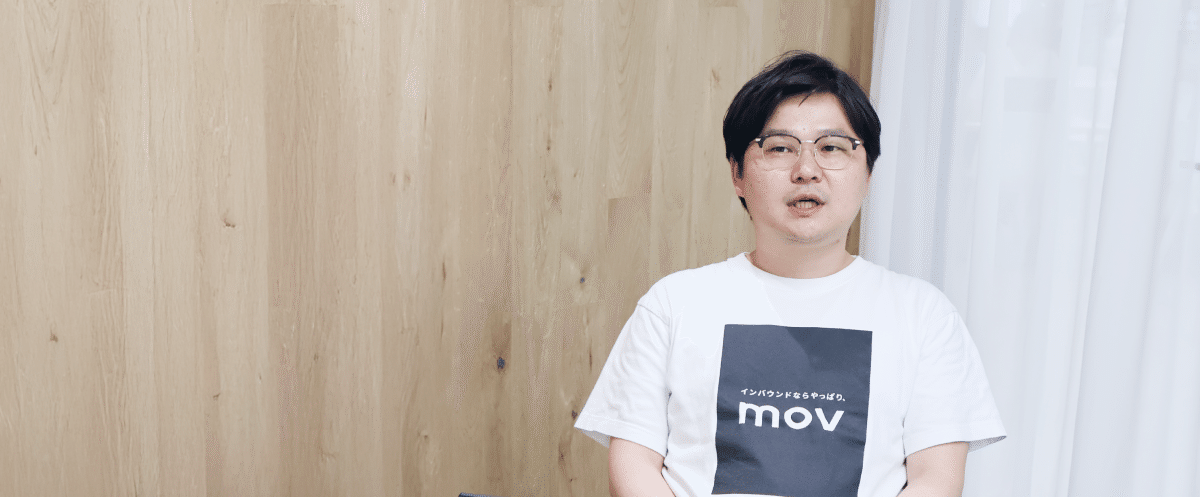- 海外PRディレクター
- カスタマーサクセス┃店舗DX
- Webエンジニア(Ruby)
- Other occupations (17)
- Development
- Business
- Other
SaaS企業の中でよくある悩みのひとつが、「BizとDevの分断」。
開発が多機能をつくっても事業成長に繋がらなかったり、Bizが望むものがなかなかプロダクトに反映されなかったり──。
そんな中、movでは現在CPO(Chief Product Officer:最高製品責任者)を置かず、事業責任者と開発責任者のふたり(Biz組織とDev組織)が“背中を預け合う”かたちでプロダクトを進化させてきました。
なぜその体制にしたのか。本当にうまく機能するのか。 そしてその結果、どんな変化が生まれているのか──。
今回は、movのSaaS事業「口コミコム」を支えるお二人に、その舞台裏を聞いていきます。
——まずは自己紹介をお願いします。
赤司:執行役員兼店舗支援事業部本部長の赤司です。過去の会社では、基幹のSaaS事業の事業責任者をやったり、新規事業の責任者、子会社やJVのボードメンバーも務めていました。2023年より執行役員としてmovに入社し、事業戦略の立案やプロダクトのグロース推進や新規事業開発、ビジネス組織全体のマネジメントを行い、movのSaaS事業「口コミコム」の全社的な売上最大化を担っています。
執行役員兼店舗支援事業部本部長 赤司
大薮:執行役員CTO兼プロダクト開発本部長の大薮です。2012年に起業してサービス立ち上げと開発に従事し、その後フリーランスを経て、2021年にmovへ入社しました。mov代表の渡邊は起業仲間でもあり、実は長い付き合いです。入社後は、店舗事業者を支援する「口コミコム」の開発にゼロイチから関わり、今に至ります。
執行役員CTO兼プロダクト開発本部長 大薮
ーー 一般的にはCPOが担う部分を、なぜ2人で分担する形にしたのでしょうか?
BizとDevの“背中を預け合う”という選択
赤司:まず前提として、SaaS業界の難易度が年々上がってきている背景があります。
2016年から2021年頃のSaaS業界は、現在と比べると市場がまだ成長途上で、競合もそれほど多くありませんでした。そのため、売上を伸ばす難易度は、今よりも低かったと考えられます。
その時代の事業責任者は、プロダクトに深く関与しなくても、売上を持続的に伸ばせうる可能性があったとも言えると思います。
しかし、ここ数年でSaaS業界は市場を拡大してマジョリティ化し、さらに今この瞬間は生成AIの登場により、AIの利活用をベースとした事業・プロダクトの再構築を図る必要がある中で、昔と比べて難易度が遥かに高くなってきています。今は、プロダクトを通して「どう価値を提供していくか」「どのような世界線にしていくのか」「最新のテクノロジーをどのように利活用し、価値最大限のレバレッジをスピード感を持ってかけられるか」などを思慮できないと勝てません。そして、この部分をCPOに一任するというより、自分自身(Biz側)もDev側も、プロダクトにコミットしなければならない。これがまず、私たちの前提にあると思っています。
大薮さんはエンジニアである前に、もともと起業家であり、プロダクトに対して同じ目線でコミットしてくれています。私自身も同じスタンスで、お互いプロダクトを中心に考える思考や目線があるのが大きく、この条件のうえで今の「背中を預け合う」体制が成り立っているんだと思います。
大薮:私の場合、過去に別事業で起業していた当時は「背中を預け合える関係」は構築できていませんでした。でも、movにはそれができる環境と仲間があった、というのも大きかったと思います。プロダクトや事業は、やっぱり一人では創ることはできません。今の体制は、自分の得意領域にフルコミットしつつ、相手を信頼し、強みを持つメンバーが同じスピード感で走って、より高い目標地点で合流できるーー、そんなイメージです。
例えば私はDev側ですが、背中を預け合える関係性でないと「Biz側は目標を達成できないかもしれない」「この案件が取れないかもしれない」といった不安や不確かな状態で進む場面が出てくると思うんです。そうなると、やはりお互いがベストを尽くせなくなるし、高い目標の達成も難しくなってしまう。だからこそ、信頼関係が大事だと思っています。この価値観は開発チームでも共有している部分です。
ーー「BizとDevの分断」はSaaS企業でよくある悩みですが、どのように信頼構築したのでしょうか?
体制の仕組みと信頼の構築
赤司:よくあるケースとして、Biz側がDev側に対して過剰な期待値やスピードを求めすぎた結果、分断が生まれてしまうことがあると思います。基本的に、私たちの場合は過度に何かを要求することは相互的にしていません。ただ一方でスタートアップだからこそ、顧客に対するアジリティ(迅速で柔軟な対応)も担保しなければいけない。個別の対応が必要なときには、各種調整をして、急な差し込みの意思決定を行うケースもあるのが現実です。そういった場面では、Dev側に急な変更や柔軟な対応をお願いすることも確かにあります。
しかしその点movでは、あらかじめ大きなロードマップ上でBizとDevの両サイドの意見や視点をすり合わせているので、よくあるような「分断」が起きにくいんだと思います。「顧客への価値提供最大化=売上最大化」という共通目標があり、目線が合っている。だからこそ、急な対応にも一定の許容と理解をもらっているのは、今の組織においてすごく大きな要素で、movのアドバンテージでもあると思います。
大薮:今の体制はプロダクトを中心に置いて「売上を最大化するためにどう動くか」が根幹にあります。開発サイドなので、当然、システムの技術的な安定性にも責任を持ってコミットしなければなりません。
ただ、それだけではなく、事業全体や顧客のことも常に意識しながら仕事をします。その姿勢をとても大事にしていて、それがDevの組織文化としてもしっかり根付いていると感じます。あくまで事業や顧客が第一。そこはBizとDevの共通認識だから、物事を進めるときに意見が割れることは少ないですね。
赤司:いま現在movでは、まだまだ顧客への提供価値の幅を広げて事業の拡大を図ることが最優先事項になっているフェーズで、Biz側の事業戦略に一定同意してもらったうえで開発を進めている状態なんです。
もし今後、優先事項が「サービスの保守や安定性を図る」というフェーズになったとすれば、また組織として今と違うアプローチに変わるかもしれません。あくまで今この瞬間は、事業拡大を図ることを優先するフェーズであるがゆえに、Biz側の方針に合わせてもらっている部分があります。
現状の目標に対して共通認識を持ち、突発的な差し込み依頼にも柔軟に対応してもらえるのは、非常にありがたく、事業を成長させやすいと感じています。Dev側が担保してくれる確実性が前提にあることで、意思決定もしやすく、まさに「背中を預け合う」関係性を築けているのだと思います。突発的な依頼や変更って、普通は嫌がられるものなので。そこは本当に大きな要素ですね。
大薮:突発的な差し込みって、エンジニアに限らず正直みんな嫌ですよね。でも、目指そうとしている目標に対して、全員が腹落ちできているからこそ、コンフリクトが起きないんだと思います。
大きなプロジェクトの急な変更などは、私からチームに話をすることもありますが、基本的に日々の業務においては、現場のBizとDevの各メンバーがやり取りしています。
ーープロダクト・事業の成長実感やチームの変化はありましたか?
“背中を預け合う”ことで得られた成果とは?
赤司:具体的な数字はここで示せませんが、定量的な部分だとチャーン率(解約率)の低さは保たれ、NRR(売上継続率)も伸びています。売上のトップラインも、かなりの角度をつけた成長ができている状態です。
大薮:スプリントレビュー(実施内容の共有と今後の方針検討)の取り組み1つとっても、Biz側とDev側の小さなPDCAサイクルの中で、意見や考えをすり合わせて確認しています。顧客への価値提供や解像度を上げるためのコミュニケーションがお互いできていて、無駄がなく、事業計画に沿ったプロダクト開発にトラクションがかかった状態がつくれています。だからこそ、それが定量的な成果にも現れているんじゃないかと思います。
ーー今あらためて課題だと感じていることはありますか?
SaaS is deadと言われる時代の転換点、変化の波にどう立ち向かう?
赤司:理想を言えば「もっと色々なことをスピード感をもってやるべきだ」と思っています。ありがたいことに、今のプロダクトは顧客の期待値に一定応えられていて、安定的に成果も出せている。でも、求めようと思えばもっとできることや、やりたいこともたくさんあります。
また、現在は明確に市場が転換期を迎え、生成AI・AIエージェントの利活用がベースとなるプロダクト・事業創り・運営の新たなルールブックを創っていく必要があると思っています。
今の組織能力とリソースにおける成果は一定の成果は出せていますが、人員が増えれば取り組めることの幅も広がり、特に重要視しているスピード感もさらに高められると考えています。例えば、プロダクトの価値を考える人や新規事業を考える人材がもっと増えれば、さらに違う世界が早期に見えてくると思いますね。
先ほども触れたように、SaaS業界全体の難易度が格段に上がっています。私たちは、1つの通過点としてIPOをめざしていますが、今は売上のトップラインだけじゃなく、利益を重視されるようになって、四半期ごとに成果を問われる世界線になっています。
さらにその中で生成AIやAIエージェントが登場して、SaaS業界での戦い方が、株式市場・テクノロジーの市況感も含めて桁違いに難しくなっていると感じます。これに対して、今の市場や競合環境、顧客のニーズの中でどう戦っていくかは、当然ながら難しい課題です。だからこそ、新しい組織能力や人材を増やすことは必要だと感じています。
大薮:数年前のSaaS業界は、ゲームルールでいえば今と比べてシンプルだったと思うんです。当時も複雑ではありましたが、一定のプレイブック(戦略やノウハウ)がありました。今は当たり前に複数のプロダクトを同時に展開する、マルチプロダクトやコンパウンドが求められたりと複雑化しています。
加えてそこに生成AIが登場したことで、これまで正解とされてきた物事や組織づくりも、根本的に考え直さなきゃいけない。生成AIの活用や社内定着化も、現在進めているところです。成果にコミットできるチーム体制はつくれていますが、これまでの常識にとらわれない組織やルールに変革していく必要があると思います。AIの力で事業やプロダクト、組織の能力にレバレッジをかけられるかどうかは、人に強く依存します。その観点でもやはり赤司さんが言うように、人材の重要性がさらに大きくなったと思います。
ーー今後めざしたい未来や、CPOのポジションを置く可能性について教えて下さい。
事業を次々と生み出す組織へ
赤司:まず、movの指針でもある「日本のポテンシャルを最大化する」という大きなテーマに対して、サービスやプロダクトを通じて価値を提供していくこと。そして、現在の市況や市場変化に対してアジリティを保ちつつ、スピード感のあるサービス開発・提供を続けていくことが、大前提にあります。
そのうえで、いま私や大薮さんがリーダーシップを持ってやっている部分を、PdM(プロダクトマネージャー)やPMM(プロダクトマーケティングマネージャー)やBizDev(ビジネスデベロップメント)を中心に、現場の組織においても、新しいプロダクトをスピード感を持って創っていける体制を構築できたらと考えています。今のサービスの延長線上であったり、ターゲットを変えたソリューションであったり、そんな新しい事業が次々に創れる複数の組織があるのは、将来的にあるべき姿かなと思っています。
大薮:アメーバ組織のような、独立したチームが複数あるイメージかもしれませんね。私たちがマネジメントする必要がない状態でも、PdMやPMM、Bizdevなどの現場駆動で意思決定できる状態が理想です。
今後、movがマルチプロダクトを進めるうえで、それぞれのプロダクト責任者としてCPOを置く可能性は十分にあり得ると思います。今現在は、口コミコムをメインに私たちが中心になって売上最大化に取り組んでいます。しかし今後は、周辺領域の事業に各責任者がいるような「事業CPO」を複数置いて、事業やプロダクトを創っていく体制をめざしたいですね。
ーー最後に、どんな人と働きたいですか?
事業・プロダクトを通して本質的な価値提供を
赤司:課題を解決して価値提供することが、私たちの基本的な仕事です。だから、ちゃんと思考できて、仮説が立てられる人がいいですね。逆に言うと、この部分を自分で考えられる人じゃないと、生成AI時代であることも含めて、これから先は厳しいかもしれません。
市場が目まぐるしく変わる中で、新しいルールをチームで手探りしながら創っていく必要があるからこそ、目線を合わせて、自分で考えてやれる人が必要だと感じます。
大薮:本当にその通りですね。プラスでいうと、熱量をしっかり持った人がいいなと思います。事業・プロダクト・顧客に向き合って、自分の意思で熱量を持って推進できる人が合っているかなと。
それと、これは少し手前味噌ですが、自分が一人のメンバーという目線で見た時に「こういうチームで働きたかった!」という組織や文化が実現できていると純粋に思っていて。無駄な労力に疲弊することなく、プロダクトや事業をどうしていくかにみんなフォーカスできていて、背中を預けられる、信頼し合える仲間がいます。成長できる環境でもあるし、経験者であれば、事業を引っ張って伸ばしていける土壌があるんじゃないでしょうか。
赤司:これまで申し上げた通り、SaaS事業を進化させ、生成AIやAIエージェントをベースとした新たな事業・プロダクトの再構築を行うことや新たに創造していくこと。そして持続的に成長率と利益率を担保していくこと。これらの新たな基準は大変難易度が高く、日々悪戦苦闘しておりますが、私たちはその中でも良い状態で事業と向き合い、成果を出し続けられています。
このmovの船に乗ってもらうことで、求めている働き方の理想像に一定見合った環境や仲間が揃っているんじゃないかと思います。事業を通して本質的な価値提供がしたい。同じ志を持ち、全員で実現できる組織や環境が、movには揃っていると自信を持っています。
ーーお二人ともありがとうございました!
全求人