外資系コンサルティングファームからベンチャー企業を経て、株式会社Modelistに入社した堀口紗矢香さん。Modelistでは執行役員として事業責任者を務め、新規プロダクトの企画や自社のマーケティング領域を担当しています。今回は堀口さんに、これまでのキャリアの変遷や、スタートアップ企業であるModelistでの経験、そしてAI活用との向き合い方について話を伺いました。
キャリアの変遷と転職の決断
──まずは、Modelistに入社する前のキャリアについて教えてください。
新卒でアクセンチュアに入社し、4年半ほど働きました。前半の2年間はITコンサルタントとして、お客様の部署に常駐しながら業務効率化のためのオペレーション改善やシステム導入のプロジェクトに携わることが多かったです。後半の2年間は営業マーケティング領域のDXコンサルや新規事業立案のプロジェクトに携わっていました。
私のキャリアの中で一番キーになるのは、ITコンサルタント時代に、ノーコーディングではありますが、お客様社内のナレッジデータベースをエンジニアでなくても操作できるようにするツールの要件定義から開発、導入まで一通り携わらせてもらったことです。ここでの経験が前職にも現在の業務にも活きています。
アクセンチュアの後は、ITスタートアップに転職しました。特にスタートアップに行きたいという強い思いがあったわけではなく、コンサルとして外からアドバイスする立場を離れ、事業会社で事業を推進する当事者として経験を積みたいと思ったからです。ここでもデータ関連の企画や、データ収集の自動化プロジェクト推進、さらには事業戦略などにも触れる機会がありました。
──規模の大きな組織から、どういった理由でModelistへの転職を決断されたのですか?
前職は入社時は100人程度の規模でした。スタートアップで働く中で、もっと0から1を創る環境に携わりたいという思いが強くなり、そこでModelistへの転職を決断しました。
実は入社前に業務委託として半年ほどModelistで仕事をしたのですが、転職を決めたのは業務委託を始めて2、3ヶ月後でした。委託業務の中で、自分が触れたアプリが世の中に出るという0から1のフェーズの経験ができたことや、目まぐるしく変化する環境を目の当たりにして、確かにスピード感の面では大変だろうなと思いつつも、間違いなく自分にとってよい経験になると感じました。0→1の事業開発を経験できるチャンスが目の前にあるので、乗るしかないと思い入社を決めました。
──Modelistでは一人目の社員として入社されたそうですね。
はい、そこも転職を決断する大きなポイントでした。私の性格として、一つのことの専門性を極めるというよりは、いろんなことを自分の目で見て、肌で感じることがしたいという思いがあったので、一人目として入社することでそれにより近づけると思いました。
──入社してみて、予想と違った点はありましたか?
スピード感や変化の激しさは想像以上でした。業務委託の時もそれなりに呉縞さん(代表)と会話していましたが、正社員になって働く時間が3〜4倍になると、Notionや業務環境が整っていく気持ちよさもある一方で、週ごとに作業環境がアップデートされていく、という変化の速さも予想をはるかに超えるものでした。
ビジネスの見え方の違い
──前職よりも「ビジネスの全体像が見える」と感じていると伺ったのですが、具体的にどのような点でそう感じますか?
一番は、情報が記録されていて、全部が可視化されている環境だからだと思います。本当の意味でオープンになっていて、隠されていることがない印象です。
コンサルの仕事はクライアントワークなので守秘義務の壁が大きく、他のプロジェクトがどうなっているかを知ろうとしても、ハードルが高かったんです。前職もオープンではありましたが、Modelistほど記録や情報が残っている環境ではなく、最初のうちは他部署の仕事内容がわからないことが多かったです。
Modelistでは人数が少ないこともありますが、隠れている情報が何もないし、直接自分に伝えられていなくても、Slackを検索したり見に行けば情報が見つかります。Notionに新しく情報が更新されたらわかるようになっているので、更新に気づいたら自然と読みに行ける環境になっています。
AIとツールの活用
──以前はAIが「使いにくいもの」と感じていたそうですが、Modelistで働く中でその認識はどう変わりましたか?
以前はAIの進化についての情報をニュースなどで見て、過度に期待しすぎていたところがあったと思います。「AIはすごい、何でもできる、もう人間はいらなくなる」という触れ込みが先行して、自分たちの業務をどう100%置き換えられるかにフォーカスしていました。
実際の業務を完全に置き換えるには精度が足りないとか、勝手なことを言ってしまうといった問題があり、「結局まだ使えないじゃん」という印象が強かったです。また、AIを使ったプロセスや情報をどう与えたらどういう結果が出るのかといった記録があまり残っておらず、プロンプトを試行錯誤した結果がナレッジになるという認識も薄かったので、出てくる結果だけを見て良い悪いを判断していました。
Modelistに来てからは、プロンプトも記録されていますし、「ここは人がやった」「ここはAIを使って、それを別のAIに渡した」といった情報が残っていて真似できる状態です。呉縞さんが営業で使っているものを私がプロダクトマネジメントの観点で使ってみるといったように、情報がオープンになっているからこそ、自分の業務に合わせた応用が効かせやすい環境です。また、業務量も多いので、AIを使わないと回らないという強制力もあり、AIとうまく共存できる環境だと感じています。
──IT経験者の視点から見て、ModelistのAI活用の特徴や独自性はどこにあると感じますか?
完全に業務を置き換えるのではなく、AIと共存する考え方が根付いています。AIを使う際もPerplexityで一般的な情報を調べて、それをNotionに残しておき、Modelistの情報と一般的な情報を組み合わせることで、より内容の濃いアウトプットが出せるというような作業を人間が指示している点が特徴的です。
AIの組み合わせ方も強みだと思います。作業を記録する際に「AIに聞いてみましょう」というボタンがNotionテンプレートに組み込まれていて、嫌でも目に入る環境になっているのでAIの活用が自然と身につきます。
──Notion、Slack、Miroなどが「三種の神器」と聞いていますが、普段はどのように業務で使っていますか?
IT経験者としてツールを使ってきた自覚はありましたが、そうは言えなくなってしまうほど、Modelistでのツールの活用レベルは深いと感じています。Notion、Miro、Slackの3つのツールは前職でも使っていましたが、前職では平均以上の80点くらいで活用できていたとすれば、もう追いつけないほどの120点、200点くらいの領域に来ている感覚があります。特にCRMのような多くのデータベースがこれほどしっかり意図がある状態で関連付けられていて、それらの動きがSlackに通知される環境も初めてですし、Miroのボードもこれほど多い環境は初めてです。前職ではどのツールも日常的に使っているのは一部の人だけという状況でしたが、Modelistでは全員がこれらのツールを毎日、深く使いこなしているのが大きな違いだと思います。
学びの文化とコミュニケーション
──Modelistでは「失敗が組織の資産になる」という文化があると聞きましたが、具体的に感じることはありますか?
例えば、何か作業がやりづらい、同じ作業を何度もやっているなと感じることがあると、次の週には誰かが改善しているか、そもそもやらなくて良くなっていることが多いです。
具体的には、プロダクトのUI/UXデザインを検討する際に「参考デザインを調べて貼り付けてください」というフィードバックがありました。しかし、次の週にはそれが仕組み化されて、ボタンを押すだけで参考素材を探せるサイトに飛べるようになっていたりします。何回も同じ内容のフィードバックは絶対になく、自然と改善できる環境が整っています。
印象的だったのは、呉縞さんとある会議の内容を確認するために動画を探した時のことです。動画が適切に保存されておらず、議事録も不十分だったため、結局探したい情報を見つけることができませんでした。その時に「記録をしっかり残すことや情報をオープンに共有することは大事だよね」とその重要性を再認識しました。これは一例ですが、日々の小さい失敗を通じて、組織全体で記録の大切さを学び、カルチャーとして定着していると感じます。
──前職と比較して、コミュニケーションやフィードバックの質・量に違いを感じますか?
コミュニケーションの総量としては前職とあまり差はないと思いますが、前提となる情報が各ツールに残っているので、理解の深さが違います。直接コミュニケーションしていなくても、その人が考えていることや状態がわかりやすい環境です。
フィードバックについても、作った資料に対して「ここはこうした方がいいよ」という断片的なアドバイスではなく、「どういう考えでそうしたのか」を聞かれたり、「こういう考え方があるから」という理由まで含めて教えてもらえることが多いです。1つのフィードバックから得られるものが非常に多いと感じています。
──呉縞さんのマネジメントスタイルで、特に印象に残っている言葉や出来事はありますか?
「働く皆が楽しく働ければいい」という言葉が一番印象に残っています。仕事はしんどいものだという意見もよく聞きますし、実際、業務量も多くて大変ではあるのですが、Modelistでは根底に「みんなが楽しく働けるといいよね」という考えがあるのを実感しています。言葉だけでなく、私たちが開発しているアプリも楽しく業務効率を上げていけるものであり、その思想がプロダクトの随所に反映されています。このような一貫性があることで大きな安心感を得られています。
バウンダリースパニングと成長機会
──Modelistで経験する「バウンダリースパニング※」について、特に印象的だった出会いや気づきを教えてください。
前職では外部の人と話す機会がほとんどなく、社内の人とだけ話すことが多かったのですが、Modelistではお客様とのミーティングなど、これまで関わりのなかった領域の人と話す機会が格段に増えました。
月に一度社外ゲストを勉強会講師として招く「Spanning Day」があるのですが、最近サーチファンドについてのお話を聞く機会があり、全く知らない分野でしたが非常に刺激になりました。直接自分の業務に関わるわけではない情報でも、その後、日常でスマホなどで見る広告や情報が目にとまる回数が増えるようになりました。かつては「読んでもわからないだろう」と思って閉じていたような情報も、実際に人から話を聞いた経験があることで、よりインプットがしやすく、これまでより深く理解できるようになりました。これがどんどん増えていくのは楽しみです。
※ハーバード・ビジネス・スクールのMichael L. Tushman教授が1977年に提唱。組織内外の異なる領域や専門分野をつなぎ、新しいアイデアや解決策を生み出すために橋渡しの役割を果たす機能や活動
──副業をされているそうですが、外部の人と仕事をすることでModelistでの学びが活かされることはありますか?
一つは社外でもツールを使う際に「記録する」というマインドを忘れずに、自分が得た知識が組織に残るようにしています。それだけでも評価されることは多く、「こういうマインドが組織にいい影響を与えるんだな」と実感できます。
逆に、Modelistの研修やお客さまの組織の課題を見ていると、バウンダリースパニングの難しさも感じますし、自分たちの事業の意義も強く感じます。また、Modelistはまだ小さい会社なので、規模の大きい企業で副業をすると、将来の成長に向けた動き方を先取りして見られるような面白さもあります。
将来展望
──「事業責任者」としてプロダクト企画やマーケティングに関わるという経験が、今後のキャリアにどのように役立つと考えていますか?
事業全体を見ながら意思決定し、複数の事業間のシナジーを考えるという経験は、どこに行っても間違いなく役立つと思います。現在のフェーズでは、マーケティングも企画もPM(プロダクトマネージャー)もCSも全部やらなければならないという状況で、実務として経験を積めるのは大きな価値があります。
将来的に規模が大きくなれば、専門性のあるマーケティング担当やCS担当が増えていくと思いますが、そういう方々と一緒に仕事をするにあたって、現場がわからない事業責任者では、組織として事業を動かすのが難しくなると考えています。私は「各部門の業務を理解している人」でありたいので、実務をこなした経験があり、それが組織のナレッジとして溜まっている状態は非常に役立つと考えています。
──スタートアップの初期フェーズに参加した経験から、特に価値があると感じていることは何ですか?
何でも新規作成という状態なので、プロダクトができた背景やシステム導入の経緯などにすべて関わっています。例えば、CRM導入でも細かい設定の苦労や、アプリをリリースする際のChrome Webストアでの住所設定の問題(代表の自宅の住所が表示されてしまった!)など、表には出てこない苦労を実体験しています。そういった「実は大変だけど、誰にも語られないこと」が体験でき、しかもその過程が記録として残っているので、他の人が同じことをする際に困らないようになっています。いつか誰かの役に立つという実感を持ちながら仕事ができるのは大きいですね。
キャリアチェンジを考えている方へのメッセージ
──最後に、同じようにキャリアチェンジを考えているIT業界の方へのメッセージをお願いします。
IT業界であれ何であれ、どの業界と比較しても間違いなく時代の最先端の仕事ができ、業務効率や生産性も最先端の働き方ができるのは大きな魅力だと思います。規模がまだ小さいからこそできることも多いですし、確かに大変ではありますが、私は飛び込んで今のところ後悔はしていません。
これからAIなどの技術で時代がめまぐるしく変わっていく中で、置いていかれないためには、変化にキャッチアップせざるを得ない環境というのはぴったりだと思います。置いていかれないためには多少飛び込むことも大事かなと感じているので、好奇心旺盛で、飛び込んでみたい、やってみたいという方々と、楽しく(時にはひーひー言いながら)働ければと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
現在私たちは、プロダクト開発やマーケティングの強化に向けて採用を行っています✨
少しでも興味を持っていただけたら、まずは面談の機会をいただけたら嬉しいです。
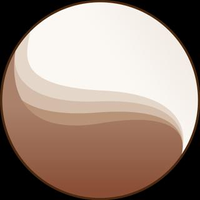


/assets/images/20928012/original/ae04bcc0-a1fc-4d1a-985c-8042d185a977?1744941943)

/assets/images/20928012/original/ae04bcc0-a1fc-4d1a-985c-8042d185a977?1744941943)

