このたびメディフォンは、元メルカリ執行役員Group CTOの若狹建さんを社外CTOとして迎えました。(社外CTO就任に関するプレスリリースはこちら:@@@)
プロダクトづくりに向き合い続けてきた当社にとって、今回の新体制は大きな転換点となります。
ではなぜ今このタイミングなのか──その背景や狙いを、CEO・澤田さん、社外CTO・若狹さん、創業メンバーでありチーフエンジニア・田畑さんの3名が率直に語り合いました。
経営から開発組織を強化し、新しいフェーズへ踏み出すメディフォンの「今」をお届けします。
目次
なぜ今、開発体制を変えるのか
出会いと信頼のルーツ
新体制の狙いと役割分担
メディフォンの未来像──開発組織がもたらす事業の進化
変化の中心に「エンジニアの力」を
なぜ今、開発体制を変えるのか
澤田:
11月14日に発表したアフラック様との業務提携(プレスリリースはこちら)を契機に、当社では開発体制の大幅な刷新を進めています。背景にあるのは、事業の着実な成長と、私たちの強みである“開発力”をさらに市場で発揮し続けるための構造的な進化の必要性です。
当社の狙う市場を見ても、自社でプロダクトを内製できている企業は限られており、最終的に市場で勝ち残るのは、自分たちの手でプロダクトを磨き続けられる組織だと信じています。今、私たちが次のフェーズに進むのは、極めて自然であり、必然だと判断しました!
若狹:
いわゆる「プロダクトレッドグロース(PLG)」を選んだという点で、メディフォンの戦略は一貫しています。事業の中心にプロダクトを据え、その力で市場を切り拓くという姿勢の表れですね。

出会いと信頼のルーツ
澤田:
若狹さんとの出会いですが、元Googleというのが3人の共通点です。私は在籍期間がお2人と2年ほどかぶっているんですが、違う事業部にいたため若狹さんとはあまり接点がなく。2人は、Google時代から面識があったんですよね。
田畑:
はい、直接同じプロダクトを担当していたわけではありませんが、当時の東京オフィスは規模も小さく、自然と顔見知りの関係でした。
澤田:
田畑さんは本当に、人徳のある方です。彼が紹介してくれる方々は皆、優秀なのはもちろん、かつ人間的にも温かみを持った方ばかりなんですよ。
若狹:
田畑さんは、まさに“エンジニアらしさ”を体現している方だと思います。技術者としての信頼を自然と集め、共に働く仲間として心から信頼できる。
澤田:
田畑さんが若狹さんをオフィスに連れてきてくださったときのことを、今でも鮮明に覚えています。初対面の瞬間から「この方は間違いなくデキる方だ!」と感じました。穏やかな語り口の中にもキレ味のよさが尋常ではなく、そのギャップに強い印象を受けたのを覚えています。
若狹:
ありがとうございます(笑)。もともとは開発現場で手を動かすことが好きな、田畑さんほどではなかった(笑)にせよ、いわゆる“職人肌”のエンジニアでしたので、特に非エンジニアの方々とのコミュニケーションが得意な方ではありませんでした。特にGoogleを離れてからは、自然とマネジメントを任される機会が増え、たとえばメルカリ在籍時には、エグゼクティブコーチの支援や各種トレーニングを受ける機会もあり、そうした積み重ねが今の自分につながっているのかもしれませんね。
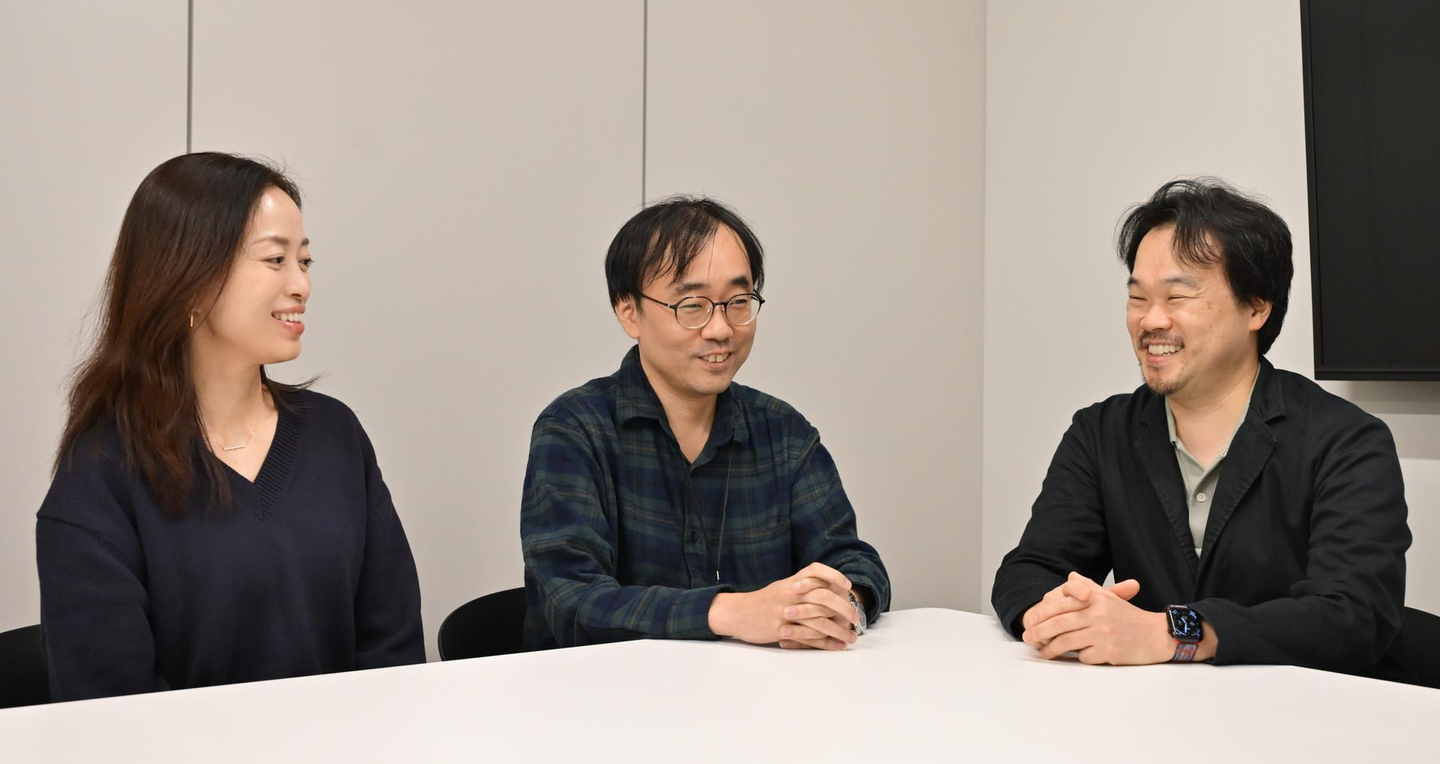
新体制の狙いと役割分担
澤田:
メディフォンのプロダクト「mediPhone(メディフォン)」「mediment(メディメント)」は、すべて田畑さんが中心となって構築してきたものです。創業当初は、まだ「医療通訳」という概念すら浸透しておらず、ビジョンだけを頼りに形にしていった。そのゼロイチの力こそ、田畑さんが持つ創業家としての圧倒的な価値だと感じています。
田畑:
私自身のこれまでの価値は、「プロダクトとはこうして作るものだ」という規範を示すことだったと思っています。コーディングの基準から品質管理、リスクの取り方、そしてチームの持続性を支える日々の細やかな判断まで、実践を通じて示してきました。
一方で、組織の拡大や評価制度の設計といった側面は得意とは言えず、今回このように役割を明確に分ける判断は非常に良い選択だと感じています。今後も「プロダクトに責任を持つ立場」として、現場に深く関わっていきます。
澤田:
事業の成長が進む中で、次のフェーズを見据えた「新たな開発体制」が不可欠だと判断しました。そこで、今回大きな転換を図るにあたり、若狹さんに「共にこの体制を支えてほしい」とお願いした次第です。
若狹:
私は“社外CTO”という立場ですが、実務的な支援を通じて、メンバーの皆さんが本来の力を発揮できる環境を整えることが、最大の使命だと考えています。
目指したいのは、「事業の成長と、自分自身の成長を、ここで働く誰もが実感できるプロダクト開発組織」です。
変革全体を通して目指すのは、プロダクト開発組織のケイパビリティに、いい意味で『余力』を持たせることです。日々のタスクに追われるだけでなく、事業サイドをはじめとするステークホルダーと深く連携し、お互いをリスペクトしながら価値創出するための時間と情熱が欠かせません。
澤田:
その『余力』を生み出すために、取り組んでいる「4つのポイント」について、説明いただけますか?
若狹:
まず1点目は採用戦略のアップデートです。生成AI時代にふさわしい少数精鋭のチームを創る上で求める人物像を明確にし、ジョブディスクリプションを刷新します。
次に2点目は評価・報酬制度の整備です。キャリアの道筋を明確にするグレード定義を策定し、会社の成長とメンバーの貢献と成長がリンクするような評価・報酬の仕組みを制度化します。
3点目はプロダクト開発プロセスの強化です。なぜやるのか (why) を明確に可視化し、価値創出ならびに事業成果 (outcome) を最大化するため、プロダクトのバックログを常に健全に保ち、PRD(プロダクト要求仕様書)に基づいた開発プロセスを徹底するなど、基本となる仕組みを整えます。
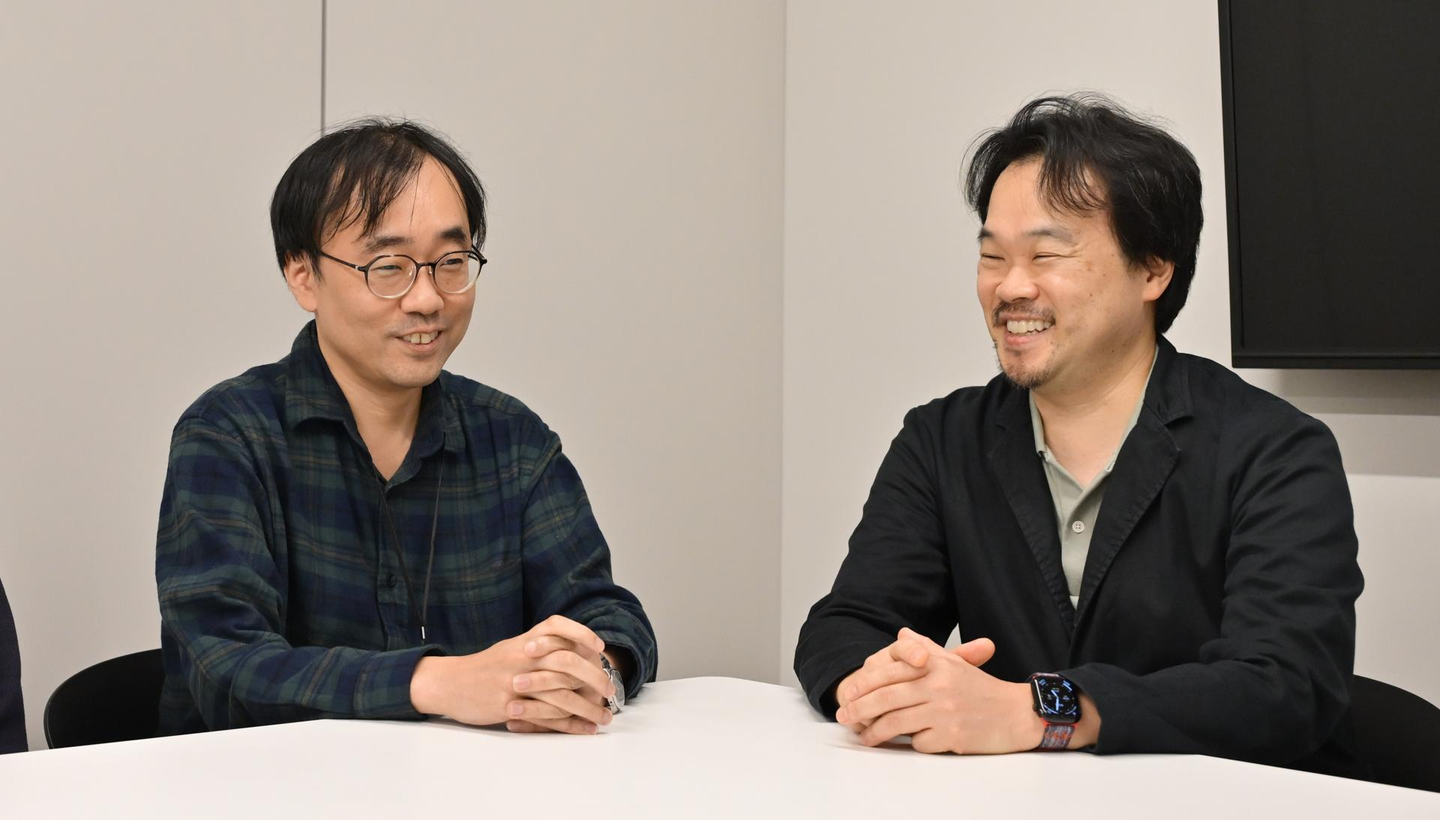
澤田:
まさに、今だからこそ必要な整備ですね。
若狹:
そして4点目は、これらの取り組みすべてを下支えするHR体制の強化です。採用のプロフェッショナルであるTA(タレント・アクイジション)や、メンバーと組織の成長に伴走するHRBP(HRビジネスパートナー)といった役割を明確化し、専門性の高い支援体制を築いていきます。
私が目指すのは、短期的な成果を追うことではなく、継続的に素晴らしいプロダクトが生まれ、また改善され、エンジニアが成長し続けられる「土壌」を創り上げる支援に全力を注ぎ、未来のリーダーへとバトンを渡すことです。
澤田:
私たちはこれまでも、「プロダクトを通じて社会を変える」というアプローチを一貫して追求してきました。今回の取り組みも、その延長線上にあるものです。本気で社会にインパクトを与えていくために、こうしたアグレッシブな戦略を選ぶことに、迷いはありません。
若狹:
まさに、メディフォンが次のフェーズに入った証だと思います。今の時代は「プロダクトが事業を牽引する」フェーズにあると強く感じています。開発はもはや事業のサポート役ではなく、事業の先頭を走る存在。そうした前提に立って、今後も全力で支援していきます。
メディフォンの未来像──開発組織がもたらす事業の進化
若狹:
開発組織への投資は、プロダクト品質の維持・向上という観点からも非常に重要です。品質確保や不具合対応のために過剰なリソースを投入し続ける状態が常態化すると、開発スピードや事業の拡張性を損なう恐れがあります。
これを回避するためには、品質を標準化・自律化できるような組織的な仕組みづくりと、それを支える継続的な投資が不可欠です。
田畑:
これまでは「事業が成立するかどうか」そのものが最大のリスクでした。資金面の制約や市場の反応など、“生存”そのものに直結するリスクが中心だったと思います。現在はそうしたフェーズを脱しつつあり、「ユーザーの期待に応えること」や「社内の健全な環境を保つこと」、さらには「機会損失を防ぐこと」といった、より日常的で複合的なリスク管理が求められる段階に入っていると感じています。

若狹:
まさに、かつての“サバイブモード”から脱し、今は“成長を選び取るモード”へと移行するタイミングにあります。組織が成長を目指す以上、一定のリスクをとる必要がある。そのバランスをとるためにも、今整えつつある体制や環境は重要な基盤ですよね。
澤田:
私たちは今、明確にグロースフェーズに突入しています。目指すのは、単なる事業規模の拡大ではなく、組織の「成熟度」の向上です。これは開発組織に限らず、ビジネスサイドを含む全社的な課題です。
プロダクトはすでに多くのユーザーに支持いただき、実績も積み上がってきています。今後はEAP(従業員支援プログラム)としての領域展開を含め、より一人ひとりに深く価値を届けられるよう進化させていきます。その実現には、開発にかけてきた熱量と同等のエネルギーを、組織そのものの構築と成熟にも注がなければなりません。
若狹:
AIが当たり前の時代となった今でも、優れたエンジニアの重要性はむしろ高まっています。技術が進化しても、「誰が」「どのような設計思想で」それを扱うかが、依然として競争優位を左右するのです。
AIを活用すること自体は、もはや前提条件の1つにすぎません。真の差別化を生むのは、本質的なエンジニアリングを理解し、その上でAIを使いこなせる人材の存在です。開発組織としての強さを維持・拡張していくためには、こうした人材を見極め、育てていく視点が不可欠です。
変化の中心に「エンジニアの力」を
若狹:
「mediPhone」と「mediment」は、すでに社会課題を解決し続け、確かな価値を提供しているプロダクトです。PMFを達成したスタートアップとして稀有な存在であり、“プロダクトで語る”という実直な姿勢に、私は強い敬意を抱いているんです。
誠実で落ち着いた組織カルチャーも特徴で、スタートアップにありがちな派手さよりも、メディフォンは地に足のついた感じがありますよね。
澤田:
私はプロダクトや事業に、その裏にある「人相」がにじみ出ると考えているんですよ。どんな価値観で、どんな姿勢で取り組んできたのか。それが、今のメディフォンの「顔」を形作っているのだと思います。
私たちは本当にやりたいことを追求し続けてきました。医療通訳や健康経営の領域で、業界そのものの健全な成長に責任を持つ存在でありたい。その思いが、これまでの行動指針となってきました。
若狹:
一方で、今のメディフォンには非連続な成長を見据えた明確な意志があります。そのためには、価値観を守りながらもさらに認知を広げていく必要がありますよね。営業や採用にも直結する発信力を、開発組織としても意識するフェーズに入っています。
澤田:
これまでの私たちは、常に「正攻法」で歩んできました。迷ったら王道を行く。その姿勢が功を奏し、ここまで自然な形で成長してきました。
田畑:
プロダクトも、組織も、足場は整いつつあります。だからこそ、今このタイミングで変化していきたい。開発体制の刷新は、その第一歩になると信じています。
若狹:
まさにそれは、違うゲームに挑戦するという明確な経営判断だと思っています。今のままでも成長はできるかもしれませんが、スタートアップとして非連続な成長に挑む。その決断に私は深く共感しています。
そして何より大切にしたいのは、これまでメディフォンを支えてきた皆さんの貢献です。これからの挑戦の中でも、それは変わらず大切にされるべき価値だと思います。
その上で、新しいゲームに一緒に参加してくれる仲間を求めていきたい。そして今いるメンバーにも、「次のステージへ向かうんだ」というメッセージを伝えながら、意識を少しずつアップデートしていく。その過程を、私も伴走者として支えていきます!
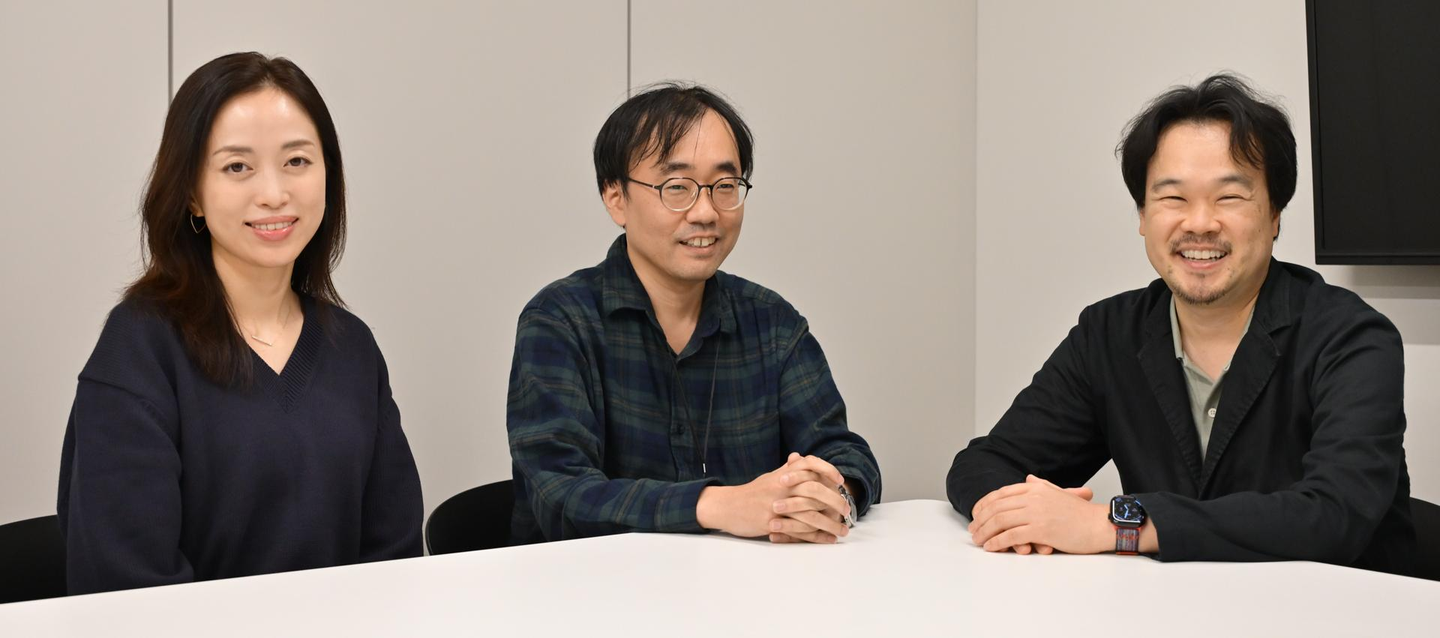
3名の対話からは、技術と組織づくりの双方に本気で向き合う姿勢と、次のステージへ挑戦する熱量がにじみ出ていました。
メディフォンの開発組織は、これまで以上に“プロダクトで価値を届ける”ことに真摯に向き合っていきます!

/assets/images/22280171/original/1f62ff71-f47d-4867-9e24-f389fccf8cb7?1760583144)


/assets/images/22280171/original/1f62ff71-f47d-4867-9e24-f389fccf8cb7?1760583144)
/assets/images/22280171/original/1f62ff71-f47d-4867-9e24-f389fccf8cb7?1760583144)

