自分で立ち上げた会社の代表でありながら、プロダクトマネージャーとして福利厚生サービスを提供するLeafea(リーフィ)に参画し2年になる中原陸さん。事業の面白さに目覚めた大学の起業部時代から、Leafeaに加わり、福利厚生で理想の社会を目指すようになるまでのお話しを伺いました。
目次
◆ 世の中をつくるデザインに出会う
◆ きっかけはマイナスのイメージ体験
◆ チームの源泉は、代表の持つ突破力
◆ 社会を変えるかもしれない福利厚生
世の中をつくるデザインに出会う
新卒で入社した会社では、エンジニアとしてホテルや旅行の予約、比較サイトの開発やディレクションに携わっていた中原さん。しかし、エンジニアというよりは、根底には事業をつくりたいとか、世の中に面白くて使ってもらえるものをつくりたいという思いがあったという。そのきっかけは大学の起業部時代に遡る。
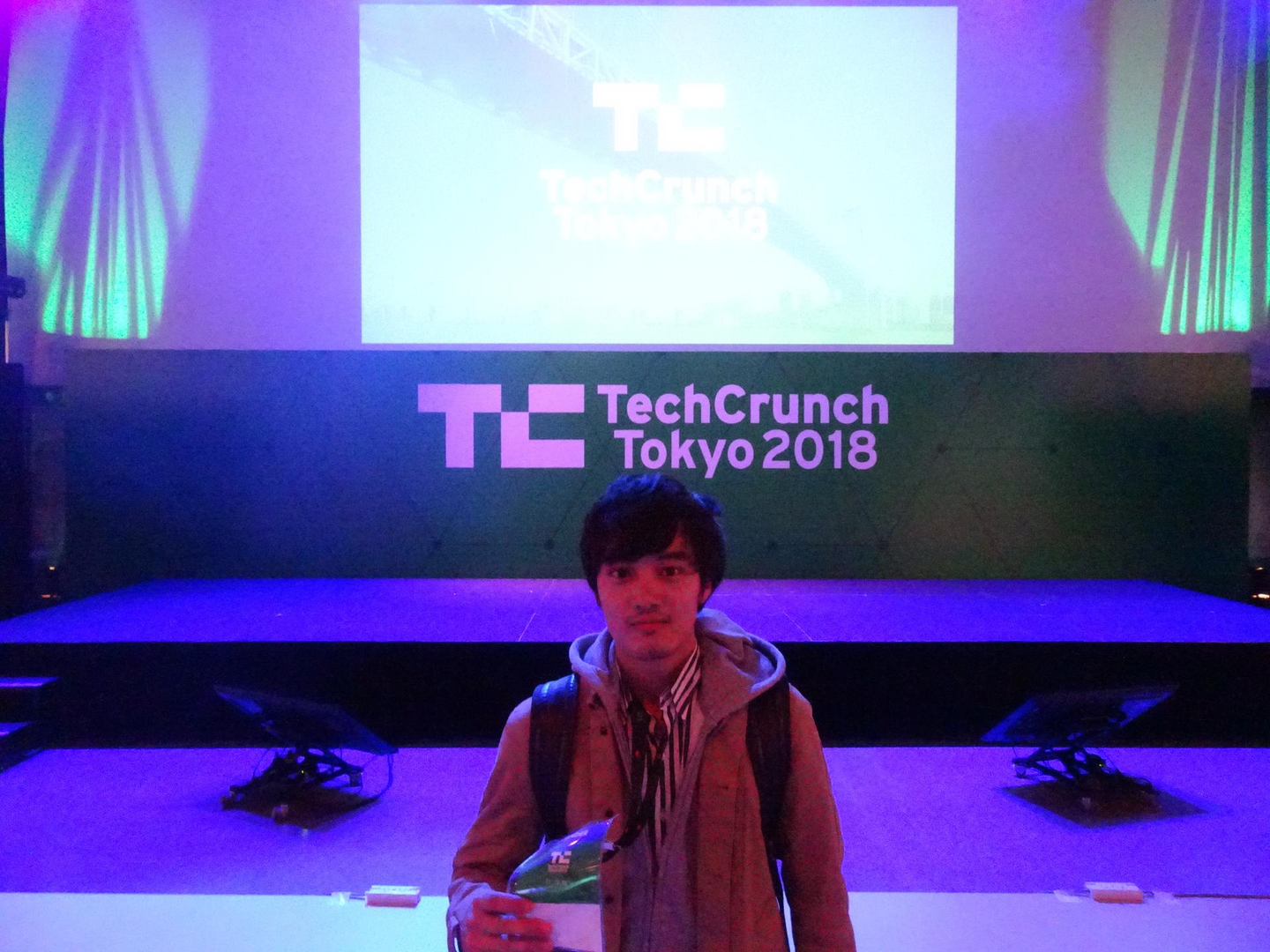
中原 「事業をつくりたいと思うようになったのには大学の学部がかなり影響しています。理系のデザイン経営工学という学部なんですが、僕は最初インテリアや建築のデザインをしたくて入ったんです。でも実際は全く違って、デザイン経営というある種、世の中をつくっていくための広義のデザイン学を学ぶ学部だったんです。事業やマネジメント、プロダクト、組織のデザインなどをうまく組み合わせて、世の中に新しい価値を生み出していこうというちょっと尖った学部だったんです。そこで価値観が変わったというか、こういうデザインってすなわち事業なんだと、事業とか会社って全部デザインされていて、そういうデザインも面白いなと感じました」
大学時代、起業部の立ち上げメンバーとしてプロダクトをつくっていく中で、圧倒的なスキル不足と、伸びている企業がどういうエコシステムで回っているのかを全く理解できていないという課題にぶつかる。
中原 「IT 事業を起こすには、ソフトウェアをつくる上での開発やプログラミングのスキルがないと、事業をつくっていくうえで解像度が低いというか、絵空事みたいで、じゃあそれ誰がつくるの? というようなフィードバックをよくもらっていました。当時はもちろんつくれませんし、つくれる人を採用するという感覚もなかったので、自分でやるしかなくつくり始めたのがエンジニアになるきっかけです。プロダクトをつくっても、それをどういう風にお客様に売っていくのか、どういう風に顧客の課題を見つけて事業を立ち上げ継続させていくのかというビジネス的なところも理解できていませんでした」
そこで、事業を伸ばしている会社に入り学びたいと思い、プロダクトのことを全て学ばせてもらえるような環境を探し、大学卒業後にエンジニアとして1社目の会社である株式会社じげんへ入社する。そこでソフトウェアのスキルとして広範な領域を学び、2年後には自分の会社を立ち上げる。そしてエンジニアからプロダクトマネージャーへ。
中原 「プロダクトマネージャーの仕事は、会社が持つプロダクトの方向性を決めて、そのプロダクトの仕様や、どういう見た目にするのか、お客様のどんな課題を解決するのか、それによってどんな成果が得られるのかなどを、色々な関係者の意見やマーケット感、顧客情報などを見て設計し、実行する際のマネジメントをすることが主な仕事です。
最初はエンジニアとして開発に携わり、初期の立ち上げはそれで軌道に乗れましたが、今後、世の中により影響を与えるプロダクトをつくっていこうとすると、自分よりも開発に最適な人と組織をつくる方がいいなと思い、より事業側にシフトしていきました。単に物をつくるというよりは、物を含めた組織や、顧客価値や、収益性といったところまで観点を広げた上でのアウトプットというか、完成系をつくっていきたいと思っています」
その後、福利厚生サービスを提供するLeafeaから声を掛けられ仲間に加わることに。入社の決めてを中原さんは次のように語る。
中原 「僕の場合は転職という形ではなく、自分で会社をやりつつもよりLeafea社に入ってコミットしないかと声を掛けていただきました。自分の会社でやっていることよりも圧倒的に成長できるし、事業も組織も成長していく環境に身を置けるタイミングはあまりないと思いました。かつ、自分の力でつくっていけるタイミングでもありました。全て整ったうえで入りたい人もいると思いますが、これから伸びていくという初期のタイミングで入れる確率を考えた時、すごくレアな機会だし、シンプルに代表や他のメンバーのコミット具合を見ていて一緒にやりきれそうだなと感じました」
きっかけはマイナスのイメージ体験
新卒で入った会社では、福利厚生サービスを提供される側だった。その時の使いづらかった体験も今の会社の事業に魅力を感じるきっかけとなる。
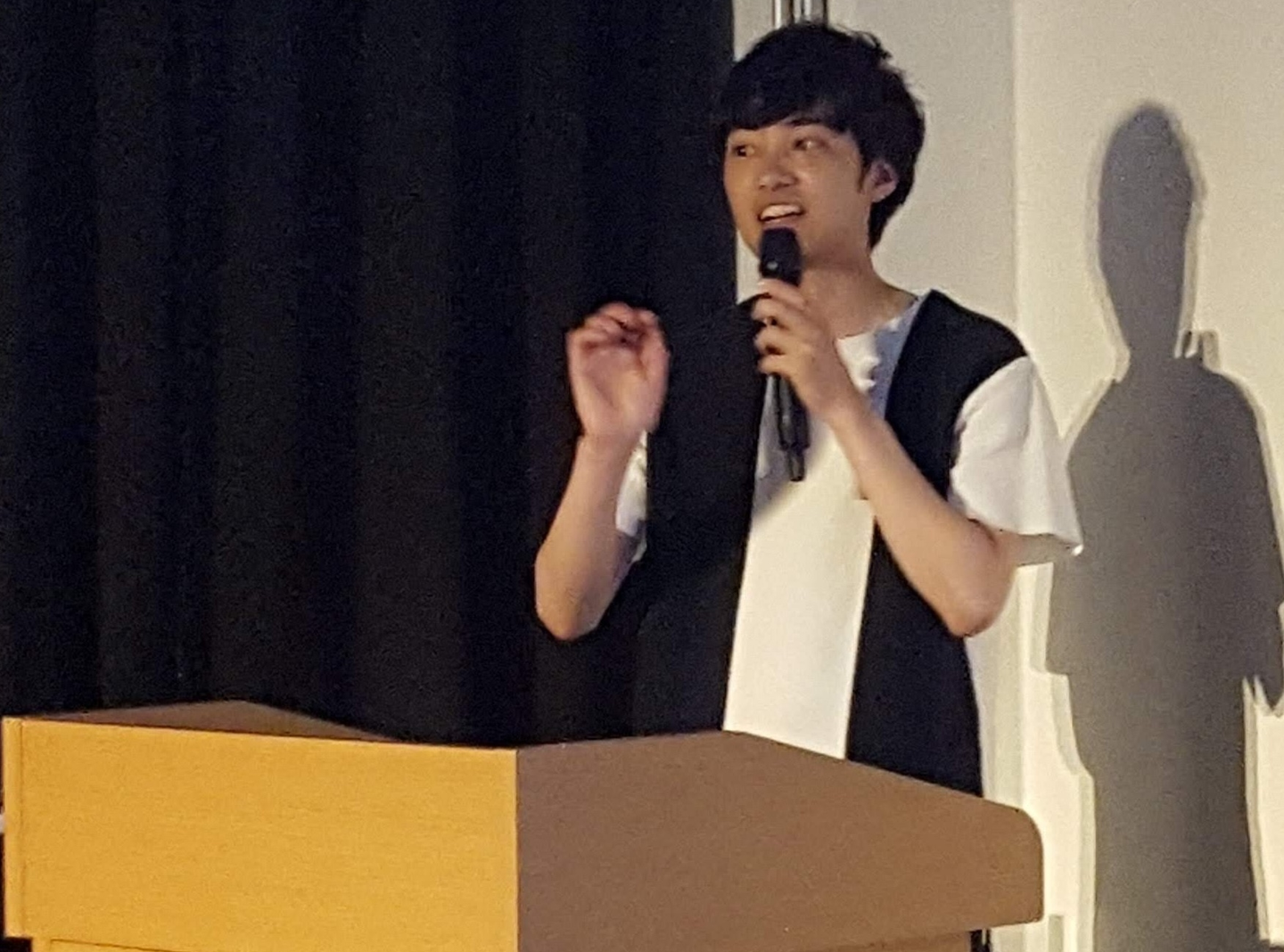
中原「提供される側だった前職の会社員時代には使いづらいし、あまり使えなかったという印象でした。これをスマホアプリなどでより使いやすい形に作り直して一気に顧客満足度の高いものをつくっていこうという思考がすごく面白いと思ったし可能性を感じました。とはいえ使いづらい理由もたくさんあって、従業員からすると急に使ってくださいと言われても欲しくない人もいると思うんです。構造として難易度は高いものの、めちゃいいねとか、会社に導入して良かったと思われるようなものをつくる可能性に挑戦できたらすごくいいなと思えてワクワクしました。
福利厚生というプロダクトだけ聞くと、割引きや優待が載っていて、様々な生活シーンで支出を下げるというようなものをイメージされると思うんですが、従業員さんの様々なデータや動きといったものをお預かりしているので、その方により最適な案内ができたり、働き方の提案や健康面を見ることもできます。その仕組みを使って地方の会社を盛り上げたり、エンゲージメントを上げたり、1つのプラットフォームとして見た時のプロダクトが広がる可能性や、さまざまな課題を解決していけるというところが面白いと感じました」
実際中に入ってみて、仕事の魅力や楽しさ、達成感はどんなところにあったのだろう?
中原 「成長環境の中にいれて、さまざまな事業が伸びていくのを肌で感じることができます。パートナーさんの福利厚生アプリをたくさんつくらせていただくので、その会社のことを理解したり、大きな会社の看板でプロダクトを出させていただいたりする経験や達成感があって、それが実際にワークして収益が生まれてきてるところをかなりの数、連続的にやっていくところは他では味えないスリルや成長性を間近で感じれます」
中原さんは現在、プロダクトマネージャーとしてプロダクトの要件定義や仕様作成、プロダクトをどういう風に持っていくのか、プロダクトのロードマップや、プロダクトビジョンをつくり、実際に現場や開発メンバー、営業チームとプロジェクト組成し、推進するためのマネジメントなどを行う。特殊なのは、開発プロダクトチームでもお客様とコミュニケーションを取る機会が多い事業体であること。お客様とコミュニケーションを取りながら、どういったプロダクトをつくっていけばいいのか、要望を聞いたり提案をしたりする。
最初はエンジニアだった中原さんは、その後プロダクトマネージャーになり、お客様とのやり取りが増える中で成長できたという。
中原「エンジニアとしてそこまでお客様と関わることがなかったので、最初はどうしても少しワーカ的な思想で、依頼されたものをそのままつくったり、言われたことを解決するので精一杯だったんです。それがもう少し全体感を見て、それが本当に必要なのか、事業的に ROI が合うのか、本当に実現可能なのか、どれくらいの時間軸だったらできるのかなど、多眼的視点で、本当にそのプロダクトや要望を引き受けるのかという視点が広がっていったのは変化でもあり面白さでもあります」
チームの源泉は、代表の持つ突破力
一緒に働くチームの雰囲気をとにかく頑張るチームという中原さん。それは、代表の思いや経験が文化になっていると話す。そして、皆がこの会社では自分がやりたいことを実現できると確信していると。

中原 「経済的に成功したいとか、自分の叶えたい世界をつくりたいとか、入ってくる時にはそれぞれにいろんな目的はあると思うんですが、このプロダクトだったらそれが叶えられそうだからみんなで頑張ってつくろうという足並みや方向性は揃っていると思います。この会社やチームの中では、自分がやりたいことを実現できるし、自分でつくっていけるという面白さや確信があります。
代表のすごいところは簡単に言うと突破力みたいなところです。これがチームの源泉だと思います。やりたいと思ったことを達成するために、色々画策したり必要なことをちゃんと把握したりしてしっかりやり切っていく、かつ諦めない。当たり前のことかもしれないんですが、全体把握と実行と忍耐。この三つが両輪というか回って、これはさすがに難しいだろうとか、これはなかなかきついという場面でも、蓋を開けてみるとうまくいってるようなことを代表が率先してやっているところは尊敬できます」
そんな代表の突破力は社内に伝染し、何事にも忍耐強く、諦めず、徹底的に真摯に取り組むスタッフを尊敬しているし、刺激を受けるという中原さん。代表も含め、上下関係はなくフラットな社内では、必要なことがあれば誰もが声をあげ議論する。中原さんが声をあげて通ったことはあるのだろうか?
中原 「初期の頃はメンバーが少なかったこともあって、プロダクトの方向性などでは必ずしも代表やチームがしたい方向性ではない方がいいと思うこともありました。そういった場合は、例えば優先順位を切り替える話をしたり、誰がどういうロールをするかとか、組織的な課題をキャッチしてそれを解決できるように間接的に裏側で動いたりもしました。でも全員がそうですね」
今後チャレンジしたいことを聞いてみると、三つあるという中原さん。それは、福利厚生でナンバーワンのプロダクトをつくること、それを全国に広げること、働く人が報われる社会をつくること。
中原 「まず一つは従業員さんを喜ばせる福利厚生でナンバーワンのプロダクトをつくることです。福利厚生というプロダクトは急に降ってくるようなものというか、従業員さんにとっては本当に必要?と思われているところがすごくあるんです。ここを変えていきたいし、変えられるのはLeafeaだけかなと思っています。福利厚生があって本当に良かったとか、それによって何かが変わったと言われるような良いものを作っていきたいです。
二つ目はそれを小さな枠ではなく全国に届けることです。そのためにも、金融機関や大手の会社とパートナーシップを組んで全国に広めていきたいです。
三つ目は、福利厚生のある意味本質のところで、福利厚生を軸として何か顧客に対して新しい価値を生み出していけるような、従業員の人がより報われる社会をつくりたいということです。報われるというのには、経済的な負担と精神的な負担をなくすという大きく分けるとこの二つがあると思います。今すでに手がけているお得な情報を組み合わせることで経済面での支出を減らすというのが一つのやり方だとすると、もう一つは、経済面でも例えば病気になった時、すぐに何かしらのサポートがあるとか、組織の人に頑張ったことが称賛されるとか、何かに挑戦しようと思えるようなような精神的に報われる仕組みをつくりたいんです。現在は経済面に寄っている部分をもっと従業員さんの負みたいなところを解決していく方向に、会社も事業もどんどんどんアップデートしていきたいです」
社会を変えるかもしれない福利厚生
確かに福利厚生といえば割引きというイメージがある。しかし、働いている人に今、本当に必要なのは精神的な支えなのかもしれない。生きるための会社勤めが、生きづらさを生んでいる状況もある。中原さんの言うように、福利厚生が生きづらさを解消するものとなって企業が積極的に導入し、利用する側も積極的に利用するようになれば、従業員が健康で働き続けることができ、業績にも影響が出るかもしれない。
福利厚生が充実して休みの取り方が変わったり生活の質が向上したりすれば、社会全体のあり方も変わっていくのかもしれない。中原さんが思う、会社がより良い福利厚生を積極的に導入していった先の社会とはどんな社会だろう。

中原 「福利厚生の社会的な貢献はすごく大きいと思っています。会社員だけでなくフリーランスの方でも特定のネットワークに属していれば使える福利厚生のサービスも提供しているので、働く人全体が対象であるという前提でお話しをすると、働く人たちの経済的な悩みや、心や体の悩みがなくなっていくと、挑戦する人がどんどん増えていき、前向きな社会になっていくと思っています。自分に余裕がないと、挑戦しようとか新しいことをしようなんて気持ちにはなれないと思います。例えばお金が足りなくて何かができないとか、心が健康じゃないとか、頑張っているのに承認欲求が満たされないとか、そういうボトムの悩みを会社やネットワークの福利厚生の仕組みで解決できれば、今まで以上に前向きに生活できるのはもちろん、自分が満たされていると今度はそれを他者に還元していこうとか、新しいことやより面白いことをしていこうという方向に向かっていけるのではないかと思っています。やろうと思っても障壁になっていた小さな課題もなくなって、挑戦が溢れる社会になれば社会的にも意味があると思っています。
具体的な話をすると、人が1人辞めないというだけでものすごく会社の雰囲気が良くなったり、それによって事業も継続できたりすることがあります。雇用を守ったり、中の結びつきを強めたりすることでよりその会社が強くなれる1つのきっかけを福利厚生がつくれたりもします。従業員の挑戦をいろいろな仕組みでサポートもできたりと、できることはたくさんあると思います。自分らしく生きられるというか、そこで挑戦したい人は挑戦できるようになる。ま、挑戦を強要するっていうわけでもないですけどね(笑)」
福利厚生のイメージは、企業からすると義務的なものであり、会社員にとっては棚ボタ的なものでそこまで期待はされていないかもしれない。しかし、中原さんのいうように、「自分らしくいれるための福利厚生」だったら積極的に使ってみたくなる。中原さんにとっての自分らしくいられる環境は「仲のいい人や信頼できる人と何かをつくれる環境」。それはそのまま今の環境でもある。自分で会社を持ちながら別の会社にも属している中原さんにとって、社長である自分と会社員の自分はどう違うのだろう?
中原 「Leafeaはフラットな組織で何かを抑制する階層もないので、僕はどちらでもあまり変わらないかもしれません。自分が経営者であれば自分のやりたいことをやれるのは当たり前のことですが、Leafeaは成長している会社で、周りには尊敬できる人たちがいて、自分でトップになってやるよりも大きな挑戦ができる楽しさの方が大きいかもしれないですね。」
最後に中原さんに、今まさにこの会社に興味を持ち始めた人への誘いの言葉をお願いしてみた。

中原 「Leafeaが面白い環境だと思うのは、プロダクト、事業、人、この三拍子が揃っていることです。お客さんに関われるC向けサービスでここまで事業も成立している会社は少ないと思います。企業さんに対してサービスを提供するだけでなく、お客さんや自分の身の周りの人の何かを変えていきたいというような思いがある人はすごく合うと思います。ぜひ門を叩いてみて欲しいです」
お話を聞いていて、会社で自分らしくいれることはとても幸せなことだと感じた。そしてLeafeaはそれを全国に広めようとしている。その仲間が増えれば、福利厚生が社会を変える日はそう遠くないのかもしれない。


/assets/images/21448953/original/307c4acb-5b8c-4131-9798-13332bcd47e7?1750940820)

/assets/images/21405063/original/64de3bae-03fc-41dc-9b17-f8baa6435dd1?1750483380)




/assets/images/21405063/original/64de3bae-03fc-41dc-9b17-f8baa6435dd1?1750483380)

