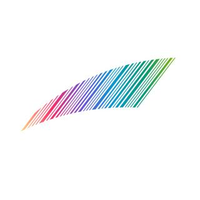- 新卒採用担当
- 27卒セールス/プランナー
- 27卒エンジニア
- Other occupations (2)
- Development
- Business
- Other
「異なる視点が強みになる」フェズで輝く若手エンジニアのリアル
フェズには、バックグラウンドに関係なく、最先端の技術とデータに挑戦できる環境があります。
商学部出身ながら、現在は自社プロダクト開発をリードするPdMの小池さんと、宇宙物理学専攻で培ったデータ分析のスキルを活かし、データ分析とエンジニアリングの両面で活躍する恒次さん。
異なる専門性を持つ二人が、フェズに新卒入社後どのように成長し、チームで価値を生み出しているのか。彼らが歩んできた道と、そのリアルな声をお届けします。

恒次さん(写真左):2023年新卒入社、開発本部/プロダクト開発部/プロダクトデータグループ所属
小池さん(写真右):2021年新卒入社、開発本部/プロダクト開発部/プロダクト推進グループ所属
ーお二人の専攻やフェズへの入社のきっかけを教えていただけますか?
小池: 大学時代は商学部で会計や金融を専攻していました。入社はちょっと特殊で、大学2年から財務インターンとしてフェズで働き、そのまま新卒で入社しました。現在は「Urumo BI(ウルモ ビーアイ)」(特許取得)という自社プロダクトのPdMをやっています。自分ではコードは書きませんが、何を作るか、どういう仕様で作るかを決める仕事をしています。
恒次:大学・大学院どちらも宇宙物理学や天文学を学んでいました。大学では望遠鏡の設計、大学院では遠方の銀河に関する観測的研究をしていました。この大学院での研究が一言でいうとデータ分析だったので、その面白さに気づいたんです。フェズを選んだのは、人数規模に対して持つデータが圧倒的に多いこと、そしてデータ利用にオーナーシップを持って自分たち主導で分析に取り組める点がおもしろそうだと感じたのがきっかけです。
ー入社して1〜2年目で、特に印象に残っているプロジェクトや挑戦はありますか?
小池:入社2年目くらいのころに、今のUrumo BIの前身となるツールのPdMを担当していました。当時、PdMとしての経験がなく本当に手探りで。一番印象に残っているのは、お客さまに言われたとおりのものを作ってもまったく使われなかったことです。お客さま自身も課題を理解しきれていない場合があるので、使われるものを作るプロとして、私たち自身がプロダクトを考え抜く必要があると痛感しました。
恒次: 入社2年目の終わり頃に担当したメディアプランナー機能が印象的です。ざっくり言うと、広告予算とターゲットに応じて最適な媒体配分を導き出す、数理最適化の機能をプロダクトに組み込むという大きな挑戦でした。入社以来データ分析がメインでしたが、このプロジェクトでデータ分析の設計から、実際にプロダクトに組み込むエンジニアリングまで一貫してできるようになったのは、自分の中で大きな進歩でしたね。

ー異なるバックグラウンドを持つ方がチームで働く中で、どのような強みが生まれていると感じますか?
小池: 抽象的な表現ですが「歯車を作る能力が身につく」ようなイメージです。ベンチャーで新しいことを追求するので、個々の役割がうまくいっても、全体が噛み合わないとお客さまに価値は届きません。だから、全員が最終的な「お客さまの成果」を自分の役割以上に意識しています。多様なメンバーがいるからこそ、自分の役割に閉じずに成果を生み出せる能力が育まれていると思います。
恒次: 小池さんと似た感覚ですね。少人数のチームなので、設計から実装まで、メンバーが全体のフローを意識して動けています。異なる専門性や職種の人が集まって議論する中で、例えば小池さんはプロダクトの提供価値を、僕は分析の妥当性を、といったように、各自が専門領域に責任を持ちつつ、全体としてどううまくいくかを意識しています。この「歯車の噛み合い」は、この1~2年で特に学びました。
ープロダクト開発で意見がぶつかったり、うまくいかなかったエピソードはありますか?それをどのように乗り越えましたか?
恒次: 直近携わったUrumo BIの新機能開発で、要件定義の部分が長引いたことがありました。結果としてはいいものができたのですが、自分の中での反省としては、特にプロジェクトの初期段階において「今注目すべき大枠」と「後から詰めるべき細部」の切り分けができていなかったと。小池さんグループから開発にわたる時に、技術的な小さな矛盾に僕が引っかかってしまい、議論を進まなくさせてしまった反省点があります。ぶつかるというより、自分がブロッカーになってしまっていたと感じた部分があったので、そこからは「今は何を話すべき場なのか」といった優先順位を学び、軌道修正しながら進められました。
小池: 実際当時は難しかったですね。恒次さんの言うことはもっともだったので。
このプロジェクトは他社でも前例がないもので、ドキュメントだけではイメージがつきませんでした。そこで、今AIが発達しているのでPdMがプロトタイプをわりと簡単に作れるようになっているんですが、それを使って簡単なものを作ってみたら、「生成AIだとこういうふうにマッチングできるんだ」「こういうアウトプットが出たらユーザーも選ぶものが少なく判断できるな」と、そこから議論が進みやすくなりました。AI時代は仕様策定のスピードも変わってきていると感じています。

ーお二人が考える、フェズやこのチームに向いているのはどんな人ですか?
恒次: まずは「ある程度能動的に動ける人」ですね。仕事が降ってくるのを待つのではなく、自ら課題を見つけて動ける人が良いです。あとは、特定の専門性へのこだわりが強すぎず、柔軟に対応できる人も向いています。会社規模が小さいので、自分の専門性が発揮できるプロジェクトが常にあるとは限らないので、そこは柔軟に動ける人のほうがよいのかなと思います。
小池: 恒次さんが新卒で入社するときに、「データに対して誠実な人でありたい」と言っていたのが印象的で、それはすごく大事なことだと思っています。今わりとそういうメンバーが多いですね。我々のプロダクトは、使われたらいいだけでなく、使われた結果が成果に直結するところが、購買データを使っているからこそできるんです。だから、「使われた先で、ちゃんと社会や経済のためになっているか」という広い視点で見られる人、ユーザー価値を本質的に追求したい人は向いているんじゃないかなと思います。
ーAIや自動化が進む中で、それぞれが今意識しているスキルや価値はどんなことですか?
恒次: 自分の中で意識しているのは、「ある程度の柔軟さ」と、「周りに影響されない頑固さ」の両方ですね。AIで簡単にものが作れる時代だからこそ、新しい技術を受け入れる柔軟さも大事。一方で、エンジニアはあくまで専門職であって、やっぱり技術的なところに対して責任を持つ人だと思っています。例えば、AIを通して出てきたアウトプットが本当に大丈夫なのか、と判断できるとか。そういうちゃんとした理解をする能力は、今まで以上に意識しないと身につかないと思っています。短期的には無駄に見える回り道をしているようでも、気になったことは時間がかかってもちゃんと調べるというところは結構大事だと思っています。
小池: わりと近い内容かもしれないですが、スキル的には僕は逆に、「いざとなれば自分でもコードが書けるようなスキル」は意識しています。少なくとも今のAIは、自分ができないことをお願いするツールではないなと。AIに命令する中でも、自分ができるからこそ正しく命令ができるからです。例えばプロトタイプをざっくり作ることはできるけど、ちゃんと継続的に使われるプロダクトのために良い命令ができるかというと、それはできません。自分が作れるようになりたいというよりは、そういう作れる手段を知っているからこそいい要求が出せる、というところがあると思っているので。
例えば直近恒次さんがやっていたプロジェクトで使っていたベクトル検索のような技術も、それを知らないと「こういうことができる」という発想自体ができない部分があったりするので、そうした複合的なスキルがあると、人間でしか生み出せない要件が出せるのだと思います。だからこそ、むしろ技術領域のスキルを個人的には高めたいと思っています。

ー 最後に、これからフェズへの入社を考える学生に伝えたいことはありますか?
恒次:入社前の自分は研究ばかりしていたので、会社で働けるのかと不安もありました。でもこの2〜3年間楽しくやれていて、技術として役立ったなと思うのが、学生時代の研究プロセスってビジネスに似ている気がするんです。こうしたいという目標に対して、どうすれば実現できるかを考えるのは同じ。なので、学生時代研究ばっかりやっていたけど結果としてよかったし役立った部分が多かったので、目先の専門性を変えることに対しては特にプレッシャーを感じることはなかったです。今学生の皆さんには、自分の興味あることは、未来のことは考えすぎずにしっかりやってほしいと思います。
小池:これからエンジニアやプロダクト開発を目指す皆さんには、ぜひフェズの環境で一緒に挑戦してほしいですね。私たちは、購買データという社会に大きなインパクトを与えられるデータを扱っているので、その開発環境も非常に魅力的だと感じています。 AIが一般化する中で、「何をデータとして使うか」が、今後はプロダクト的にも社会的にも一番価値になると思っているので、興味があればぜひ話を聞きに来てください。
購買データという、社会に大きなインパクトを与えるデータを扱えるのは、フェズならではの魅力です。ここでは、あなたのこれまでの経験や個性が、きっと大きな強みになります。私たちと一緒に、データとAIで未来を創造する最前線で活躍しませんか?
興味を持ったら、ぜひ私たちのチームに話を聞きに来てください!