- フロントエンドエンジニア
- PjM
- オープン募集/職種なんでも
- Other occupations (32)
- Development
- Business
- Other
昨日社内で行われたAIコーディング勉強会の様子をレポします!
私が非エンジニアで専門的なレポートが難しい…
ということで今回は議事録を食わせてAIに書かせてみました。
勉強会、色々なところでやっているんですよ。すごい。
私は別部署から来たのでEM室にきて知ったんですが、自主的に勉強をして皆に共有する会を開催するって当たり前じゃないと思うんです。もっと褒められていくべきだと思うんです。
開催自体、本当に尊敬しているのでぜひ共有したいと思ってレポに起こしました。
※沢山技術の説明をしていただいたのですがスペース的に端折っている部分もありますので技術面はテックブログでm(__)m
なぜかギャル口調になってますが、どうぞ↓
はいよー!みんな、こんにちわん🐶
先日開催された社内AI勉強会、実はこんなきっかけで始まったんだ! 砂原千里さんが「Devinでクレジット無駄にしたの、マジもったいなくね?😭」って叫んだのが始まり(笑)。
最初は失敗談シェアのゆるい会のはずが、予想外の人が集まって(40人も!)急遽ガチな共有会になったんだって!👏AIにお金と時間を溶かした勇敢なエンジニアたちが集まったんだ!
ってことで、今回も内容チェックしていくよ!🙌
AIツールを使う前に
会社でAIツールを使うには申請が必要!
「これこれこういう目的で使いたいんですけど」って申請してね。
AIの正しい使い方とかルールブックみたいなガイドラインも作成中!完成が楽しみだよ~~~!
会社のデータとAI
会社のデータ(お客さんの大事な情報とか)とAIを直接つなぐのは、セキュリティ的に危険!
絶対にやめて!CursorっていうAIツールを使うときは、プライバシーモードをオンにするのを忘れずに!あと、AIモデルを選ぶときにDeep Seekっていうのは、今は避けた方が良いらしいよ。
みんなはどうAI活用してるの?
🌟板谷さん
まず、AIを育てるには、プロジェクトの構造とか、ファイルの中身をちゃんと理解してもらうのが超大事!だから、最初にプロジェクトの設計図をしっかり書いたり、コードの一つ一つに丁寧な説明を書いてあげるのが、実は一番の近道なんだよ。
さらにさらに!Cursorには秘密兵器、「CursorのProject Rules」っていうのがあるんだ。これを設定すると、AIの精度がアップするらしい!しかも、最近のアップデートで、このルールを AI が自動で生成してくれる機能まで追加されたとか!AIがルールを作ってくれるみたいだから、ぜひ試してみて!
Pythonとか、色々あるみたいだから自分の開発スタイルに合わせるのがおすすめ!
実例として、昔の CodeIgniter 3っていうので書いてたコードを、最新のCodeIgniter 4にアップデートするのにCursorを使ってみたら、マジでいい感じにコードを補完してくれたらしい!古い書き方から新しい書き方に変換してくれるのは、まさに 時短の魔法!✨
ドキュメント作りとか、テストコード書くのって、結構工数かかるじゃない?
でも、Cursorに「お願い!」って言えば簡単に終わらせてくれるから、積極的に活用してみて!
🌟砂原さん
えーっとね、ちょっとした短いコード書く時とかは、ChatGPTに「こんな感じのコードお願い!」って言うと、大体の形を作ってくれるんだよね。そしたら、細かいところはCopilotでちょちょいと直す、みたいな感じで使い分けてるかな。DevinっていうAIツールも試してみたんだけど…
うーん、複雑なAPIに対して簡単な指示しか出さなかったから、あんまり期待した結果にならなくて。
だから今後は、まず自分でコードの土台をちょっと作ってからDevinに「この続き、お願い!」って言ってみようかなって思ってるんだよね。
🌟平さん
僕の場合はね、Copilotのエージェントモードっていうのがマジですごくて!
AIが色々やってくれるんだよ。それと、Claude 3.7っていう賢いAIモデルと、MCP、あとGitHubっていうコード管理サービスを組み合わせて使ってるんだ。
AIが自分でコード書いたり直したりしてくれるおかげで、開発効率が上がってる実感があるよ。
あと、リポジトリっていうコードの保管場所を整理するのに、プロンプトファイルっていう指示書みたいなものと、自分で作った命令を活用したり、MCPとメモリーバンクっていう一時的な記憶領域をうまく使ったりする方法も紹介したんだ。コーディングだけじゃなくて、作ったコードをみんなに見てもらう準備(PR作成)とか、レビュー(他の人のコードチェック)にもAIを活用できる例も話したよ。
今後の課題としては、AIにどういう風に指示したら一番うまく動いてくれるか、とか、色々な情報が散らかっちゃうのをどう整理するか、みたいなところかな。AIを使いこなすコツを、「ルンバが掃除しやすいように部屋を片付ける」ことに例えるとわかりやすいよ!
🌟村松さん
私、CursorっていうAIツール、まだ使い始めたばっかりなんですけど、自分のチームは複数のプロダクトがあるチームで。理解しきれてないリポジトリーを開いてこの機能ってどこで実装してたんだっけみたいなところを探す1歩目とかがすごい時間短縮に!😭✨
目的のコードがどこにあるか見つけられるのが、本当に助かってます!
APIっていう、色々なプログラムをつなぐ仕組みを作る時に、設計書を修正するのにCursorを使ってみたんですけど…なんか、いらない改行とかスペースがたくさん入っちゃうことがあって。
だから、既存の設計書を頑張って直すよりも、AIが修正しやすいように一度作り直した方が、もしかしたら早いかもって思ったんだよね~。
🌟岡本さん
僕、新しいアプリとかをゼロから作る場合は、まずAIに「任せるんで、これ作ってみて!」っていうアプローチをしてるよ。もしAIが作ったものが、んー、ちょっと違うなって思ったら、またやり直せばいいかな、みたいな。で、6割できたら、後は細かくコードを追いかけながら仕上げる。個人的には、PyCharmとJunieでガッと作って、CursorとGeminiで仕上げるって使い方が、なんか相性良かったんだよね。UIの修正はその場しのぎが多いし、複雑なバグの原因を探すのは、まだAIがちょっと苦手なこともあるみたいで。CursorでAIがファイルを直そうとして壊しまくる現象も経験したよ(笑)。
例えば、元々Aっていうファイルを直してもらってたとするじゃん?AIが「こんな直し方どう?」って。その時に別のBっていうファイルを見てから「さっきの直し方で!」ってお願いすると、なぜかBの方にA向けの直し方を適用しちゃって、肝心のAは全然直ってないしBは壊れるし、直し方自体が間違ってたって勘違いしてさらにハマる、みたいな😅
あと、会社のパソコンのセキュリティ制限で、AIが自動でフォルダ作ったりファイルを消したりできないこともあったね。今後は、プロダクトマネージャーとか企画系の人が、エンジニアにいちいち頼らなくても、自分で色々試せるような環境を作っていきたいなって思ってるよ。新技術を使った新サービスは、何度も試行錯誤しないとイメージつかめないからね。
🌟武藤さん
僕、インフラ担当なんですけど、DevinっていうAIツールを使用して今まで時間かかってたドキュメント作りの時間を減らしたり、Devin Wikiっていう仕組みで、Git上のコードとか設計の情報を見やすくしたり、人だと難しいけどAIなら複数タスクをお願いするのがすごく簡単になったりした例を紹介させてもらったんです。AIに「こういうことやって」ってお願いする時の指示の細かさとか、元になるドキュメントがちゃんと整理されていることが、やっぱり大事だなって思ったよ。
今後は、インフラの構成図や作業手順書自動化して承認フローと連携させたり、サーバーの監視を自動化したりするのを目指してます🤔
🌟瀬戸さん
僕は応募フォームの試作品を作ったり、MCPサーバーを自作してJIRAに入ってる情報からAIに実装をお願いして完成までできました。ただ、やっぱり大きくて複雑なシステムとかだと、まだAIの精度が低いかな。AIのおかげでコードを書くスピードは上がったんだけど、書いたコードがちゃんと動くかテストしたり、他の人に見てもらったりする手間が増えるから、テストとかレビューも自動化していく必要があるなと思ってる。
あと、AIが作ったコードが 必ずしも 一番良いとは限らないので、ちゃんと判断できる技術力も、僕たちエンジニアには重要だってことも伝えたい!✨
🌟大沼さん
僕がAIを活用したのは、プログラムのバグを見つけて直す時なんですけど、原因がすぐに分かって修正できた例を紹介させてもらいました。
でもね、AIに細かい指示を出さないと、全然違う答えが返ってきたり、バージョンアップ対応の時、公式ドキュメントの情報が少ないと古いバージョンの書き方を提案されたりする場合もあるんですよね。GitHubにissue立ててAIツールが、コードを書くだけじゃなくて、プルリクエストっていう、修正したコードをみんなに見てもらうための申請までやってくれることに、今すごく期待してるんですよ!
🌟伊東さん
僕が取り組んだのは、ユニットテストっていう、プログラムの機能がちゃんと動くかをチェックするテストを導入することなんですけど、それにCopilotとCursorっていうAIツールを活用した例を紹介させてもらったよ。
テストのパターンを考えたり、複雑なコードの内容を理解するのに、どちらのツールも本当に役に立ちましたね。ただ、どのファイルに対してテストを書くかを指定しやすいのは、個人的にはCursorの方が使いやすかったです。昔からあるコードだと、AIが期待通りのテストコードをなかなか作ってくれないっていう課題も、やっぱりあるんだよね。
今後は、MCPを使ってデータベースの情報を取得させ、テスト用のデータ(MOCデータ)をAIに作らせる、みたいなことに期待したいと思ってます🙌
ちょーヤバくない?!マジでみんなAI使いこなしてんじゃん!
色んな話聞いてたら、自分もなんか試してみたくなってきたんじゃない?
でも時間なくなっちゃったみたいで、続きはまた今度だって!次、来週やる予定らしいよ!
そのあとは、2週間おきくらいにできたらいいな~。
AIの進化、すごすぎ!
みんなで色々教え合えば、もっとすごいことできそうじゃん?!
じゃあ、また次のレポートで会おー!バイバーイ👋
/assets/images/3970293/original/94dc2a11-6938-44c4-ad15-df077be65105?1569861159)

/assets/images/3970293/original/94dc2a11-6938-44c4-ad15-df077be65105?1569861159)


/assets/images/3970293/original/94dc2a11-6938-44c4-ad15-df077be65105?1569861159)



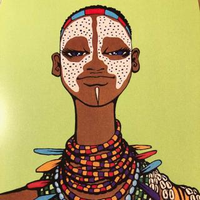

/assets/images/21145582/original/94dc2a11-6938-44c4-ad15-df077be65105?1747633971)

