教育に“失敗体験”をどう組み込むべきか?
最近、有識者と「教育とは何か?」というテーマで話をする機会がありました。その中で強く印象に残ったのが、「教育設計の中に“失敗体験をどう積ませるか”という視点が抜け落ちているのでは?」という指摘です。
成長のターニングポイントは“失敗”だった
皆さん自身の経験を思い返してみてください。「自分がグッと成長できたな」と思った瞬間はどんな時だったでしょうか?
私自身は、「失敗体験」が成長のきっかけになっていたケースがいくつもあります。もちろん、ただ失敗しただけでは意味がありません。“失敗を糧にし、最後までやりきった経験”こそが、次の行動を変え、力になってきました。恥ずかしさ、悔しさ、申し訳なさ——そんな感情と向き合いながら乗り越えてきたからこそ、強く記憶に残り、ノウハウやスキルになっていると感じます。
教える立場になると“失敗させない”ことに意識が向きがち
不思議なことに、自分自身は失敗から多くを学んだと実感していても、いざ部下や後輩を育てるとなると「失敗させない」方向に動いてしまうことがあります。
- 早いうちに挑戦させすぎて、心が折れないように…
- スキルが足りないから、安心して任せられない…
- 失敗して組織に損害が出ないように…
- 余計なトラブルが起きないように…
きっと理由はいろいろありますし、それ自体は間違っているとは言えません。そろそろ挑戦させても大丈夫だろうという安全ゾーンが見えてきてから、新しい業務を任せる上司や先輩の方が多いと思いますし、私自身も同じ考えに近いと思います。
組織が成熟するほど“失敗が許容されにくく”なる
小さな組織や黎明期のチームでは、ある程度の失敗がむしろ成長のチャンスとされます。たくさん挑戦して、たくさん失敗してノウハウが積み上がっていく。しかし、組織が大きくなると一つのミスが大きな損失になりかねず、「いかに失敗しないか」が重視されるようになっていきます。組織が大きくなるほど、失敗の規模が大きくなっていってしまうのです。
その結果として
- 失敗しないための管理が強化される
- 保守的な空気が生まれる
- 失敗を恐れて挑戦が減る
といった、挑戦と学びにブレーキをかけるマインドが組織に蔓延してしまいます。
さらに問題なのは、過去に失敗から学びノウハウを積み上げた世代が引退すると、技術継承がうまくいかず、組織力が落ちてしまうということです。この部分が何十年と企業が生き残っていく上での大きな試練だと感じています。
老舗倒産は何年目くらいが多いのか、AIに聞いてみた。
=================================================================================
◾️ 創業30~35年目:第1の壁
- 先代からの事業承継が本格化する時期
- 2代目・3代目に経営交代するが、「ノウハウや人脈が継承されない」「方向性がぶれる」などで事業が傾く
- バブル期創業企業がこの辺りで苦しくなるパターンも多い
◾️ 創業50年前後:第2の壁(事業モデルの陳腐化)
- 元々のビジネスモデルが時代に合わなくなり、抜本的な変革が求められる
- しかし、「変えられない/変えたくない」文化が強く、時代に取り残されがち
- 競争力が落ちる → 売上減少 → 過去の資産・借入で持ちこたえる → ある日限界がくる
◾️ 創業70年~100年:最後の壁(組織疲労+人材難)
- 経営者も高齢化、後継者不足が顕著に
- 従業員も高齢化、組織に“惰性”が生まれ、変化に対応できなくなる
- 「代々続いた会社なのに倒産するなんて…」という典型的な老舗倒産がここで起きやすい
=================================================================================
このように老舗として30年以上事業が続いていた企業の倒産においては
- 「ノウハウや人脈が継承されない」
- 「変えられない/変えたくない」文化
- 「組織の高齢化」
なんていうワードが目に留まります。おそらく作業方法は継承できていても、かつての先人たちと同じような失敗体験を含めた経験値まで技能を継承できているケースは稀です。
そのため、「なぜ、この手法でないといけないのか」に対する解をもっている人が少なくなっていき、やがて「理由はわからないけど、変えられない」といった事に陥ってしまう。もしくは本当に変えてはいけないことすら変えてしまう。それによって無自覚に企業のノウハウを喪失してしまったりしている可能性もあります。

——では、どうすればいいのか?
冒頭の有識者との会話の中で出てきたのが、「教育の中に“小さな失敗”を意図的に組み込むべきではないか?」という視点でした。
もちろん、失敗を経験すること自体が目的ではありません。重要なのは、
- 小さな失敗をあえて経験させること
- その後に、しっかりと支える体制を用意しておくこと
- そこからリカバリーする思考や習慣を育てること
これらを“教育の仕組み”として設計することです。
そうすることで、「失敗への耐性」や「試行錯誤する姿勢」を自然と身につけられるようになります。
失敗は、誰にとっても精神的・体力的にしんどいものです。だからこそ、「ただ崖から突き落とす」ような教育ではなく、“安全に試行錯誤できる場”をつくることが必要なのです。
「この失敗は織り込み済みだから大丈夫だよ。サポートするから、一緒に乗り越えてみよう」
そんな言葉をかけられる環境があるだけで、挑戦する側の安心感は大きく変わります。精神的な負担を和らげながらも、「試行錯誤の姿勢」については遠回りになろうとも、さまざまな経験をしてもらう。
「なぜこんなトラブルが起きたのか?」
「こうしたらどうだろう?」
「あぁしたら、うまくいくかもしれない」
そうやって自ら問いを立てて考えるようになる。それこそが、思考力・応用力・そして深い理解へと繋がっていくのです。
もちろん、教育する側としてはもどかしさもあるでしょう。「答えを言ってしまいたい」気持ちもあります。それでも我慢して、あえて遠回りを見守る忍耐力が求められます。
だからこそ必要なのは、個人ではなく、組織全体として“小さな失敗から学ぶ教育”を支える仕組みです。
若手社員の成長の全体像を描き、その中に「小さな失敗からの学び」をどう位置づけるか。
これは教育担当者だけでは実現できません。なぜなら、どれだけ現場が意図をもって教育していても、
経営層や上司がその挑戦の“ムダに見える時間”を「なんでそんなことしてるんだ!」と否定してしまえば、すべてが水の泡になってしまうからです。
つまり、経営層が「失敗を含む試行錯誤にこそ価値がある」と本気で思えているかどうか。
この意識の有無が、会社全体の教育文化を左右するのだと思います。長い目で見れば、こうした「小さな失敗の経験」こそが、企業にとって最も大きな資産になる。人が育ち、知恵が継承され、技術が残る。そんな会社になれるかどうかの分岐点だと感じています。自分自身への自戒も込めて、私たち自身の組織においても、こうした「失敗体験を含めた教育体制」をどのように築いていけるかを改めて考え、できることから一つずつ実践していければと思います。
/assets/images/5015970/original/180d86a9-9cd0-4ca8-9bd8-0d8dbd2a632c?1589429132)
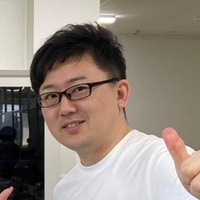
/assets/images/5015970/original/180d86a9-9cd0-4ca8-9bd8-0d8dbd2a632c?1589429132)
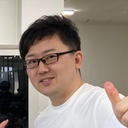

/assets/images/5015970/original/180d86a9-9cd0-4ca8-9bd8-0d8dbd2a632c?1589429132)


/assets/images/5015970/original/180d86a9-9cd0-4ca8-9bd8-0d8dbd2a632c?1589429132)

