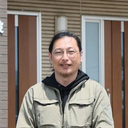みなさんはじめまして!
北海道の浦河で「神馬建設」という工務店の社長をしている神馬充匡(じんば みつまさ)です!
【プロフィール】
代表取締役6年目になる、今年47歳。 学生時代から17年間土木を学んだ後、 実家の工務店にもどり、建築14年目を迎える三代目です。 やらない後悔より、やって後悔。 一度きりの人生。楽しくやりきろうって思っています。
1. 氷河期世代とは?なぜ「見捨てられた」と言われるのか
1-1. 氷河期世代の定義

「就職氷河期世代」とは、1993年から2005年の間に就職活動を行った世代を指し、特に1975年〜1984年生まれの人々は「就職氷河期コア世代」とも呼ばれます。
この時期はバブル崩壊後の不況によって企業の新卒採用が大幅に抑えられ、多くの若者が希望する職に就くことができませんでした。
当時、求人倍率は急落し、2000年には0.99倍と、新卒者が一人につき1つの求人もない厳しい状況に陥りました。その結果、多くの人が非正規雇用を余儀なくされ、正社員としてのキャリアをスタートできなかったのです。
私自身、1998年に就職活動を経験しましたが、その厳しさを肌で感じました。大学の就職説明会に来る企業数が一気に半減し、選択肢が狭まる中で、何とか職に就けたというのが実情です。しかし、この時期に正社員になれなかった人々は、その後のキャリア形成においても大きなハンデを背負うことになりました。
1-2. 見捨てられた背景

就職氷河期世代が「見捨てられた」と言われる背景には、複数の社会的要因が絡んでいます。
①新卒一括採用制度の問題点
日本の企業文化では、長らく「新卒一括採用」が一般的でした。この制度では、新卒時に正社員になれなかった場合、再び正社員のチャンスを得ることが極めて難しくなります。つまり、氷河期世代の多くが新卒時点で正社員になれなかったことで、その後も不安定な雇用環境に置かれ続けたのです。
例えば、欧米諸国では転職市場が活発で、年齢に関係なくキャリアアップの機会があります。しかし、日本では「新卒で正社員になれなかった=キャリアのスタートラインに立てなかった」と見なされ、企業側も中途採用に消極的でした。
結果的に、氷河期世代は正社員への道が極端に狭められ、見捨てられる形となったのです。
②非正規雇用の増加と賃上げの遅れ
政府の労働政策も、氷河期世代の厳しい状況に拍車をかけました。2000年代初頭、小泉政権の規制緩和により派遣労働が拡大し、企業は正社員の採用を抑え、非正規雇用を積極的に活用するようになりました。これにより、氷河期世代は「非正規労働に固定化される」という新たな問題に直面しました。
さらに、最近では賃上げの動きが進んでいるものの、その恩恵を受けるのは主に若手世代です。厚生労働省のデータによると、20〜30代の賃金はこの10年で上昇しているのに対し、氷河期世代の賃金上昇はほぼ停滞しています。これは、若手人材の確保に企業が注力している一方で、氷河期世代のキャリアアップが後回しにされている現状を反映しています。
③社会支援が後手に回った歴史的背景
氷河期世代の就職難は、長らく「自己責任」として片付けられてきました。しかし、近年になってようやく政府や企業もその問題に目を向け始めています。例えば、厚生労働省は「就職氷河期世代活躍支援プログラム」を打ち出し、特定求職者雇用開発助成金やキャリアアップ助成金を通じて氷河期世代の雇用を促進しようとしています。
しかし、支援策が本格化したのはここ数年の話です。それまでの間、氷河期世代は十分な支援を受けられず、厳しい状況に置かれ続けていました。「支援が遅すぎた」と感じる人も多く、政府の対応の遅れが、結果として「見捨てられた」という感覚を生んでいます。
2. 現在の氷河期世代が直面する課題
2-1. 雇用と賃金の問題

氷河期世代が今もなお直面している最大の問題の一つが、雇用の不安定さと低賃金の固定化です。
非正規雇用の割合が依然として高い現状
バブル崩壊後の厳しい就職状況により、新卒時に正社員としての職を得られなかった氷河期世代の多くは、その後も非正規雇用から抜け出せない状況が続いています。厚生労働省の調査によると、氷河期世代の約4割が非正規雇用で働いており、これは他の世代と比べても高い割合です。
企業側としては「即戦力」を求める傾向が強く、長年非正規として働いてきた氷河期世代の人材が、年齢を理由に正社員採用の機会を得にくいという現状があります。特に40代後半〜50代前半の転職市場は厳しく、未経験分野への転職はさらに難易度が高まります。
賃金格差やキャリアアップの難しさ
非正規雇用で働き続けた場合、賃金は大きく上がらず、将来的な生活の安定も見通しが立ちにくいのが現状です。日本の平均年収は上昇傾向にあるものの、賃上げの恩恵は主に若手世代に向けられており、氷河期世代の賃金上昇はほとんど進んでいません。
さらに、氷河期世代は「経験年数」が少ないことを理由に昇進の機会が制限されるケースも多く、管理職に就ける人の割合も他の世代と比べて低い傾向にあります。その結果、長年働いても正社員と比べて大きな給与差が生じ、「働き続けても将来が見えない」という不安を抱える人が多いのです。
このような問題を解決するためには、企業側の意識改革や、再雇用の支援制度の充実が求められています。
2-2. 社会的孤立と不安定な生活基盤
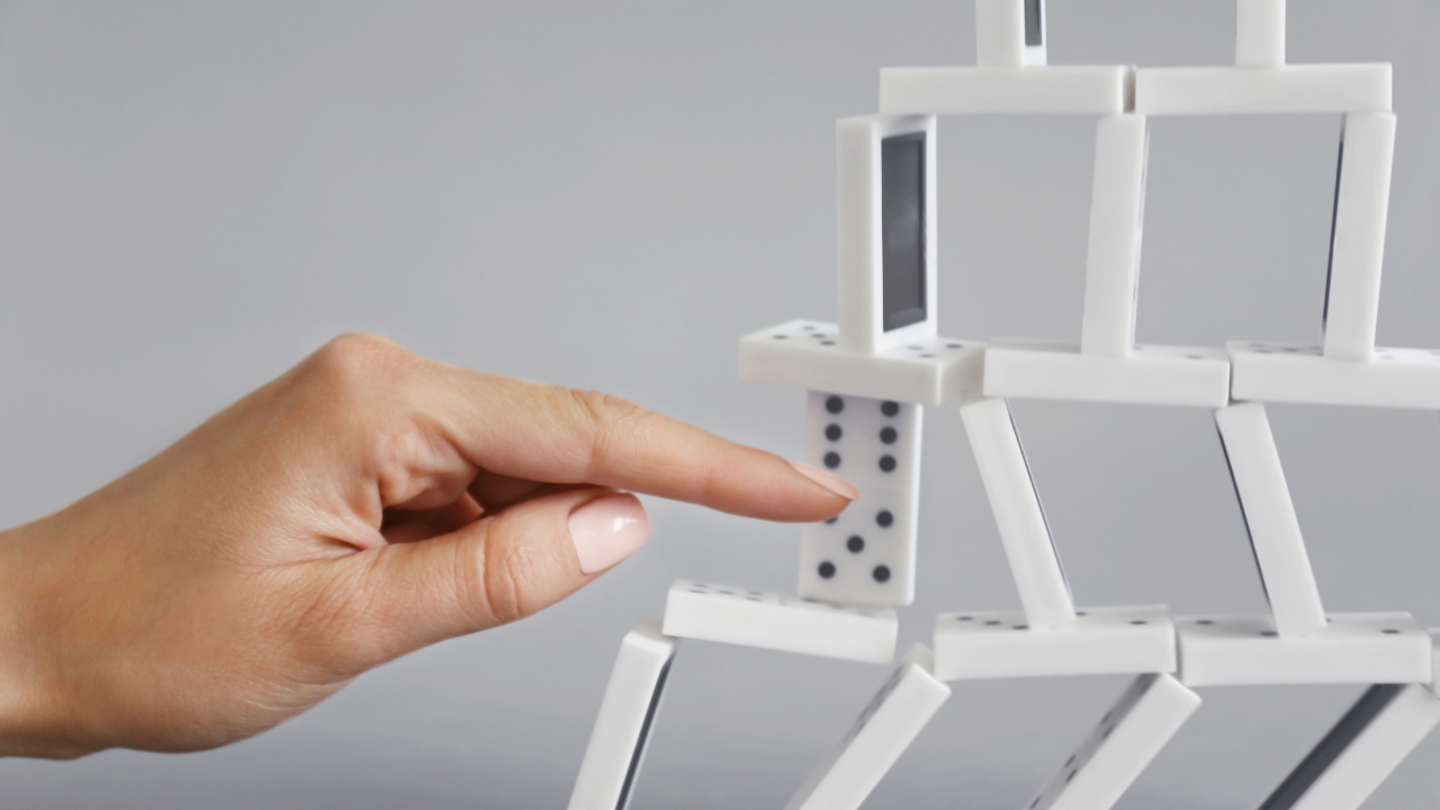
氷河期世代の問題は、単なる雇用や賃金の問題にとどまらず、社会的孤立や生活基盤の不安定さにも及んでいます。
引きこもりや無業者の割合が突出している理由
近年の調査では、40代〜50代の氷河期世代の中で、長期間無業状態にある人や引きこもり状態の人の割合が他の世代と比べて突出していることが明らかになっています。内閣府の調査によると、40〜64歳の「中高年ひきこもり」の推定人数は約61万人にも上り、その多くが氷河期世代に該当します。
この背景には、以下のような要因が考えられます。
- 就職難によるキャリアのスタート遅れ
→ 新卒時に正社員になれず、そのまま仕事に就くことができなかった人が多い。 - 非正規雇用の固定化によるキャリアの断絶
→ 低賃金や契約終了の不安が常に付きまとい、安定した生活を築くことができなかった。 - 社会復帰が難しい環境
→ 40代・50代になってからの転職は厳しく、長期間の無業状態が続くと再就職のハードルがさらに高くなる。
社会的孤立が生む問題とその連鎖
氷河期世代の一部は、孤立した生活を余儀なくされています。友人や同僚と疎遠になり、家族との関係も希薄になりがちです。特に、親と同居している人が多い世代ですが、親の高齢化により**「8050問題」**(80代の親が50代の子どもを養う問題)が深刻化しています。
また、生活基盤の不安定さは、健康や精神面にも影響を及ぼします。長期間の無職状態が続くと、社会との接点が減り、うつ病や健康問題を抱える人も少なくありません。
このように、氷河期世代の問題は単なる「雇用の問題」にとどまらず、社会全体で取り組むべき深刻な課題であることがわかります。
大前提、氷河期世代と言われる方々の現状には様々あると思っています。
家族を持っていて、家庭を持っていて、既に子供が独立し、自分たちの夫婦の暮らしだけを維持すれば良いような状況にある人、上の世代がつっかいているが、ために昇進できず、自分のやりたいことをやれない人、もしくはたまた、奨学世代の影響をもろに受け、賃金の低さや雇用機会の喪失に苦しんでいる人。私はこの両方の方々にとって、地方(田舎)で、エッセンシャルワーカー(生活に欠かせない仕事)として働くことが非常に有意義なことであると考えています。
3.氷河期世代こそ田舎でエッセンシャルワーカーになるべき理由
「氷河期世代」と呼ばれる私たちの世代。気づけば40代〜50代となり、社会人としての経験を重ねながらも、未だに思うような働き方ができずに悩んでいる方も多いのではないでしょうか?
- 子育てが終わり、夫婦2人の生活を考え始めた人
- 昇進ができず、仕事のやりがいを見失っている人
- 低賃金で働き続けることに疲れてしまった人
こうした現状にある方々にこそ、「田舎でエッセンシャルワーカーとして働く」という選択肢を考えてほしい。今回は、その理由をじっくりお伝えします。
3-1. 田舎は物理的な豊かさより「暮らしの豊かさ」のある場所

都会には、便利なショッピングセンターや娯楽施設があり、何でもすぐに手に入る環境が整っています。
一方で、田舎にはそれほどの利便性はないかもしれません。
ですが、田舎には「物質的な豊かさ」ではなく、「暮らしの豊かさ」があるのです。
- 広大な自然の中で心が癒される
- 新鮮で美味しい食材が手に入る
- 地域の人々とのつながりが生まれる
特に、「子育てを終えた方」にとっては、都会での利便性にこだわる必然性はありません。むしろ、夫婦2人の暮らしを大切にし、心地よく過ごせる環境を選ぶことができる世代です。その点、浦河のような地方都市は、ゆったりとした時間の流れの中で、心豊かに生きることができる場所だと言えます。
3-2. 田舎ではエッセンシャルワーカーが「本当に必要とされる」仕事になる

都会と田舎の違いは、単に「便利かどうか」だけではありません。特にエッセンシャルワーカーに関しては、田舎の方がはるかにその価値が高いのです。
都会では「誰かがやる」仕事でも、田舎では「いなければ成り立たない」仕事
たとえば、介護・福祉、建設、物流、医療などのエッセンシャルワークは、都会では代替が効くかもしれませんが、田舎ではそうはいきません。
エッセンシャルワーカーがいなければ、地域の暮らしが成り立たないのです。これは、ただ「仕事がある」という話ではなく、地域にとって本当に必要とされる存在になれるということ。
都会では「なんとなく働いている」仕事でも、田舎では「自分の仕事が、誰かの暮らしを支えている」という実感を持てるのです。
3-3. 田舎こそ「やりがい」と「安定」が手に入るチャンスがある

また、エッセンシャルワーカーを雇用する田舎の企業は、深刻な人手不足に直面しています。その理由は、若い世代が都市部へ流出し、上の世代が次々と引退しているから。
つまり、田舎では「上のポスト」が空いている状態なのです。都会では年功序列やポストの詰まりによって昇進のチャンスが限られますが、田舎では即戦力として重要な役割を担える可能性が高いのです。
- キャリアアップのチャンスが多い
- 待遇改善が進んでいる
- 安定した生活を送ることができる
さらに、田舎ではエッセンシャルワーカー不足が深刻だからこそ、賃金改善の動きが加速しています。都会よりも、むしろ田舎の方がエッセンシャルワーカーの待遇が良くなっていく可能性があるのです。
4.浦河で「自分らしい生き方」を見つける。神馬建設のサポート体制とは?
「働くこと」と「生きること」。どちらか一方を優先するのではなく、どちらも大切にしながら自分らしい暮らしを実現する。そんな理想を、浦河で叶えるために、神馬建設は“あなたに合った働き方”を用意しています。
「田舎でエッセンシャルワーカーとして働く」という選択肢を考えるなら、仕事だけでなく、その人自身の生き方に寄り添うことも大切です。そこで今回は、神馬建設がどのように社員一人ひとりの生き方をサポートしているのかについてお伝えします。
4-1. 3つの働き方から、自分に合うスタイルを選べる

私たちは、一人ひとりが理想のライフスタイルを実現できるように、3つの働き方を用意しています。
- もっともっと成長コース
仕事を通して自らの成長を最優先に考えたい人を対象にしています。仕事における目標設定のウエイトを少し高くしています。 - 着実コース
仕事を着実にこなしながらも、プライベートも充実させたいと考える方を対象にしています。ワークライフバランスのとれた生活スタイルを望む方にふさわしいコースです。 - ゆっくりコース
自らの人生を豊かにするために、仕事に必要な能力を着実に高め、他者や会社の役に立ちたいと望む方に最適なコースです。
私たちは、ただ働く場所を提供するだけではなく、一人ひとりのライフスタイルに寄り添った働き方をサポートします。就労時間の柔軟性もその一つ。ライフステージに応じた働き方の変更も可能です。
4-2. 就労時間が比較的短くライフ重視の生活が可能

また、勤務時間も非常に特徴的で、比較的就労時間が短く残業もないので、プライベートや休息の時間もゆっくり取ってもらえるようになっています。
▼(4/1〜9/30)
勤務時間:7:45〜17:00(実働:6.75時間)
休憩時間(2時間)
am 10:00~10:30
pm 12:00~13:00
pm 15:00~15:30
▼(10/1〜3/31)
勤務時間:7:45〜16:30(実働:6.75時間)
休憩時間(1.5時間)
am 10:00~10:30
pm 12:00~13:00
4-3. あなたの人生に寄り添う、柔軟な福利厚生制度

働く上で欠かせないのが、「ライフイベントに寄り添う制度」です。たとえば、一般的な育児休暇に加え、次のような柔軟な休暇制度を取り入れることを考えています。
①介護休暇
親の介護が必要になったとき、仕事との両立は容易ではありません。だからこそ、介護と仕事を両立できる仕組みを整備し、サポートしていきます。
②パートナーケア休暇
もし大切な人が病気になったら——
例えば、パートナーが癌を患い、支えが必要になったとき。
そんなときに、「一緒にいる時間を確保できる制度」があればどうでしょうか?単なる「仕事の休み」ではなく、大切な人のために使える時間をつくる。私たちは、そんなサポートを企業として提供していきたいと考えています。
その他福利厚生の面に関しては、下記の記事でもご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
5.浦河の魅力──小さな幸せと、消えゆく日本の四季を感じる暮らし
都会には、物質的な豊かさが揃っています。高層ビルが立ち並び、どこへ行ってもコンビニやスーパーがあり、少し歩けばスターバックスやおしゃれなカフェが見つかる。
一方で、浦河のような田舎には、そういった便利な環境はありません。最寄りのスターバックスまで車で2時間。札幌までは、移動に4時間かかる。
でも、そんな浦河だからこそ、都会では決して味わえない魅力が詰まっています。今回は、浦河での暮らしを豊かにする2つの大きなポイントをご紹介します。
5-1. 小さな幸せをたくさん感じられる場所

浦河には、最新の商業施設や派手な娯楽施設はありません。
しかし、その代わりに、何気ない日常の中に溢れる小さな幸せがあります。
たとえば、
- 車で1時間走れば、まだ人間の手が入っていない大自然が広がる。
- 「こんな花がこの時期に咲くんだ」と、季節の移ろいを肌で感じる。
- 「こんな鳥がいるんだな」と、今まで見たことのない野生動物に出会う。
都会にいると、どうしても日々の忙しさに追われて、こういったささやかな発見に気づくことが難しいものです。浦河では、自然の中に身を置くことで、五感が研ぎ澄まされ、心が豊かになる瞬間を何度も味わえます。
5-2. 日本から消えゆく四季を、間近で感じられる
地球温暖化の影響で、日本の四季は徐々に変わりつつあります。
都市部では、春と秋が短くなり、冬の寒さも昔ほど厳しくありません。
しかし、浦河には、まだはっきりとした「四季」が残っています。
春──生命が芽吹く季節

引用元:©2020 jinba kensetsu all rights reserved.(https://www.urakawa-tabi.com/about/)
浦河の春は、桜が咲き乱れ、子馬たちが立ち上がる美しい季節。
まだ冷たい空気の中で、新しい命が次々と生まれ、
「春が来た」と実感することができます。
夏──爽やかな風が吹く季節

引用元:©2020 jinba kensetsu all rights reserved.(https://www.urakawa-tabi.com/about/)
都会の夏は蒸し暑く、エアコンが欠かせませんが、
浦河の夏は、海辺に昆布が干され、涼しい風が吹く過ごしやすい季節。
汗をかくほどの暑さが少なく、自然の風が心地よく感じられます。
秋──色彩が変わる季節

引用元:©2020 jinba kensetsu all rights reserved.(https://www.urakawa-tabi.com/about/)
木々が燃えるように紅く色づき、
鮭が川を上る姿を見ることができる浦河の秋。
ただの景色ではなく、生き物たちの営みの中で季節が巡ることを実感できます。
冬──静かで穏やかな季節

引用元:©2020 jinba kensetsu all rights reserved.(https://www.urakawa-tabi.com/about/)
本州のような豪雪地帯とは違い、浦河の冬は雪が少なく、穏やか。
しかし、海辺ではオオワシやオジロワシが羽を広げる姿が見られ、
冬の厳しさの中にも、生命の力強さを感じられる特別な季節です。
5-3. 都会にはない、浦河ならではの豊かさ

引用元:©2020 jinba kensetsu all rights reserved.(https://www.urakawa-tabi.com/about/)
「物がたくさんあること=豊かさ」ではない。浦河の暮らしは、そう気づかせてくれます。
日々の何気ない発見、季節の変化をじっくり味わう時間、都会では気づかなかった小さな幸せが、ここにはたくさんあります。
「浦河での暮らし、ちょっと気になるかも…」
そう思ったら、一度訪れてみてください。きっと、都会では味わえない「本当の豊かさ」に出会えるはずです。
6.この記事のまとめ
氷河期世代の多くは、長年の不遇により厳しい状況に置かれています。しかし、都会での不安定な生活から抜け出し、田舎でエッセンシャルワーカーとして働くことで、新たなキャリアや充実した生活を手に入れることができるかもしれません。
神馬建設では、個々のライフスタイルに合わせた働き方を提供し、社員が「自分らしく生きる」ことを支援。浦河の豊かな自然と温かいコミュニティの中で、新たな人生を築くことができる環境を整えています。
「今の働き方に悩んでいる」「新しい人生の選択肢を探している」そんな方は、ぜひ一度、浦河という場所を訪れてみてください。


/assets/images/4861760/original/28144748-d770-45d9-bc7a-c44efc7f127e?1586147985)
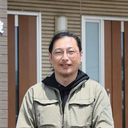
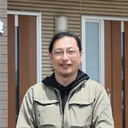
/assets/images/4861760/original/28144748-d770-45d9-bc7a-c44efc7f127e?1586147985)
/assets/images/18240153/original/28144748-d770-45d9-bc7a-c44efc7f127e?1718444995)