【社長インタビュー・第一弾】動いた人から、未来が動く ― TPS 新社長・瀬尾が語る、これからのエンジニアリングと人財への想い
2025年、TPSは大きな節目を迎えました。
新社長に就任したのは、東洋エンジニアリングで設計現場からDX改革までをリードしてきた瀬尾 範章。「現場を知り、経営を変え、そして未来を創る」――そんな挑戦を続けてきた瀬尾が、TPSという新たな舞台で描くビジョンとは?
今回のインタビューでは、瀬尾の言葉を通じて、「TPSがこれから目指す未来の姿」をお届けします。
本記事は二部構成で、第一弾は「TPSの事業戦略」、第二弾は「TPSが目指す環境と求める人物像」について綴っております。
▼新社長Profile:瀬尾 範章
青山学院大学 大学院修了後、2004年に東洋エンジニアリングへ入社。 配管エンジニアとしてキャリアをスタートし、国内外の設計拠点および10か所以上の建設現場で豊富な現場経験を積む。2015年には、東洋エンジニアリング史上最大規模のプロジェクトにて、1,000人超の設計チームを統括。 また、2013~2016年にはビジネス・ブレークスルー大学大学院 経営研究科グローバリゼーション専攻を修了し、マネジメントとグローバル視点を掛け合わせた実践的な経営力を磨いた。 その後、2019年に東洋エンジニアリンググループのDXを推進するDXoT*推進部の部長に就任。生産性を6倍に引き上げることを目標に、デジタルの力を活用した業務改革を推進した。
*DXoT:Digital Transformation of TOYOの略
そして、2025年6月、テックプロジェクトサービス代表取締役社長に就任。
“1 つの判断”が、現場全体を止める――悪いバタフライエフェクトの教訓

東洋エンジニアリングで配管エンジニアとしてキャリアをスタートさせた瀬尾。
2012年、シンガポールでのエチレンプラント改造プロジェクトにて、配管リードエンジニアとして現場を担当。その中で、ある重大なミスを経験する。
設計段階で後回しにした配管の部材が現場に届かず、進捗はストップ。何もできない現場。 現場のリーダーが「空輸でもなんでもいいので、1週間以内に届けられないでしょうか。」と瀬尾を訪ねたと言う。
空輸チャーター便の手配には莫大なコストがかかる。
それでも瀬尾は決断し、調達チームと世界中から部材をかき集め、スケジュールを立て直した。 結果としてプロジェクトは黒字で完了したがこの体験は彼の価値観を根底から変えたと瀬尾は当時を思い起こす。
「このとき、目の前の“現場、現物、現実”の重みを改めて知りました」
この原体験をきっかけに、瀬尾は「現場の判断ミスがプロジェクト全体に連鎖する構造」への課題意識を抱くようになる。以後、DX改革の中心となり、図面や資材の流れについて、リアルタイムで見える化を徹底。リアルタイムで判断・行動できる仕組みを築いていった。
「自分の経験はいわば"悪いバタフライエフェクト"を生みました。けれど、逆にいえば、現場の誰かの小さな気づきが、プロジェクト全体を救う“良いバタフライエフェクト”も生み出せる。」
そう語る瀬尾が今、目指すのは――
「良いバタフライエフェクト」が自然に起きる組織。
誰かの気づきが、現場を、会社を、未来を動かす。 それが、彼の描くTPSのビジョンだ。
変革の先頭に立つ――TPSが切り拓く“ライフサイクル型”エンジニアリング

——異なる“文化”の共存こそがTPSの武器に
TPSには、他社にはない強みがある。
それは、設計・調達・建設(EPC)を担う人財と、保全を担う人財が、同じ組織で一体となって働いていること。
通常なら、これら異なる専門性を持つ人たちは、異なる組織・会社で働いているのが一般的である。
しかしTPSでは、一つの組織の中で“共存”し、機能している。
「新卒とキャリア採用が混在し、経験も文化もバラバラ。でも共通の目的に向かって一つにまとまっている。それって奇跡に近いことです。」
と、瀬尾は語る。
この「多様性を許容し、目的に向かって協働できる力」こそが、TPSの強みであり、「育てるエンジニアリング」を実現する土台になっている。
——“建てて終わり”から“育てる”へ
「“つくって終わり”の時代は、もう終わった。これからのエンジニアリングは、“育てる“フェーズに移る。」

瀬尾が描くのは、 “ライフサイクル型の価値提供モデル“だ。
TPSは、「建設」と「保全」という2つの力を長年培ってきた。そこにデジタル技術をかけあわせることで、「建てた後も継続的に価値を提供し続ける企業」へと進化していくことができる。
この新しいモデルを「最速で実現できるのがTPS」。
そう断言できるのは、TPSには以下のような強みがあるからだ。
- EPCと保全、両方の現場経験
- 高難度案件で磨いた設計・対応力
- 医薬・ファインケミカル領域での実績と信頼
- DXを基盤とした“情報の見える化”の素地
これらを組み合わせ、TPSは「構造的に成長する」ビジネスモデルへの転換を目指している。
稼ぐ力×価値創造力×展開力――三位一体戦略

TPSの未来を形づくるのは、以下の3つの力を融合させた戦略だと瀬尾は語る。
▸ 稼ぐ力
プロジェクト遂行力を高め、高収益・高効率型の案件を着実に獲得。 部門を越えた情報連携と即応体制をTPSのコンパクトな組織力で実現。
▸ 価値創造力
建設と保全の知見に、デジタル技術を掛け合わせることで、運転後の最適化や改善提案まで視野に入れた「先回り設計」を推進。 顧客とともに長期的な価値を生み出すモデルへと進化。
▸ 展開力
高難度案件を通じて蓄積されたGMP*対応ノウハウや品質マネジメントの知見を他分野・他市場へ応用。
リピート受注や設計資産の再活用による高収益化も見据える。
*GMP:医薬品や食品などの製造における品質管理基準である「適正製造規範 (Good Manufacturing Practice)」の略称
——すべては「現場力」から始まる
こうした全ての戦略の土台にあるのが、瀬尾が新入社員時代から大切にしてきた「現場」の力だ。
「TPSは、現場の小さな声を、会社全体を動かす力に変えられる組織です。だからこそ、変革の先頭を走るのは、TPSだと信じています。」
TPSがもつ“稼ぐ力”を、「構造的な成長モデル」へと昇華させ、東洋エンジニアリング全体の変革を牽引する存在になる――
それが、新社長・瀬尾範章が描く次のTPSの姿である。
次回、第2弾では「こんな人と仕事がしたい」。
人物をテーマとした内容をお届けいたします!ぜひご期待ください。

/assets/images/21172619/original/2705f398-a11f-47f3-b20e-9e8824bb3083?1747889336)


/assets/images/21172619/original/2705f398-a11f-47f3-b20e-9e8824bb3083?1747889336)
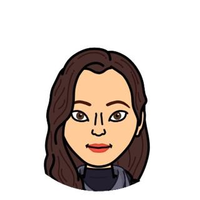


/assets/images/21181143/original/2705f398-a11f-47f3-b20e-9e8824bb3083?1747966073)

