こんにちは!株式会社アクルの採用担当です。
今回は、エンジニア リーダーの松野さんにお話をお伺いしました。
社会の安心・安全を支える「不正検知システム ASUKA」の開発や、新規事業の立ち上げに携わる松野さん。
エンジニアとして技術を磨きながら、事業の中核を担うやりがいや成長環境について語っていただきました。
不正検知という“社会課題”に挑む。アクルのエンジニアが感じる仕事の意義
― アクルに入社されたきっかけを教えてください。
Forkwellで転職活動をしていた際に、アクルから声をかけてもらったのがきっかけです。自社で不正検知サービスを開発・運営している点に魅力を感じました。自社開発体制で、エンジニアとして主体的に関われる環境が整っていたことも大きかったですね。
― 不正検知やFintechの領域には、もともとどんな印象を持っていましたか?
不正検知は、コロナ禍以降オンライン取引が増えたことで、今後さらに重要になる分野だと感じていました。Fintechについては、システムの観点から見ても「お金を扱う」という厳しく難しい領域という印象がありましたね。
― 実際にASUKAの開発に携わってみて、どんなやりがいを感じますか?
社会の安全を支える不正検知システムを通じて、人々が安心してオンライン取引を行える環境づくりに貢献できていることです。「自分の技術が社会に役立っている」と実感できる瞬間が多いのは、この仕事ならではだと思います。
― エンジニアとして成長を感じるポイントはありますか?
金融や不正検知といった高い信頼性が求められる領域で、セキュリティを踏まえた設計や、システムの安定性・拡張性を意識した構築・運用を経験できている点に、大きな成長を感じています。
責任の大きい環境だからこそ、障害を未然に防ぐための設計や、運用時のリスク評価、将来的な負荷を見据えたアーキテクチャの検討など、エンジニアとして重要な判断力を日々磨くことができています。こうした経験を積み重ねる中で、自分の技術力や視野が着実に広がっていると実感しています。
第二創業期、エンジニアにも裁量を。事業を動かすフェーズへ
― アクルの変化を、エンジニアとしてどう感じていますか?
不正検知やFintech分野への注目が高まる中で、求められる技術レベルは年々向上していると感じております。常に新しい技術を学び続ける必要がありますし、当社でも資格取得など自己研鑽を大切にする文化が根付いています。
私自身も、資格取得への取り組みはもちろん、社外のエンジニアと交流するためにもくもく会へ参加したり、日々の技術ニュースをチームへ共有したりすることで、メンバー全体のスキル向上に貢献したいと考えております。
― プロジェクトの要件や仕様はどのように決めているのですか?
まず、ビジネス側から要望や課題をヒアリングし、エンジニア側で実現方法や影響範囲を整理します。そのうえで、チーム内で議論を重ねながら方向性を固め、必要に応じてプロトタイプを作成し、関係者と認識を合わせていく進め方を取っています。
要件定義や仕様策定では、技術的な観点だけでなくビジネスの視点も欠かせません。ユーザー価値や事業への影響も踏まえながら、最適な形を模索していくことを意識しています。
― 裁量の大きさを感じる場面はありますか?
裁量の大きさを感じる場面は多いですね。NEXT チームは特に自由度が高く、技術選定からタスク管理、進め方の判断まで、自分の裁量で進められる部分が大きいと感じています。
その分プレッシャーもありますが、チーム内で報連相を徹底し、一人で抱え込まないようにすることで、適切にリスクをコントロールしながら進めています。自分の判断で動ける環境だからこそ、責任感を持って意思決定する大切さを日々実感しています。
― ご自身の提案が反映されたエピソードはありますか?
RDS から Aurora へ移行する計画は以前からあったのですが、なかなか着手する機会がありませんでした。そこで私から「ぜひ取り組みたい」と提案し、上司に相談した上で検証から本番切り替えまで、メイン担当として進めさせていただきました。
移行は決して簡単な作業ではなく、RDS と Aurora の性能差を見極めるための負荷試験、適切な ACU(スペック)の検証、障害発生時を想定したフェイルオーバー対応、切り替え作業に必要な時間計測など、段階的に多くの検証を重ねました。また、関係部署への説明や調整も丁寧に行い、当日の作業が滞りなく進むよう事前準備にも力を入れました。
その結果、運用効率とシステムの安定性を向上させる改善につなげることができました。自分の提案が実際のプロダクト改善として形になり、無事に移行を完了できたことは、エンジニアとして大きな自信になりましたし、今後の挑戦への励みにもなっています。
技術と挑戦を支える開発現場・文化
↑オンラインミーティングの様子
― 開発環境について教えてください。
私の所属する部署では、主な開発言語として Ruby を使用し、フレームワークには Ruby on Rails を採用しています。また、案件に応じて Go 言語とそのフレームワークである Gin を用いた開発も行っております。
インフラ基盤には AWS(ECS、Lambda、S3 など)を利用しており、Terraform を使ってインフラ構成をコードで管理しています。さらに、アプリケーションのコンテナ化には Docker を活用し、サービスの可搬性と運用効率を高めています。
コード管理には GitHub を使用し、ドキュメント作成・タスク管理・コミュニケーションには Confluence、Jira、Slack などを組み合わせて、開発を円滑に進めております。
― 技術選定や新ツール導入の進め方は?
新しい技術やツールの導入には前向きに取り組んでおります。導入を検討する際は、まずプロジェクトの要件やスケジュールに照らし合わせながら、実際の運用で開発効率や保守性が向上するかどうかを慎重に判断しています。
特に新規案件では、チーム内の他のメンバーが無理なく対応できるかという点も重視しています。技術選定の際には、GitHub のスター数、ドキュメントの充実度、情報量(記事の多さ)などを確認し、長期的に運用できるかどうかも含めて判断しています。
その上で、導入効果が見込めると判断できれば、既存のやり方に固執せず柔軟に取り入れる方針です。実際に、Go 言語と Gin フレームワークを用いた新規開発にも挑戦し、プロジェクトに適した技術を積極的に選択する文化づくりにも貢献できたと感じております。
― コードレビューやナレッジ共有で意識していることは?
コードレビューでは、指摘が相手にとって理解しやすく、前向きに受け取っていただけるような伝え方を意識しています。単に修正点を指摘するのではなく、その背景や改善理由を添えることで、レビュー自体が学びの機会になるよう心がけています。
また、ナレッジ共有においては、まず「この資料はどの立場の人が読むのか」を意識し、読み手に合わせた分量や構成を大切にしています。質問が少なく、読み進めるだけで理解できる資料を目標としており、図や表を適切に使いながら、手順や意図が直感的に伝わるよう丁寧にまとめるようにしています。これによって、チーム全体の理解度や開発効率が向上することを意識して取り組んでおります。
― チャレンジを歓迎する雰囲気はありますか?
はい、とてもあると感じています。新しい技術の導入や改善提案を積極的に受け入れる文化があり、失敗を恐れずに試行錯誤できる環境が整っています。エンジニア一人ひとりが主体的に学び、挑戦できる空気があることは、アクルらしさの一つだと感じています。自分の意見やアイデアを発信しやすい環境があるからこそ、成長につながる機会も多いと感じています。
― AIの活用についてはどう考えていますか?
開発や資料作成の際には、AI を積極的に活用しています。作業効率の向上には非常に役立ちますが、AI が提示する内容をそのまま鵜呑みにするのではなく、自分で正しさを判断し、必要に応じて検証する姿勢が重要だと考えています。
AI はあくまで支援ツールであり、最終的な要件の整理や仕様の判断は人間が責任を持って行うべき部分です。AI を効果的に使いこなしながら、プロダクトにとって最適な判断を自律的に下せるエンジニアでありたいと考えています。
↑こんな感じでSlackでナレッジの共有が行われています
「技術を極めたい」も「事業を学びたい」も叶う。キャリアの広がり
― 入社当初と比べて成長を感じる部分は?
入社当初と比べて大きく成長を感じているのは、システム全体を俯瞰して課題を見つけ、改善提案まで一貫して行えるようになった点です。特にインフラ面では、安定稼働を意識した設計や判断を自ら主導できるようになり、より長期的な視点でシステムを見る力が身についたと感じています。
また、管理する立場になったことで、個々の作業だけでなくプロジェクト全体の流れやチームの状況を踏まえて判断する力も鍛えられました。以前よりも広い視点で物事を捉えられるようになったことは、自分自身の成長として大きいと感じています。
― リーダーとして意識していることは?
リーダーとして意識しているのは、メンバー全員が気持ちよく開発に取り組める環境づくりです。意見を言いやすい雰囲気をつくり、困ったときにすぐ相談できるようなサポート体制を整えることを大切にしています。
また、業務の属人化をなくし、チーム全体の負荷を減らすために、自動化による効率化にも積極的に取り組んでいます。日々の作業が少しでもスムーズになり、メンバーが開発に集中できるような環境を整えることが、リーダーとしての役割だと考えております。
― 将来的に挑戦したいことは?
将来的には、より大規模なシステムの設計やアーキテクチャ設計に携わり、技術面での専門性をさらに高めていきたいと考えております。
また、技術力だけでなくマネジメント力も磨き、チームを率いるエンジニアリーダーとして成長していきたいと思っています。個々のメンバーが力を発揮できる環境づくりにも貢献しながら、チーム全体としてより大きな価値を生み出せる存在を目指していきたいです。
“安心して挑戦できる”ベンチャーで働くという選択

― チームの雰囲気を一言で表すと?
「勉強熱心で仲の良いチーム」です。
みんな自己研鑽に積極的で、資格勉強や情報共有も活発。お互いに支え合える雰囲気があります。
― 一緒に働く仲間の印象は?
向上心が高く、新しい技術を吸収する姿勢が印象的です。困ったときに気軽に相談できる関係性もあり、成長意欲を刺激されます。
― どんな方と一緒に働きたいですか?
不正検知という社会課題に興味があり、新しい技術を学ぶ意欲がある人ですね。特に、将来的にリーダーを目指したい方や、インフラにも関心のある方にはぴったりの環境だと思います。
アクルは、「決済にかかわるあらゆる課題を解決する」というミッションのもと、
不正検知という社会的意義の高い領域で事業を展開しています。
自社開発で技術を磨きながら、社会に貢献できるやりがいのある仕事です。
今後は新規事業も加速していきます。
主体的に学び、挑戦したいエンジニアの方。
私たちと一緒に、技術で社会の安心をつくっていきませんか?

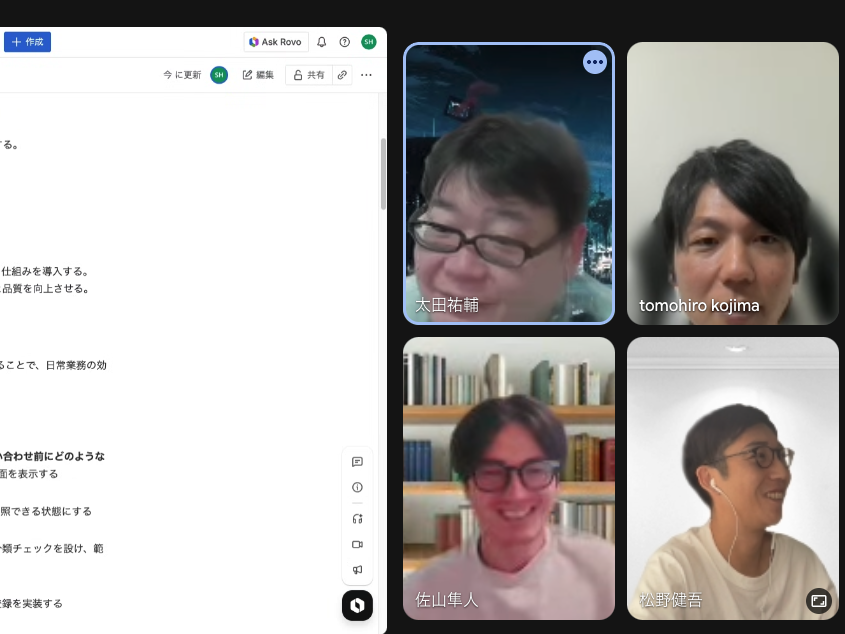

/assets/images/22514217/original/a379b6da-2efb-4730-872c-a03be8f30145?1763526336)

/assets/images/2011300/original/7e1626ec-446f-4ebb-9839-bdccff07d90e?1516606692)


/assets/images/2011300/original/7e1626ec-446f-4ebb-9839-bdccff07d90e?1516606692)

