【COOメッセージ】僕らがエンタメの縁の下の力持ちであり続ける理由。~エンタメの“裏方”をワンストップで支える仕組みづくり~
HIKIFUDAは、「ものづくりから世界を拡張する」というミッションのもと、エンターテインメント業界に特化した課題解決型のサービスを展開しています。現在はOEM事業を基盤に、製造業におけるBPOサービスと業務DX支援を組み合わせた独自のアプローチで、業界全体の変革を目指しています。
今回は、クリエイターが創造に集中できる環境とは何か、そしてそれを支える実行力の裏側について、取締役COO兼CFOの秋田さんに語っていただきました!
【プロフィール】
秋田 浩平
取締役 COO / CFO。大学卒業後、みずほ銀行にて約10年間法人営業を担当。その後、税理士法人ベリーベストで4年間、事業承継を中心とした法人向けコンサルティングに従事。ITSでは、経理代行や財務・税務アドバイス、融資支援など幅広い金融コンサルを経験し、2023年に独立。2024年より正式にHIKIFUDAにジョイン。
エンタメの“裏側”にある課題に、正面から向き合いたい
僕がHIKIFUDAにジョインしたのは、まだ会社が立ち上がったばかりの黎明期でした。最初は外部CFOという立場で参画し、1年以上そのポジションを務めたのち、2024年から正式に取締役として関わるようになりました。
もともとエンタメ業界に深く携わっていたわけではなく、それまでのキャリアは金融やコンサルティングが中心でした。ただ、まったくの無縁だったかというとそうではなくて、僕自身、ゲームやマンガが好きで、趣味としてずっと触れてきた世界でもありました。だからこそ、HIKIFUDAの事業に初めて触れたとき、「これは、自分の“好き”と“仕事”がつながるかもしれない」と直感的に思ったんです。
それに、自分のこれまでのバックグラウンドが、まったく新しい業界でどこまで通用するのか——そんな挑戦心もあって。正直、ワクワクしていましたね。
実際に参画してまず感じたのは、エンタメ業界の“裏側”が想像以上に属人的で、非効率だということでした。
クリエイターとファンという“表の関係性”に注目が集まりがちなこの業界ですが、それを支えるための計画、人員配置、資金管理、業務フローといった「守り」の部分が非常に脆弱なんです。たとえばグッズ製造においても、10種類の商品をつくるなら、それぞれ別々の会社に連絡・発注し、納期管理もバラバラに行う必要がある。マルチタスクが当たり前で、担当者が疲弊してしまっているケースも珍しくありません。
さらに、クリエイター側も「ファンのために」という思いが強いために、価格設定や収益性に対する視点が弱くなりがちです。お金がなければ次の活動はできない——その現実との間で葛藤している方も多いと感じます。
だからこそ、僕らのように財務や経営の視点を持つ存在が、冷静に全体を設計し、持続可能な仕組みをともに作っていくことが大切だと、強く実感しています。

分断された業務フローを、ワンストップで解決する仕組みを
当社では、グッズのOEMから販売代行、在庫管理、配送までを一気通貫で担っています。こうしたモデルが評価される理由のひとつに、僕らが単に「モノを作って終わり」ではなく、資金繰りやキャッシュフローといった経営的な視点をしっかり織り込んでいるという点があります。
通常、グッズは製造が終わったタイミングで仕入れ代金を支払うのが一般的です。でも、クリエイターや中小の事業者にとって、制作段階で大きな資金が必要になるのはかなりの負担になる。そこで僕らは、販売が完了してから支払いが発生する仕組みを整え、キャッシュアウトを極力抑える設計にしています。
お金の不安が減れば、クリエイターはより自由に、より良い創造活動に集中できます。ファンの期待に応えるために自己犠牲してしまうような方々が、少しでも現実と折り合いをつけながら活動を続けられるように。僕らの存在意義は、そうした“バランスを整える”ところにもあると思っています。
一方で、現場と接してよりリアルに感じているのが、マルチタスクに追われるエンタメ業界の構造的な課題です。たとえば、グッズを作るにしても、企画、スケジュール管理、製造、配送、販売、在庫管理……と、1つのプロジェクトの中で、実に多くの業務が存在します。そして、それらを1人の担当者がすべて抱えてしまっているケースも少なくありません。
僕たちはそうした構造的な課題を、「横ぐし」で解決する存在でありたい。単なる業務受託ではなく、お客様のビジネスパートナーとして、最初の企画段階から出口まで伴走したいと考えています。
具体的には、最近では、あるクラウドファンディングプラットフォームを運営する企業様とご一緒しています。
クラウドファンディングを利用するプロジェクトオーナーの多くは、リターン品(返礼品)の製造や配送などの実行フェーズにまで手が回らないという課題を抱えています。そこで僕たちは、企画段階から製造、物流、在庫管理までをワンストップで支援。製造工場の手配や配送代行まで含めて一括で担うことで、プロジェクトオーナーの方々がコア業務に集中できる体制を整えました。
これは、エンタメ領域のバックオフィスを包括的にDXする好事例だったと思います。プロジェクトオーナー、プラットフォーム、HIKIFUDA——それぞれの強みが活きる“三方よし”の関係が実現できたと感じています。
現在は他のプラットフォームやファンクラブ運営会社、YouTuber・VTuber関連の企業とも話を進めており、より多くのプロジェクトを支える体制づくりを広げているところです。
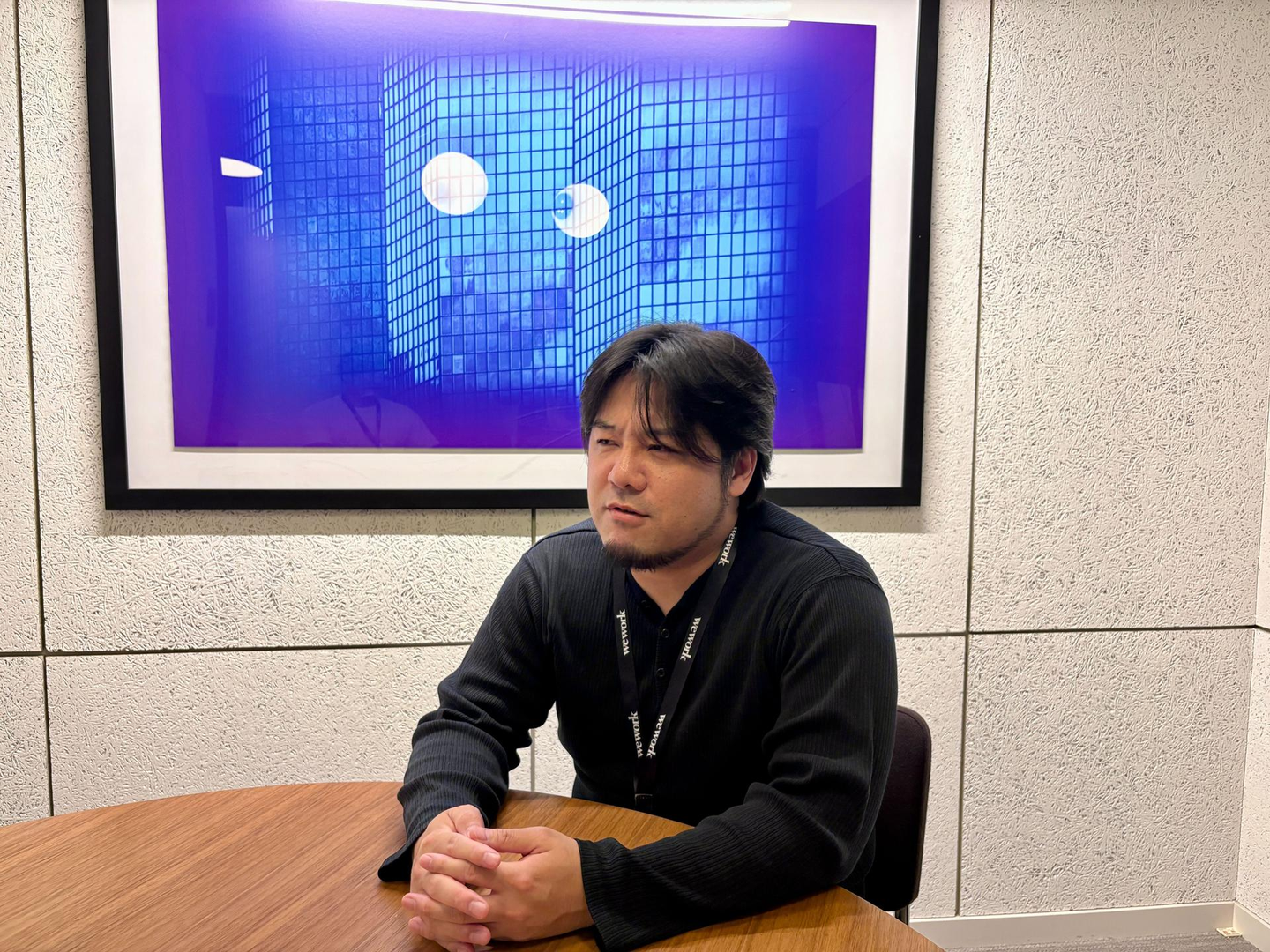
現場に根ざした「実行力」が、HIKIFUDAを支えている
こうした“実行力”こそが、HIKIFUDAの一番の強みだと僕は思っています。
イベントの成功に向けて、何をいつまでに準備し、どう進行していくべきか。その全体像を掴み、逆算してスケジュールを引き、必要なアクションを実行していく。単に「納品を間に合わせる」ではなく、「どうすればビジネスとして最適解になるか」を常に考えて動いています。
実際に、ある広告プロジェクトでは、年始に依頼を受けてから、わずか2ヶ月半で駅に広告を掲出するというチャレンジがありました。お客様も最初はスケジュール感が見えていなかったのですが、僕らが全体を逆算し、必要なステップを提示して、デザイン・制作・実施までを一気にまとめ上げたんです。
「ここまで短期間でやりきれるのは、御社だけだった」と、ありがたい評価もいただきました。
そういうとき、自分たちが担っている「実行力」が、誰かの挑戦を後押しし、前に進めているんだと実感します。
HIKIFUDAの面白さは、そうした“実行力”を支えているチームにもあります。
僕を含め、営業メンバーは現在4名。なかには、エンタメ業界にどっぷり浸かってきたメンバーもいますし、僕や代表の入澤のように、もともと金融やバックオフィス領域出身の人間もいます。だからこそ、多様な視点を持ち寄りながら、「現場感」と「経営目線」の両方で問題解決できるのが強みだと思っています。
COO/CFOとして、僕がHIKIFUDAで担っている大きなミッションのひとつは、エンタメ業界における「バックオフィスの価値」を高めることです。
エンタメはクリエイターやファンの情熱で成り立っているからこそ、つい「人力でなんとかする」ことが前提になってしまいがちです。でも、情熱だけでは続かない。持続可能な仕組みがあってこそ、良いクリエイションは続いていきます。そこをしっかり支え、業界の当たり前にしていくのが、僕自身の使命だと感じています。

業界の枠を超えて、新しい価値を届けていく
これから挑戦したいのは、HIKIFUDAの可能性をエンタメの枠を超えて広げていくこと。
いまはアニメや音楽、IP業界などが中心ですが、僕らの「ものづくりとバックオフィス支援の仕組み」は、他のエンタメ領域や、ノベルティが必要な一般企業にも展開できると考えています。
実際、すでに新しい業界へのアプローチも少しずつ始まっています。「ものづくりから世界を拡張する」というHIKIFUDAのミッションを、より多様な分野で体現していきたいですね。
そして、こうした新しい挑戦を一緒に面白がってくれる仲間とも、これからもっと出会いたいと思っています。
HIKIFUDAは、いわゆる“ベンチャー”を乗り越え、次のステップに進んでいるフェーズです。でも、だからといって挑戦が終わったわけではありません。むしろ今は、「どれだけ世の中に影響力を与えられるか」を本気で試されている段階です。
僕たちは、挑戦意欲と行動力がある人にぜひ来てほしいと思っています。時代は大きく変わり、AIも急速に台頭している今、望めば何でも実現できる可能性があります。そうした環境を積極的に活かし、チャレンジしたい人を全力で歓迎します。
僕らの仕事の面白さは、自分の「好き」と仕事を自然に結びつけられるところにあります。僕自身もゲームが好きで、その趣味をそのまま仕事に活かせているんです。
さらに、同じように「好き」な仲間が集まり、縁の下の力持ちとして、クリエイターの方々が本来の「創造」に集中できるようにしっかりとサポートしている。そのような意味で、エンタメ業界の中でも少し特別な役割を担っている会社だと感じています。
だからこそ、こういう環境で挑戦してみたいと思った方には、ぜひ仲間になってほしいですね。
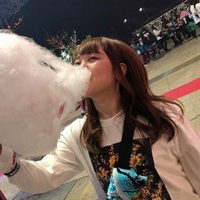

/assets/images/19703393/original/b2504a9f-3fde-4438-8fff-37f5ed855202?1731570926)


/assets/images/19703393/original/b2504a9f-3fde-4438-8fff-37f5ed855202?1731570926)





/assets/images/19703393/original/b2504a9f-3fde-4438-8fff-37f5ed855202?1731570926)

