プロダクトオーナー自らがコンピューターに!?|徹底した現場目線から生まれた 生成AIライティングツール「Writing Assistant」
マーケターの業務範囲は、今や拡大の一途をたどっています。市場の飽和や顧客ニーズの多様化などによって戦略・戦術立案の重要性は増す一方で、日々の業務に忙殺され、「考える」業務に時間を割けずにいます。この課題に対し、シナジーマーケティングは、25年のデジタルマーケティングの知見と生成AI技術を融合させたAIライティングツール「Writing Assistant」を2025年4月に提供開始しました。
今回は、Writing Assistant開発のキーマンであるプロダクトオーナーの豊田さん、CTOの馬場さん、エンジニアの東さんに、開発プロセスやプロダクトにかける想いなどを聞きました。
(ロングインタビュー版はこちらから)
■この記事のポイント
・「Writing Assistant」の特徴
AIが既存の資料などから、ターゲット顧客や配信チャネルの特性に合わせて、最適な訴求テーマや洗練されたテキスト原稿を自動で提案してくれる点が特徴。
・開発プロセス
プロダクトオーナー自らマーケティング業務を体験することで解像度を高め、機能開発の制度を向上。結果、戦略的かつ読者のニーズに応えるコンテンツを作成できる「二段階のアプローチ」と、極限まで手入力を減らしたシンプルなUI/UXが完成した。
・今後の展望
現場の課題を深く理解する開発プロセスを経て、今後はマーケティング施策全体をシームレスに繋ぐプラットフォームへの進化を目指す。
プロフィール
豊田 航輔 / プロダクトデザイン部 プロダクトマネジメントグループ
2021年新卒入社。入社以来営業担当を務め、2024年4月より新規プロダクト企画の担当となり、Writing Assistantを企画。現在はWriting Assistantをより多くの企業様に使ってもらえるように、プロダクトオーナーとして奮闘中。
馬場 彩子 / 取締役 兼 CTO
2001年に株式会社四次元データ(現 シナジーマーケティング株式会社)にローンチメンバーとして入社。Synergy!をはじめとするSaaSのローンチやML/AI研究など多岐にわたるプロジェクトに携わる。長年スタッフエンジニアとして活躍後、2020年にCTOに就任。インフラ・アプリケーションの大規模刷新プロジェクトと組織変革を主導。2023年より取締役兼CTO。
東 優 / プロダクト開発部 第6プロダクト開発グループ
2011年中途入社。iNSIGHTBOX、メール広告配信サービス、en-chantと主に「Synergy!」以外の開発に従事。現在は生成AIに興味津々。
※部署名・役職は取材当時(2025年4月)のものです
マーケターの業務をアシストして、業務効率化と品質向上をサポート
―― 「Writing Assistant」はどのようなツールですか?
豊田:Writing Assistantは、既存の資料を読み込ませるだけで、ターゲット顧客に合わせて最適な訴求テーマを提案し、それを含んだマーケティングコンテンツを制作することができるツールです。独自のプロンプト設計により、専門知識なしにターゲットに最適化したテーマを自動提案し、最速1分程度で各種テキストのドラフトを生成します。Web記事、電子メール、SNS投稿といった複数のメディア形式に対応した質の高いテキスト原稿を一度に作成できる、まさにマーケターの頼れるアシスタントです。
人ではなく、Writing Assistantがアシスタントの役割を果たすことで、「日々の業務に追われてコンテンツ企画・制作の時間が不足しがちなマーケティング担当者の負担を大幅に軽減」できるだけでなく、「企業やチームの規模に囚われず、今よりも低コストかつ短期間でマーケティング施策の成果最大化」が実現できると考えています。
馬場:そのような考えから、「Writing Assistant」という名称には、「単なるツールではなく、人間のメンバーのように企業や部署の状況に寄り添い、最適なご支援ができるプロダクトでありたい」という思いが込められています。
東:このツールの特徴は、AIが既存の資料などから、ターゲット顧客や配信チャネルの特性に合わせて、最適な訴求テーマや洗練されたテキスト原稿を自動で提案してくれる点にあります。AIに関する高度な専門知識や複雑な初期設定は一切不要。誰でも直感的に操作でき、短時間で高品質なコンテンツを生み出すことが可能です。
【撮影場所:WeWork 麹町】
―― 企画・開発がはじまったきっかけを教えてください。
馬場:既存のソリューションでは手が届かなかったマーケティング業務領域への支援を形にするため、新たなプロダクト開発の検討がスタートしました。その構想を具体化する過程で、マーケティングの最前線における業務プロセスや直面する課題を徹底的に洗い出した結果、特に文章作成、すなわちライティング業務が担当者にとって大きな負荷となっている実情が明らかになりました。
豊田:私が営業の前線にいた頃、多くの企業がセグメント配信の重要性を認識しつつも、コンテンツ制作の負荷の高さからその効果を十分に引き出せていない状況を目の当たりにしていました。「限られた時間の中で働くマーケターが、伝えたいメッセージを的確かつ迅速に形にできる。そんな世界を実現したい」という思いもありました。
プロダクトオーナー自らがマーケ現場に飛び込み、課題を自分事化
―― 開発プロセスを教えてください。
馬場:2024年4月から4か月間はプロダクトの方向性を探るための調査と検討を繰り返し、8月に方向性が決まりました。その後、追加調査を行い、プロダクトに必要な機能を絞り込みました。アルファ版、ベータ版を経て、2025年4月に製品版の提供を開始しました。
―― 企画立案からわずか1年という短期間で「Writing Assistant」のサービス提供を開始していますが、スピード開発を実現できた要因を教えてください。
馬場:開発チーム内の密なコミュニケーションと迅速な意思決定プロセスが挙げられます。プロジェクトの中核メンバーは豊田さん、東さん、私の3人で、毎日ミーティングをしながら密に連携して開発を進めていきました。必要に応じて、社内のデザイナーやエンジニアにも適宜協力してもらいました。
豊田: それに加えて、特に力を注いだのは、実際にマーケティング業務に携わる担当者への徹底したヒアリングです。現場が抱える生々しい課題やニーズを深く掘り下げることで、真に役立つツールの姿を追求しました。
当時マーケティングの実務経験がなかったので、ヒアリングした内容から想像を膨らませることはできても、やはり限界がありました。そこで、私自身が実際の記事作成業務などに参加することで、マーケターが日々の業務で直面する困難や、本当に必要としているサポートは何かを、身をもって理解することができたと考えています。
―― 開発時に工夫した点や苦労した点も聞かせてください。
東:工夫した点は、コンテンツ作成フローです。まず、届けたい相手(ターゲット層)と伝えるべき内容(訴求テーマ)を明確に定め、そのうえでWriting Assistantが具体的なテキストを生成する、という二段階のアプローチにしています。これによって、より戦略的かつ読者のニーズに応えるコンテンツを作成し、コンテンツマーケティングの成果最大化をご支援します。
豊田:他にも、誰でも簡単にパパッとコンテンツを作成できるように、極限まで手入力を減らしたシンプルなUI/UXにしています。社内メンバーにベータ版を操作してもらい、「ここが使いづらい」などの意見を取り入れて使いやすさに磨きをかけました。
苦労した点は、プロンプトの設計です。担当した当初、私自身が生成AIの経験もエンジニアリングの知識もなく、何から手をつけていいか分からない状況でした。しかし、東さんや馬場さんの助言を受けながらとにかく手を動かし続けた結果、プロンプトに触れる時間と量が増えるにつれて理解が深まりました。最終的には、プロンプトの良し悪しの判断や、自分がイメージしたものを大体出力できるようになりました。
生成AIを活用して、マーケティングの「新しい当たり前」を創造する
―― 今後の展望を教えてください。
東:現在の生成AI技術には、まだ技術的な制約や我々の理解が及んでいない部分があるのが実情です。そのため、まずは着実に開発経験を積み重ね、実践的な知見を蓄積していくことが重要だと考えています。そして、時流に沿ったプロダクトを生み出すためには、技術の進化にただ追従するだけでは不十分です。私たちは、技術が進化する未来を予測し、「次にどのようなプロダクトを創るべきか」という構想力を常に広げておく必要があると考えています。
馬場:今後数年の展望として、私たちは「Writing Assistant」を含む当社のプロダクト群を、単なる個別のツールから、マーケティング施策全体をシームレスにつなぐ一つの統合プラットフォームへと進化させたいと考えています。コンテンツの作成から配信、反応分析、そして改善に至るまで、あらゆるプロセスを網羅するものです。
その実現の鍵となるのが、AI技術を活用した直感的でシームレスなインターフェースです。私たちは、このインターフェースを通じて、企業とステークホルダー間のコミュニケーションを根底から変え、より円滑な関係性を築くプロダクトを提供するためにこれからも創造を続けていきます。

若手が活躍し、誰もがチャレンジできる環境で、あなたの「やってみたい」を形にしませんか。生成AIをはじめとする最先端技術を活用したプロダクト開発に携わり、お客様のビジネスを加速させる情熱を共有してくださる方をお待ちしています。募集要項または「話を聞いてみたい」からお問い合わせください。



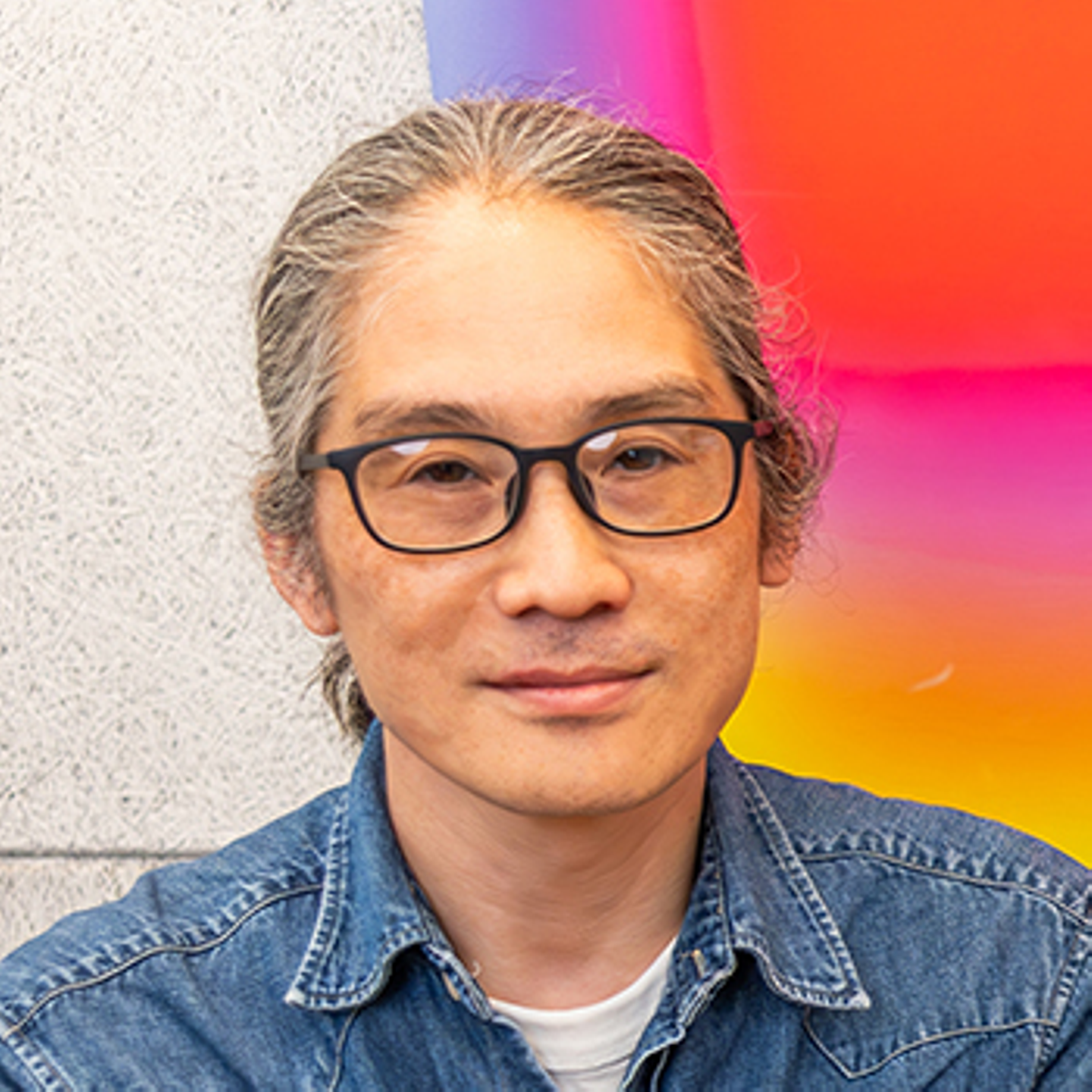


/assets/images/6353161/original/3b7b43a7-b34b-4467-91bd-529a2081c4a6?1664191160)


/assets/images/6353161/original/3b7b43a7-b34b-4467-91bd-529a2081c4a6?1664191160)
/assets/images/6353161/original/3b7b43a7-b34b-4467-91bd-529a2081c4a6?1664191160)

