いま、日本企業のグローバル展開がますます求められる中で、私たちストライクは「クロスボーダーM&A」に本格的に取り組み始めました。特に中堅・中小企業にとって、海外への挑戦は決して簡単なものではありません。そうであるにもかかわらず、そうした企業を本気で支援できるプレイヤーは、いまだ限られています。
「私たちがやるしかない」そう考えて始まった新規事業の立ち上げは、社員の自発的な動きから始まりました。現場から自然と芽吹いた挑戦が、今や会社全体の意志へと広がりつつあります。
今回は、クロスボーダーM&Aにかける想いを代表取締役社長の荒井と副社長の鈴木、そしてクロスボーダーM&A事業を立ち上げた豊住に聞きました。ストライクにとってクロスボーダーM&Aとはどんな意義があるのか、どんなやりがいを感じているのか。語ってもらった内容をお届けします。
クロスボーダーM&Aに挑む理由――誰もいない市場にこそ価値がある
――ストライクが本格的にクロスボーダーM&Aに取り組む理由を聞かせてください。
鈴木:企業のニーズが高まっているからです。私たちのお客様のなかにも「海外企業を買いたい」「海外に展開したい」という声が少なくありません。一方で、そのニーズにしっかりと応えられるプレイヤーが少ないのも事実です。特に中堅・中小企業の規模のクロスボーダーM&Aを支援できる仲介会社は、ほとんどないと言えるでしょう。
私自身、以前はアメリカで仕事をしていたので、日米間の文化や慣習の違いを肌で感じてきました。だからこそ、日本企業が海外と手を結ぶうえで、きちんとした伴走役が必要だと思うのです。
――市場があるのに、なぜ他の仲介会社や支援機関は踏み込まないのでしょうか?
荒井:おそらく効率が悪いからだと思います。大型案件なら投資銀行が動きます。しかし、中堅規模のクロスボーダーM&Aは、手間のわりに実入りが少ないと敬遠されがちです。一方で私たちは、これまで数多くの中堅・中小企業のM&Aを手がけてきました。
その実績と、築き上げてきたノウハウがあるからこそ、無理のないコスト構造を構築できるのです。大手のような一兆円を超える派手なM&Aはできませんが、数億〜100億円クラスのM&Aをきちんと支援できるのが、ストライクの存在意義だと思っています。

ストライクだからできる。自走と信頼で切り拓く未開の地
――クロスボーダーM&Aの事業はどのように立ち上がったのでしょうか?
荒井:決して、計画的に始めたわけではありません。もちろん、いつかは手掛けるべきだとは考えていました。しかし、それは組織が300名を超え、体制を整えた後のことです。
実は、私が指示をする前に豊住がひそかに始めていました(笑)。しかし、それを止めなかったのは「いける」と思っていたからです。誰かが「やってみたい」と動き出し、筋が通っていれば会社の指示を待つ必要はありません。
過去にもスポーツチームのM&Aという領域が自然発生的に立ち上がったことがあります。トップダウンで「これをやれ」と言うよりも、現場から湧き上がる熱意に任せた方が、いい結果が出ると信じているんです。
――社員主導で新しい事業が生まれる文化が根付いているのですか?
荒井:もちろん、見通しが甘いものは止めます。しかし、なんでもかんでも厳しく見ていたら、社員の自発性は育ちません。メリハリが大事なので、やってみてうまくいかなくても咎めず、動いたこと自体を歓迎したいと思っています。
組織としての統制は取りつつも、挑戦には寛容でありたい。それが、結果的にクロスボーダーM&Aのような新しい取り組みにもつながっていると思います。
――豊住さんは、なぜクロスボーダーM&Aを始めたのでしょうか?
豊住:ニーズがあるのに、誰も手を出していなかったからです。私がストライクに入社したのは、自分のやりたいことにチャレンジできると思ったから。転職の際に、M&A業界大手の代表のみなさんと話した結果、ストライクがもっとも自由に働ける社風を感じました。
私は、すでに他の人がしている仕事をするために、この業界に飛び込んだわけではありません。他の人がやっていない仕事だからこそ、私がやる意義があると思っています。もちろん、それは簡単な仕事ではありません。正直に言えば、クロスボーダーM&Aも、荒井や鈴木の力を借りて、どうにか成約に結びつけられました。

――やはり難しいチャレンジだったのですね。
鈴木:クロスボーダーM&Aは法制度も文化も違う海外の企業と相対しなければならず、国内のM&Aとは桁違いに難しいチャレンジです。そのため、豊住も動き始めてから学んだことも多いでしょう。
それでも、まずは動く姿勢が大事ですし、壁にぶつかったときに楽しみながら打開策を探せる豊住ならではの成果だと考えます。そのような人がこの仕事に向いていると思います。

派手な大型案件でなくてもいい。社会にとって意義のある仕事を
――クロスボーダーM&Aと聞くと、巨大企業の派手な買収劇をイメージしてしまいます。ストライクが扱う案件は、どのようなものが多いのでしょうか?
荒井:ストライクでは、そのようなニュースで見るような派手なものは狙っていません。むしろ新聞の一面を飾るような数千億円を超える規模の案件は、別の会社がやった方がいいとさえ思っています。私たちが価値を発揮できるのは、数億〜数百億円ぐらいの中規模の案件です。
たとえば最近は日本酒の酒蔵さんに関するM&Aセミナーをやったこともあります。英語サイトを作って海外に発信したり、日本酒の魅力を世界に伝えようとがんばっている酒蔵さんがたくさんいる。そこに海外の投資家が関心を示しているんです。
――意外と知られていない日本の価値が、海外では評価されているのですね。
荒井:そうなんです。たとえば、私たち日本人にとっては当たり前のものでも、海外の人から見たら魅力的に映ることは珍しくありません。渋谷のスクランブル交差点だって、日本人からしたら「ただの交差点」かもしれませんが、海外の人にとってはフォトジェニックな観光地ですからね。
M&Aでも同じです。日本企業の魅力を見抜ける海外の目線が入ることで、これまで見落とされていた価値が掘り起こされます。そのような“新しい視点との出会い”が、クロスボーダーならではの面白さです。

――クロスボーダー案件での難しさも聞かせてください
荒井:為替の問題や税制や法制度の違い、文化的な摩擦……国内のM&Aでは起きないことが、クロスボーダーでは当然のように起こります。その一つひとつに対応するには、人手もいりますし、コストもかかります。国ごとの会計の違いを勉強するだけでも、大きな労力でしょう。
そのため、従来のクロスボーダーM&Aでは、投資銀行などが巨大なチームを編成しなければならず、大型の案件でなければ利益を出せませんでした。しかし、私達は中堅・中小企業のM&Aに特化してきたからこそ、コストをかけずとも支援ができますし、必要なネットワークも揃っています。それこそが、中規模の案件でも利益を出せる秘密です。
ストライクが大切にしている「M&A観」
――クロスボーダーに限らず、ストライクがM&Aという事業を通じて大事にしている価値観を聞かせてください。
荒井:一言でいえば「仲間づくり」です。かつては日本でM&Aと聞くと、ネガティブな印象を持っている方も少なくありませんでした。
しかし、M&Aは単に企業を売買するだけでなく、1社ではできなかったことを、2社一緒になることでできるようにするという価値も含まれています。M&Aによって業績が上がれば、社員の給料も上がるし、会社は税金を多く納めて、自治体や国にも貢献できますよね。上場企業であれば株主にも還元できる。つまり、M&Aは“皆で豊かになるための手段”なんです。
――だからこそ、案件の大きさではなく「意義」が問われると。
荒井:その通りです。どれだけ本質的な価値を生むかが、ストライクの存在意義です。そしてそれを支えるには、単なるテクニックではなく、“何のためにやるのか”という価値観が欠かせません。
たとえば、売り手が「社員の雇用を守りたい」と言ったら、そこを最優先にするのが我々の仕事です。「高く売れればそれでいい」という発想だけでは、いいM&Aにはなりません。相手の想いにどこまで寄り添えるか。そこに本当のプロフェッショナリズムが問われると思っています。
――差別化という点については、どう考えています?
荒井:私は「差別化」とは、自分たちが発信することではないと思っています。投資家、求職者、お客様……選ぶ側が「だからストライクにした」と感じるものこそが、差別化です。言い換えれば「真似できそうで、真似してもうまくいかない」こと。それが本質的な差別化なんだと思います。
言語化できるような強みは、もう誰かがやっているはずです。そうではなく、言語化できないけど上手くいく、不思議と信頼される――そういう“空気”みたいなものが、ストライクの強みかもしれません。
特にM&Aは“人と人”の仕事ですから、ロジックだけではうまくいきません。「この人たちと一緒にやってみたい」「この会社に任せたい」と思ってもらえるかどうか。そこを大切にしてきたつもりです。
求めるのは“地に足のついた野心家”
――クロスボーダーM&Aという新たな領域で、今後どのような体制づくりを目指しているのでしょうか?
鈴木:今はまだ豊住がひとりで立ち上げている段階ですが、いずれはチームとして強化していきたいと思っています。とはいえ、具体的なKPIや「何人増やす」といった数値計画は作っていません。あまり数字目標を掲げてしまうと、数字を追うことが目的になってしまうからです。
それよりも、「意味のあるM&Aを一件ずつ丁寧にやっていく」。その積み重ねを大切にしたいんです。

――とはいえ、目標感のようなものがあれば聞かせてください。
鈴木:個人的には、まず年間10件くらいは成約できる体制にしたいですね。月1件ペースは、正直かなり大変ですが、それくらい世の中にはニーズがあると感じています。
実際、今でも国内外から相談は来ているので、それに応えられる体制を少しずつ整えていきたいと思っています。
――そんな立ち上げフェーズで、どんな人と一緒に働きたいと考えていますか?
荒井:クロスボーダーM&Aのような挑戦的な領域では、「明るくて前向きな人」が向いていると思います。どんな仕事にも明るく・楽しく・前向きに取り組める人に来てほしいですね。
スキルについては、入社後にしっかり学んでもらえば大丈夫です。ただし、M&Aは人のお金を扱う仕事ですから、当然ながら責任感は求められます。そこはしっかり理解したうえで、一緒に前に進んでいける人を歓迎したいです。

――豊住さんも、入社してから会計知識などを覚えたのですか?
豊住:入社当初は、会計や財務については基礎的な知識しかありませんでした。周囲と比べても、できないほうだったと思います。だからこそ、入社してからは「自分で学ばないといけない」と強く感じて、必死でキャッチアップしました。冷や汗をかきながら勉強したのを今でも覚えています。
この仕事では「誰かが教えてくれる」と思わないほうがいいです。教えてもらうのを待つより、自分から学ぼうとする姿勢が欠かせません。むしろ、少し失敗しながらでも、自分の意志で学びに向かえる人のほうが、この仕事には向いていると思いますし、失敗の数が成功へ近づく一番の方法だと思っています。
――クロスボーダーM&Aというと英語が必須だと思いますが、そこはどうなのでしょう?
豊住:英語はあくまで“ツール”にすぎません。もちろん、ある程度コミュニケーションができることは必要ですが、それ以上に大切なのはEQ——つまり、相手の感情や背景を読み取る力です。
特に売り手側が日本企業である場合、売却に対する思いや不安を汲み取る力が求められます。語学力は後からいくらでも伸ばせますが、人の気持ちを丁寧に理解しようとする姿勢こそ、この仕事で本当に大事なスキルだと思っています。
――最後に、ストライクに興味を持った方にメッセージをお願いします。
豊住:M&Aという仕事は、全業種と関わり、かつ経営者と直接対話ができるという点で、非常にダイナミックです。動く金額も大きく、その分責任も大きい。でも私は、それこそがこの仕事の面白さだと思っています。プレッシャーを楽しめる人、緊張感をモチベーションに変えられる人には、ぴったりの環境です。
また、ストライクでは、自分で考えて、自発的に動くことが求められます。そのため、ゼロイチで新しいことに挑戦したい人、自分で価値をつくり出したいという意志がある人には、これ以上ないフィールドです。
この仕事は、会社の名前で評価されるものではありません。最終的に「ストライクに頼みたい」ではなく、「あなたに頼みたい」と言われるような人になれるかどうかがすべて。だからこそ、「自分がどうなりたいか」とストライクの方向性が合っているかどうかを、ぜひ大切にしてほしいと思います。
/assets/images/13534395/original/142d01c3-b3b3-4275-91b5-28e906d91b20?1686293038)

/assets/images/21187292/original/ace4a7a5-5483-4a19-96ea-e34a85085340?1747994354)

/assets/images/13534395/original/142d01c3-b3b3-4275-91b5-28e906d91b20?1686293038)

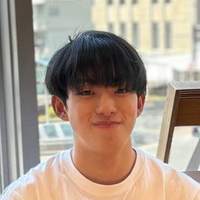
/assets/images/13534395/original/142d01c3-b3b3-4275-91b5-28e906d91b20?1686293038)

