Forbes 30 Under 30「世界を変える30歳未満30人」に選出・代表下山が描く"一生戦う会社"のビジョン
こんにちは、Senjin Holdings経営管理部の笠原です。
今回は特別企画として、代表取締役社長・下山明彦がForbes JAPAN 30 Under 30「世界を変える30歳未満30人」に選出されたことを記念し社内インタビューを実施しました。一見複雑に見える事業ポートフォリオの真意、そして「一生戦う会社」として描く壮大なビジョンまで、その哲学の核心に迫ります。
『Forbes JAPAN 30 UNDER 30』特設サイト:https://forbesjapan.com/feat/30under30/2025/
目次
世界を加速させるための事業デザイン
マーケティング×AI×アートが生み出すシナジー
「共同体の作家性」を抽出する独自のアプローチ
一生戦う覚悟で築く100年企業への道筋
人類が永遠にやり続けそうなことを事業の軸に
世界を加速させるための事業デザイン
笠原:Forbes「世界を変える30歳未満30人」選出おめでとうございます。改めて、Senjin Holdingsがどんな会社なのか教えてください。
下山:ありがとうございます。うちの会社は一言で表現するのが難しいのですが、「世界を加速させる」ことを実現するための企業です。その根底にあるのは、いろんな共同体──企業や自治体、組織──が持つ固有性や作家性を見つけ出し、それを事業や組織にフィードバックしていくことで、今まで世界になかった価値を創出していこうという思想です。
具体的には、人間の欲求に向き合うマーケティング事業を主軸に、AI開発、アート事業、そしてインキュベーション事業という4つの柱で構成されています。これらは一見バラバラに見えるかもしれませんが、すべて「共同体の作家性を抽出し、表現し、実装する」という一貫したテーマで繋がっているんです。人間とAIが協働しながら欲求を実現していく時代において、その最前線を走り続けるためのインフラとして機能することを目指しています。

マーケティング×AI×アートが生み出すシナジー
笠原:事業ポートフォリオを見ると、マーケティング7割、AI2割、アート1割という構成ですが、これらがどう連携しているのでしょうか?
下山:まさにそこが我々のユニークネスです。マーケティング事業で培ったクライアントとの関係性があるからこそ、その会社が作るべきプロダクトを僕らが開発できる。逆に、自社でAI開発をしているからこそ、最前線のソリューションやシステムを提供し続けることができるんです。
そして、アート事業があることで、クライアント企業のアイデンティティや本質的な課題を上流から捉えることができる。例えばベースフードさんとの仕事では、社員の方々と対話する中で「『いただきます』って言ってもらいたい」という想いが浮かび上がりました。これって、レッドブルやプロテインには絶対にない感情なんです。そういう共同体としての作家性を見つけ出し、それを事業戦略やブランディングに落とし込んでいく。この循環が、普通の広告代理店とは全く違う価値を生み出しています。
クライアントに対して役務提供と資本提供を一体的に行うインキュベーション事業も、この思想の延長線上にあります。本質的な支援をすることで企業が伸び、結果として世界を加速させていく。そのために最適な関わり方を追求した結果です。
「共同体の作家性」を抽出する独自のアプローチ
笠原:「共同体の作家性」という概念が印象的ですが、具体的にはどのようなアプローチで抽出されているのでしょうか?
下山:これは僕の宗教学のバックグラウンドが大きく影響しています。要するに、ある共同体において「どういう祈りを設定するか」ということなんです。万博を例に挙げると、各国が自国の価値や固有性を表現する場として機能していますよね。アメリカは8割が宇宙、日本は技術と文化、フランスはフランスらしさ──それぞれの国の作家性が明確に現れています。
僕たちがやっているのは、企業や組織に対して同じようなプロセスを提供することです。まず、コミュニティのリーダーと対話し、その共同体が持つ本質的な価値や方向性を見つけ出す。それをアーティスト兼経営者兼学者として表現し、組織全体に「こういうブランドでいきましょう」「こういうカルチャーでいきましょう」と提示していく。
これは必ずしもいわゆる「アート作品」を作ることではありません。ロゴ制作、オフィスレイアウト、組織の儀式的な要素まで含めて、その共同体のアイデンティティを様々な形で表現していきます。結果として生まれるアーティファクトが、その共同体の象徴として残り続け、人類の歴史に刻まれるものになる。そこまでを見据えています。

山形県西川町・シンボルアート
一生戦う覚悟で築く100年企業への道筋
笠原:1社目で設立された仮想通貨事業とは違い、今回は「一生戦う会社」として設計されているとお聞きしました。
下山:はい、これが前回との大きな違いです。仮想通貨の会社を作った時は「起業ってどんな感じなんだろう」という経験的な側面があり、2年以内にイグジットするという制約条件を自分で設けていました。でも今回は真逆で、一生やり続けるつもりで設計しています。僕が100年生きたら、この会社が100年企業になる。そういう覚悟で臨んでいます。
その背景には「人類が永遠にやり続けそうなことをやろう」という思想があります。具体的には、人間の欲求に対して欲しいものを作り、その取引を支える資本主義的な循環、美しいものを作りたいという創造欲求、そして真理や知恵を切り開いていく探求心。これらは土器の時代からあったもので、これからも人類が続ける限り必要とされ続けるでしょう。
だからこそ、この会社は単なる支援会社ではなく、世界を変えそうな人間たちと一緒に仕事ができ、様々な夢やキャリアが実現され続ける生態系として機能したいと考えています。思想は中核にあって、手段や戦略は時代に合わせて進化していく。そういう構造で会社を作っています。
人類が永遠にやり続けそうなことを事業の軸に
笠原:最後に、今後のグローバル展開も含めた展望をお聞かせください。
下山:すでにシリコンバレーでの事業展開や、ASEANリーダーとの連携も進めています。特にASEANでは、インドネシアの財閥企業や王宮での作品展示など、各国の共同体と深く関わる形でのアート事業を展開しようとしています。これも「共同体の作家性を抽出する」という我々のコアバリューの延長線上にあります。
究極的には「オルト×地球」として、地球自身の作品とは何かを考え、2050年頃に月面で展示会を開催できたら面白いなと思っています。それくらいスケールの大きなことを、本気で実現したいと考えています。
今、11月にオフィス移転を控えていて、240坪の新オフィスに加えて既存オフィスもインキュベーション施設として活用予定です。優秀な人材が集まり、切磋琢磨できる環境を整えることで、さらに大きな価値を生み出していきたい。人類の歴史に残るような、本当にインパクトのある事業を、仲間と一緒に作り上げていく。それが僕たちの描く未来です。



/assets/images/3835909/original/8f6acf18-04bd-42cd-9219-b1f47873bf0d?1674693574)


/assets/images/3835909/original/8f6acf18-04bd-42cd-9219-b1f47873bf0d?1674693574)


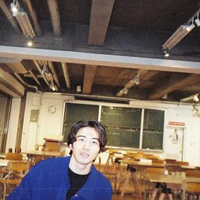


/assets/images/3835909/original/8f6acf18-04bd-42cd-9219-b1f47873bf0d?1674693574)

