- Human Resources
- Data Scientist
- カスタマーサクセス、コンサル
- Other occupations (5)
- Development
- Business
- Other
こんにちは。SCIENメンバーインタビュー企画を担当する松本です!
第1回の川田さんに続く今回の主役は、未経験からエンジニアとして実装に励みながら、デザインでも存在感を放つ塩谷浩太さん。二刀流の原点、学び続ける姿勢、チームを支えるコミュニケーションの作法まで、ぎゅっと詰めてお届けします。
◆ 学部3年、未経験から「実装×デザイン」へ — 越境の第一歩
Q1: 簡単にご経歴(入社前・現在)を含めて自己紹介をお願いします
塩谷さん:
現在は大学の学部3年生で、システム制御や画像認識系を専攻しています。
SCIENには田端さんの紹介で入らせていただきました。当時は全くの未経験として入社しましたが、現在はエンジニアとしてプロジェクトに参画しながら技術を学び、デザインではポスターや名刺などの制作も担当しています。
◆ 学びが実務に接続する現場 — 研究と現場の往復運動
Q2: SCIENのどこに魅力を感じて入社したのでしょうか?
塩谷さん:
インターンとしての活動が大学の学業にプラスに働くと思い、SCIENに入りました。
専攻はシステム制御や画像認識寄りですが、音の深層学習にも関心があり音だけで空間を把握する研究にも惹かれています。田端さんから研究室のアドバイスやお話をよく聞かせてもらっています。
大学では深層学習にほとんど触れていなかったのですが、SCIENのプロジェクトで深層学習の勉強を実務で加速でき、大変良い経験になっています。
— 研究⇄実務の往復は、知識を一次情報化する最短ルートですね!SCIENでは院生メンバーが多く、具体的な助言に触れられる点も大きなメリットです。
◆ 「文字から設計する」デザイン — フォント起点の思考法
Q3: SCIENでデザイン担当といえば塩谷さんですが、以前からデザインに興味があったのですか?
塩谷さん:
そうですね。もともと大学で文化祭実行委員に入り、そこでデザイン系の部署で自分の考えたデザインをAdobeで作成して印刷するということをしていたので、その経験をSCIENでも活かせていますね。
ここで、前回のインタビューの川田さんに塩谷さんの第一印象を伺ったので、共有いたします!
川田さんのコメント:
最初に振られていた仕事がデザイン系で、「デザインできるのは強いな」と感じました。寿司パのドットのデザインを見た時、リアルな寿司ではなく、あえて画質を落としてドットを選ぶ判断が塩谷くんらしい。AI時代になるほど、最終的な見え方を決める「どんなプロンプト・設計にするか」という人のデザイン力・表現力が重要になる。素直に羨ましい能力です。

ー 実際に塩谷さんが作成した寿司パのデザイン
◆ ドット寿司の舞台裏 — 「文字→画」で整える設計思考
Q4: 私も塩谷さんの寿司パのドットポスターの大ファンなのですが、あのデザインはどのように作成したのですか?
塩谷さん:
寿司パのビジュアルは、タイトルのフォントをAIっぽくプログラミング風にしたので、それに合わせる形で寿司の絵をドット絵に選びました!大体デザイン系のお仕事は最初は結構何も浮かばなくて困るんですけど、1個1個試してるうちに、なんか自分でなんとなくいいなって思ってくるものですね。寿司パの時もいくつか試して“しっくり来た”組み合わせに落ち着き、制作時間は4~5時間ほどでした。
— まず「文字の解像度」を決め、そこから「画」を合わせるリバース設計。小さな試行を積む姿勢が、結果の説得力を底上げしているのですね!
◆ 未経験の駆動力 — 小さな更新で昨日の自分を超える
Q5: 未経験からエンジニアとしてのキャリアを始めたとのことですが、続けられるモチベーションやコツはありますか?
塩谷さん:
未経験だからこそ、新しいコマンドを覚えて実行できた時に、2か月前の自分よりエンジニアっぽくなっている実感がすごく感じられて、それがモチベーションになっていますね!
大学ではPythonコードもほとんど打てず、入社当時はAIの会社で力になれるのだろうかと不安でした。しかしオフィスに通い詰めて田端さんや大山さんに手取り足取り教えてもらえたおかげで、できることが日々増えていると感じています。
また、初心者として技術に関する知識に乏しい分、初歩的なことを躊躇なく聞けたことが今の自分につながっていると思っています。
ー 成長の本質は「微差の積み上げ」です!できることが離散的に増える瞬間を自覚し、それを次の挑戦の燃料に変える。ここを武器にできる人は、成長曲線が逓増しますね!
◆ 「納得するまで議論」— 声が届く場が強みを引き出す
Q6: ご自身の強みと、それを最大限に活かせているSCIENの良さは?
塩谷さん:
私自身かなり議論好きで、中途半端な理解で終わるのではなく納得できるまで意見を交わしたい性格なんですね。
SCIENのミーティングなどでも自分が納得しない部分は積極的に発言するのですが、それは発言しやすい空気がSCIENにはあって、そこはかなり自分に合ってると思います。
ー 心理的安全性がある場では、疑問が資産になります。塩谷さんは未経験=沈黙にするのではなく、問いの質でSCIENに貢献し、自分自身を成長させているのですね!
◆ 情報は流通して価値になる — WOLと日常コミュニケーション
Q7: SCIENには知識や情報、進捗状況を開示するWorking Out Loud という文化があります。その文化がある環境で意識していること、普段のコミュニケーションで大切にしていることはありますか?
塩谷さん:
普段の情報共有で意識していることは二つあり、一つはPMに伝えるつもりで進捗を可視化しています。マネージする側にとってもメンバーが何をやっているかわからないと活動しづらいと思うので、PMに進捗を把握してもらえるように書いています。
もう一つは、自分のためです。今日やったこと・次回のタスクをメモ的に書くことで、稼働した時にスムーズにタスクに移れるようにしています。
コミュニケーションでは、オンラインではリアクションを積極的にするように心がけています。情報発信している人の立場に立った時に、反応をもらえると嬉しいと思うので、気軽な気持ちでリアクションを押していますね。
— 相手の立場になって行動を起こせる人、リアクションの即応はチームの熱損失を減らし、小さな作法の積み重ねが、プロジェクト速度を底上げしますね。塩谷さんのリアクションの速さはSCIENでトップクラスです!
◆ 多様性が学びを立体化する — 専門が交差する組織文化
Q8: SCIENはどんな雰囲気ですか?
塩谷さん:
医療関係や深層学習に精通している方がいたりと、多様な強みを持つ人が集まっていて、さらに互いの良さを認め合う文化があると思います。
— まさに、SCIENでは毎週なんでも輪講会という、メンバーが持つ専門知識を勉強会のように情報共有する場があります。専門性もバックグラウンドも越境するほど、学びは立体になる。SCIENらしい景色ですね!
◆ 世代を越えて通じる対話力 — 現場で育つベーススキル
Q9: SCIENに入って身についた力はありますか?
塩谷さん:
年上の社会人の方々と自然体で会話できるようになり、コミュニケーションの引き出しが増えた感覚です。今まで同世代や2つ上の先輩としか話したことなかったので、インターンを始めた当初はかなり緊張していましたが、SCIENの皆さんは本当に気さくで、いい意味で友達と話している感覚で楽しいです(笑)
— 現場コミュ力はトランスファラブルスキル。どの職種でも利く「基礎・土台」がここで鍛えられます。
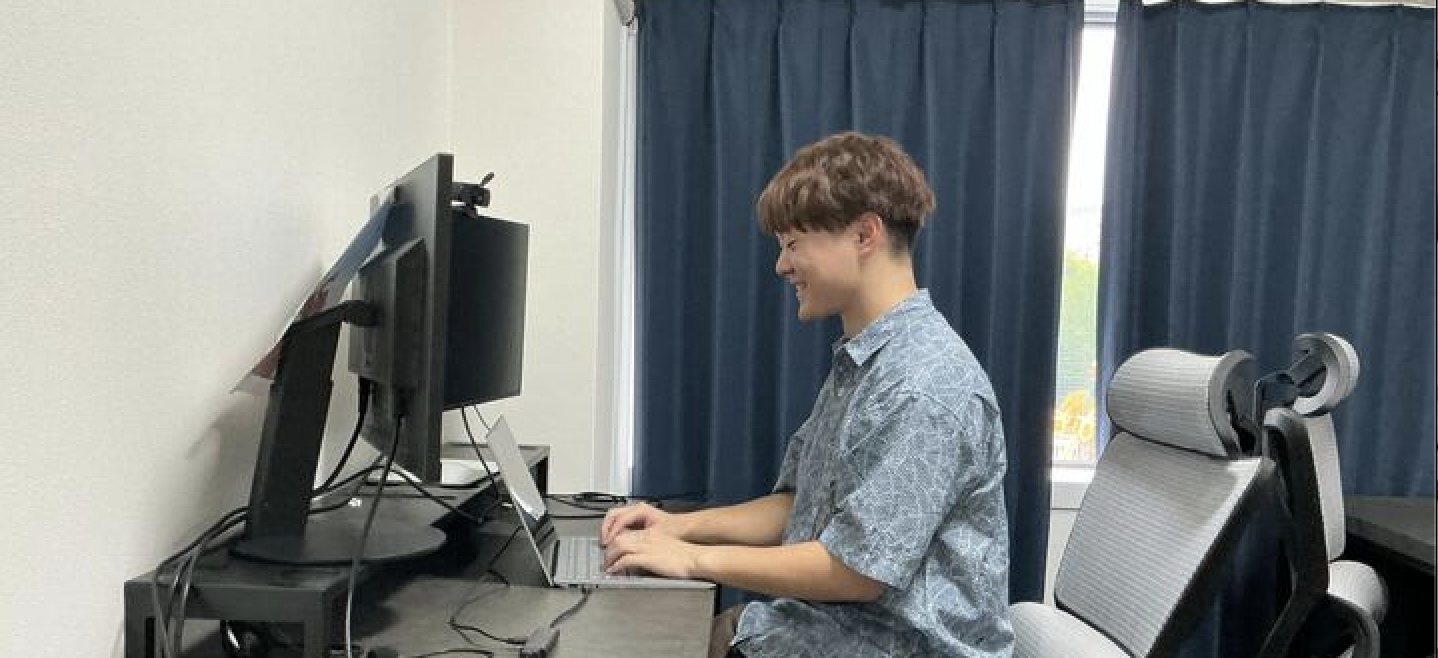
◆ 学ぶ側から教える側へ — 二刀流に「教育」を重ねる
Q10: 今後のビジョンやなりたい姿はありますか?
塩谷さん:
機械学習をさらに深め、いずれは新人を指導できる立場になりたいです。
また、デザイン力を活かして今後はアプリ開発にも挑戦して、実際に“使われる”プロダクトづくりに関わりたいと思っています。
Q10: 最後に、SCIENに興味ある人へ一言お願いします!
塩谷さん:
多分野の強者が集う環境で、情報量は多いです。そのぶん吸収できる人には最高の場所。画像だけでなく、機械学習全般を学びたい人におすすめです!
ー 好奇心×自走力がある人は、ここで学習速度のギアが一段上がります。情報の多さはノイズではなく、選び取りの訓練場!実装で手を動かし、言語化で知を固定する — その往復を楽しめる人に最適な環境です。
次回予告
次回は、塩谷さんが「ギャップがすごい。しっかりされている方」と語るメンバーへのインタビューをお届けします。お楽しみに。
/assets/images/20704127/original/cd145185-d8df-4d90-b37d-67b0ad9dd673?1742493600)
/assets/images/20704127/original/cd145185-d8df-4d90-b37d-67b0ad9dd673?1742493600)
/assets/images/20704127/original/cd145185-d8df-4d90-b37d-67b0ad9dd673?1742493600)
