【この記事について】 この記事は約12,000字あります。普通なら「長すぎる」と言われるでしょう。 でも、これがタッキーの営業スタイルそのものです。 最後まで読めたあなたは、もしかするとopenpageが求める人材かもしれません。
「世界レベルで物語を作りたい」
この一言に、滝沢郁也さんのすべてが集約されている。
前職でARR10億円規模のSaaS事業成長に貢献し、8名のインサイドセールスチームを率いた実績を持つ彼が、なぜ株式会社openpageという新天地を選んだのか。そこには単なるキャリアアップを超えた、深い「物語性」への憧れと、常人には理解されにくい「変態的」とも呼べるほどの営業への執念があった。
今回のインタビューでは、滝沢さん(通称:タッキー)の赤裸々な告白から、現代のスタートアップで働く意味、そして個人と組織が共に成長する理想的な環境について、徹底的に掘り下げていく。
第一章:成功体験からの飛躍 ─ 前職での軌跡と転職への想い
MRR100万円から始まった挑戦
滝沢さんが前職に入社した当時、担当プロダクトのMRR(月次経常収益)は100〜200万円程度だった。今となっては小さな数字だが、そこから主力事業として育て上げ、最終的にSaaS事業全体でARR10億円以上の規模まで成長させる過程で、彼はインサイドセールスという領域で確固たる実績を築いていく。
「THE MODELの組織分業が注目され始めた時期で、インサイドセールスの専任担当や経験者がいない中での立ち上げでした。どうあるべきか、まさに手探りで形にしていったんです」
当時はまだインサイドセールスという概念自体が日本企業に浸透していない時代。アメリカ発の営業手法論「THE MODEL」が語られ始めたばかりで、分業体制への挑戦は文字通り前例のない取り組みだった。
型作りから組織拡大まで
顧客リスト管理からアプローチ手法まで、成果の出る型を一つひとつ構築していく作業は、まさに職人芸の世界だった。どのタイミングでどんなメッセージを送るのか、どういう順序で情報を提供すれば商談につながるのか──すべてを実証ベースで積み上げていく。
「成果が出る組織」への変革を推進し、インサイドセールス組織も拡大。最終的に8名規模のチームを率いる責任者として、全体の数値管理、アクション設計、経営レポーティングまで担う立場まで上り詰めた。
しかし、滝沢さんはインサイドセールスという枠に留まることはなかった。
「自分の役割に閉じず、成長のために必要なアクション、ボトルネックを見つけて、落ちているボールを積極的に拾う」
この姿勢で、フィールドセールスにも挑戦し、MVPを獲得するなど、営業プロセス全体での成果を追求していった。

成功の頂点で感じた限界
しかし、成功の頂点に立った時、滝沢さんは新たな課題に直面する。
「自分が携わった事業が大きくなり、その時の立場でやれることはやりきった感覚を感じました。200名以上の規模になった会社では、組織的な分業や管理体制が整備されている一方で、自分のやれる範囲は限られてくる。新しい事業作り、組織作りをこれからして大きくなるスタートアップで、何が必要か、どう向き合うかから関われるポジションの方が、良い仕事ができそうだと思ったんです」
200名を超える組織では、確かに体制は整備される。しかし、それは同時に個人の裁量や影響範囲の制限を意味していた。組織の成熟と個人の成長欲求のジレンマ──これは多くのスタートアップ経験者が直面する課題でもある。
第二章:「物語性」という価値観 ─ openpageとの運命的出会い
転職を決意させた最大の要因は、openpageが持つ「物語性」への深い共感だった。しかし、この「物語性」とは一体何を意味するのか。
滝沢さんの説明は、単純な機能提供を超えた、より深い価値創造への視点を示している。
「物語性とは、例えば、何かを使ってこれだけ効果が出る、だけではなく、その先に、顧客の活動自体が変革し、仕事のやり方が大きく変わるなど広がりがあるようなものです」
これは営業現場での豊富な経験から生まれた洞察だ。滝沢さんは法人間コミュニケーションの根深い課題を肌身で感じていた。

「営業をしていて、お客様とのやり取りで目線がずれて失注する、顧客が望まないコミュニケーションを営業がしているという課題は感じていました。ただ仕組みの中でより良いコミュニケーションにする環境が本質的だと思いました」
openpageのビジョンは、まさにこの課題の本質に迫るものだった。営業やカスタマーサクセスなど法人間のコミュニケーションを切り口に、「顧客とその先にいる方との可能性を広げる」という壮大な構想。この可能性の先を見たいという想いが、滝沢さんの転職への決断を後押しした。
第三章:変態エピソード満載 ─ 前職時代の異常なまでの営業執念
滝沢さんの「変態度」を語る上で外せないエピソードの数々は、彼の営業に対する異常なまでの執念を物語っている。
エピソード1:全メンバーのカレンダーを監視する男
最初のエピソードは、同僚のカレンダー全チェックという、一般的な営業担当者では考えられない行動だ。
「違うプロダクトを扱う他の人のカレンダーを見て、その打ち合わせをするなら自分らのプロダクトの紹介を5分させてと、全メンバーのカレンダーをチェックしていました」
普通の営業担当者なら、自分の担当領域に集中するところだが、滝沢さんは違った。会社全体のあらゆる商談機会を見逃さないという徹底ぶりは、もはや営業への愛情を超えた執念と呼ぶべきレベルだろう。
エピソード2:1〜2年越しで追いかけ続ける「ネチネチセールス」
さらに驚くべきは、滝沢さんの諦めない営業スタイルだ。通常の営業では、断られたら次のターゲットに移るのが効率的とされる。しかし滝沢さんは、年単位での長期戦を展開する。
「お役に立てる自信がある企業に対しては、断られたときに、次に行こうとしないんです。いいなと思ってもらうために、どういう情報があれば役に立てるのか、僕らのプロダクトを抜きにして、手前で考えるべきは何か──1〜2年越しでコミュニケーションを取って受注、継続的な関係構築をします」
この粘り強さは、単なる「しつこさ」ではない。実際に新規受注の最高取引単価を実現しているのだから、これは戦略的な執念と呼ぶべきかもしれない。

エピソード3:常識を覆す「超長文メール」戦術
営業メールの常識を真っ向から否定する滝沢さんの手法も興味深い。「7秒以内に読める文量」「ファーストビューに収める」という業界の常識に対し、彼は独自のアプローチを取る。
「それは目的やシーンによると思います。メールを開いてもらったら、他と違うな、ちゃんと自分たちを理解しているなって思ってもらうことが勝負。文量でうっと思われるかもしれませんが、本当に役立つと思ったときに、それを文章に尽くすことで伝わることもある」
Why you(なぜあなたなのか)、Why now(なぜ今なのか)といったセールスの基本要素を徹底的に文章化し、結果的に超長文になっても、確実に返事をもらえている。これは常識に囚われない、本質的な価値提供への執念の表れだ。
エピソード4:忘年会後にオフィスで仕事する狂気
そして、最も「変態的」なエピソードが、忘年会後の仕事だ。一般的には考えられない行動の背景には、滝沢さんの人生哲学が込められている。
「忘年会後にオフィスに戻って仕事をしていました。コンプラ的に毎回じゃないですが(笑)」
「自分の人生のテーマがあります。世界レベルで物語を作りたい、その理想がある。やれるときにやれるだけやらないと、やらないといけないことも見えてこないというスタンス。やれると思ったらやる。忘年会の後だろうが、もうちょっとやれるなと思ったらやる」
これは単なるワーカホリックではない。明確な理想に向かう執念であり、「世界レベルで物語を作りたい」という壮大な目標があるからこそ、常識的な働き方の枠を超えてしまうのだ。
第四章:1人THE MODELから企画まで ─ 新天地openpageでの全方位挑戦
前職での気づきがもたらした新たなアプローチ
openpageでは、前職での専門性を活かしながらも、より幅広い領域への挑戦が始まった。興味深いのは、インサイドセールスの専門家がなぜ他領域にも関わることにしたのかという点だ。
「もともとインサイドセールスを前職で注力していたのは、前職は希望を出せばチャレンジできる環境だったから。フィールドセールスでも成果は出せていて、それを続ける選択肢もありました。ただ事業グロースにおいて商談機会の設定の数や質が、一番、事業の影響度が大きいと思ったので、自分がそこをやれるのが良いと思ってやっていました」
つまり、インサイドセールスへの専門特化は、実は事業インパクトの最大化という戦略的判断だったのだ。
全プロセスへの関与という新たな挑戦
openpageでは、この考え方をさらに発展させている。
「事業を大きくしていくことを考えたとき、フィールドセールス、カスタマーサクセス、それぞれ何が足りないか、ちゃんと前に進むように向き合いたい。インサイドセールスだけでなく全プロセスをやらせてもらっています」
現在の業務配分は興味深い。インサイドセールスが4割、フィールドセールスが2割、カスタマーサクセスが2割、企画やマネジメントが2割という構成だ。この「1人THE MODEL」とも呼べるスタイルは、スタートアップならではの働き方である。

経営陣からの手厚いフィードバック体制
全領域に関わるからこそ、適切な指導体制が重要になる。
「藤島さんや田中さん、志村さんなどにフィードバックをもらいながら、ちゃんと前に進み続けられる環境があります。それができるのが良いなと思いました」
自己完結できる営業への進化
特に重要なのが、自分自身で受注まで完結できるようになったことだ。
「僕の中では、openpageで一通り経験させてもらい、自身で受注もできました。何が受注するかわからない状態でインサイドセールスをやっても、良い取り組みにならない。営業がどんな提案をして、お客様とどんな調整が必要かわからない状態は良くないですから」
インサイドセールスの質を高めるために、フィールドセールスを経験する。この逆算的な学習アプローチが、滝沢さんの成長を加速させている。
そして現在は、事業企画の領域にも関わっている。
「そこからビジネスの企画も担当しています。インサイドセールスとして自身も向き合ってきた、それをカスタマーサクセスなどでも必要なことなら優先度を定めてやる。意図的にやらせてもらっていて、やりたいんです」
第五章:インサイドセールスのプロが仕掛ける「エクスパンション設計」の革新
従来のエクスパンションを超えて

カスタマーサクセス領域での滝沢さんの取り組みで特に注目すべきが、エクスパンション設計だ。
「インサイドセールスの観点を活かすなら、エクスパンションは今取引している顧客にユーザー追加などをするだけでなく、窓口の方が関与していない部門にも取り組みを拡大したい。これはインサイドセールスに近いアプローチです」
既存の窓口を通じた追加購入に留まらず、顧客組織内の新たな部門への横展開を積極的に仕掛ける。これは従来のエクスパンション(既存顧客からの売上拡大)の概念を大きく広げるアプローチだ。
インサイドセールス的観点の応用
具体的な手法は、まさにインサイドセールスの応用である。
「顧客とあるべき状態を描き、商談を設定する、提案とそれによる態度変容、それができる準備体制──これをカスタマーサクセスの中でインサイドセールス的な観点も織り交ぜながらやる」
単なる既存顧客のフォローではなく、新規開拓と同様の戦略的アプローチを既存顧客の新部門に対して展開する。滝沢さんならではの発想だ。
カスタマーサクセスとサポートの本質的違い
この取り組みの背景には、カスタマーサクセスに対する深い理解がある。
「カスタマーサクセスとサポートの違いを考えると、ツールが使えて運用できていればいい、じゃない。顧客の変わる状況や課題に対して価値が作れるから、その対価がもらえる。それを推進するのがカスタマーサクセスの役割です」
単なる技術サポートを超えて、顧客の事業成長に積極的に関与する。変化する課題に対して新たな価値を提案し続けることが、真のカスタマーサクセスだという考えだ。
経営陣との協働による形作り
この革新的なカスタマーサクセスの形は、経営陣との密な連携から生まれている。
「藤島さんにも教えてもらいながらカスタマーサクセスの形を作っています。自分らもカスタマーサクセスで使われているプロダクトですから、ノウハウもお客様に戻していきたい」
自社でopenpageを活用しながらカスタマーサクセスを実践し、そこで得た知見を顧客に還元する。この実践知の循環こそが、openpageの競争優位性を支えている。
「ここまで読んでくださった方、ありがとうございます。タッキーの長文メールを受け取る顧客もきっとこんな気持ちでしょう。でも続きが気になりませんか?」
第六章:多様な専門性が交差する成長環境 ─ チームメンバーとの化学反応
バリエーション豊かな仲間たち
openpageでの成長を支えているのは、多様なバックグラウンドを持つ仲間たちの存在だ。
「仲間のバリエーションが素晴らしいんです。藤島さん、田中さん、志村さん、北森さん、よしきなど、それぞれバックグラウンドや経験、専門領域がある」
それぞれが異なる専門性を持ちながらも、お互いの強みを活かし合える関係性。この多様性こそが、チーム全体の力を底上げしている。
専門性に基づく相談体制
この多様性の真価は、実際の業務改善に直結している点にある。
「カスタマーサクセスは藤島さんに聞き、よしきと現場で相談するなど、助けを求められる人がいる。現場感と専門性を織り交ぜてスピーディに実行し、早く結果が出る。経験を積んで成長できます」
課題に応じて最適な相談相手を選べる環境。理論と実践のバランスを取りながら、迅速な判断と実行が可能になっている。この循環が、個人の成長を加速させているのだ。

アウトプット機会による成長加速
さらに重要なのが、学んだことを即座にアウトプットできる環境だ。
「お客様に営業やカスタマーサクセスはこうしたら良いと伝えていく立場のため、責任を持たないといけないです。顧客に話すアウトプットの機会に対して『これでは足りない』『この場合はどうすればいいのでは?』と常に振り返るタイミングを作ってます。それは専門性を深めて成長するのに良い環境です」
顧客への提案という実践の場があるからこそ、自分の知識や経験が本当に価値があるかを常に検証できる。教えることで学ぶ。これが、滝沢さんの専門性をさらに深めているのだ。
第七章:健全性と自由度が生む理想的な働きやすさ
対話を重視する組織文化
openpageの働きやすさについて、滝沢さんは「健全性」という印象的な言葉で表現する。
「前提として、頭ごなしに『俺たちはこういうやり方だからこれに合わせろ』ということをしない社風があります。ちゃんと意見を聞いて、事業に関わることであれば、基準を示しつつフィードバックしてもらえる健全性があります」
一方的な指示ではなく、対話を重視する文化。事業に関わる提案であれば真摯に耳を傾け、適切な基準を示しながら建設的なフィードバックを行う。この姿勢こそが、滝沢さんの言う「健全性」の本質だ。

合理的な意思決定プロセス
この健全性を支えているのは、合理的な経営姿勢にある。議論は建設的で、感情的な判断やノリで物事を決めることがない。意思決定のプロセスそのものにこだわりがあるからこそ、メンバーは安心して働けるのだ。
「健全性を感じるのは、今いるメンバーがいろんな経験をしてきた上で、ちゃんと自分で判断して自分で動ける人が多いから。いろんな意見をどう解釈して物事を進めるべきかの判断ができる。なので人に対して尊重する姿勢があります」
豊富な経験に裏打ちされた判断力と実行力を持つメンバーが集まっているからこそ、互いを尊重し合える関係性が自然と生まれている。
経営陣の相補的リーダーシップ
特に印象的なのは、2人の代表の相補的な関係性だ。
「藤島さんと田中さんのバランスも良いです。藤島さんは共感タイプで、アイデアを広げてくれる、選択肢を見せてくれる、一緒に選択肢を考えてくれる。田中さんは『それをやりたいならこういう考えや動きをした方がいい』と、取り組み方や判断基準を示すタイプ」
藤島さんの発想力と共感力、田中さんの実行力と判断力。この異なる強みが組み合わさることで、チーム全体に理想的な指導体制が生まれている。
自由と責任の好循環
「二人の考え方に対して理解できれば、あとは自身の経験、やりたい目的から何をしなければならないかを判断し、自身で試行錯誤すれば止められることもなく、自由で動きやすい。責任は伴いますが働きやすいです」
経営陣の方向性を理解した上で、個人の裁量で行動できる環境。よくわからない理由で止められることもなく、合理的な判断に基づいて自由に動ける。この透明性の高い意思決定プロセスが、真の働きやすさを生み出している。
働きやすさの本質的定義
「働きやすさは職場や仕事に何を求めるかですが、自分は仕事で何を成し遂げて、どんな環境で、誰とどんなことをしたいかを重視します。その意味で働きやすいです」
単なる快適さではなく、成長と貢献の機会があること。そして何より、合理的で建設的な環境で自分の理想を追求できること。滝沢さんにとっての「働きやすさ」は、openpageの健全な組織文化と完全に合致しているのだ。
第八章:事業責任者への道 ─ 描くキャリアビジョンと立ち上げへの執念
明確なキャリアビジョン
openpageでの滝沢さんには明確な目標がある。
「openpageでは1つの事業の責任者ポジションを担えるようになりたい。なので北森さんと事業企画の仕事も担っています」
この目標設定の背景には、前職での経験から得た深い洞察がある。

所有感の欠如という重要な気づき
「前の会社では事業が小さいところから大きいところまでやりましたが、最終的に自分のプロダクトと思えなかったのが本音です。どうやって事業運営されていたか、自分が向き合い方がどうだったかなど、色々考えましたが、結局、立ち上げの最初をやらないと分からないと思いました」
事業の成長過程を一通り経験しながらも、最終的に「自分のプロダクト」という実感を持てなかった。この率直な振り返りから、事業立ち上げの初期段階に関与することの重要性に気づいたのだ。
立ち上げフェーズの本質的価値
「周りを巻き込んで事業を進める初めの立ち上げがわかっていなかった。いろいろな法人の会社様や自治体様と話していて、openpageの営業のプロセス変革を支援していますが、さらなる可能性を感じてます」
事業の立ち上げでは、関係者を巻き込みながら進める経験そのものに価値がある。現在の顧客との対話を通じて、openpageが営業プロセス変革を軸としながらも、その枠を超えた広がりを感じているという。営業活動だけでなく、様々な提案活動や関係構築活動への応用可能性が見えてきているのだ。
新規事業開発への野心
「今後新しい価値を生み出して、新しいストーリーを作っていこうとしています。そのために役割を広げて、自分自身でopenpageの物語を新しく作る」
滝沢さんの野心は、openpageの既存価値を基盤として、新たな領域への事業展開を描くことにある。営業プロセス変革で培ったノウハウを、より広範な提案活動や関係構築の場面に応用する新規事業を開発していきたいという構想が、彼の中で具体化しつつある。
単なる従業員から事業の物語を自ら紡ぐ主人公へ。そのためには、既存事業の深い理解と新規事業への挑戦、両方の経験が不可欠だと考えているのだ。この明確なビジョンが、滝沢さんの日々の行動を支える原動力となっている。
第九章:同期3名の絆 ─ 信頼関係が導いた転職という選択
2人の同期の存在
実は、openpageへの転職には特別な背景がある。前職の同期である、丸山さん、よしきさんがすでにopenpageで働いていたのだ。
「転職理由として、まる、よしきがいるのはありました。2人がいて、2人が生き生きと働いていて良いと言っている会社。藤島さんや田中さん、openpageの事業が良いと言っている。その同期2人を信用していました」
この2人の存在が、転職の決断に大きな影響を与えた。2人が生き生きと働いていて、会社や経営陣、事業について良いと言っている。その同期2人を信用していたというのが、転職理由の一つだった。
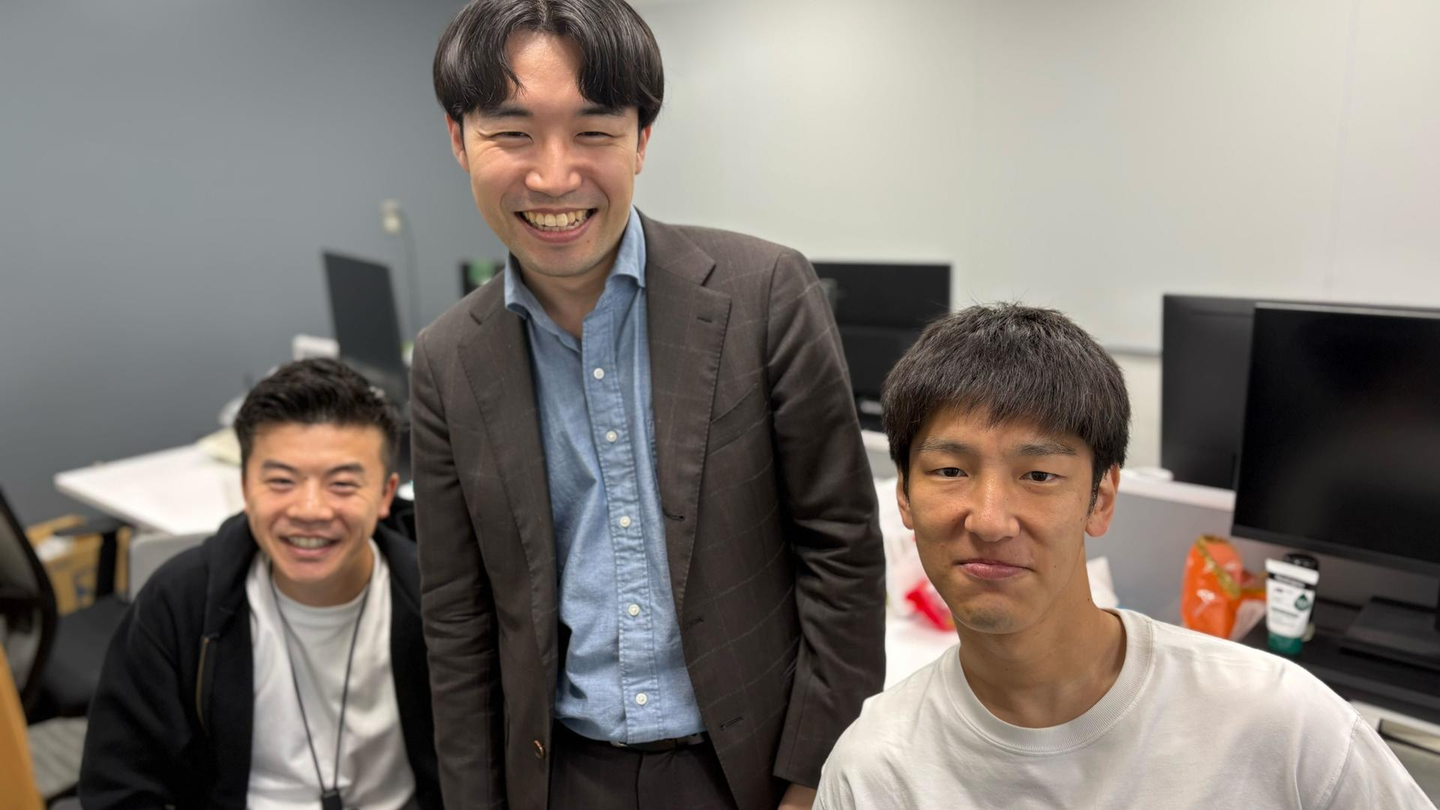
信頼の質
この信頼関係は、表面的なものではない。
「前職の同期2人とは、一緒に仕事をするときにいろんな人と関わる中で、どうしても一緒に働きたい人、信用できる人だと思っています。この人と一緒に働いたら働きやすいな、と感じる2人でした」
日常的にプライベートな付き合いがあるわけではない。しかし、様々な人と協働する中で自然と見えてくる、その人の仕事への向き合い方や人間性。そうした部分で「この人となら」と思える相手だったという。
職場での信頼関係が、人生の重要な転機における判断を左右する。滝沢さんの転職は、まさにそんな人と人とのつながりに支えられた決断だった。
第十章:チームメンバーの魅力 ─ チャーミングな個性が織りなす強さ
「チャーミング」という表現の意味
openpageのメンバーについて、滝沢さんは「チャーミング」という印象的な表現を使う。
「openpageで強調したいのは、それぞれの強みがあるということ。良いと思うのは、みんなチャーミングなところです」
この独特な表現の真意を探ると、チームの本質的な魅力が浮かび上がってくる。
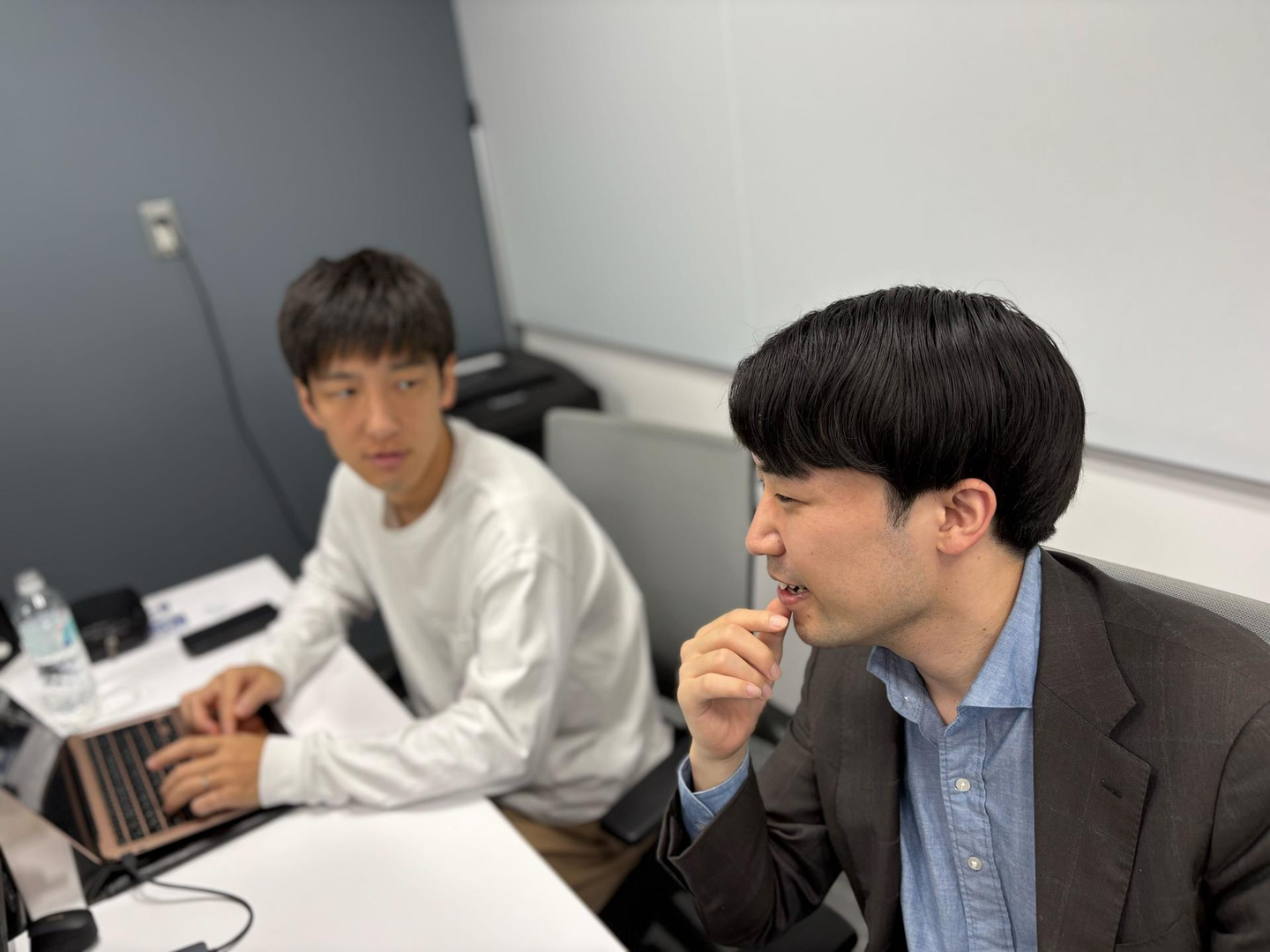
仕事と人生のバランス感覚
「わかりやすく言うと、ガツガツしたり、仕事のことしか考えていない、厳しいという感じでもない。もちろん仕事が好きな方も多いので全くそうでないわけではありませんけどね。ただそれと同じくらい、グルメ、ゴルフ、ライブなど、それぞれ好きなものやこだわりがあります」
スタートアップにありがちな、仕事一辺倒の雰囲気とは一線を画している。仕事への情熱は持ちつつも、それぞれが個人的な興味や趣味を大切にしているバランス感覚。これが滝沢さんの言う「チャーミング」さの一面だ。
自然な関係性の構築
「部活動のような形で仕事外のことを共有することもあって、それも自由。そういう関係性を作れる人たちというのが一番の魅力です」
強制的ではない、自然な形での交流が生まれる土壌がある。部活動のような気軽さで仕事以外の話題も共有でき、それが押し付けがましくない。こうした関係性を築ける人材が集まっていることが、チームの大きな強みだという。
芯の強さと柔軟性の両立
しかし、これは単なる「仲良しクラブ」ではない。
「芯は持っているが、いろんなものを見て受け入れて、正しいことを判断して前に進んでいけそうな人が多い。チームは強いです」
各メンバーには確固たる価値観や専門性がありながら、同時に他者の意見を受け入れる柔軟性も兼ね備えている。この絶妙なバランスこそが、openpageの「チャーミング」なチーム文化を支える真の強さなのだ。
まだ読んでますか?普通の採用記事なら既に終わってます。でもタッキーの『超長文メール戦術』も、相手が最後まで読んでくれるから成果が出るんです
第十一章:経営陣の視座の高さ ─ ロジカルシンキングと長期視点の融合
驚きとしての視座の高さ
openpageに入って最も印象的だったのが、経営陣の視座の高さだった。
「思ったことは、すごく良い驚きとして、藤島さんや田中さんが見ている視座、目指している視座が高く、かつその解像度も高い。これは魅力です」
単に理想を語るだけでなく、その実現への道筋まで具体的に描けている点に、滝沢さんは強い印象を受けたという。

上場の先まで見据えた戦略
多くのスタートアップで上場がゴールに近い形となってしまっている中で、openpageの経営陣はその先まで見据えている。
「たとえばスタートアップは上場がゴールになってしまっているように感じることが多いですが、上場の仕方、上場後の成長なども詳細に想像し、そこにゴール設定したときにプロダクトやサービスのあり方で、何が必要でどうポテンシャルを磨くかを常に向き合っています」
IPOは通過点に過ぎず、その後の持続的成長まで視野に入れた戦略設計。この長期視点こそが、openpageの事業戦略の特徴だと滝沢さんは感じている。
チーム全体での実行体制
そして、それが経営陣だけの構想で終わらない点が素晴らしいという。
「それが2人の中だけでなく、チームの中でワークするように会議体など設計されています。これは魅力です」
「そういう考えを持っている事業、そこに共感しているメンバー、それを実現できるプロダクトがあります。視座がずれず、目先のものより中長期のやりたいことを持っているチーム。何をやらなければならない、自分はどう動くべきかを考えて動ける人が多いです」
高い理想を組織全体で共有し、実行に移せる仕組みが整っている。メンバー一人ひとりが長期的な視点を持ち、自律的に行動できる環境が作られているのだ。
建設的な組織運営
滝沢さんが特に感銘を受けるのは、組織運営の建設的さだ。
「周りを見ても、『これ何のためにやっているのか?』『建設的じゃないな』というものが無い。リスペクトできる人たちです」
無駄な会議や形式的な業務が排除され、すべての活動に明確な目的がある。この合理性と透明性が、チーム全体への信頼感を生み出している。
第十二章:デジタルセールスルームの魅力 ─ 営業現場からの生の声
営業経験者としての実感
営業経験者として、滝沢さんはopenpageのプロダクトであるデジタルセールスルームの価値を肌身で感じている。
「自分も営業をやっていました。自身もお客様の役に立てるよう、どういう提案が良いか考えていましたが、うまくいかない場面もありました。プロセスの中でお客様の求めるものを届ける、ということをopenpageほど考えていませんでした」
これまでの自分の営業活動を振り返ると、顧客のことを考えているつもりでも、openpageが実現しているレベルの顧客中心設計には至っていなかったという率直な反省だ。
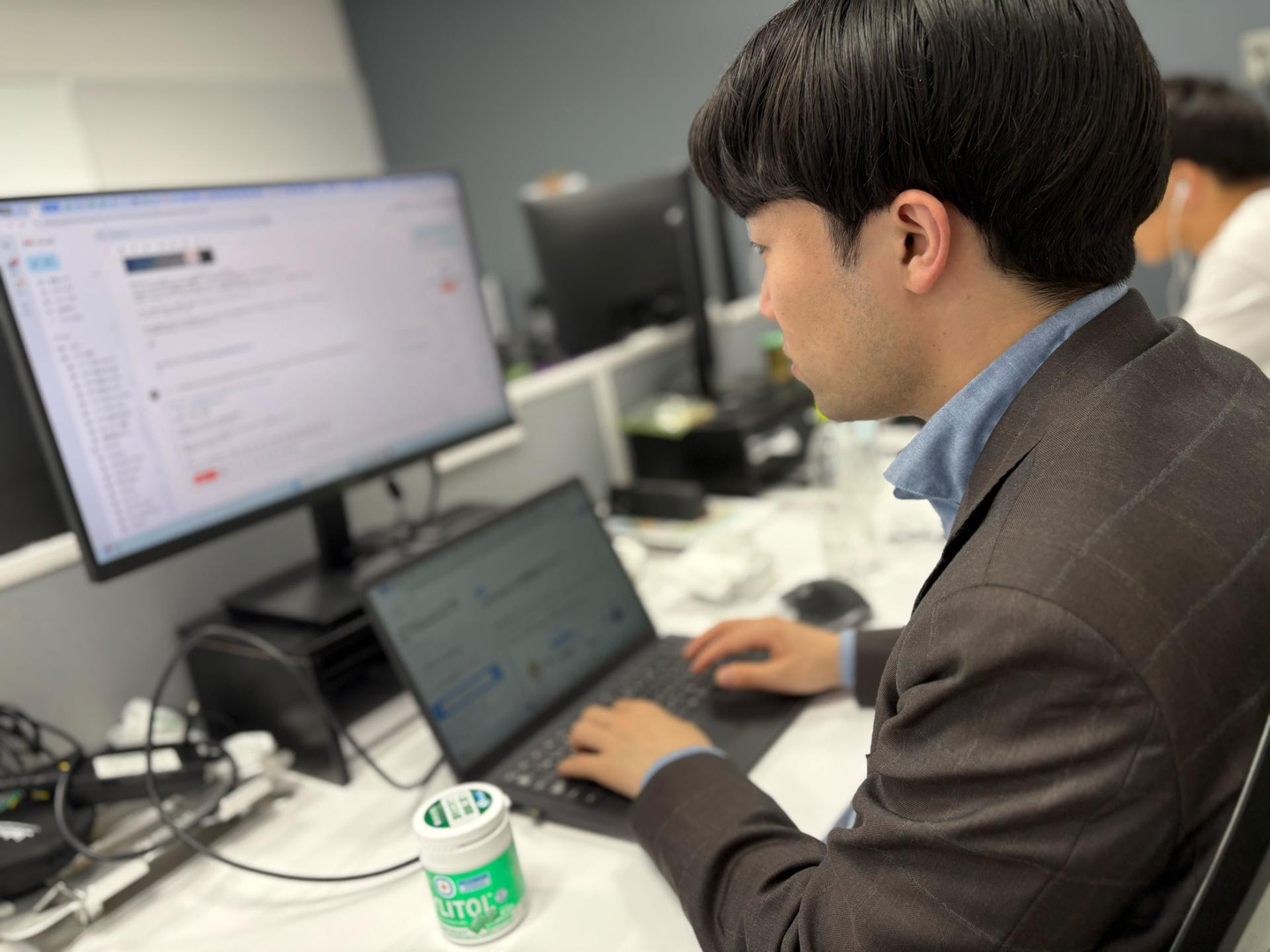
従来の営業の課題
「反応が良かったが塩対応など課題はありました。でもopenpageの考え方は『アポ数が足りないから何回か連絡しろ』という根性の営業マネジメントじゃないんです」
多くの営業組織にありがちな、曖昧な顧客反応の解釈や、数をこなせば何とかなるという発想。こうした根性論では解決できない本質的な課題に、openpageは明確な答えを提示している。
目線のズレを解消する仕組み
openpageが解決する最も重要な問題は、営業と顧客の間に生じる認識のズレだ。
「お客様との目線のズレがなくなります。自分たちの営業活動にフォーカスしすぎると顧客とズレがある。openpageという環境は顧客とともに提案活動をし、自然と顧客とズレをなくす」
売り手の都合で進めがちな従来の営業プロセスを、顧客と共に歩むプロセスに変える。この発想の転換こそが、openpageの核心的価値だという。
顧客の検討プロセスを支援
さらに、顧客の社内調整を支援する機能にも大きな価値を感じている。
「顧客が検討を進めるのに必要な情報、社内で通すための情報提供をする。自分も施策を上申する際に、やっぱり面倒だと思うときに、openpageがあったら良いと思いました」
滝沢さん自身が社内で新しい取り組みを提案する立場として、その煩雑さを実体験している。だからこそ、顧客の社内調整プロセスを効率化するopenpageの価値を深く理解できるのだ。
理論と実績の両立
「いま、openpageの導入企業は成果を出している会社だらけです。コンセプトが良いし成果も出ている。商材に合わせてどういう営業提案をするべきか、どんどん磨きをかけています。世の中の営業のベストプラクティスをどんどん溜め込んで実践し、磨いていく。そのやりこみ要素もあります」
優れたコンセプトだけでなく、実際の成果も伴っている点が重要だと滝沢さんは強調する。openpageには様々な業界・商材での営業における優れたユースケースが蓄積され、それがさらなる改善につながる好循環が生まれているのだ。
第十三章:顧客の反応とリアルな現場感覚
展示会での圧倒的な手応え
実際の顧客の反応について、滝沢さんは非常にポジティブな手応えを感じている。
「よく展示会とかで案内していると、『打ち合わせしてその後資料を送り、検討してもらっているが状況がわからず失注する』というのはよく聞く課題です。これに効きます」
この課題は、多くの営業担当者が直面する普遍的な悩みだ。提案後の顧客の検討状況が見えず、結果的に失注してしまうという問題に、openpageは明確な解決策を提供している。そして展示会では、多くの来場者が話を聞きたいと商談化に発展するという手応えを得ている。

顧客の期待を超える価値提案
openpageの製品を見せたときに、『こんなのなかった』『確かにこれがあるとお客様が検討しやすいイメージが湧く』という反応が多いです」
提案プロセスでは、顧客から「探していたものにぴったりだ」という反応を得ることが多い。営業担当者からは「自分たちが実現したい営業ができる」という声も聞かれる。これは単なる機能への評価を超えた、本質的な価値への共感を示している。
営業体験の質的向上への着目
openpageの特徴的な点は、営業で使うだけでなく、その営業の先にいる顧客の体験までこだわっている点だ。営業担当者の効率化だけでなく、最終的に提案を受ける側の体験も向上させる。この双方向の価値創造が、顧客からの高い評価につながっている。
市場適合性の確証
「サービスやコンセプトはすごく理解してもらえています」
顧客の理解度の高さは、プロダクトの市場適合性を示す重要な指標だ。単に機能が評価されるだけでなく、openpageが目指すビジョンやコンセプト自体に共感を得られている。この深いレベルでの理解こそが、持続的な顧客関係の基盤となっているのだ。
第十四章:データ活用による営業革命 ─ 推測から確信への転換
リアルタイムでの顧客分析
openpageの特長の一つは、詳細なデータ活用にある。滝沢さんは毎日のルーティンとして、このデータと向き合っている。
「細かいところでは、アクセスログ、毎日各社の提案のPVを見て、検討状況を顧客のPV状況から分析しています」
これは従来の営業では不可能だった、リアルタイムでの顧客の関心度測定だ。アクセスログや提案資料の閲覧状況から、顧客の検討の深さや興味の方向性を具体的に把握できる。
推測営業からの決別
「openpageがないと、提案した顧客に『検討してもらっているかもしれない』と一様に連絡していました。しかし、openpageを使うと検討しているかPVで見定め、本当に検討している顧客をフォローできます。その逆も然りで、検討する意志を示していただいたにもかかわらず、PVがついていない場合には、何か変化があったのでは?と、寄り添ったコミュニケーションを取ることができるようにもなるんです」
従来の営業では、提案後の顧客の反応を推測で判断するしかなかった。しかし今では、データに基づいて本当に検討している顧客を見極め、優先度をつけてフォローできる。この転換により、営業効率が大幅に向上している。また、積極的な顧客への推進だけでなく、ネガティブな兆候が出た顧客に対するケアができる点は、まさに顧客起点の営業スタイルと言えるだろう。
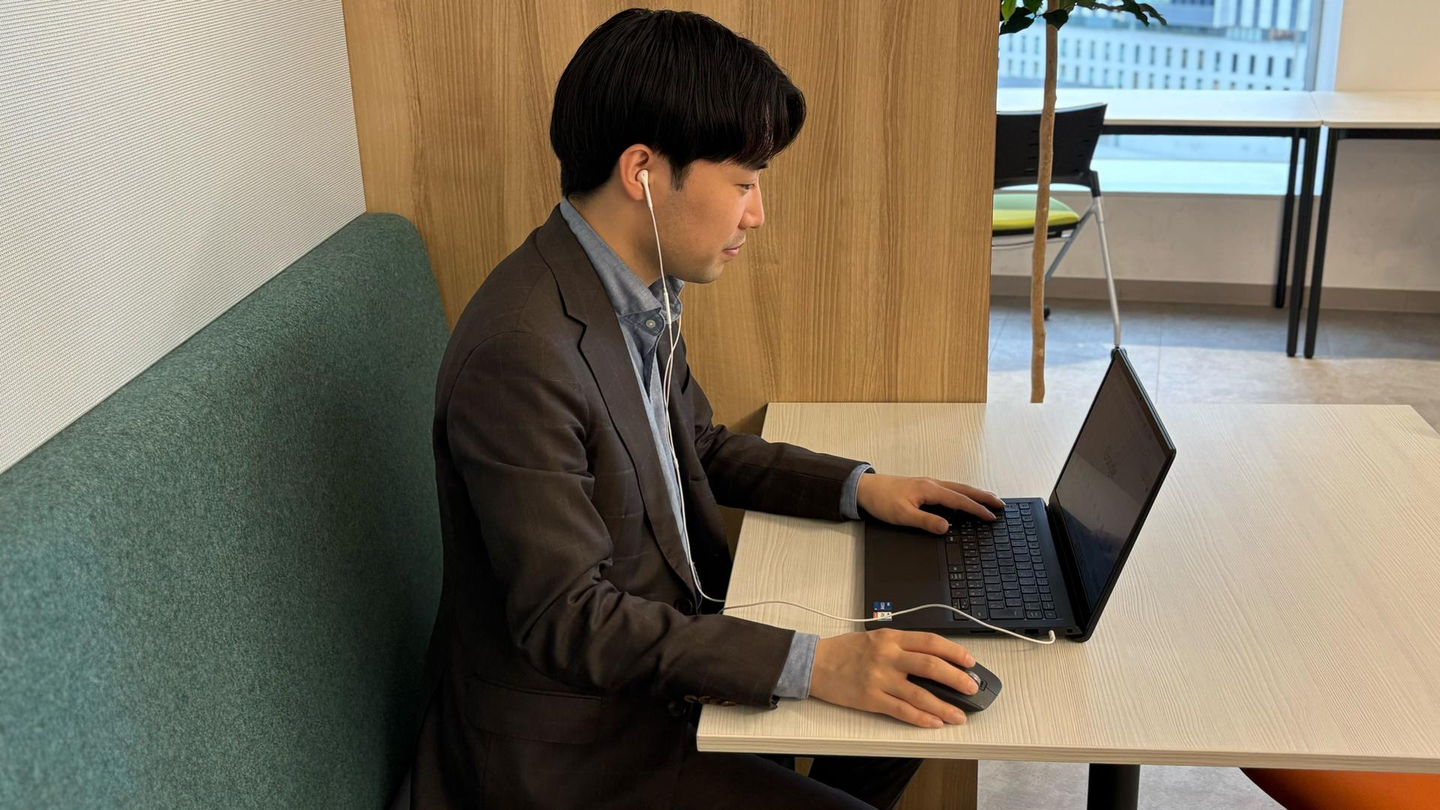
精密な仮説構築
さらに、このデータは仮説立案の精度向上にもつながっている。
「タイムラインでどういう情報を見て何に興味を持っているか、どこを重点的に検討しているかを想像し、仮説を立てて提案できます」
顧客の閲覧パターンから興味の方向性や検討の焦点を読み取り、それに基づいた戦略的な提案が可能になる。営業の精度が飛躍的に向上しているのだ。
経験とデータの融合
「これまでは営業の経験や肌感覚に頼っていた案件の進め方が、顧客の興味・関心をデータからある程度予測することによって、誰でも論理的に提案を進めやすくなります。データを踏まえて、どんな仮説提案をするべきか、試行錯誤することで提案の精度も上がっていきます」
従来の営業が経験と勘に頼っていたのに対し、openpageでは経験とデータを融合させた営業が実現できる。営業担当者の直感を否定するのではなく、データでアシストする形で、より効果的な営業活動が可能になっている。
組織的な活用体制
「毎日の朝会で提案中のお客様のデータを確認して、『検討していただけているか』『検討していただけている場合に何が気になっていそうか』を確認して、アクションプランまで練るようにしています」
このデータ活用は個人レベルに留まらず、チーム全体で共有される。毎朝の朝会でデータを検討し、アクションプランを策定するまで、組織的な取り組みとして定着している。データドリブンな営業が、組織全体の文化として根付いているのだ。
第十五章:等身大の悩みと葛藤 ─ 自由度の裏返しとしての「やりきり」への挑戦
成功の影に潜む課題
ここまで順風満帆に見える滝沢さんのopenpageでの日々だが、実は深刻な悩みを抱えている。
「やりきりですね(笑)。自由度、働きやすさの裏返しで、カスタマーサクセスにおける取引拡大(エクスパンション)、インサイドセールスの商談数の基準の大幅引き上げなど、求められるオペレーション、やらないといけないことがあります」
嬉しそうに語る滝沢さん。まるで困難な課題を楽しんでいるかのような表情だ。それは「やりきり」の課題。理想的な働き方の環境があるからこそ、逆に自分に課すハードルも高い。

明確な戦略と実行の壁
「経営的な優先度は明確、アクションも藤島さんとの議論で具体で言語化されている。それをやりきれるかは自分の覚悟にかかっています」
興味深いのは、戦略レベルでの曖昧さは一切ないということだ。経営的な優先度は明確で、藤島さんとの議論を通じて具体的なアクションまで言語化されている。問題は、それを最後まで完遂できるかという実行力の部分。この責任の重さを、滝沢さんは変態的なまでに楽しんでいるようにも見える。
無難を拒む組織文化
「普通の考え方では、『○○さんはいったんカスタマーサクセスを頑張ろう』と目標を絞るのが無難です」
普通なら、一つの領域に集中する方が確実だろう。しかし、滝沢さんはその無難な選択を意図的に避けている。これは個人の性格だけでなく、openpageという組織全体が無難な仕事で終わらせない文化を持っているからでもある。
経営目線での高い基準
「ただ自分は、そもそもスタートアップとして早いスピードで課題解決したい。チームとして良いし、みんな自分の役割に向き合っている、うまくいっているが、案件のパイプラインなどまだまだ劇的に変えていきたい」
スタートアップとしての使命感が、彼を駆り立てる。チーム全体がうまく機能している今だからこそ、さらに高いレベルを目指したい。これは単なる個人の向上心ではなく、経営目線で仕事をしているからこその発想だ。
組織全体の水準向上への貢献
「自分が大きく突き上げる何かを生んで、ブレイクスルー、非連続成長を起こし続けたい。突き上げるためのやりきりは無難な考えでは起きない」
「自分も無難な目標じゃないものを課して、まだまだやりきれないと悩んで仕事しています」
「やばい」レベルの自己要求は、実はopenpageの組織全体の水準を高めることにも貢献している。高い基準を持つメンバーがいることで、チーム全体が無難な仕事で満足することなく、常により高いレベルを目指す文化が醸成されているのだ。
滝沢さんの率直な告白に、彼の真の姿が表れている。理想の高さと現実のギャップに日々格闘しながらも、それを楽しんでいるかのような変態的な熱量。この姿勢が、組織全体の成長エンジンとなっている。
約10,000字通過。タッキーの営業メールもこのくらいの情報量で顧客を納得させます。あと少しです
第十六章:日々の仕事のリアル ─ 越境を奨励する組織での経営者的働き方
型破りな業務配分
滝沢さんの具体的な日々の業務について、より詳しく聞いた。
「IS(インサイドセールス)、FS(フィールドセールス)、CS(カスタマーサクセス)それぞれ仕事しています。IS4割、FS2割、CS2割、企画やマネジメント2割です」
この業務配分の背景には、openpageの独特な組織哲学がある。THE MODELのような分業体制が一般的な中で、openpageは意図的に越境することを奨励している。「インサイドセールスの仕事はこういうもの」という固定的な定義をせず、個人の能力に合わせて仕事を采配しているのだ。
異常な効率性の秘密
「ISは大手企業から中小企業までの法人向けの商談獲得に加え、自治体など企業以外のステークホルダーも対象にしています」
インサイドセールスの対象も、従来の法人営業の枠を超えて自治体やパートナーなど全国に広がっている。注目すべきは、滝沢さんがインサイドセールスの業務量で目標をハイ達成しつつ、他の仕事もケロッと同時にこなしていることだ。これは、openpageのインサイドセールスの効率が異常に高いことを示している。

経営者的働き方の実現
だからこそ、こんな経営者のような働き方ができるのだ。単一の職種に縛られることなく、事業全体を俯瞰しながら必要な領域に自分のリソースを投入していく。この柔軟性こそが、滝沢さんが目指す「1つの事業の責任者ポジション」への道筋を作っている。
多様性が生む物語性
法人から自治体まで、様々なステークホルダーを対象とするこの多様性が、後述する「物語性」の実現につながっている。openpageが目指す社会インフラとしての可能性は、こうした越境的な働き方から生まれているのだ。
滝沢さんの働き方は、単なる個人の能力の高さを示すものではない。組織が個人の可能性を最大化する環境を提供し、個人がその期待に応えて成果を出す。この好循環こそが、openpageの強みの源泉なのだ。
第十七章:物語性の真髄 ─ 国づくり、街づくりへの壮大なビジョン
コミュニケーション革命から始まる物語
最後に、滝沢さんが最も大切にしている「物語性」について、より深い展望を聞いた。
「僕は物語性を大事にしています。openpageの物語性は、お客様と、お客様のお客様、そこの取引のコミュニケーションのズレをなくし、前に進め、新しい関係性を作り、発展させていくことです」
openpageの価値は、単なる営業効率化に留まらない。顧客とその先にいる人々とのコミュニケーションを改善することで、これまでにない関係性を創造していく。これこそが滝沢さんの言う「物語性」の本質だ。

あらゆる組織での活用可能性
「これまで生まれてこなかった関係が生まれ、新しい取り組みが生まれていく。僕らは営業やその後の工程を担うなら、企業や自治体はあらゆる組織でいろんなシーンで使える」
滝沢さんの目は確信に満ちている。企業間取引をするあらゆる組織で活用が進むだろうと予想している。規模は問わない。大企業から中小企業まで、提案や交渉のシーンはすべてopenpageが使える場面だ。
商慣習のアップデート
「いろんな新しいことを生み出していきたい。北森さんとは自治体やパートナーとの関係深耕もしています。裾野は広がり続けています。いろんな顧客が使うことを想定した動きを事業開発でしています」
これは単なる構想ではない。事業の裾野は確実に広がり続けており、openpageによってあらゆる商慣習がアップデートされる可能性を秘めている。従来のアナログな提案や交渉プロセスが、デジタル化によって劇的に進歩していく未来が見えている。
デジタル化による社会進歩
「その先に、国づくり、街づくりにも関われる。本来、法人や自治体が大きく実現したいことを叶えられるパートナーにopenpageはなれる。その物語は魅力的です」
デジタル化で世の中が進歩する。この大きな流れの中で、openpageは単なるツールを超えた役割を果たす。法人や自治体が抱える大きな課題の解決パートナーとして機能する未来像を、滝沢さんは明確に描いている。
比類なき影響力への確信
「自分たちの影響範囲はすごく大きい、面白い会社だと思います。他のプロダクトではここまで大きなストーリーは描けないはずです」
滝沢さんの確信は揺るがない。他のプロダクトでは実現できない規模のストーリーを描ける。この言葉に、彼がopenpageを選んだ真の理由が集約されている。単なる営業支援ツールを超えた、社会インフラとしての可能性を見出しているのだ。
エピローグ:転職という選択を超えた、人生の物語への挑戦
約12,000字にわたる長大なインタビューを通じて見えてきたのは、「変態的」とも呼べる営業への執念を持ちながら、それを社会的な価値創造につなげていく現代的な働き方のモデルだった。
カレンダー監視、1〜2年越しの追跡営業、超長文メール、忘年会後の仕事──これらの「変態エピソード」は、一見すると個人的な特異性に見える。しかし、その根底にあるのは「世界レベルで物語を作りたい」という明確なビジョンだ。
滝沢さんが提唱する「物語性」は、現代のビジネスパーソンにとって重要な示唆を含んでいる。単純な機能提供や効率化を超えた、より深い変革への関与。顧客とその先にいる人々との新しい関係性の創造。そして最終的には、あらゆる商慣習のアップデートを通じて、デジタル化による社会進歩に貢献できる可能性。
これは、個人のキャリア発展と社会への貢献を一体化させる、新しい働き方の哲学と呼べるかもしれない。
前職でARR10億円規模の事業成長に貢献した滝沢さんが、なぜスタートアップのopenpageを選んだのか。それは、成長の質に対するこだわりだった。安定した環境ではなく、自分が物語の主人公になれる環境。越境を奨励され、経営者的な働き方ができる環境。そして何より、自分の「変態的」な執念を、組織の成長エンジンとして活用できる環境。
特に印象的だったのは、成功談だけでなく、現在の悩みも率直に語ってくれたことだ。「やりきり」への挑戦、理想と現実のギャップ、無難な選択を拒否する執念──これらの等身大の葛藤を嬉しそうに語る姿に、滝沢さんの本質が表れている。
また、転職の決断に同期2人の存在が大きく影響したというエピソードも印象深い。ビジネス的な判断だけでなく、人間関係における信頼が重要な決断を支える。この人間的な側面も、現代の転職においては重要な要素だろう。
openpageでの営業アプローチも興味深い。PVデータによる検討状況分析という徹底的にデータドリブンな手法と、超長文メールや粘り強い追跡営業という極めて人間的なアプローチの両立。これは、デジタル時代の営業の一つの理想形かもしれない。

そして、openpageというチームの文化的な特徴──「チャーミング」なメンバー、健全で合理的な意思決定、経営陣の高い視座──これらが、個人の能力を最大化する環境を作り出している。個人の成長と組織の成長の好循環が、ここにある。
滝沢郁也さんの物語は、まだ始まったばかりだ。「世界レベルで物語を作りたい」という壮大な目標に向かって、彼の挑戦は続いている。
その過程で生まれる成功も失敗も、すべてが新しい価値創造につながっていく。変態的な執念を社会的価値に転換する──これこそが、現代のビジネスパーソンが目指すべき一つの理想形なのかもしれない。
openpageという舞台で、滝沢さんがどんな新しい物語を紡いでいくのか。そして、その物語が最終的に企業間取引のあらゆるシーンで、どんな社会的インパクトを生み出していくのか。今後の展開が、非常に楽しみでならない。

/assets/images/21165365/original/3ff4f912-5858-4406-b3ee-8f29caf7faf7?1747810835)


/assets/images/21165365/original/3ff4f912-5858-4406-b3ee-8f29caf7faf7?1747810835)




/assets/images/21165365/original/3ff4f912-5858-4406-b3ee-8f29caf7faf7?1747810835)

