ニューロマジックでは、2022年にDEI担当執行役員が就任して以来、DEIの取り組みを加速させています。
今回はDEIの中でも特に「多様性」に焦点を当て、2024年9月に開催されたイベント「Hills Breakfast」での登壇を、DEI担当執行役員の永井さんと学生インターンの須田さんが振り返ります。執行役員と学生インターン、異なる視点を持つ二人が語る「多様性」のリアルとは?
本記事は前編・後編に分かれていますので、ぜひ最後までご覧ください!
※この記事はSERVICE DESIGN BLOGの転載です
「多様性」という言葉を皆さんはどのように捉えていますか?
近年メディアでも頻繁に取り上げられるワードではあるけれど、「具体的に何を指すものなのか」そして「どんなアクションを起こせば良いのか」という捉え方に、かなり個人差があるように思います。
ニューロマジックでは「『都市』のような組織を目指し、社会の変化に対して影響し続ける」というビジョンのもと、多様性に対する「意識」を「実践」に移すべく、様々な取り組みを行なっています。
本記事の前編では、学生インターンの私、須田桜子が、DEI担当執行役員の永井菜月さんが登壇されたトークイベント「Hills Breakfast」(2024年9月)を振り返りながら、永井さんへのインタビューを通して、多様性について探っていきます。
■永井 菜月(ながい なつき)
上智大学院グローバルスタディーズ研究科卒業。2018年当社入社。サービスデザイナーとしてユーザーインタビューなどの企画・実施から、調査結果を基にしたサービスの体験設計やブランドデザインを担当。 2020年よりチームリーダーとして育成や同グループの事業づくりにも携わる。また学生時代から多様性やEquity(公平性)について関心を持ち、修士課程では米国のマイノリティコミュニティを研究。2022年よりDEI担当執行役員。2024年5月より現職。
多様性の実践における4つの指標
Hills Breakfastは、社会課題の解決に挑む起業家や、ジャンルレスな表現を通して国内外で活躍するアーティストなど、社会貢献、テクノロジー、アートといった多様な分野で活躍されている方が、自身のアイデアを発信する朝のトークイベントです。用いられるのは、「PechaKucha」という独自のプレゼン方式。20枚のスライドを1枚あたり20秒で語り、スピーディーかつコンパクトに進行されるユニークなスタイルです。永井さんは、「多様性の実践」というテーマで登壇されました。
現在ニューロマジック社内のDEI施策に尽力されているだけでなく、これまで学業やプライベートでも多様性に向き合ってきた永井さん。プレゼンテーションでは、「多様性の実践」の指針として、以下の4つを挙げました。
■「何のための/誰のための議論?」を常に振り返る
自分の尺度だけで判断をせず、この議論は「何のため」「誰のためか」を常に意識することで、あらゆる問題の本質的な解決を目指す。
■制度化、明文化
身体的・精神的に弱っているときに助けを求めるのは難しいからこそ、支援制度や相談窓口は、誰もが安心して使えるよう制度として整え、明文化しておく。
■パーソナルストーリーを言語化/可視化
他者の経験や背景を知ることで新たな学びを得たり、エンパワーメントされたりすることがあるので、自分自身が経験したことを言語化して共有することで、ポジティブな影響を広げる。
■選択の自由を保証
誰もが自分のタイミングで働き方や暮らし方を選べる自由を保障することが、多様な人生を支える基盤になる。
「パーソナルストーリー」を交換する大切さ
永井さんがプレゼンテーションで話されていた多様性の実践における4つの指針。これらの観点にどのようにして至ったのか。永井さん自身のストーリーもお伺いしながら、「多様性の実践」に対する考えをお聞きしました。
須田:まず、Hills Breakfastで登壇されたなかで、特に印象に残っていることをお聞かせください。
永井:イベント後に参加者から直接声をかけていただけたのが嬉しかったです。キャリアと子育ての両立に苦戦してきた女性や、DEIを社内で推進していて組織変革に課題を感じている方など、壁にぶつかりながらも自分なりに課題に取り組んできた方から共感の声をいただけたのはすごく良い経験でした。
須田:登壇を見ていた方とその場で意見交換ができるのが良いですね。
永井:感想だけではなく、その人が持っている深いストーリーを共有すると、人と人との繋がりもできるので、自分の経験を発信していくことは本当に大事ですね。
須田:今のお話は、永井さんが「多様性の実践」に向けて実際に取り組まれている「パーソナルストーリーの共有」と深く関わることだと感じました。私たちが普段から「パーソナルストーリーの共有」をするためにはどんな心がけが必要なのでしょうか?
永井:パーソナルストーリーに対するアプローチ方法はいろいろあると思います。それぞれが話すきっかけは、本でもドラマでも何でも良いんです。プライベートなことだから自分が話したくないことはもちろん話す必要はないけれど、私は自分が経験して、他の人もライフステージのなかで経験するかもしれないようなことは積極的に共有していこうと思っています。社内だったら、社員の個人のつぶやきを共有するSlackチャンネルを活用したり、会議の場でも雑談のなかでそういう経験を共有したりしています。
須田:確かに身近なところで話すきっかけはたくさんありそうですね!パーソナルストーリーを語ることは、永井さんが登壇のなかでも取り上げていた「当事者のための議論」にも繋がると思います。
社会のなかで問題を抱えている当事者が存在しても、実態を知らないと共感することも難しくてつい無関心になってしまいます。関心を持つためにも、誰かのパーソナルストーリーを聞いたり自分で話したりすることは大事ですね。
永井:そうなんです!当事者が身近にいてもなかなか気付けないですよね。当事者が発信できる環境でパーソナルストーリーを共有してもらえるとお互いに理解も深められるし、私たちも実態を知ったうえで共感できると思います。
例えば私自身も女性役員として経営者交流会に行くと男性ばかりですごく戸惑うこととか、強烈なマイノリティ性を感じることがあります。逆に、自分が経験していない問題を「こういうことがあってね」と具体的に教えていただけると想像できる景色がモノクロではなくカラーになるんですよね。
「誰しもが問題を抱えうる」ということを想像できるようになることは、DEIの施策をするうえで非常に重要で、当事者意識を持つことはとても大切なテーマです。
個人の経験から考える「多様性の実践」
ここまでパーソナルストーリーの交換が生む共感や気づきについて取り上げてきましたが、永井さんがこれらを「多様性の実践」のために取り入れたきっかけには、永井さんご自身の経験が深く関わっているようです。
須田:永井さんが日本語版制作プロジェクトを行ったZINE『Sammys』では「食を通じて他者を理解する」ことを目的として、それぞれ異なる文化的背景を持つ人々が作るサンドイッチを、彼らのライフストーリーとともに紹介しているのが印象的でした。『Sammys』の制作を通して永井さんの多様性への意識に変化はありましたか?
永井:多くの人にとって馴染みのあるサンドイッチという食べ物から、ポップに多様性が考えられて、多様性にもいろんな伝え方やアプローチがあるということに気づきました。私は大学院で研究をしていたこともあって、多様性に向き合うとなるとどうしても堅いアプローチで取り組んでいたけれど、こういう方法もあるんだなと!
須田:身近なところにヒントがあるんですね。私ははじめからかしこまって考えてしまうので、まずは身近なところできっかけを見つけてみたいです。
登壇のなかでも大学院での研究のお話がありましたが、永井さんが学生時代に文化人類学を専攻されたきっかけについて教えてください。
永井:私は大学院でアメリカのムスリムコミュニティを研究していたのですが、そのきっかけとなったのは、私が小学生の時にアメリカで起こった「9.11 同時多発テロ」です。ニュースで映像を見たときはかなりの衝撃を受けました。
その当時のメディアでは、イスラム教とテロが安易に結びつけられ、あまり良くないイメージを付けられていたのですが、そこから学校で歴史や宗教について学ぶと、そのイメージがいかに覇権主義的で、かつイスラム教の実態とは異なっているかを知りました。そこからムスリムの人々がどんな生活を送っているのかに興味を持って、それが研究できるのが文化人類学だったので専攻しました。
須田:大学院在学中には研究の一環でアメリカ現地のムスリムコミュニティを訪れ、インタビューなどをされていたとのことですが、実際にアメリカで暮らすムスリムの方々と接してみて感じたことはありますか?
永井:2001年に起こった同時多発テロの後は、アメリカのなかでもムスリムの人々はかなり差別的な目を向けられていました。そのようななかで私はムスリムコミュニティ内で発刊されている雑誌を研究しながら実際にムスリムの人々と関わっていました。
そういった状況だったので、私は勝手に雑誌のなかで差別への闘いや対米社会へ向けた主張などが多いかな、と思っていたんです。もちろん、さまざまなかたちで差別に向き合い、闘うことも重要ですし、この雑誌を発行していた団体も積極的にアドボカシーなどを行っていたのですが、雑誌では「自分たちがより良いムスリムとして存在すること」に真摯に向き合っていたんです。
論文では、当時の社会で偏見の目を向けられていた当事者であるムスリムの人々の多様な生活実態を、実際に交流することを通して理解し、まとめることができました。
須田:そうだったんですね。私もこのお話から当事者の実態を知ることの大切さを改めて理解できました。
こうやって現地で生活をされたり研究されたりすることって、サービスデザインのリサーチとかなり重なりますよね。
永井:サービスデザイナーって蓋を開けると文化人類学を学んでいた人が結構多いんです!
須田:そうなんですね!これまでの学びが、実務の場で結びついていくのですね。
柔軟な思考と対話で支えるサービスデザインの現場
ここからはサービスデザインの現場での「多様性の実践」に目を向けます。多様なユーザーの潜在的な感覚や可能性に働きかけ、持続的に価値を生み出すサービスをつくるためには、現場においてどのような問いの立て方や環境づくりが求められるのでしょうか。
須田:私はインターンとしてサービスデザインについて日々学びながら、「多様性の実践」とサービスデザインは、当事者への共感が鍵となるという点でかなり密接に繋がっていると感じるようになりました。
永井:そうなんです!2年ほど前にデンマークのコペンハーゲンで「Service Design Global Conference 2022(SDGC22)」が開催され、私は日本で行われたSDN(Service Design Network)日本支部主催の参加レポートを聞きに行きました。実際にカンファレンスに参加した方々が口々に言っていたのが、その会議内でキャロライン・クリアド=ペレス著の『存在しない女たち』というフェミニズムの本が話題に上がっていたということ。
自分たちがユーザーに共感してサービスを作っていくなかで、「誰に共感するのか」、そして「誰に目を向ければならないのか」ということを考えるきっかけとなったそうです。
須田:アップデートしていくなかで、それがマイノリティの目線でつくられたサービスだとしても、マイノリティに属していない人も結果的に恩恵を受けることに繋げられると良いですよね。
永井:私もDEIの執行役員になってそのことを意識するようにしています。
DEIの施策を検討するうえでも、きっかけは何らかの課題を持っている人向けだったとしても、結局はみんなが働きやすくなるようにすることを考えています。
須田:ニューロマジックには社内で共通して「誰が言うかではなく、何を言うか」を大切にするという文化があると思います。私が普段インターンとして働いていても、学生インターンの私なりの意見を皆さんが尊重してくださるので、この風通しの良さは「多様性の実践」をするための環境としてもとても大切だなと感じます。
永井:この風潮は会社の公式のビジョンとして掲げられているわけではないのですが、私が入社する前から根付いている「会社全体のゆるやかな共通事項」なんですよね。
これに関するトピックとして、以前に社内のメンバーの1人が、当時あった規則に関してやりずらさを感じていることを勇気を出して言ってくれたことがありました。そのときにある役員が、「当たり前を疑う良いきっかけになりました」と感謝していたことが私には印象深く残っています。これを機に、私も働くうえで困ったことがあるときには声をあげたり、また困っている人に対してしっかりと耳を傾けることの大切さを改めて感じました。
須田:「当たり前を疑うこと」と「疑いに耳を傾けること」は普段から意識していないとなかなか自然と実践することが難しいですよね。そういった話し合いができる環境は本当に大事ですね。
永井:現在、組織を運営するなかで議題に上がっているのは、「社内のメンバーがニューロマジックの風通しの良さを実感していても、過去に声を上げづらい経験があると、今も困ったときに躊躇してしまう人がいるのではないか?」ということです。そのためにも、ニューロマジックを風通しの良い環境に保つことに加えて、そういう人たちがよりオープンに話しやすい環境づくりをするためにどんなことができるかを中長期的に考えていきたいと思っています。
「意識」から「実践」へ
ここまで永井さんの登壇内容をもとに「多様性の実践」について考えてきました。今回のインタビューを通して、私は、多様性が「他者の立場や経験に思いを巡らせること」ではないかと考えるようになりました。この場合、「思いを巡らせる=理解する」ではなく、「たとえ完全には理解できなくても、当事者に歩み寄ろうとする」という意味に近いと思います。自分は問題の当事者ではないから無関係だと思っていても、誰しもがあらゆる社会の枠組みのなかでマイノリティになる可能性があるため、決して他人事ではありません。そのうえで、自分が当事者として経験していない問題でも、それらを知るきっかけを積極的につくり、当事者意識を育んでいくことが大切ではないでしょうか。
しかし、多様性を尊重できる社会にするためにはそのように「意識」することに加えて、行動に移して「実践」することが必要です。後編では、デザインプロセスという領域で、実際に多様性をどう反映させていくかについて話していきます。
/assets/images/5579099/original/a999b3a9-39a0-4405-b18c-e53691d6e95a?1601289726)
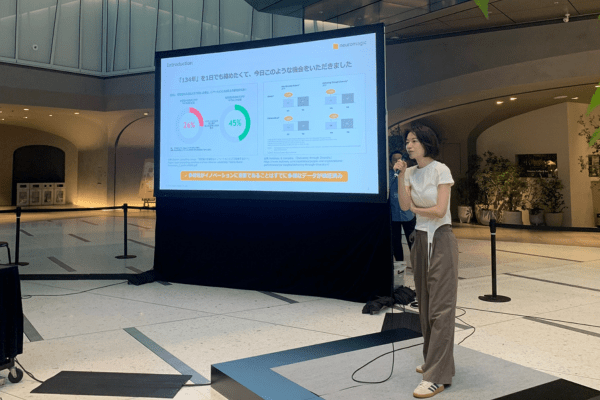
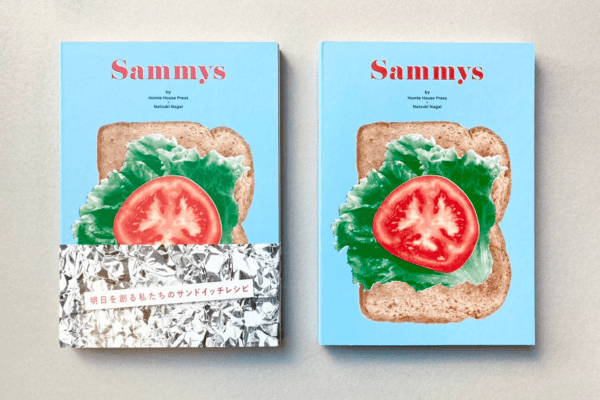

/assets/images/5579099/original/a999b3a9-39a0-4405-b18c-e53691d6e95a?1601289726)
/assets/images/5579099/original/a999b3a9-39a0-4405-b18c-e53691d6e95a?1601289726)
